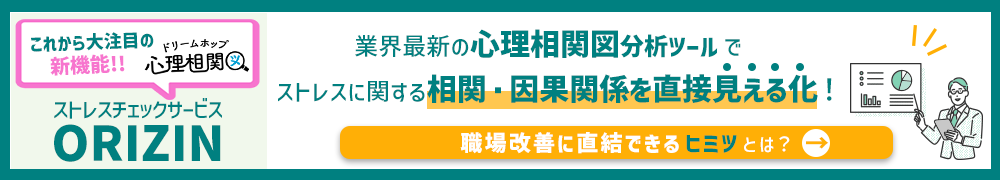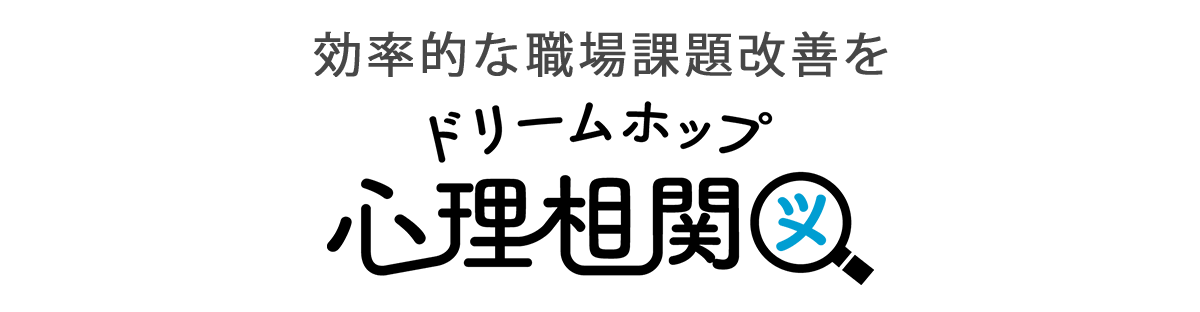ストレスチェックと産業医の役割|企業のメンタルヘルス対策を徹底解説
更新日:2025/02/03

従業員の健康管理や職場の安全管理でも大きな役割を果たしている産業医。ストレスチェックにおいても産業医は欠かせない存在です。
本記事では、ストレスチェックと産業医の役割について、企業の人事担当者や経営者、そして従業員自身も知っておくべき必須事項を網羅的に解説します。ストレスチェック制度の概要から、産業医の役割、具体的な実施手順、注意点などを確認していきましょう。
労働安全衛生法に基づき、ストレスチェックの実施は企業の義務となっています。ストレスチェック制度の目的を理解し、適切な実施と職場環境改善につなげ、従業員のメンタルヘルスを守り、生産性向上に貢献できます。ストレスチェックにおける産業医の役割を正しく理解することで、ストレスチェックを効果的に活用し、より健康的な職場づくりを実現できるでしょう。
さらに、集団分析の活用方法など、ストレスチェックに関する実践的な情報もお伝えします。ストレスチェックの場面でも産業医を味方につけ、企業のメンタルヘルス対策を万全なものにしましょう。
PCAグループでは、産業医との顧問契約についても対応しております。くわしくはお問い合わせください。
ストレスチェック制度の概要

現代社会において、仕事によるストレスは大きな社会問題となっています。過剰なストレスは、従業員の心身の健康を損なうだけでなく、生産性の低下や離職率の増加など、企業活動にも悪影響を及ぼします。そこで、従業員のメンタルヘルス対策として、2015年12月からストレスチェック制度が義務化されました。
ストレスチェック制度とは
ストレスチェック制度とは、労働安全衛生法に基づくメンタルヘルスの状況確認と早期対処に役立つ制度です。
事業者は従業員の心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)を実施します。ストレスチェックのその結果に基づいて、従業員自身のストレスへの気づきを促し、必要な場合には医師による面接指導を行います。
心理的な負荷がある従業員をいち早く医師やカウンセラーにつなげることで、メンタルヘルス不調を未発症段階で予防することを目的としています。
【関連記事:【企業必見】ストレスチェックでわかる退職リスク!離職防止のための具体的な対策と活用事例】
ストレスチェックの目的
ストレスチェックの主な目的は、従業員のメンタルヘルス不調を予防することにあります。具体的には、以下の3点が挙げられます。
- 従業員自身のストレスへの気づきを促す
- 職場環境におけるストレス要因の把握
- メンタルヘルス不調の未然防止と早期発見
法律で定められたストレスチェックの目的
厚生労働省によれば、ストレスチェックの主な目的は以下のとおりです。
労働者のストレスの程度を把握し、労働者自身のストレスへの気付きを促すとともに、職場改善につなげ、働きやすい職場づくりを進めることによって、労働者がメンタルヘルス不調となることを未然に防止すること(一次予防)
従業員が精神的な負担を抱え、調子を崩してしまう前に「負担がかかっている」ということを知り、早期介入・課題解決できるようにするための制度、と考えられるでしょう。
ストレスチェックの内容
厚生労働省の実施マニュアルにおいて、ストレスチェックは「職業性ストレス簡易調査票等を用いて行う」ことが推奨されています。
57問・80問の調査票を用いることが一般的ですが、事業場の実情に合わせて、設問や実施方法をカスタマイズすることも可能です。
ストレスチェックの対象者
ストレスチェックの対象者は、原則として50人以上の労働者を雇用する事業場のすべての労働者です。対象となる従業員の例を見てみましょう。
対象となる従業員
以下の雇用形態の従業員は、原則としてストレスチェックの対象となります。
- 正社員
- 契約社員
- パートタイマー
- アルバイト
- 派遣労働者
- 出向者
雇用形態に関わらず、50人以上の労働者を雇用する事業場では、ストレスチェックの実施が義務付けられています。労働契約の形態や労働時間の長短は関係ありません。派遣労働者と出向者については別途注意が必要なため、後述します。
【関連記事:ストレスチェックの受検を従業員に拒否されたら?受検率を高めるポイントを解説】
対象外となる従業員
以下の場合は、ストレスチェックの対象外となります。
- 休職者
- 長期出張者
- 短期間のアルバイト
ただし、休職者や長期出張者であっても、職場復帰が見込まれる場合には、ストレスチェックを実施することが望ましいとされています。
派遣労働者のストレスチェックと集団分析
派遣労働者については、派遣元事業者がストレスチェックを行うことになっています。しかし、集団分析を行う場合は、実際の職場である派遣先で行わなければ意味がありません。そのため、派遣先と連携をとり、派遣先でもストレスチェックと集団分析を行うことが望ましいでしょう。
(参考:派遣労働者に対するストレスチェック等の実施に関する考え方 |厚生労働省)
出向者のストレスチェックと集団分析
出向には在籍出向と移籍出向の2つの形態があります。
在籍出向とは、もとの所属先企業との雇用契約を残したまま、出向先で業務を行う形です。一方で移籍出向では、出向先企業と雇用契約を結びます。
在籍出向の場合は、派遣労働者と同様に、もとの所属先(出向元の事業場)でストレスチェックを行いますが、出向先においてもストレスチェックと集団分析を行うことが望ましいでしょう。
移籍出向の場合はシンプルに、出向先においてストレスチェックの実施・集団分析を行えば良いことになります。
ストレスチェックの実施時期と頻度
ストレスチェックは、原則として年に1回実施することが義務付けられています。実施時期は事業場ごとに自由に設定できますが、従業員の負担を考慮し、業務に支障が出ない時期を選ぶことが重要です。
また、ストレスチェックの結果を踏まえ、職場環境改善などの対策を実施する必要があるため、年度終わりギリギリの時期に行うよりも、余裕を持って実施しましょう。
実施後は報告書の提出も必要です。
【関連記事:ストレスチェック報告書の書き方・労基署への提出方法・提出期限を徹底解説!】
その他、ストレスチェックの実施の概要について、以下の表をご覧ください。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 実施頻度 | 原則として年1回以上 |
| 実施時期 | 事業場ごとに設定可能 |
| 調査方法 | 紙媒体またはWebツール |
| 結果の通知 | 本人への通知が義務付けられている |
ストレスチェックにおける産業医の役割

産業医は、ストレスチェック制度において重要な役割を担っています。単にストレスチェックの実施を監督するだけでなく、労働者のメンタルヘルスを守るためのさまざまな活動を行います。
職場では産業医と連携し、効果的なメンタルヘルス対策を推進していく必要があります。
【関連記事:産業医とは?役割・仕事内容・必要性・選び方などを徹底解説】
【関連記事:産業医の選任:基本と探し方、トレンドを解説】
産業医の法定義務
産業医には、ストレスチェックに関して法律で定められた義務があります。最も重要なのは、高ストレス者への面接指導です。
【関連記事:職場環境改善の鍵!ストレスチェックで高ストレス者に対応するための3ステップ】
【関連記事:ストレスチェックにおける高ストレス者判定基準と対応方法】
ストレスチェック実施後の面接指導
ストレスチェックの結果、高ストレス者と判定された労働者に対しては、産業医による面接指導が義務付けられています。これは、労働者のプライバシーに配慮しながら行われなければなりません。
産業医の立場から、高ストレス者の心身の状況を把握し、課題の洗い出しを行います。
【関連記事:【担当者向け】ストレスチェック後の面接指導とは?注意点と流れも紹介】
高ストレス者への対応
高ストレス者とは、ストレスチェックの結果、心理的な負担が一定の基準を超えたと判断される労働者を指します。産業医は、高ストレス者に対して面接指導を行い、その結果に基づいて必要な措置を講じます。
必要な措置の例として、以下のようなことが挙げられます。
- 専門医療機関への受診を促す:精神科、心療内科など、状態に応じた受診先・受診方法をアドバイスする
- 休養を促す:有給休暇等の活用だけでなく、場合によっては休職の検討を行う
- 日常生活上の指導を行う:睡眠・食事・運動などの生活習慣についてアドバイスを行う
- 職場側に業務量の調整を提案する:残業が多い場合は減らす、夜勤が負担になっている場合はシフトの調整を行うなど望ましい方法を考える
- 配置転換を提案する:職場側とのミスマッチを起こしている場合や通勤が負担になっている場合など、異動で解決できそうなことがあれば、職場側に打診する
面接指導の内容と実施方法
面接指導では、労働者の現在の状況やストレスの原因、今後の対応策などを話し合います。産業医は、労働者の状況に合わせて適切なアドバイスや支援を行います。
プライバシー保護の観点から、面接指導の内容は厳重に管理されます。場所や実施時間など、十分に配慮を行いましょう。
ストレスチェック以外にも産業医の役割がある

ストレスチェック以外にも、産業医は職場環境の改善や健康管理など、幅広い役割を担っています。これらの活動を通して、労働者の健康を守り、生産性の向上に貢献します。
職場環境の評価と改善提案
産業医は、職場の環境を評価し、心身の不調の発生を予防するための改善提案を行います。長時間労働の是正やハラスメント対策など、介入する場面は多岐にわたります。
メンタルヘルスにおいてはもちろんのこと、身体的な健康管理・安全管理にも関係します。たとえば、後述の職場巡視によって職場内の危険箇所・事故発生リスクを把握し、転落事故を防止することや化学物質による健康被害を防止することにも、産業医の知識と経験が活かされます。
メンタルヘルス対策の推進
産業医は、企業全体のメンタルヘルス対策を推進する役割も担います。管理監督者・従業員への教育や相談体制の構築など、さまざまな活動を通して、職場全体のメンタルヘルス向上を目指します。
たとえば、以下のような活動が想定されます。
- メンタルヘルスに関する研修を実施する
- 従業員の相談窓口に参画する
- メンタルヘルス向上のための社内制度設計に参画する
【関連記事:EAP(従業員支援プログラム)を徹底解説!導入のメリット・デメリット、具体的な内容とは?】
職場巡視と健康相談
産業医は、定期的に職場を巡視し、労働者の健康状態や職場環境をチェックします。
また、高ストレス者以外でなくても、労働者からの能動的な健康相談にも対応し、必要な場合は医療機関への受診を勧めます。職場巡視や健康相談は、労働者の健康状態を早期に把握し、適切な対応を行ううえで重要です。
【関連記事:産業医の職場巡視とは?目的・必要性・実施頻度・方法を徹底解説】
健康診断の結果チェック
産業医は、労働者の健康診断の結果をチェックし、健康上の問題がないかを確認します。必要に応じて、再検査や精密検査を勧めることもあります。
また、健康診断の結果をもとに、生活習慣の改善指導などを行うこともあります。健康診断とストレスチェックの結果を総合的に判断することで、より効果的な健康管理が可能になります。
| 役割 | 内容 |
|---|---|
| 面接指導 | 高ストレス者と判定された労働者との面談を行い、ストレスの原因や状況を把握し、適切なアドバイスや支援を行う。 |
| 職場環境評価 | 職場環境のストレス要因を分析し、改善策を提案する。長時間労働の是正、ハラスメント対策、職場コミュニケーションの改善などを含む。 |
| メンタルヘルス対策推進 | 管理監督者・従業員教育、相談窓口設置、メンタルヘルスに関する研修実施など、企業全体のメンタルヘルス対策を推進する。 |
| 健康診断結果チェック | 健康診断の結果を確認し、健康上の問題を早期に発見し、必要な場合は医療機関への受診を勧める。 |
| 職場巡視 | 定期的に職場を巡回し、労働者の健康状態を観察し、職場環境の改善点などを把握する。 |
| 健康相談 | 労働者からの健康相談に対応し、適切なアドバイスや指導を行う。 |
産業医は、これらの役割を通じて、労働者の健康を守り、企業の生産性向上に貢献しています。職場では産業医と積極的に連携し、効果的なメンタルヘルス対策を推進していくことが重要です。
ストレスチェック実施の手順
ストレスチェックを正しく実施するためには、適切な手順を踏むことが重要です。
ストレスチェックの実施には、大きく分けて準備段階・実施段階・事後対応の3つの段階があります。
Step 1:準備段階
準備段階では、ストレスチェックの実施計画を立て、必要な資料を準備します。実施計画には、実施時期、対象者、実施方法、結果の分析方法などを盛り込みます。
また、対象者・管理職者への周知も重要です。ストレスチェックの目的や実施方法などを説明し、協力を得られるようにしましょう。
調査票の準備と配布
厚生労働省が推奨するストレスチェックの調査票を使用するか、もしくはそれに準拠した調査票を使用します。調査票は、対象者全員に配布し、記入漏れがないように注意が必要です。
配布方法は、紙媒体だけでなく、Webシステムを利用する方法もあります。Webシステムを利用する場合は、システムの操作方法などを対象者に周知する必要があります。
ストレスチェックの「ORIZIN」を使えば、57問版・80問版のストレスチェックが簡単に実施でき、独自の設問を盛り込むことも可能です。スマホで直感的に操作・回答・管理でき、回答する従業員にとっても、実施担当者にとっても負担が少なく、受検率向上に役立ちます。
【関連記事:80項目版のストレスチェックの特徴は?57項目版との違いを解説】
Step 2:実施段階
実施段階では、対象者に調査票を記入してもらい、回収します。回収率を高めるためには、実施期間を十分に確保することが重要です。
また、記入方法がわからない対象者には、個別にサポートを行うなどの配慮も必要です。
回収と集計
回収した調査票は、速やかに集計します。
集計方法は、手作業で行う方法と、Webシステムを利用する方法があります。Webシステムを利用する場合は、集計作業が自動化されるため、効率的に作業を進めることができます。
集団分析
集計結果をもとに、集団分析を行います。集団分析では、職場全体のストレス状況を把握し、職場環境の改善につなげることが目的です。
分析結果は、産業医と共有し、職場環境改善のための対策を検討します。
Step 3:事後対応
ストレスチェックの実施後は、高ストレス者への面接指導や報告、集団分析の結果を踏まえた職場環境の改善を行います。
高ストレス者への面接指導
ストレスチェックの結果、高ストレス者と判定された従業員には、産業医による面接指導を行います。面接指導では、ストレスの原因や対処方法などを話し合い、従業員のメンタルヘルス不調の予防や改善を図ります。
実施報告
労働基準監督署に実施報告書を提出します。報告書には産業医のサインも必要です。
ストレスチェック実施の際の注意点

ストレスチェックを実施する際には、以下の点に注意する必要があります。
プライバシー保護
ストレスチェックの結果は、個人のプライバシーに関わる情報であるため、適切に管理する必要があります。結果の取り扱いには十分注意し、漏洩や不正利用がないように対策を講じなければなりません。
個人情報の適切な管理
ストレスチェックの結果は、個人情報保護法に基づき、適切に管理する必要があります。具体的には、結果を保管する場所を限定したり、アクセス権限を設定したりするなどの対策が必要です。
情報セキュリティ対策
Webシステムを利用してストレスチェックを実施する場合は、情報セキュリティ対策を徹底する必要があります。システムへの不正アクセスやデータ漏洩を防ぐために、適切なセキュリティ対策を講じることが重要です。
たとえば、アクセス制御や暗号化などの技術的な対策に加え、従業員へのセキュリティ教育なども重要です。
集団分析の結果を職場改善に活かす
ストレスチェックは、単に実施するだけでなく、その結果を職場環境の改善に活かすことが重要です。
集団分析の結果から、職場におけるストレス要因を特定し、具体的な改善策を検討・実施することで、従業員のメンタルヘルス不調の予防や改善を図ることができます。以下の表に、集団分析の結果から考えられる職場環境の改善策の例を示します。
| ストレス要因 | 改善策の例 |
|---|---|
| 仕事の量が多 | 業務分担の見直し、業務効率化の推進 |
| 人間関係が悪い | コミュニケーション研修の実施、相談窓口の設置 |
| 上司からのサポート不足 | 上司向けの研修の実施、評価制度の見直し |
これらの改善策はあくまでも例であり、実際の職場環境に合わせて適切な対策を検討する必要があります。
また、改善策を実施した後は、その効果を検証し、必要に応じて改善策を修正していくことも重要です。ストレスチェックを継続的に実施し、PDCAサイクルを回すことで、職場環境の改善を図り、従業員のメンタルヘルスを維持・増進していくことが重要です。
専業医はまさに、そのPDCAサイクルにおいて、専門的な知見と技術を提供する役割を担い、職場のウェルビーイング向上のために重要な存在であると言えるでしょう。
【関連記事:メンタルヘルス×組織開発で生産性向上!企業の成長を促す最強戦略】
ストレスチェックに産業医を巻き込み、働きやすい職場をつくる

ストレスチェック制度における産業医の役割、実施手順と注意点について解説しました。
産業医は、ストレスチェック実施において重要な役割を担います。高ストレス者への面接指導は産業医の法定義務であり、プライバシーに配慮した適切な実施が求められます。また、職場環境の評価や改善提案、健康診断結果のチェックなど、従業員の健康管理全般に関しても重要な役割を果たします。職場では、産業医と連携して、効果的なメンタルヘルス対策を推進していく必要があります。
毎年のストレスチェックは単なる義務ではなく、働きやすい職場をつくり、経営の安定・向上につながるチャンスです。効果的にストレスチェックを行い、心身の不調が重くなる前に対処したり、働きづらさの芽に気づいて職場改善を進めたりすることで、離職率が下がり、生産性が上がることも期待できます。
それらの取り組みに産業医の専門的な知見・スキルを活用すれば、職場改善の深さもスピードも向上するでしょう。
産業医との付き合い方には、顧問としてしっかり頼るスタイルもあれば、必要な分だけ頼る「アラカルト利用」もあります。自社の状況や規模に合わせた産業医の活かし方について、ぜひご相談ください。