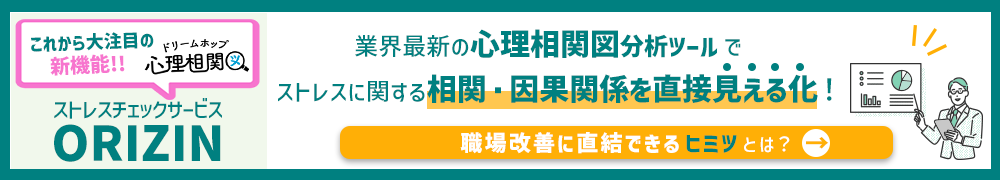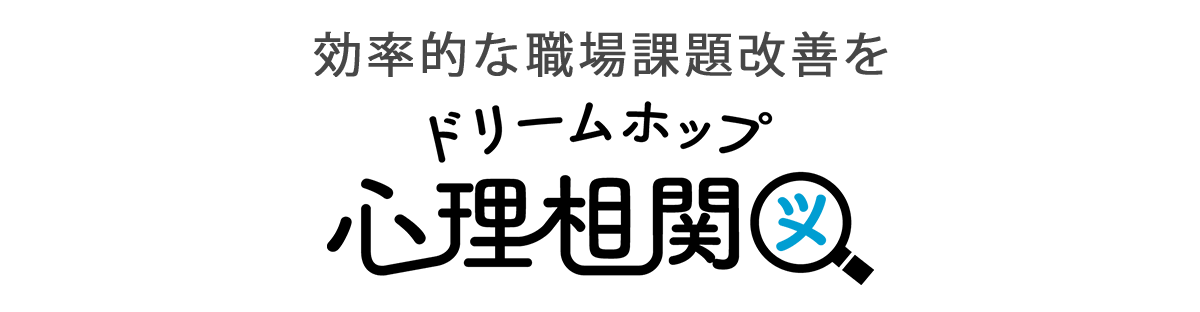産業医の職場巡視とは?目的・必要性・実施頻度・方法を徹底解説
更新日:2025/02/04

産業医による職場巡視は、従業員の健康を守り、生産性向上につながる重要な取り組みです。しかし、その目的や必要性、具体的な方法を理解していない担当者も多いのではないでしょうか。
本記事では、職場巡視の目的・必要性・実施頻度・方法から、業種別のポイント、職場巡視後の対応まで、網羅的に解説します。法令遵守はもちろんのこと、従業員の健康と安全を確保し、生産性の高い職場環境を構築するための具体的な方法を確認しましょう。
働きやすい職場をつくることで、離職率の低下など、経営面でも良い影響があらわれてきます。離職率の高さを改善したい方は、以下の資料もあわせてお役立てください。
職場巡視の基礎知識―目的と必要性

産業医の職場巡視は、労働安全衛生法および労働安全衛生規則(第15条)に基づく、従業員の健康障害を予防するための重要な活動です。単なる職場見学ではなく、医学的専門性に基づいた現状把握と予防措置こそが、職場巡視の真髄です。事業者は、産業医の職場巡視を円滑に進めるための協力体制を整え、その結果を職場環境改善につなげる必要があります。
【関連記事:産業医とは?役割・仕事内容・必要性・選び方などを徹底解説】
職場巡視の目的
職場巡視の目的は、大きくわけて以下の3つに集約されます。
- 職場環境のリスクアセスメント:職場環境における物理的、化学的、生物学的、そして心理社会的要因など、さまざまなリスクを評価し、健康障害発生の危険性を明らかにします。リスクの特定だけでなく、その程度や影響範囲の把握も重要です。粉じん、騒音、有害物質、温度、湿度、照度、感染対策、作業姿勢、人間関係など、多岐にわたる要素を綿密にチェックします。
- 従業員の健康状態の把握:従業員の作業状況や健康状態を観察し、潜在的な健康問題の早期発見に努めます。長時間労働や過重労働による疲労蓄積、VDT作業による眼精疲労や腰痛・関節痛・肩こり(筋骨系障害)、特定の作業による職業病の兆候などを見逃さないようにします。面談を通して、従業員の健康に関する悩みや不安を直接聞き取ることも重要です。ストレスチェックの結果も参考にしながら、個別の状況に応じた対応を検討します。
- 健康障害の予防と健康増進:リスクアセスメントと健康状態の把握に基づき、具体的な予防措置や健康増進のための施策を提案します。作業環境の改善、作業方法の見直し、健康教育の実施、メンタルヘルスケアプログラムの導入など、多角的なアプローチで健康障害の発生を予防し、従業員の健康増進を図ります。職場環境と従業員の健康状態を継続的にモニタリングし、改善策の効果検証を行うことも重要です。
これらの目的を達成することで、職場における健康障害を未然に防ぎ、従業員の健康と安全を守り、ひいては企業の生産性向上に貢献します。
【関連記事:【企業必見】ストレスチェックでわかる退職リスク!離職防止のための具体的な対策と活用事例】
職場巡視の内容
職場巡視では、以下の項目を中心に確認を行います。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 職場環境 |
|
| 作業内容 |
|
| 健康管理 |
|
これらの項目をチェックすることで、潜在的な問題を早期に発見し、適切な対策を講じることが可能になります。
ウェルビーイング経営における職場巡視の重要性
近年注目されているウェルビーイング経営においても、職場巡視は重要な役割を担います。ウェルビーイング経営とは、従業員の身体的、精神的、社会的な健康を促進し、働きがいのある環境を整備することで、企業の持続的な成長を目指す経営手法です。
【関連記事:ウェルビーイング経営の事例解説:日本でのウェルビーイング施策とは?】
職場巡視を通して、従業員の健康状態や職場環境の実態を把握することは、ウェルビーイング経営を実践するうえで不可欠な要素となります。具体的には、以下の点で職場巡視が貢献します。
- 従業員の健康状態の把握と課題の特定:職場巡視により、従業員の健康状態や職場環境における課題を具体的に把握することができます。従業員の健康リスクを低減し、健康増進を図るための対策を効果的に実施することが可能になります。
- 働きがいのある職場環境の整備:職場巡視で得られた情報に基づき、職場環境の改善や働き方改革を推進することで、従業員のワークエンゲージメントを高め、生産性向上につなげることができます。心理的安全性の確保やハラスメント対策も重要な要素です。
- 企業の持続的な成長への貢献:従業員の健康と幸福は、企業の持続的な成長にとって欠かせません。職場巡視を通して従業員のウェルビーイングを向上させることで、企業の業績向上やブランドイメージの向上がかないます。離職率の低下や優秀な人材の確保にもつながります。
職場巡視は、ウェルビーイング経営を実践するうえで欠かせないツールです。産業医は、専門的な知見に基づき、企業のウェルビーイング経営をサポートする重要な役割を担っています。
【関連記事:産業医の選任:基本と探し方、トレンドを解説】
職場巡視の実施頻度とタイミング

職場巡視は、労働安全衛生法により、毎月1回以上、条件を満たせば2ヶ月に1回以上実施することが義務付けられています。
2ヶ月に1回とするためには、事業者の同意と、衛生管理者による巡視結果などの情報提供が毎月必要となります。まずは最低限の基準である法定の頻度から確認しましょう。
法定要件
産業医は、原則として毎月1回以上の職場巡視を行わなければなりません。そのほか、衛生管理者も職場巡視を行います。
| 職場巡視実施者 | 実施頻度 |
| 産業医 | 毎月1回以上(条件を満たせば2ヶ月に1回以上) |
| 衛生管理者 | 毎週1回以上 |
そのほか、頻度の規定はありませんが、安全管理者も職場巡視を行うことがあり建設業ではさらに細かな規定があります。
産業医の職場巡視が2ヶ月に1回とできる条件は、「事業者の同意」と「産業医への情報提供」です。事業者から産業医に提供しなければならない情報は以下の3点です。
- 衛生管理者による職場巡視の結果
- 休職者・体調不良者の状況、ストレスチェックの集団分析結果など、衛生委員会からの情報
- 週40時間以上かつ1か月あたり100時間以上働いた労働者の氏名と時間外労働の時間
実情に合わせて調整する
法定要件は毎週1回以上ですが、職場の状況によってはさらに頻度を高めることや、確認のためにミーティングを行うことも望ましいでしょう。
事故・インシデントが起きやすい職場の場合
労働災害の発生リスクが高い職場では、より頻繁な職場巡視が必要です。建設現場や製造工場など、危険を伴う作業が多い職場では、事故やインシデントの発生状況を把握し、予防策を講じるために、2ヶ月に1回以上の頻度で産業医による巡視を行うことも検討しましょう。
事故の発生傾向や危険箇所の特定、安全対策の実施状況などを確認し、労働災害の未然防止に努めることが重要です。
高ストレス者が多い職場の場合
メンタルヘルス不調のリスクが高い職場では、従業員の精神的な健康状態を把握するため、職場巡視の頻度を高める必要があります。
ストレスチェックの結果を踏まえ、高ストレス者が多い部署や職種を重点的に巡視し、職場環境の改善や相談体制の強化など、適切な対策を講じることが重要です。また、長時間労働やハラスメントの発生状況なども確認し、必要に応じて個別面談などを実施することも効果的です。
【関連記事:職場環境改善の鍵!ストレスチェックで高ストレス者に対応するための3ステップ】
健康面で不安を抱える人が多い職場の場合
高齢者や持病のある労働者が多い職場では、健康状態の悪化を早期に発見し、適切な対応をするため、職場巡視の頻度を高める必要があります。
定期的な巡視を通じて、労働者の健康状態の変化や職場環境における健康リスクなどを把握し、必要な場合は産業医面談や医療機関への受診を勧めるなど、適切な対応を行うことが重要です。
職場巡視のタイミングは、事業者と産業医が協議のうえで決定します。業務の繁閑や、定期健康診断の実施時期なども考慮し、効率的かつ効果的な巡視計画を立てることが重要です。また、巡視の実施日時や場所、巡視内容などを事前に周知することで、従業員の協力を得やすくなり、より実効性の高い巡視につながります。
効果的な職場巡視の方法とチェックポイント

職場巡視では、働きやすい状況を維持するために環境面や健康面をチェックします。以下に挙げるのは各面に関する重要なポイントです。綿密なチェック項目と適切な基準値に基づいて実施することで、職場環境の改善と従業員の健康管理を効果的に進めることができます。
環境面のチェックポイント
企業内の労働環境に関する各種基準は、労働安全衛生法によって定められています。CO2濃度や気温をはじめとして、照明や採光の度合いなども、細かく数値の範囲が規定されているのです。これらは従業員の作業に適した基準であるため、範囲外の項目があれば調整の対象になります。また、気流や粉じんの量など、専門知識がなければ測定が難しい項目も少なくありません。したがって、衛生管理者との連携によって着実に巡視・測定を実施していくことが重要です。
さらに、職場が整理整頓され、安全で清潔に保たれているか点検することも忘れてはいけません。化学物質を扱わないから、工場ではないからといって無関係なものではないため、どの職場でも丁寧に確認しましょう。
具体的なチェック項目と基準値
| チェック項目 | 基準値 | 備考 |
|---|---|---|
| 室温 | 17℃~28℃ | 季節や作業内容によって調整が必要 |
| 湿度 | 40%~70% | 適切な湿度を維持することで、乾燥やカビの発生を抑制 |
| 照度 | 作業内容に合わせた適切な照度 | 適切な照度を確保することで目の疲れや作業効率の低下を防ぐ |
| 騒音 | 作業内容に合わせた適切な騒音レベル | 過度の騒音は、聴力障害やストレスの原因となる |
| CO2濃度 | 5,000ppm以下 (空気調和設備により調整が可能な場合には1,000ppm以下) |
換気を適切に行い、CO2濃度を低く保つ |
| 整理整頓 | 通路の確保、物の適切な配置 | 転倒や物の落下による事故を防ぐ |
| 清潔さ | ゴミや汚れの除去、定期的な清掃 | 衛生的な環境を維持することで、感染症などを予防 |
(参考:事務所衛生基準規則|eGov法令検索)
健康面のチェックポイント
職場巡視を行えば、従業員が働いている様子をチェックできます。部門長に残業や出張の状況を問えるので、産業医が職場の実態を把握する良い機会です。以前に実施したストレスチェックの結果などを整理しておくと、意見交換も効果的に行えるでしょう。
職場でパソコンが使われているなら、VDT作業についても確認が必要です。過度のVDT作業は、視力の悪化や腰痛など多くの悪影響を生じさせるため、問題の有無を入念に調べなければなりません。また、職場における喫煙のように、健康に害を及ぼす習慣も十分にチェックします。
パワハラやセクハラを受けて悩んでいる従業員がいないかヒアリングすることも大事です。メンタルヘルス不調の兆候を早期に発見し、適切な対応をすることが重要です。
具体的なチェック項目と注意点
| チェック項目 | 注意点 |
|---|---|
| 長時間労働の有無 | 過労死ラインを超える労働時間、残業時間の把握、休日出勤の頻度を確認 |
| VDT作業の状況 | 作業姿勢、休憩時間、目の疲れ、肩こり、腰痛などの症状を確認。 VDT作業に関するガイドラインを遵守しているか確認 |
| ハラスメントの有無 | パワハラ、セクハラ、マタハラなど、ハラスメントの有無を確認するためのヒアリングを実施 |
| メンタルヘルス | ストレスチェックの結果を踏まえ、メンタルヘルス不調の兆候がないか確認。 必要に応じて、産業医面談などを勧奨 |
| 職場環境の衛生状態 | 整理整頓、清潔さ、換気状況などを確認。 感染症予防対策が適切に行われているか確認 |
【関連記事:ストレスチェックと産業医の役割|企業のメンタルヘルス対策を徹底解説】
業種や職場の特徴別・職場巡視のポイント

業種によって、職場環境や従業員が抱えるリスクは大きく異なります。産業医は業種ごとの特性を理解し、重点的に確認すべきポイントを把握しておく必要があります。以下、業種の例をあげて職場巡視のポイントを解説します。
製造業の場合
製造業は、他の業種と比べて労働災害発生リスクが高い業種です。そのため、職場巡視では、機械の安全装置や保護具の着用状況、作業手順の遵守など、安全衛生管理体制を重点的に確認する必要があります。また、騒音、振動、粉塵、有害物質など、健康障害を引き起こす要因への対策も重要です。
危険機械作業の安全対策
製造業ではプレス機や工作機械など、危険な機械を扱う作業が多く存在します。産業医は、これらの機械の安全装置が適切に機能しているか、作業員が安全手順を遵守しているか、保護具を正しく着用しているかなどを確認する必要があります。また、機械の操作資格や教育訓練の実施状況についても確認することが重要です。
有害物質への曝露対策
製造業では、化学物質や粉塵、溶接ヒュームなど、さまざまな有害物質に曝露するリスクがあります。産業医は、作業環境における有害物質の濃度測定結果を確認し、適切な換気や保護具の着用など、曝露対策が適切に行われているかを確認する必要があります。
労働安全衛生法で定められた基準値を遵守しているかどうかも重要なチェックポイントです。化学物質の安全データシート(SDS)が整備され、従業員が容易にアクセスできるようになっているかも確認しましょう。
長時間労働・深夜業務への対策
製造業では、生産需要に応じて長時間労働や深夜業務が発生しやすい傾向があります。産業医は、労働時間管理の状況を確認し、過重労働による健康障害のリスクを評価する必要があります。
また、深夜業における健康管理や休憩時間の確保についても確認することが重要です。長時間労働や深夜業務に従事する従業員に対しては、面談や健康診断などを実施し、健康状態を把握することも重要です。必要に応じて、作業時間の調整や休憩時間の増加、労働環境の改善などを提案する必要があります。
卸・小売業の場合
卸・小売業では、立ち仕事や重量物の運搬による腰痛や、不規則な勤務時間による生活リズムの乱れ、顧客対応による精神的なストレスなどが問題となる場合があります。職場巡視では、これらの健康リスクを把握し、適切な対策がとられているかを確認する必要があります。
また、従業員の年齢層や男女比なども考慮し、それぞれの健康課題に合わせた対策を検討することが重要です。
身体的負荷軽減のための対策
長時間労働による疲労の蓄積は、健康障害を引き起こす大きな要因となります。産業医は、従業員の労働時間の実態を把握し、過重な労働負担がかかっていないかを確認する必要があります。とくに、長時間労働や深夜業に従事する従業員に対しては、健康診断などを実施し、健康状態を把握することが重要です。
産業医は、必要に応じて、作業時間の調整や休憩時間の増加、労働環境の改善などを提案します。
顧客対応によるストレスへの対策
顧客対応の多い職場では、クレーム対応や過度な要求などによる精神的なストレスを抱える従業員も少なくありません。産業医は、従業員のストレス状況を把握し、メンタルヘルス対策が適切に行われているかを確認する必要があります。
ストレスチェックの実施状況や、相談窓口の設置状況、休暇取得の推奨など、企業のメンタルヘルス対策全体を評価し、改善点を提案することが重要です。
【関連記事:EAP(従業員支援プログラム)を徹底解説!導入のメリット・デメリット、具体的な内容とは?】
感染症対策
小売業では、不特定多数の顧客と接するため、感染症対策が重要となります。産業医は、職場における感染症対策の状況を確認し、適切な対策がとられているかを確認する必要があります。
とくに、新型コロナウイルス感染症などの流行時には、最新のガイドラインに基づいた対策が実施されているかを確認し、必要に応じて助言を行うことが重要です。
運送業の場合
運送業では、長時間の運転による疲労や睡眠不足、事故のリスクなどが問題となります。職場巡視では、運転時間管理や休憩時間の確保、車両の安全点検など、安全衛生管理体制を重点的に確認する必要があります。
また、健康診断やストレスチェックの結果を踏まえ、個々のドライバーの健康状態に合わせた対策を検討することが重要です。
長時間運転による健康リスクへの対策
長時間運転は、ドライバーの疲労を蓄積させ、集中力の低下や居眠り運転につながる危険性があります。産業医は、運転時間管理の状況を確認し、法定の休憩時間や休息期間が適切に確保されているかを確認する必要があります。
また、ドライバーの健康状態を定期的に把握し、疲労の蓄積や睡眠不足の兆候が見られる場合は、適切な指導や助言を行うことが重要です。
| チェック項目 | 確認内容 |
|---|---|
| 運転時間管理 | 法定の運転時間、休憩時間、休息期間が遵守されているかを確認する。 運行記録計やデジタルタコメーターの記録などを確認する。 |
| 車両の安全点検 | 車両の定期点検、日常点検が適切に行われているかを確認する。 ブレーキ、タイヤ、ライトなどの状態をチェックする。 |
| 健康状態の把握 | 定期健康診断、ストレスチェックの結果を確認し、ドライバーの健康状態を把握する。 必要に応じて、面談や追加検査などを実施する。 |
| 安全教育の実施状況 | 安全運転に関する教育訓練が定期的に実施されているかを確認する。 交通ルール、運転技術、事故防止対策などに関する教育内容を確認する。 |
医療・福祉サービスの場合
医療・福祉サービス業では、感染症への曝露や腰痛、精神的なストレスなどが問題となります。職場巡視では、感染症対策や労働災害防止対策、メンタルヘルス対策など、多岐にわたる項目を確認する必要があります。
また、従業員の年齢層や職種なども考慮し、それぞれの健康課題に合わせた対策を検討することが重要です。夜勤を含む不規則な勤務体制の職場では、従業員の健康状態を継続的にモニタリングし、健康障害の早期発見に努める必要があります。
感染症対策の徹底
医療・福祉サービス業では、感染症への曝露リスクが高いため、徹底した感染症対策が求められます。産業医は、標準予防策の実施状況、個人防護具の着用状況、手指衛生の徹底など、感染症対策が適切に行われているかを確認する必要があります。また、感染症発生時の対応マニュアルが整備され、適切な対応が取れる体制が整っているかどうかも重要なチェックポイントです。
これらの業種以外にも、建設業やIT業界など、それぞれの業種に特有の健康リスクが存在します。産業医は、業種ごとの特性を理解し、職場巡視において重点的に確認すべきポイントを把握しておくことが重要です。
外国人労働者とともに働く場合
外国人とともにはたらくうえで、外国人労働者自身も、その他の従業員やマネージャーもストレスを抱える場合があったり、より安全管理に気を配らなければならなかったりします。産業医は、以下のような点についてとくに注意深く観察します。
- 外国人労働者にもわかりやすく手順や注意点が伝わっているか
- 事故やインシデントの発生が増えていないか、発生するケースに傾向はあるか
- お互いの文化を相互理解し、配慮する手立てがあるか
- 外国人労働者自身がストレスや困りごとを表現できているか
- すべての従業員のストレスの状況はどうか
職場巡視後の対応と改善策

職場巡視は、単に職場を見回るだけではなく、その後の対応と改善策までを含めて初めて効果を発揮します。巡視で見つかった課題を適切に処理し、職場環境の改善につなげることが重要です。
以下、職場巡視後の対応と改善策について、具体的なステップを踏まえて解説します。
早急に改善しなければならない点への対応
職場巡視で発見された問題点の中には、従業員の健康や安全に直結する緊急性の高いものも含まれます。たとえば、転倒の危険性がある場所、有害物質の漏洩、機器の故障などです。
これらの問題点は、速やかに対処しなければ、重大な事故や健康被害につながる可能性があります。早急な対応が必要な問題点については、その場で応急処置を行い、その後、恒久的な対策を講じる必要があります。たとえば、転倒の危険性がある場所には、すぐにバリケードを設置し、後日、床の補修などの工事を行うといった対応が考えられます。また、関係部署に迅速に報告し、連携して対応することも重要です。
課題の共有と改善計画の策定
職場巡視で発見された課題は、事業者・衛生管理者・産業医の間で共有し、改善計画を策定・実行する必要があります。巡視後速やかにミーティングを実施し、課題を共有することが望ましいでしょう。
ミーティングでは、巡視で発見された課題を一つずつ確認し、その原因と対策について議論します。原因の分析には、労働安全衛生法などの法令やガイドラインも参考にすると良いでしょう。
対策については、具体的な方法、実施時期、担当者、必要な予算などを明確に定めた改善計画書を作成します。改善計画書は、関係者全員で共有し、進捗状況を定期的に確認することが重要です。
具体的な改善計画の例
以下に、具体的な改善計画の例を挙げます。
| 課題 | 原因 | 対策 | 実施時期 | 担当者 | 予算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 事務所内のCO2濃度が高い | 換気が不十分 | 換気システムの導入 | 3ヶ月以内 | 施設管理部 | 100万円 |
| 倉庫内の照明が暗い | 照明器具の老朽化 | LED照明への交換 | 1ヶ月以内 | 施設管理部 | 50万円 |
| 製造ラインでの騒音が大きい | 防音対策が不十分 | 防音壁の設置 | 6ヶ月以内 | 製造部 | 200万円 |
外部機関活用とリスク管理
自社だけでは対応が難しい課題については、外部機関の活用を検討することも重要です。たとえば、専門的な知識や技術が必要な場合、あるいは、中立的な立場からの意見を求めたい場合などです。
外部機関としては、労働衛生コンサルタント、産業保健総合支援センター、労働基準監督署などが挙げられます。
また、職場巡視後の対応として、リスク管理も重要な要素です。残存リスクの洗い出しを行い、発生した場合の影響度や発生確率を評価し、優先順位をつけて対策を講じる必要があります。リスクアセスメントの実施や、緊急時対応マニュアルの作成なども有効な手段です。定期的な見直しを行い、変化する状況に合わせた対応が必要です。
職場巡視とその後の対応は、継続的なプロセスです。一度実施して終わりではなく、定期的に巡視を行い、課題を抽出し、改善策を実施し、効果検証を行うというPDCAサイクルを回すことが重要です。そうすることで、職場環境の改善を継続的に進め、従業員の健康と安全を守り、生産性の向上につなげられます。また、過去の職場巡視の結果や改善策を記録しておくことで、次回の巡視に役立てることができます。過去の記録を分析することで、新たな課題の発見や、より効果的な改善策の立案につなげることが期待できます。
職場巡視に加え、日頃から従業員の状況を把握するパルスサーベイを活用しておけば、大掛かりなコストをかけず、トラブルの早期発見・対処が可能です。
産業医の職場巡視で職場改善をスピードアップ

職場巡視は、ただ実施するだけでは意味がありません。巡視によって得られた情報を適切に分析し、具体的な改善策に落とし込み、実行していくことで、初めてその効果を発揮します。最後に、職場巡視を通して職場改善をスピードアップさせるためのポイントを解説します。
職場巡視結果の分析と共有
職場巡視で得られた情報は、まず整理・分析する必要があります。環境測定の結果や従業員からのヒアリング内容などを客観的に評価し、潜在的な問題点や改善の余地を探ります。
問題点を特定する際には、法令違反の有無だけでなく、従業員の健康や安全に影響を与える可能性のある要素にも注目することが重要です。分析結果は、事業者や衛生管理者、人事担当者など関係者と共有し、共通認識を持つことが重要です。
具体的な改善策の立案と実行
分析結果に基づいて、具体的な改善策を立案します。改善策は、実現可能性が高く、効果が期待できるものである必要があります。また、費用対効果も考慮し、優先順位をつけて取り組むことが重要です。
以下の表は、職場巡視でよくある問題点と、その改善策の例です。
| 問題点 | 改善策 | 期待される効果 |
|---|---|---|
| 長時間労働 | 業務の効率化、人員配置の見直し、ノー残業デーの設定 | 従業員の疲労軽減、メンタルヘルス不調の予防 |
| 職場環境の悪化(騒音、温度、照明など) | 設備の改善、レイアウト変更 | 作業効率の向上、健康障害の予防 |
| 人間関係の悪化 | コミュニケーション研修の実施、相談窓口の設置 | ハラスメントの防止、良好な職場環境の醸成 |
| VDT作業による健康障害 | 作業時間の管理、休憩時間の確保、適切な機器の導入 | 眼精疲労、肩こり、腰痛などの予防 |
立案した改善策は、速やかに実行に移すことが重要です。実行にあたっては、関係部署との連携を密にし、進捗状況を定期的に確認します。また、必要に応じて外部機関の支援も活用します。
効果測定と見直し
改善策を実行した後、その効果を測定し、評価することが重要です。効果測定は、客観的なデータに基づいて行う必要があります。
たとえば、長時間労働の改善策であれば、残業時間の推移を指標として用いることができます。効果が十分でなかった場合は、改善策を見直し、再度実行します。
職場環境は常に変化するため、定期的に職場巡視を行い、改善策を継続的に見直していくことが重要です。PDCAサイクルを回すことで、職場環境の改善を継続的に進めることができます。
産業保健スタッフとの連携
産業医は、職場巡視を通じて得られた情報を、産業保健スタッフ(公認心理師、保健師、看護師など)と共有し、連携して対応することが重要です。産業保健スタッフは、従業員の健康管理や健康相談など、日々の業務を通じて従業員の健康状態を把握しています。産業医は、産業保健スタッフからの情報も踏まえ、より効果的な改善策を立案することができます。
また、産業保健スタッフは、産業医が立案した改善策の実行を支援することもできます。産業医と産業保健スタッフが連携することで、より迅速かつ効果的な職場改善を実現することができます。
職場巡視は、職場環境改善の第一歩です。得られた情報を適切に活用し、具体的な改善策を実行することで、従業員の健康を守り、生産性の向上につなげましょう。