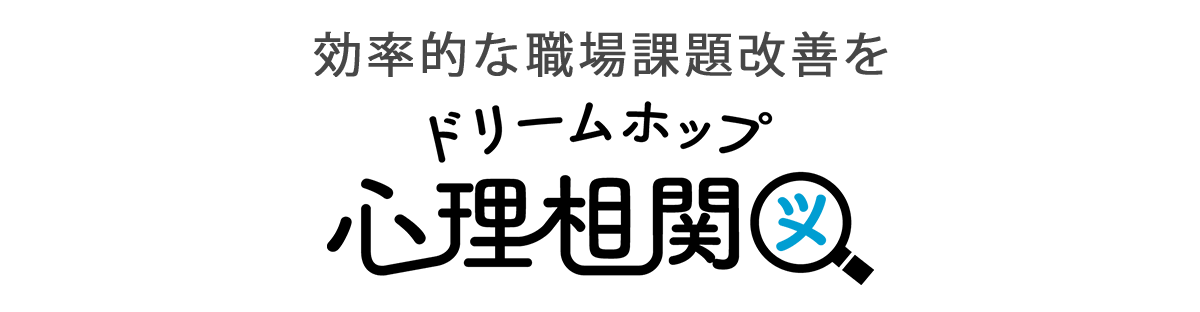産業医の選任:基本と探し方、トレンドを解説
公開日:2025/02/06
更新日:2025/02/10


産業医の選任は、企業にとって従業員の健康管理と生産性向上に不可欠な取り組みです。しかし、選任義務の基準や手続き、産業医の種類、探し方など、多くの疑問を抱えている担当者の方もいるのではないでしょうか。
本記事では、産業医選任の基本から探し方、最新のトレンドであるオンライン産業医まで、網羅的に解説します。労働安全衛生法に基づく選任義務の有無、嘱託産業医と専属産業医の違い、医師会や健診機関、産業医紹介サービスといった具体的な探し方、さらに顧問契約とスポット利用といった契約形態の違いを確認しましょう。
また、近年注目を集めるオンライン産業医のメリット・デメリットや導入時の注意点、今後の展望についても押さえておきたいポイントです。法令遵守はもちろんのこと、従業員の健康と企業の成長を支える適切な産業医選任を実現しましょう。
産業医とは?選任義務と役割

産業医とは、企業で働く従業員の心身の健康を守り、健康で快適な職場環境づくりをサポートする医師のことです。
労働安全衛生法に基づき、一定規模以上の事業場では産業医の選任が義務付けられています。選任を怠ると罰則(50万円以下の罰金)の対象となるため、必ず法令を確認してください。
【関連記事:産業医とは?役割・仕事内容・必要性・選び方などを徹底解説】
産業医選任の法的背景:労働安全衛生法ほか
産業医の選任義務は、労働安全衛生法によって定められています。この法律は、労働災害の防止と従業員の健康障害を予防し、快適な職場環境を形成することを目的としています。
労働安全衛生法第13条では、労働者の健康を保持するために必要な措置のうち具体的なものの一つとして、産業医の選任が挙げられています。
選任義務のある事業場の規模は、以下のとおりです。産業医の選任は企業単位でなく「事業場」単位となることに注意してください。
| 従業員数 | 産業医の種類 | 人数 |
|---|---|---|
| 50人以上999人以下 | 嘱託産業医もしくは専属産業医 | 1人 |
| 500人以上999人以下(有害業務を行う場合) | 専属産業医 | 1人 |
| 1000人以上3000人以下 | 専属産業医 | 1人 |
| 3001人以上 | 専属産業医 | 2人以上 |
なお、「有害業務」とは、粉じん、鉛、有機溶剤、特定化学物質、放射線を取り扱ったり、高温、低温、異常気圧等の環境下における業務を指します。
産業医の種類:嘱託産業医と専属産業医
産業医には、大きくわけて嘱託産業医と専属産業医の2種類があります。
嘱託産業医
嘱託産業医は、企業と契約を結び、月に1回程度、もしくは必要に応じて事業場を訪問し、従業員の健康管理を行います。
他の医療機関に勤務したり、開業医として活動したりしながら、産業医業務を兼任する医師もいます。専属産業医は原則として複数の企業の産業医を兼務できませんが、嘱託産業医の場合は複数の企業で兼務することも可能です。
専属産業医
専属産業医は、企業に常駐し、従業員の健康管理に専念します。大規模な事業場や健康リスクの高い職場において、より専門的で継続的な健康管理体制を構築するために設けられています。
従業員数が多い企業や健康障害リスクの高い業務を行う企業では、専属産業医の選任が義務付けられています。
産業医の主な業務内容
産業医の業務内容は多岐にわたりますが、主なものとしては以下のものがあります。
- 職場巡視:職場環境の確認や作業方法の観察を通して、労働災害や健康障害の発生リスクを評価します。
- 健康診断:健康診断結果に基づき、従業員への健康指導や必要な措置を勧告します。また、事業者に対して健康診断の実施方法や結果の分析について助言を行います。
- 面接指導:メンタルヘルス不調の兆候が見られる従業員や、長時間労働をしている従業員に対して、医師による面接指導を行います。必要に応じて、適切な医療機関への受診を勧めます。
- 健康教育:従業員に対して、健康増進や疾病予防に関する教育を実施します。生活習慣病予防、メンタルヘルス対策、過重労働対策など、さまざまなテーマで教育を行います。
- 作業環境測定:粉じん・鉛・特定化学物質などの有害物質を取り扱う職場では、作業環境測定を行い、従業員の健康への影響を評価します。
- 休職・復職支援:病気や怪我で休職した従業員の復職支援を行います。主治医と連携を取りながら、職場復帰に向けたサポートを提供します。
- 過重労働対策:長時間労働による健康障害を予防するため、労働時間管理や勤務体制の改善について事業者へ助言を行います。
- 衛生委員会への参加:事業場の衛生管理に関する事項を審議する衛生委員会に産業医として参加し、専門的な立場から意見を述べます。
【関連記事:産業医の職場巡視とは?目的・必要性・実施頻度・方法を徹底解説】
産業医を選任するメリット
産業医を選任することで、企業は以下のようなメリットを得ることができます。
- 労働災害・健康障害の予防:専門家による職場環境の評価や健康管理を通じて、労働災害や健康障害のリスクを低減できます。
- 生産性向上:従業員の健康状態が改善することで、欠勤や休職が減少し、生産性の向上が期待できます。
- 企業イメージ向上:従業員の健康に配慮した職場環境づくりは、企業イメージの向上につながります。
- 法令遵守:労働安全衛生法に基づく選任義務を果たすことで、法令遵守の姿勢を示すことができます。
- メンタルヘルス対策の強化:メンタルヘルス不調の早期発見・早期対応が可能となり、従業員のメンタルヘルス対策を強化できます。
- ウェルビーイング経営の実現:従業員の健康管理を経営戦略の一環として捉え、ウェルビーイング経営の実現に貢献します。
- 職場環境改善:産業医からの助言に基づき、職場環境を改善することで、より快適で安全な職場づくりが可能となります。
【関連記事:ウェルビーイング採用とは?企業と従業員の幸福度を高める戦略】
産業医の探し方:3つのルートを徹底解説

産業医の探し方には、大きく分けて以下の3つのルートがあります。
- 医師会に相談する
- 健診機関から紹介を受ける
- 産業医紹介サービスを利用する
それぞれ見ていきましょう。
医師会への相談:地域ネットワークを活用
各地域の医師会に相談する方法です。
医師会は地域医療の中核を担っており、多くの医師が所属しています。産業医の選任についても相談に乗ってくれる場合が多く、地域の医療事情に精通した医師を紹介してもらえる可能性があります。とくに、地方で産業医を探している場合、医師会が貴重な情報源となります。
メリット
- 地域に根ざした医師を紹介してもらえる。
- 地域医療の事情にくわしい医師を見つけやすい。
- 紹介手数料がかからない場合が多い。
デメリット
- 医師会によっては紹介サービスを行っていない場合もある。
- 紹介された医師との相性が合わない場合、変更を申し出にくい場合がある。
- 産業医業務に割ける時間が少ない医師もいる。
健診機関からの紹介:健康診断との連携
健康診断を実施している医療機関に産業医を紹介してもらう方法です。健診機関には、産業医資格を持つ医師が所属しているケースが多く、健康診断と産業保健の一体的なサービスを提供している場合もあります。健康診断の結果に基づいて、適切な健康指導やアドバイスを受けられるメリットがあります。
メリット
- 健康診断と産業保健を連携させやすい。
- 健康診断の結果を踏まえたアドバイスを受けられる。
- 一括して依頼することでコスト削減できる可能性がある。
デメリット
- 健診機関によっては産業医の紹介を行っていない場合もある。
- 日ごろの業務内容を把握してもらいにくい。
- 紹介された医師との相性が合わない場合、変更を申し出にくい場合がある。
産業医紹介サービス:専門家によるマッチング
産業医紹介サービスを利用する方法です。産業医紹介サービスは、企業のニーズに合わせて最適な産業医を紹介してくれます。
専門のコンサルタントが、企業の業種、規模、従業員の健康状態などを考慮し、経験豊富な産業医をマッチングします。また、契約手続きや料金交渉なども代行してくれるため、手間を省くことができます。産業医紹介サービスは近年増加しており、産業医を紹介するほかにもさまざまなサービスが提供されています。
メリット
- 企業のニーズに合った産業医を紹介してもらえる。
- 経験豊富な産業医を見つけやすい。
- 契約手続きや料金交渉などを代行してもらえる。
- 複数の候補者から比較検討できる。
デメリット
- 紹介手数料やサービス利用料などの費用がかかる。
| 探し方 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 医師会 | 地域に密着した医師を紹介してもらえる可能性が高い。 | 紹介サービスを行っていない医師会もある。 変更の申し出がしづらい場合も。 |
| 健診機関 | 健康診断と産業保健の連携がスムーズ。 | 日々の業務内容を把握しづらい。 変更の申し出がしづらい場合も。 |
| 産業医紹介サービス | 企業ニーズに合った医師を紹介。 手続き代行などサポートが充実。 |
費用がかかる。 |
それぞれの探し方にはメリット・デメリットがあります。自社の状況や希望に合わせて最適な方法を選びましょう。たとえば、費用を抑えたい場合は医師会への相談、健康診断との連携を重視するなら健診機関、迅速に産業医を見つけて経営面でもプラスの効果を期待したい場合は産業医紹介サービスの利用を検討するのが良いでしょう。
嘱託産業医とのかかわり方2タイプ

嘱託産業医との契約形態は、大きく分けて顧問契約とスポット利用の2種類があります。それぞれの特徴を理解し、自社のニーズに合った契約形態を選択することが重要です。
顧問契約
顧問契約は、毎月一定の契約料金を支払うことで、継続的に産業医サービスを受ける形態です。定期的な職場巡視、健康相談、衛生委員会への参加など、包括的なサポートを受けられます。顧問契約のメリット・デメリットは以下のとおりです。
| メリット | デメリット |
|---|---|
|
・継続的な関係構築による、企業の実情に合わせたきめ細やかな対応が可能 ・定期的な職場巡視による、潜在的な問題の早期発見 ・健康相談窓口の設置による、従業員の健康意識向上 ・緊急時の対応もスムーズ |
・毎月固定費が発生するため、費用負担が大きくなる場合も ・実際に利用するサービスが少ない場合、費用対効果が低いと感じることも |
産業医との顧問契約は、とくに従業員数が多い企業や規模が拡大傾向にある企業、すぐさま大掛かりな問題はなくても職場環境を整えていきたい場合などにおすすめです。
スポット利用(アラカルト産業医®)
スポット利用は、必要なサービスのみを都度依頼する形態です。
健康診断の実施、ストレスチェック後の面接指導、特定の健康相談など、必要なときに必要なだけ産業医サービスを利用できます。スポット利用のメリット・デメリットは以下のとおりです。
| メリット | デメリット |
|---|---|
|
・必要なときだけ利用できるため、費用を抑えられる ・特定の業務に特化した専門医を選べる ・顧問契約と比較して、契約手続きが簡素 |
・継続的な関係構築が難しいため、企業の実情を深く理解してもらう場合は顧問契約を検討したい ・緊急時の対応には限界がある ・サービス内容によっては、割高になる可能性も |
スポット利用は、まずはお試しで利用してみたいという企業や、特定の課題解決を目的としたピンポイントなサポートを受けたい企業におすすめです。
「アラカルト産業医®」という名称で、多様な業務から必要なものを選んで利用できるサービスもあります。
PCAグループの株式会社ドリームホップでは、産業医サービス「irodori」でアラカルト産業医®のサービスを行っています。そのほか、顧問契約のご相談も承っています。
オンライン産業医:これからの産業保健

2020年11月の厚生労働省の通達により、産業医による面接指導がオンラインでも可能になりました。これによって、場所や時間に縛られない柔軟な産業保健活動が可能となり、オンライン産業医への期待が高まっています。
本項では、オンライン産業医のメリット・デメリット、適切な実施方法、選任時の注意点、そして今後の展望について解説します。
(参考:情報通信機器を用いた労働安全衛生法第66条の8第1項、第66条の8の2第1項、第66条の8の4第1項及び第66条の10第3項の規定に基づく医師による面接指導の実施について|厚生労働省)
(参考:情報通信機器を用いた産業医の職務の一部実施に関する留意事項等について|厚生労働省)
オンライン産業医のメリット
オンライン産業医のメリットは多岐にわたります。
- 場所を選ばない:遠隔地や移動が困難な従業員でも容易に面接指導を受けられます。これは、地方の事業場や、複数の拠点を持つ企業にとって大きなメリットです。
- 時間の節約:移動時間や待機時間が削減され、従業員も産業医も時間を有効活用できます。これは、多忙な従業員や、限られた時間の中で多くの従業員をサポートする必要がある産業医にとってとくに重要です。
- 感染症対策:対面接触を減らすことで、感染症のリスクを低減できます。コロナ禍においてはとくに重要なポイントとなりました。
- コスト削減:産業医の交通費や出張費などのコストを削減できます。これは、とくに地方の事業場にとって大きなメリットとなります。
- 記録の容易さ:オンラインシステムを利用することで、面接指導の内容や記録を容易に管理できます。これは、健康管理の質の向上にもつながります。
オンライン産業医のデメリット
メリットが多い一方で、オンライン産業医にはデメリットも存在します。
- 通信環境:安定したインターネット環境が必要となります。通信環境が悪いと、円滑なコミュニケーションが難しくなり、適切な指導ができない可能性があります。
- 情報セキュリティ:個人情報の取り扱いには細心の注意が必要です。適切なセキュリティ対策を講じなければ、情報漏洩のリスクが高まります。
- 非言語情報の欠如:対面に比べて、表情や仕草などの非言語情報が伝わりにくい場合があります。これにより、従業員の微妙な変化を見逃してしまう可能性があります。
- ITリテラシー:従業員や産業医に一定のITリテラシーが求められます。オンラインシステムの操作に不慣れな場合、ストレスを感じたり、利用をためらったりする可能性があります。
- 緊急時対応:急な体調不良など、緊急時には対応が難しい場合があります。対面での迅速な対応が必要な状況も想定しておく必要があります。
自社の状況にあわせてオンライン産業医契約を検討しましょう。オンライン専門サービスや紹介サービスを利用すれば、ITに慣れた医師が対応してくれるだけでなく、従業員にとっても利用しやすいツールが用意されています。
オンライン面接指導の適切な実施方法
オンライン面接指導を適切に実施するためには、以下の点に留意する必要があります。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 環境 | 静かでプライバシーが確保された場所を選び、周囲の音や視覚的な情報にも配慮する。 |
| 機材 | 高画質・高音質のカメラとマイクを使用し、安定したインターネット回線を確保する。 |
| 事前の準備 | 事前にオンラインシステムの動作確認を行い、操作方法を熟知しておく。 |
| コミュニケーション | 表情や声のトーンに気を配り、丁寧に説明する。必要に応じて画面共有などを活用する。 |
| 記録 | 面接指導の内容を記録し、適切に管理する。 |
オンラインで産業医面談を行う場合は、スマホで利用できることや予約のしやすさも従業員にとって有益なポイントです。従業員・自社のニーズにあわせて適切な実施方法を検討しましょう。
オンライン産業医選任の際の注意点
オンライン産業医を選任する際には、以下の点に注意しましょう。
- 経験と実績:オンライン診療の経験や実績が豊富な産業医を選ぶことが重要です。オンラインでのコミュニケーション能力や、ITツールの利用状況なども確認しましょう。
- セキュリティ対策:個人情報保護の観点から、適切なセキュリティ対策がとられているかを確認しましょう。使用するシステムのセキュリティレベルや、データの保管方法などを確認することが重要です。
- サポート体制:オンラインシステムのトラブル発生時などに備え、迅速なサポート体制が整っているかを確認しましょう。緊急時の対応についても確認しておくことが大切です。
- 費用:オンライン産業医の費用体系を事前に確認しましょう。対面診療とは異なる料金設定となっている場合もあります。
今後のオンライン産業保健の展望
オンライン産業保健は、今後ますます発展していくと予想されます。AIやIoTなどの技術を活用した、より高度な健康管理システムの開発も進んでいます。たとえば、ウェアラブルデバイスで従業員の健康状態をリアルタイムでモニタリングし、異常を検知した場合には自動的に産業医に通知するシステムなどが考えられます。
また、オンライン面談だけでなく、健康相談やストレスチェックなどもオンラインで実施できるようになり、従業員の健康管理がより便利で効率的なものになっています。産業医ともストレスチェックの集団分析結果や高ストレス者の情報などを共有すれば、さらに従業員へのケアが行き届き、結果として働きやすい職場づくりに役立ちます。
技術の進歩とともに、新たな課題も出てくる可能性がありますが、オンラインで相談できることで確実に従業員のウェルビーイングは促進されます。情報セキュリティや倫理的な問題など、適切な対策を講じながら、オンライン産業保健のメリットを最大限に活かしていくことが重要です。
【関連記事:エンゲージメントとは?意味や種類、向上させるメリット・方法を解説】
適切な産業医選任でウェルビーイング経営を実現

適切な産業医を選任することは、従業員の健康管理だけでなく、企業の生産性向上やリスク管理、そしてウェルビーイング経営の実現に不可欠です。本記事では、産業医選任の法的背景、嘱託産業医と専属産業医の違い、医師会や健診機関、産業医紹介サービスといった探し方、顧問契約とスポット利用の比較、そして近年注目を集めるオンライン産業医のメリット・デメリットまでを解説しました。
企業規模や業種、従業員の健康状態などを考慮し、自社に最適な産業医の選任方法を選択しましょう。医師会や健診機関への相談、産業医紹介サービスの活用など、さまざまなルートがあります。とくに、時間や場所の制約を受けにくいオンライン産業医は、地方の中小企業などにとって有効な選択肢となり得ます。面接指導の適切な実施や情報セキュリティへの配慮を行いつつ、オンラインで産業医に相談できる機会を構築すると良いでしょう。
産業医との良好な関係構築も重要です。定期的な面談や情報共有を通じて、企業の健康課題を明確化し、効果的な健康経営施策を推進しましょう。適切な産業医選任は、従業員の健康増進、ひいては企業の持続的な成長につながる重要な投資です。