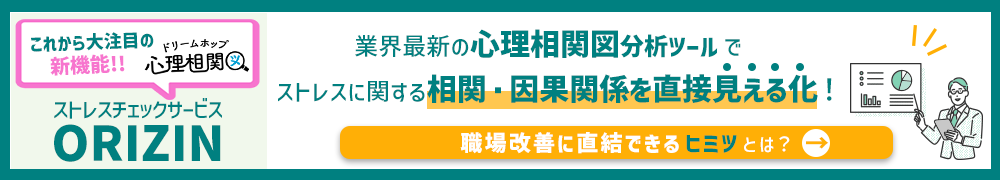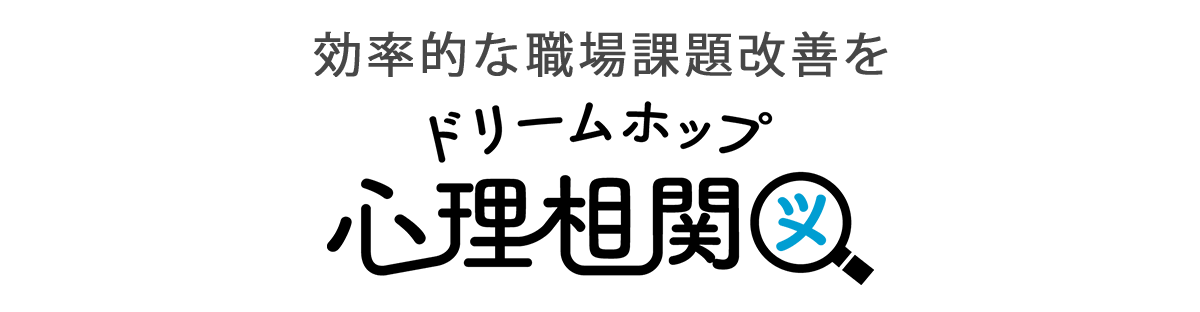ストレスチェック報告書の書き方・労基署への提出方法・提出期限を徹底解説!
更新日:2025/02/13


ストレスチェック制度に基づき、事業者は毎年1回、ストレスチェックの実施と結果に基づく報告書の提出が義務付けられています。本記事では、ストレスチェック報告書の書き方、労基署への提出方法、提出期限までを徹底解説します。
法令違反による罰則を回避することができます。本記事では、ストレスチェック報告書の入手方法から記入上の注意点、作成手順、提出期限、提出先(労基署)、提出方法まで、わかりやすく解説しています。報告書に記載すべき必須項目や報告書の様式入手方法、提出期限超過時の対応、電子申請の可否についても回答しています。
ストレスチェック報告書の作成・提出に関する疑問をお持ちの方はぜひ最後までご覧ください。
ストレスチェックについてわかりやすく解説した資料もご用意しています。あわせてお役立てください。
ストレスチェック報告書の提出義務

ストレスチェックの実施後、事業者はストレスチェック報告書(正式名称:心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書)を所轄の労働基準監督署へ提出する義務があります。この義務は労働安全衛生法によって定められており、対象となる事業者とそうでない事業者、そして提出義務違反に対する罰則が存在します。
提出義務のある事業者
常時50人以上の労働者を使用する事業者は、毎年1回以上ストレスチェックを実施し、その結果をまとめたストレスチェック報告書を提出する義務があります。「常時50人以上」とは、ストレスチェックを実施する月の末日時点において、常用雇用されている労働者数が50人以上に達している場合を指します。
以下の労働者は、常時使用する労働者数に含まれません。
- 名簿届出済みの派遣労働者
- 1週間の所定労働時間が、通常の労働者の4分の3未満である短時間労働者
- 海外勤務者等
また、派遣労働者(派遣社員)の場合、派遣元事業主が派遣労働者に対してストレスチェックを実施し、その結果を派遣先事業主に提供する必要があります。
提出義務のない事業者
常時使用する労働者数が50人未満の事業者には、ストレスチェック報告書の提出義務はありません。
ただし、従業員の健康管理の観点から、ストレスチェックを実施することは推奨されており、今後義務化される可能性が高まっています。少人数の事業場であっても、労働者のメンタルヘルス不調のリスクは存在するため、積極的にストレスチェック制度を活用することが重要です。
【関連記事:【企業必見】ストレスチェックでわかる退職リスク!離職防止のための具体的な対策と活用事例】
提出しない場合の罰則
ストレスチェック報告書の提出義務のある事業者が、正当な理由なく報告書を提出しない場合や、虚偽の内容を記載した報告書を提出した場合は、50万円以下の罰金が科せられる可能性があります(労働安全衛生法第120条の5)。
都道府県労働局長または労働基準監督署長は、報告書の提出を怠った事業者に対して、報告書の提出を命じることができます。
ストレスチェック報告書の提出は、労働者の健康管理と職場環境改善のために重要な役割を果たします。法令を遵守し、適切な手続きを行うようにしましょう。
【関連記事:ストレスチェックの受検を従業員に拒否されたら?受検率を高めるポイントを解説】
ストレスチェック報告書の作成方法
ストレスチェック報告書の作成は事業者の義務であり、正確な情報に基づいて作成する必要があります。
報告書の入手方法、記入上の注意点、そして具体的な作成手順を解説します。
報告書の入手方法
ストレスチェック報告書の様式は、以下の3つの方法で入手できます。
- 厚生労働省のWebサイトからダウンロード:厚生労働省のWebサイトには、ストレスチェック報告書の様式が掲載されています。ダウンロード後、印刷して使用することができます。
- 厚生労働省の入力支援サービスを利用:厚生労働省は、ストレスチェック報告書の作成を支援する入力支援サービスを提供しています。オンライン上で必要事項を入力し、作成した報告書をダウンロードできます。
- 報告書作成に対応したストレスチェックツールの利用:ストレスチェック後に報告書を自動で作成するツールを利用することで、ストレスチェックの準備・実施から報告に至る流れを大きく効率化できます。
ストレスチェックツール「ORIZIN」は、ストレスチェック実施後の報告書を簡単に作成・出力できる機能を備えています。
記入上の注意点
ストレスチェック報告書を作成する際には、以下の点に注意しましょう。
- 正確な情報の記入:報告書には、労働者数や面接指導を受けた労働者数など、正確な情報を記入する必要があります。誤った情報を記入した場合、法令違反となる可能性があります。
- 記入漏れがないようにする:記入漏れがあると、報告書が受理されない場合があります。すべての項目を丁寧に確認し、記入漏れがないようにしましょう。
- 適切な様式を使用する:厚生労働省が定める様式を使用するようにしてください。独自に作成した様式では、受理されない可能性があります。
- 印刷時の用紙:印刷する際は、白色度80%以上の用紙を使用してください。これは、報告書の読みやすさを確保するためです。
作成手順
ストレスチェック報告書の作成手順は以下のとおりです。
- 報告書の入手
- 必要情報の収集
- 報告書への記入
- 確認と提出
【報告書の入手】
前述の方法で、ストレスチェック報告書の様式を入手します。
【必要情報の収集】
報告書に記入するために必要な情報を収集します。具体的には、以下の情報が必要です。
- 労働保険番号
- 対象年
- 検査実施年月
- 事業の種類
- 事業場の名称・所在地
- 在籍労働者数
- 検査を受けた労働者数
- 面接指導を受けた労働者数
- 検査を実施した者
- 面接指導を実施した医師
- 集団ごとの分析の実施の有無
- 産業医の情報(氏名、所在医療機関、所在地)
【報告書への記入】
収集した情報をもとに、報告書の各項目に正確に記入します。
記入方法については後述します。
【確認と提出】
記入内容に誤りがないか確認した後、所轄の労働基準監督署へ提出します。提出方法には、e-Govによる電子申請、郵送、または直接持参があります。
正確かつ漏れのない報告書を作成し、提出期限内に提出しましょう。
ストレスチェック報告書の提出期限と提出先
ストレスチェック報告書の提出期限を過ぎると罰則の対象となる可能性があります。また、提出先を間違えると、再提出の手間が発生し、期限に間に合わなくなる可能性も出てきます。
提出期限と提出先について正しく理解しておきましょう。
提出期限
ストレスチェック報告書の提出期限は、法律で明確に定められていません。ストレスチェックの実施は毎年1回以上とされていますが、報告書の提出時期については、各事業所で自由に設定できます。
多くの企業は、事業年度の終了後や年度末などに合わせて提出しています。他の報告書と合わせて提出するケースもよくみられます。期限を社内で明確に定め、遅延なく提出することが重要です。
具体的な提出期限設定の例としては、以下のようなものが考えられます。
- ストレスチェック実施月の翌月末
- 事業年度の終了月の翌月末
- 毎年3月末
自社に合った提出期限を設定し、担当者間で共有することで、スムーズな提出業務を行うことができます。
提出先(労基署)
ストレスチェック報告書の提出先は、事業所を管轄する労働基準監督署です。管轄の労基署がどこになるかは、厚生労働省のWebサイトなどで確認できます。
提出方法
ストレスチェック報告書の提出方法は、大きく分けて以下の2種類があります。
| 提出方法 | 説明 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| e-Gov電子申請 | e-Govのシステムを利用してオンラインで提出する方法。 | 郵送や持参の手間が省け、申請状況を確認できる。 | 電子証明書が必要。 システム操作に慣れが必要。 |
| 郵送または持参 | 紙の報告書を郵送または労基署へ直接持参する方法。 | インターネット環境がなくても提出できる。 | 郵送費や持参のための時間が必要。 提出状況の確認が難しい場合がある。 |
どちらの方法で提出する場合でも、提出書類に不備がないか、提出期限内に提出できているかを最終確認することが重要です。
提出後に労基署から問い合わせがあった場合に備え、提出書類のコピーを保管しておきましょう。また、提出後に受領印や受付番号などを確認できる場合もあるので、保管しておくと安心です。
ストレスチェック報告書に記載する内容と書き方

ストレスチェック報告書の具体的な記載項目とそれぞれの書き方について、くわしく説明します。
| 項目 | 記入内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 労働保険番号 | 14桁の番号を記入 | 労働保険加入証明書等で確認 |
| 対象年 | ストレスチェックを実施した年 | 西暦で記入 |
| 検査実施年月 | ストレスチェックを実施した年月 | 複数月にわたる場合は最終月を記入 |
| 事業の種類 | 日本標準産業分類の中分類を選択 | 不明な場合は労働基準監督署に問い合わせ |
| 事業場の名称・所在地 | 事業場の正式名称と所在地 | 事業場ごとに報告書を作成 |
| 在籍労働者数 | 対象年月の末日現在の労働者数 | 短時間労働者・派遣労働者は含まない |
| 検査を受けた労働者数 | 実際に検査を受けた労働者数 | 複数回受けても1人とカウント |
| 面接指導を受けた労働者数 | 医師の面接指導を受けた労働者数 | |
| 検査を実施した者 | 医師、保健師等の氏名 | |
| 面接指導を実施した医師 | 面接指導を実施した医師の氏名 | |
| 集団ごとの分析の実施の有無 | 実施の有無を選択 | |
| 産業医の記名欄 | 産業医の氏名 | 事業者側で記名可能 |
| 事業者職氏名 | 事業者の職氏名 |
労働保険番号
事業場に割り当てられた14桁の労働保険番号を記入します。労働保険番号は、労働保険加入証明書や保険料申告書で確認できます。番号が不明な場合は、管轄の労働基準監督署に問い合わせましょう。
対象年
ストレスチェックを実施した対象年を西暦で記入します。ストレスチェックが年をまたいで実施された場合は、報告日(報告書の提出日)に最も近い実施対象年を記入します。
検査実施年月
ストレスチェックの検査を実施した年月を記入します。複数月にわたって検査を実施した場合は、検査が完了した最終月の年月を記入します。
事業の種類
事業内容を日本標準産業分類の中分類に合わせて選択し、記入します。自社の事業に該当する分類が不明な場合は、管轄の労働基準監督署に問い合わせることをおすすめします。
事業場の名称・所在地
ストレスチェックを実施した事業場の正式名称と所在地を記入します。本社だけでなく、支店や工場など、それぞれでストレスチェックを実施した場合は、事業場ごとに報告書を作成する必要があります。
在籍労働者数
ストレスチェックを実施した対象年の末日時点で、事業場に在籍する労働者数を記入します。短時間労働者(1週間の所定労働時間が通常の労働者の4/3未満の者)や派遣労働者は、この数に含めません。
検査を受けた労働者数
ストレスチェックの検査を実際に受けた労働者数を記入します。同じ労働者が複数回検査を受けていても、人数としては1人とカウントします。
面接指導を受けた労働者数
ストレスチェックの結果、医師による面接指導を受けた労働者数を記入します。
面接指導の実施有無にかかわらず、ストレスチェック実施後に報告書を提出する義務があります。
【関連記事:【担当者向け】ストレスチェック後の面接指導とは?注意点と流れも紹介】
検査を実施した者
ストレスチェックの検査を実施した者の氏名と資格を記入します。検査を実施できるのは、医師、保健師、または一定の研修を修了した看護師、精神保健福祉士などです。複数名で実施した場合は、全員の氏名と資格を記載します。
面接指導を実施した医師
面接指導を実施した医師の氏名を記入します。面接指導を実施した医師が複数名いる場合は、全員の氏名を記載します。
面接指導を受けた労働者がいない場合は、空欄で問題ありません。
集団ごとの分析の実施の有無
ストレスチェックの結果を、部署や職種などの集団ごとに分析したかどうかを記入(選択)します。
集団ごとの分析は、職場環境改善に役立つ貴重な情報源となり、今後集団分析の実施が義務化される可能性が高まっています。ストレスチェックツール「ORIZIN」とあわせて、集団分析を実施し、その結果から組織内のさまざまな因子の相関や各項目の因果関係をわかりやすく図示・可視化する「ドリームホップ心理相関図®」を活用すれば、ストレスチェックの準備・実施から職場改善までスムーズに進められます。
【関連記事:ストレスチェック集団分析結果の見方は?部署・年代・階層別の傾向と対策を解説】
産業医の記名欄
ストレスチェックの実施体制や結果について、産業医に確認を取り、記名します。産業医の氏名、所属医療機関名、所在地などを記入します。産業医の記名は、事業者側で行うことも可能です。
事業者職氏名
ストレスチェック報告書には、産業医の記名のほかに事業者の代表者氏名と、報告書作成責任者の氏名の記入が必要です。
これらの項目を漏れなく正確に記入することで、ストレスチェックの実施状況を適切に報告し、職場環境改善につなげられます。
よくある質問
ストレスチェック報告書の提出に関して、よくある質問をまとめました。
Q. 提出期限を過ぎてしまった場合はどうすれば良いですか?
ストレスチェック報告書の提出期限は、法令で定められた日付ではなく、各事業所で設定します。
万が一実施年度分の提出ができていないまま次年度を迎えた場合は、提出が遅れた理由を添えて、所轄の労働基準監督署に相談しましょう。悪質な場合は罰則の対象となる可能性がありますので、注意が必要です。
Q. 報告書の記載内容に誤りがあった場合はどうすれば良いですか?
報告書の記載内容に誤りがあった場合は、訂正した報告書を速やかに提出する必要があります。誤りを訂正した理由を明記し、所轄の労働基準監督署に相談しましょう。
Q. 労働者数が50人未満の場合は、報告書の提出は必要ですか?
常時使用する労働者数が50人未満の事業場について、2024年11月現在においてはストレスチェック報告書の提出義務はありません。
ただし、ストレスチェックの実施自体は推奨されています。少人数の事業場でも、労働者のメンタルヘルス対策に取り組むことが重要です。
Q. ストレスチェック報告書はどこに保管すれば良いですか?
ストレスチェック報告書は、検査結果等の記録と同様に、検査実施日から5年間保存しましょう。紛失や漏洩を防ぐため、適切な方法で保管することが重要です。
Q. ストレスチェック報告書の書き方の具体例はありますか?
厚生労働省によって、ストレスチェック報告書の記入例が公開されています。
参考:ストレスチェックの実施義務と報告書の記入・提出について|厚生労働省
Q. ストレスチェックの実施時期はいつが良いですか?
ストレスチェックの実施時期は法令で定められていません。自社の状況に合わせて、適切な時期に実施しましょう。
Q. 集団ごとの分析とは何ですか?
集団ごとの分析とは、部署や職種など、特定の集団におけるストレスの傾向を分析することです。集団分析を行うことで、職場環境の問題点を特定し、効果的な改善策を講じることができます。50人以上の事業場では、集団ごとの分析を行うことが推奨されています。
ストレスチェック報告書を正しく提出しよう
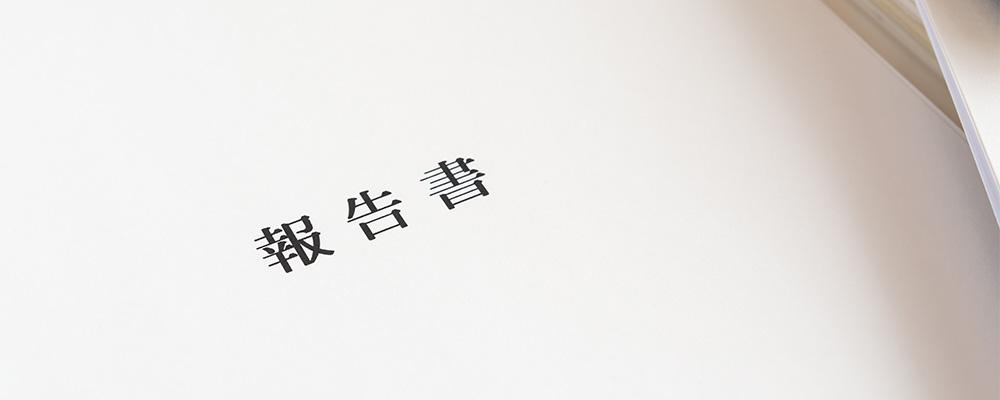
この記事では、ストレスチェック報告書の書き方、労基署への提出方法、提出期限について解説しました。ストレスチェック報告書の提出や内容は、労働安全衛生法によって義務付けられています。常時50人以上の労働者を雇用する事業者は、毎年1回、ストレスチェックを実施し、その結果を報告する必要があります。
ストレスチェックは実施して終わりではありません。報告書の提出を行うのはもちろんのこと、実施結果の集団分析を適切に行い、働きやすい職場づくりを実行に移すことこそが本来の目的にかなう動きです。
法令遵守の一歩先に進み、ストレスチェックを活かしながら、一人ひとりにとって働きやすく、パフォーマンスを最大化できる組織をつくりましょう。