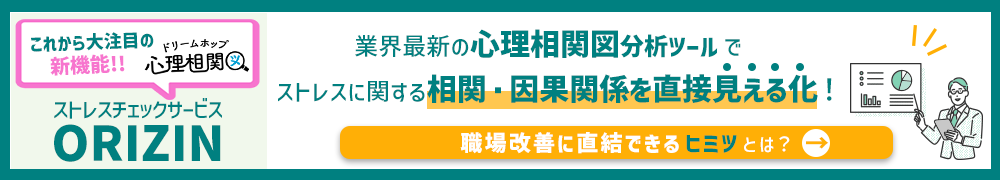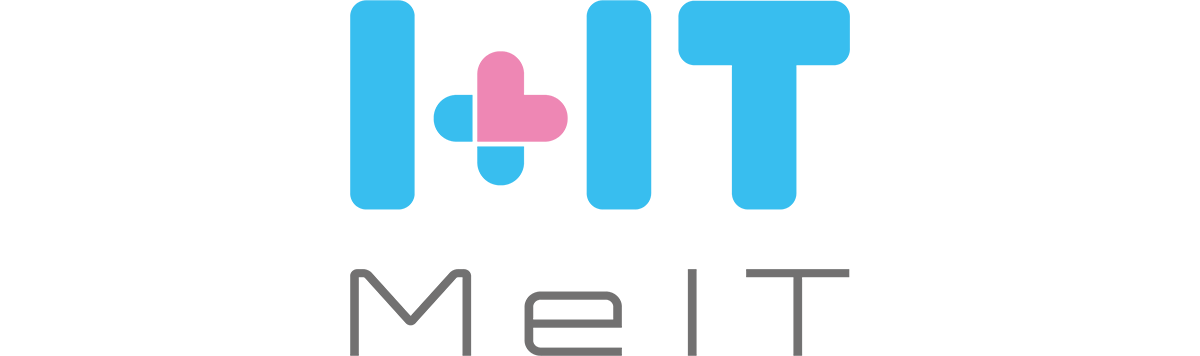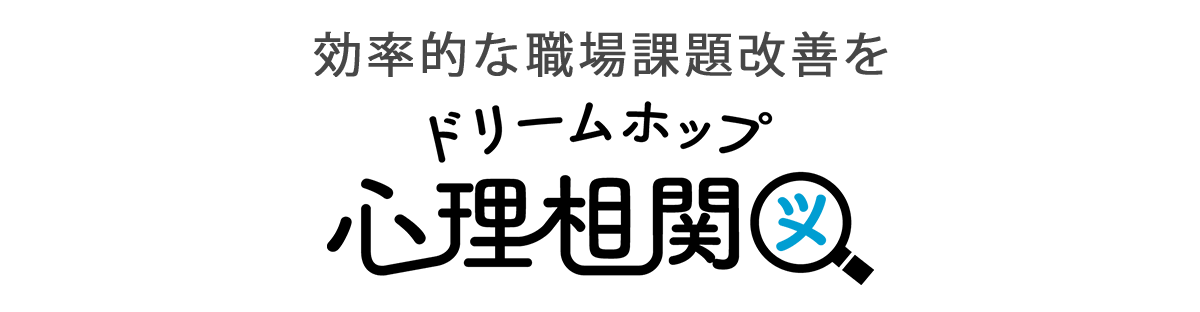ストレスチェック基本の「き」がわかる!導入手順・実施方法・注意点まとめ
更新日:2025/04/03

法令で義務付けられているストレスチェック制度は、従業員のメンタルヘルス不調を未然に防ぎ、健康的に働くための重要な取り組みです。しかし、制度導入にあたって「何から始めたら良いのかわからない」「具体的な手順が知りたい」と悩んでいる担当者の方もいるのではないでしょうか。
この記事では、ストレスチェックの基本を「き」から解説し、導入手順や実施方法、注意点などを網羅的にまとめました。法改正を踏まえ、50人未満の事業場における今後の義務化にも触れているので、まだ未導入の事業場の方も必ず最後までご覧ください。
ストレスチェックとは?
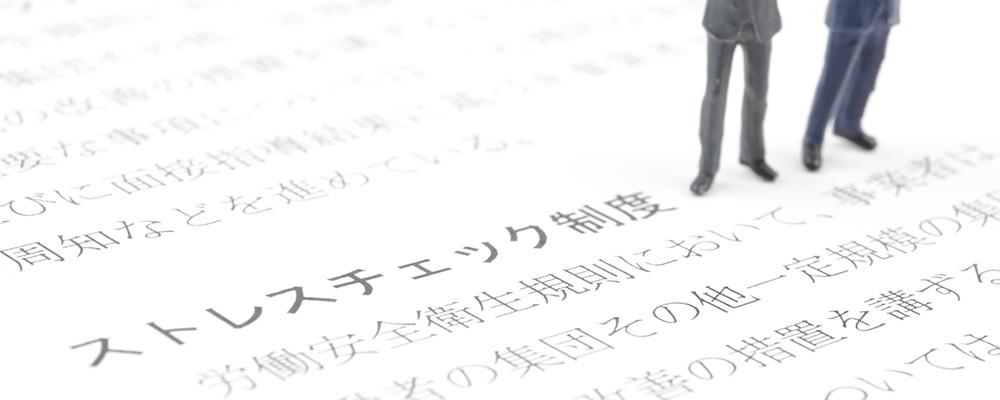
ストレスチェックとは、労働安全衛生法に基づき、職場における労働者のストレスの状況を把握するために行われる検査のことです。労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止し、健康的に働くことができる職場環境づくりを目的としています。質問票を用いて、自身のストレス状況を客観的に評価します。
ストレスチェックの定義と目的
ストレスチェックは、正式には「心理的な負担の程度を把握するための検査」と呼ばれ、労働安全衛生法第66条の10に規定されています。
職場におけるさまざまな要因によるストレスを評価し、その結果に基づいて必要な措置を講じることで、労働者のメンタルヘルス不調を予防・改善することを目的としています。単にストレスの度合いを測るだけでなく、職場環境改善につなげることが重要です。
ストレスチェックの目的は以下のとおりです。
- 労働者のストレス状況の把握
- メンタルヘルス不調の未然防止
- 健康的に働ける職場環境づくり
- 労働生産性の向上
ストレスチェックは、労働者自身のストレスへの気づきを促し、セルフケアの重要性を認識させる機会にもなります。また、事業者にとっては、職場環境の問題点を把握し、改善につなげるための貴重なデータとなります。
ストレスチェックでわかること
ストレスチェックでは、主に以下の項目について評価します。
| カテゴリ | 内容 |
|---|---|
| 仕事のストレス要因 | 仕事の量、質、人間関係、役割など、仕事に関連するストレス要因の評価 |
| 心身のストレス反応 | イライラ、不安、抑うつ、身体症状など、ストレスによる心身の反応の評価 |
| 周囲のサポート | 上司や同僚、家族など、周囲からのサポートの程度を評価 |
これらの項目に対する回答を分析することで、現在のストレスレベルやメンタルヘルス不調のリスクを把握することができます。ただし、ストレスチェックは診断ではなく、あくまでも自己申告に基づく評価であるため、医療機関での診断とは異なる場合があります。結果を参考にしつつ、自身の状態を客観的に見つめ直すことが大切です。
【関連記事:【企業必見】ストレスチェックでわかる退職リスク!離職防止のための具体的な対策と活用事例】
ストレスチェックの法的根拠
ストレスチェックは、労働安全衛生法に基づいて実施が義務付けられています。現在の規定では、常時使用する労働者が50人以上いる事業場では、年に1回以上、ストレスチェックを実施することとされています。
また、ストレスチェックの実施方法や結果の取り扱いについても、同法や関連する指針で定められています。
ストレスチェックの法改正で50人未満の事業場も対象に

ストレスチェック制度は、これまで常時50人以上の労働者を使用する事業場を対象としてきました。働く人々のメンタルヘルスの重要性が叫ばれるなか、「ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会」で議論が行われてきました。そして、2025年3月14日、ストレスチェックを50人未満の事業場でも義務とすることを含む、労働安全衛生法の改正の閣議決定がなされたのです。
メンタルヘルス不調の労働者が増加するなかで、より多くの労働者の健康を守るための重要な改正だと言えるでしょう。
【関連記事:50人未満の事業場におけるストレスチェック:実施するメリットと方法】
現状の義務対象:常時使用する労働者が50人以上いる事業場
現状では、常時使用する労働者が50人以上の事業場において、ストレスチェックの実施が義務付けられています。事業者は労働者の健康管理を適切に行う責任を負っているためです。50人未満の事業場でも実施することができます。
2025年3月14日の閣議決定
2025年3月14日、ストレスチェック制度が常時使用する労働者が50人未満の事業場にも義務化されることを含む、労働安全衛生法改正の閣議決定がありました。これにより、規模の大小を問わず、すべての事業場でストレスチェックの実施が義務付けられることになります。
| 事業場規模 | 現状 | 法改正以降 |
|---|---|---|
| 50人以上 | 義務 | 義務 |
| 50人未満 | 努力義務 | 義務 |
実際の法改正は2年以内を目処に行われる見込みです。50人未満の事業場においても、ストレスチェック制度導入の準備が必要です。制度の導入には、実施体制の構築、ストレスチェックツールの選定、従業員への周知など、さまざまな準備が必要です。
早めの準備を進めることで、スムーズな制度導入を実現し、従業員のメンタルヘルス対策を効果的に進められます。また、ストレスチェックの実施は、単に法律の遵守だけでなく、従業員の健康を守り、生産性を向上させるための重要な取り組みです。ストレスチェックを通じて、職場環境の改善につなげ、より働きやすい職場づくりを目指しましょう。
ストレスチェックの導入手順

ストレスチェックをスムーズに導入するために、準備段階から事後措置まで、段階的に解説します。それぞれのステップで何をするべきか、具体的な方法やポイントを把握しましょう。
準備段階
準備段階では、担当者を選定し、実施時期やツールを決定します。できるだけ具体的にロードマップを描きましょう。
担当者の選定
ストレスチェックの担当者は、従業員のプライバシー保護に関する知識を持ち、従業員との良好なコミュニケーションがとれる人物を選定することが重要です。
産業医や保健師、人事労務担当者などが適任です。複数名でチームを組む場合、役割分担を明確にしておきましょう。
実施時期の決定
ストレスチェックの実施時期は、繁忙期を避け、従業員が比較的落ち着いて受検できる時期を選ぶことが大切です。
また、定期健康診断の実施時期と合わせることで、従業員の負担を軽減できます。実施時期が決まったら、従業員に早めに周知し、協力を呼びかけましょう。
ストレスチェックツールの選定
ストレスチェックツールは、Webツールと紙媒体の2種類があります。
Webツールは集計作業が自動化され、効率的に実施できます。紙媒体はインターネット環境がない職場でも実施可能であることがメリットです。自社の状況に合わせて、適切なツールを選びましょう。
実施段階
実施段階では、従業員への周知、ストレスチェックの実施、集団分析を行います。正確なデータを得るため、適切な手順で実施しましょう。
従業員への周知
ストレスチェックの実施目的や方法、個人情報の保護について、従業員に事前に十分に説明し、理解と協力を得ることが重要です。実施前に説明会を開催したり、資料を配布したりするなど、丁寧な周知を心がけましょう。
ストレスチェックの受検は強制ではなく、任意であることを明確に伝えましょう。事前だけでなく実施後にも集団分析結果などの共有を行い、職場改善に向けた具体的な動きが感じられれば、従業員も進んで受検できるようになります。
【関連記事:ストレスチェックの受検を従業員に拒否されたら?受検率を高めるポイントを解説】
ストレスチェックの実施
ストレスチェックの実施にあたっては、プライバシーに配慮した環境を用意し、従業員が安心して受検できるよう配慮しましょう。
Webツールを使用する場合は、システムの動作確認を事前に実施し、トラブル発生時の対応策を準備しておきましょう。紙媒体を使用する場合は、回収方法や保管場所を明確にしておきましょう。
集団分析の実施
ストレスチェックの実施後、回答結果を集計し、集団分析を行います。
集団分析では、職場全体のストレス状況を把握し、職場環境改善に役立てるためのデータを得ることができます。分析結果は、個人情報が特定できないように加工し、職場改善のプロジェクトなどで活用しましょう。
【関連記事:ストレスチェック集団分析結果の見方は?部署・年代・階層別の傾向と対策を解説】
事後措置
事後措置として、高ストレス者への面接指導と職場環境改善を行います。ストレスチェックの結果を適切に活用し、従業員の健康管理につなげましょう。
高ストレス者への面接指導
高ストレス者には、医師による面接指導を勧奨します。面接指導では、ストレスの原因や対処法について相談し、必要に応じて医療機関への受診を勧めるなど、適切なサポートを行いましょう。
面接指導の実施にあたっては、プライバシーに配慮し、本人の同意を得ることが重要です。
【関連記事:職場環境改善の鍵!ストレスチェックで高ストレス者に対応するための3ステップ】
職場環境改善
集団分析の結果を踏まえ、職場環境の改善に取り組みましょう。長時間労働の是正、休暇取得の促進、コミュニケーションの活性化など、具体的な改善策を検討し、実行しましょう。
職場環境改善は、従業員のストレス軽減だけでなく、生産性向上にもつながります。継続的な改善活動が重要です。
ストレスチェックの実施方法

ストレスチェックの実施方法をWebツールと紙媒体の2種類に分けて説明します。それぞれの特徴を理解し、自社に合った方法を選択することが重要です。
Webツールを使った実施方法
Webツールを使ったストレスチェックは、近年主流となっている方法です。インターネットに接続できる環境があれば、いつでもどこでも実施でき、業務外の時間にプライベートを保ちながら回答できることも大きなメリットです。また、集計や分析も自動で行われるため、担当者の負担を軽減できます。
Webツール実施のメリット
- 実施場所を選ばない
- 集計・分析の自動化
- コスト削減
- 回答データの安全性が高い
Webツール実施のデメリット
- インターネット環境が必要
- ITリテラシーの低い従業員への配慮が必要
Webツール選定のポイント
- 法令対応は十分か
- セキュリティ対策は万全か
- サポート体制が充実しているか
- 費用は適切か
紙媒体を使った実施方法
紙媒体を使ったストレスチェックは、インターネット環境が整っていない場合や、ITリテラシーに不安のある従業員が多い場合に適しています。Webツールと比較して、導入コストが低い場合もありますが、集計や分析は手作業で行う必要があるため、担当者の負担が大きくなりやすいでしょう。
紙媒体実施のメリット
- インターネット環境が不要
- ITリテラシーが低い従業員でも受検しやすい
紙媒体実施のデメリット
- 集計・分析に時間がかかる
- 回答用紙の管理が必要
- コストがかかる場合がある
ストレスチェックの実施にかかる時間
ストレスチェックの実施(回答)にかかる時間は、使用する質問票の種類や設問数によって異なりますが、おおむね数分~数十分程度です。実施時間は、従業員の負担にならないよう、適切に設定することが重要です。休憩時間を利用して実施したり、実施時間を複数回に分けたりするなどの工夫も有効です。
ストレスチェックの注意点

ストレスチェックは従業員のメンタルヘルス対策として重要な役割を果たしますが、適切に実施されなければ、かえって従業員の不安を増大させたり、個人情報保護の観点で問題が生じたりする可能性があります。実施に際しては、以下の注意点に留意することが不可欠です。
個人情報の保護
ストレスチェックで得られた情報は、個人の健康状態に関する極めてセンシティブな情報です。そのため、個人情報保護法に基づき、厳重な管理体制を構築する必要があります。具体的には、以下の点に注意が必要です。
- アクセス制限:ストレスチェックの結果にアクセスできる担当者を限定し、パスワード管理などを徹底する。
- 保管場所のセキュリティ:結果を保管する場所のセキュリティ対策を強化し、不正アクセスや紛失を防ぐ。
- 情報伝達のセキュリティ:結果を伝える際には、メールの誤送信などに注意し、安全な方法で伝達する。
- 従業員への周知:個人情報の取り扱いについて、従業員に事前に十分に説明し、理解と同意を得る。
個人情報保護委員会のガイドラインなどを参考に、適切な対策を講じることが重要です。
ストレスチェック結果の取り扱い
ストレスチェックの結果は、従業員の健康状態を把握するための重要な指標となりますが、結果のみで判断するのではなく、従業員との面談などを通して、状況を総合的に判断することが重要です。また、以下の点にも注意が必要です。
- 結果のフィードバック:従業員には、本人にのみ結果をフィードバックし、他の従業員や上司に見られないように配慮する。
- 結果に基づく不適切な対応の禁止:ストレスチェックの結果を昇進・昇格、人事異動、解雇などに利用することは禁止。
- 集団分析の目的:集団分析は、職場環境の改善点を把握するために行うものであり、個人の特定につながらないよう注意する。
不適切な実施によるリスク
ストレスチェックを不適切に実施すると、さまざまなリスクが生じる可能性があります。主なリスクは以下のとおりです。
| リスク | 内容 |
|---|---|
| 従業員の不安増大 | 強制的な実施や結果の不適切な利用により、従業員の不安や不信感を増大させる可能性 |
| 個人情報漏洩 | 適切なセキュリティ対策を講じなければ、個人情報が漏洩するリスクがある |
| ハラスメントの発生 | ストレスチェックの結果を理由としたハラスメントが発生する可能性がある |
| 職場環境の悪化 | ストレスチェックが形骸化し、職場環境の改善につながらなければ、かえって職場環境が悪化する可能性がある |
これらのリスクを回避するためには、実施体制の整備、従業員への丁寧な説明、適切な結果の取り扱いが重要です。
実施後のフォローアップの重要性
ストレスチェックを実施しただけでは、従業員のメンタルヘルス対策は完了しません。実施後のフォローアップこそが重要です。具体的には、以下の点に注意します。
- 高ストレス者への面接指導:高ストレス者には、医師による面接指導を勧奨し、必要な場合は適切な支援につなげる。
- 職場環境改善:集団分析の結果を踏まえ、職場環境の改善策を検討し、実施する。
- 継続的な支援:ストレスチェックは一度実施すれば終わりではなく、継続的に実施し、従業員のメンタルヘルス状態を把握し、必要な支援を提供することが重要。
心配ならツールを導入する
これらの注意点をカバーしやすいのが、ストレスチェックツールの利用です。
たとえば、ストレスチェックツール「ORIZIN」では、受検勧奨や状況確認も担当者画面から簡単にでき、メールの誤送信などのリスクを軽減できます。
具体的な内容を閲覧できる従業員をアカウントで限定できるため、ストレスチェックの結果管理の安全性も確保でき、労基署への報告まで一貫して対応可能で事務処理の負担感も大幅にカットできるでしょう。
ストレスチェックで使用する質問票

ストレスチェックでは、労働者のストレス状態を把握するために質問票が用いられます。この質問票は、厚生労働省が定めた基準に基づいて作成されており、心身の健康状態や職場環境に関する質問が含まれています。適切な質問票を選択・活用することで、効果的なストレスチェックを実施し、労働者の健康管理につなげることが重要です。
質問票の種類と特徴
よく知られているストレスチェックの質問票には、主に以下の3種類があります。
| 種類 | 特徴 |
|---|---|
| 職業性ストレス簡易調査票(57項目) | 57問で構成され、ストレスの状態を簡潔に把握できます。短時間で実施できるため、多くの事業場で利用されています。 |
| 職業性ストレス簡易調査票(80項目) | 職業性ストレス簡易調査票(57項目)に、新職業性ストレス簡易調査票の推奨尺度セット短縮版(23項目)が加わっており、より具体的な情報がわかります。集団分析の精度向上にもおすすめです。 |
| 職業性ストレス簡易調査票(簡略版23項目) | 仕事内容やストレスの自覚、職場環境に特化した質問がコンパクトにまとまっています。簡単な現状把握に活用できます。 |
これらの質問票以外にも、事業場の特性や労働者の状況に合わせてカスタマイズされた質問票を使用することも可能です。「ORIZIN」のように、ストレスチェックツール内で自由に質問を作成できるケースもあります。
質問票の設問例
ストレスチェックの質問票には、さまざまな設問が含まれています。いくつか例を見てみましょう。
心身の健康状態に関する設問
- 最近、気分が落ち込むことが多い。
- 最近、イライラすることが多い。
- 最近、よく眠れない。
- 最近、疲れやすいと感じる。
- 最近、食欲がない。
職場環境に関する設問
- 仕事の内容にやりがいを感じている。
- 自分の能力を活かせる仕事だと感じている。
- 上司や同僚との人間関係は良好である。
- 職場の雰囲気は良い。
- 仕事とプライベートのバランスが取れている。
これらの設問は、労働者のストレス状態を多角的に評価するために設計されています。また、回答結果を分析することで、職場におけるストレス要因を特定し、職場環境改善につなげることが重要です。
高ストレス者への面接指導

ストレスチェックの結果、高ストレス者と判定された従業員に対しては、医師による面接指導を勧奨することが事業者に義務付けられています。この面接指導は、従業員のメンタルヘルス不調を早期に発見し、適切な対応をするための重要なプロセスです。従業員のプライバシーに配慮しながら、丁寧に進めていく必要があります。
【関連記事:ストレスチェックと産業医の役割|企業のメンタルヘルス対策を徹底解説】
面接指導の目的
面接指導の主な目的は、以下のとおりです。
- ストレスの原因や状況の把握
- 従業員の現在の心身の健康状態の確認
- 必要な場合は、医療機関への受診勧奨や就業上の措置に関する助言
- 職場環境改善への示唆を得ること
面接指導は、従業員が安心して話せる環境で行われることが重要です。秘密保持を徹底し、従業員が安心して自分の状況を話せるように配慮する必要があります。
面接指導の方法
面接指導は、産業医や医師、保健師などによって行われます。実施方法は以下のとおりです。
- ストレスチェック結果に基づいて、高ストレス者と判定された従業員に面接指導を勧奨する。
- 従業員が面接指導を希望した場合、日時や場所などを調整する。
- 面接指導では、ストレスの原因や状況、現在の心身の健康状態などを丁寧にヒアリングする。
- 必要に応じて、医療機関への受診を勧奨したり、就業上の措置(休職、配置転換など)について助言したりする。
- 面接指導の内容は記録し、プライバシーに配慮して適切に管理する。
面接指導は、一方的な指導ではなく、従業員との対話を通じて行うことが大切です。従業員の気持ちに寄り添い、共感しながら話を聞くことで、信頼関係を築き、より効果的な面接指導を行うことができます。
医師による面接指導の勧奨
事業者は、高ストレス者と判定された従業員に対し、医師による面接指導を勧奨する義務があります。
ただし、従業員が面接指導を希望しない場合、強制することはできません。その場合でも、事業者は、改めて面接指導の重要性を説明し、医師との面接を促す努力をすることが求められます。
| 勧奨の方法 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 書面による勧奨 | ストレスチェックの結果と医師による面接指導の勧奨を記載した書面を交付する。 | 自社に合う適切な書面を作成する。 |
| 口頭による勧奨 | ストレスチェックの結果を伝え、医師による面接指導の必要性を説明する。 | 勧奨の内容を記録に残しておく。 |
従業員が医師による面接指導を受けた場合、医師は事業者に対して、面接指導の結果に基づいて、就業上の措置に関する意見を提出することができます。事業者は、医師の意見を尊重し、従業員の健康状態に配慮した適切な措置を講じる必要があります。ただし、医師の意見を強制的に実施する義務はありません。最終的な判断は、事業者が行います。
【関連記事:中小企業の「産業医がいない」問題を解決!費用を抑えた導入方法と注意点】
職場環境改善

ストレスチェック後の職場環境改善は、従業員の健康を守り、生産性を向上させるうえで非常に重要です。高ストレス者への個別対応だけでなく、職場全体の環境を見直し、改善していくことが求められます。具体的な改善策を検討し、実行していくことで、より働きやすい職場づくりを進めましょう。
職場環境改善の重要性
ストレスチェックの結果を分析し、職場におけるストレス要因を特定し、適切な対策を講じることで、従業員のメンタルヘルス不調を予防し、健康で安全な職場環境を構築することができます。
また、職場環境の改善は、従業員のモチベーション向上や生産性向上にもつながり、企業全体の業績向上にも貢献します。
具体的な改善策
職場環境改善にはさまざまなアプローチがありますが、大きく分けて以下の3つの視点から対策を検討することが効果的です。
作業管理
過重労働や長時間労働を是正し、適切な作業分担、作業手順の見直し、休憩時間の確保など、作業管理の改善に取り組みましょう。業務量の適正化や、業務プロセスの効率化も重要です。
また、テレワークやフレックスタイム制など、柔軟な働き方を導入することも有効な手段です。
| 課題 | 具体的な改善策 |
|---|---|
| 長時間労働 | ノー残業デーの設定、業務効率化の推進、労働時間管理システムの導入 |
| 過重労働 | 業務量の適正化、人員配置の見直し、業務分担の明確化 |
| 休憩時間の不足 | 休憩時間の確保を徹底、休憩スペースの整備 |
人間関係
良好な人間関係を築けるよう、コミュニケーションの活性化、ハラスメント対策、相談しやすい雰囲気づくりなどを推進しましょう。管理職向けの研修や、チームビルディング研修なども有効です。また、相談窓口の設置や、外部相談機関の導入も検討しましょう。
職場内の風通しの良さを向上させることで、ストレスの軽減につながります。
| 課題 | 具体的な改善策 |
|---|---|
| ハラスメント | ハラスメント防止研修の実施、相談窓口の設置、社内規定の整備 |
| コミュニケーション不足 | 社内イベントの開催、コミュニケーションツールの導入、1on1ミーティングの実施 |
| 人間関係のトラブル | 早期発見・早期対応、関係者へのヒアリング、適切な仲裁 |
【関連記事:エンゲージメントとは?意味や種類、向上させるメリット・方法を解説】
職場環境(物理的環境)
働きやすい環境作りのためには、職場環境の整備も重要です。温度、湿度、照明、騒音、換気などに意識を向け、快適な作業空間を提供しましょう。整理整頓された清潔な環境を維持することも大切です。
また、在宅勤務環境の整備支援なども検討しましょう。快適な物理的環境は、従業員の集中力向上やストレス軽減につながります。
| 課題 | 具体的な改善策 |
|---|---|
| 騒音 | 防音対策、静かな作業スペースの確保 |
| 照明 | 適切な明るさの照明器具の設置 |
| 温度・湿度 | 空調設備の整備、適切な温度・湿度の維持 |
法令対応から職場改善まで対応できるストレスチェックツールORIZIN

この記事では、ストレスチェックの基本について、導入手順、実施方法、注意点などを中心に解説しました。ストレスチェックは、労働安全衛生法に基づき、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防ぐための重要な取り組みです。常時使用する労働者が50人以上の事業場は義務化されていますが、2025年3月14日の閣議決定により、将来的には50人未満の事業場にも義務化される見通しです。
ストレスチェックを効果的に実施するためには、担当者の選定、実施時期の決定、ストレスチェックツールの選定など、綿密な準備が必要です。実施後は、高ストレス者への面接指導や職場環境改善などの適切な事後措置が不可欠です。個人情報の保護やストレスチェック結果の適切な取り扱いなど、注意点も遵守しなければなりません。適切に実施することで、職場環境の改善や生産性の向上につながるだけでなく、従業員の健康を守ることにもつながります。ぜひ、この記事を参考に、ストレスチェック制度の導入・運用を検討してみてください。