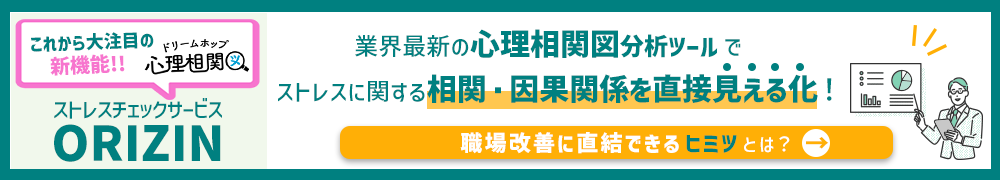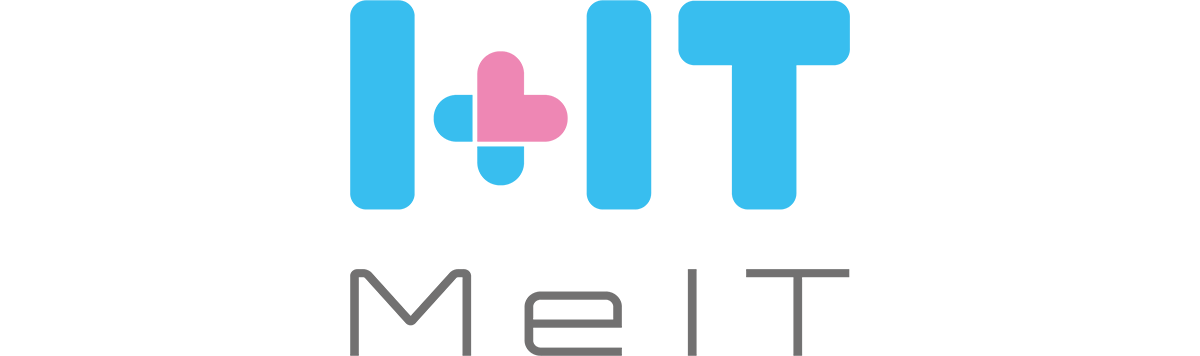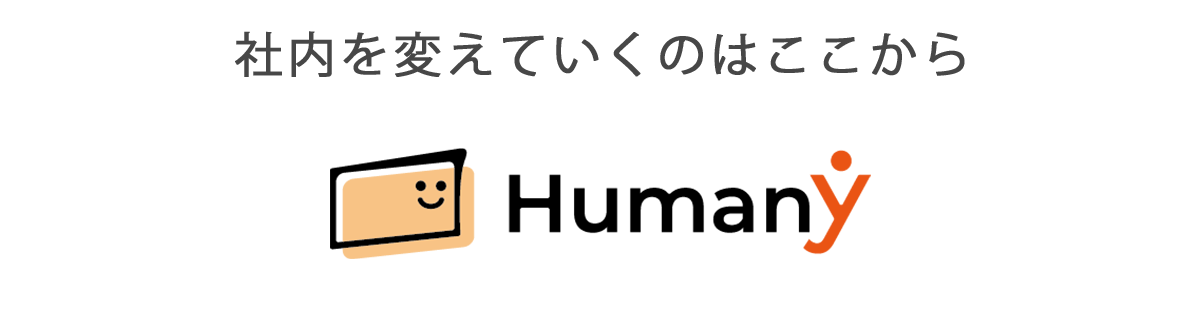50人未満の事業場におけるストレスチェック:実施するメリットと方法
公開日:2023/05/09
更新日:2025/03/03

50人未満の事業場におけるストレスチェックの実施義務化はまだですが、メンタルヘルス対策の重要性が高まる中、実施を検討する企業が増えています。
この記事では、50人未満の事業場がストレスチェックを実施するメリット・デメリット、実施方法、法的な位置づけ、最新の動向までを網羅的に解説します。とくに、50人未満の事業場ならではの注意点や、産業医選任義務との関係性、プライバシー確保の重要性についてもくわしく説明します。
ストレスチェック導入の必要性や、適切な実施方法を理解し、従業員の健康を守りながら生産性向上を実現するための第一歩を踏み出せるでしょう。規模が小さくても、適切なストレスチェック実施体制を構築することで、大きなメリットを得ることができます。
ストレスチェックとは?

ストレスチェックとは、労働安全衛生法に基づき、労働者のストレスの状況について検査を行うものです。本人に結果を通知して自らのストレスへの気づきを促し、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させるとともに、職場環境の改善につなげるための制度です。
ストレスチェックの定義と目的
ストレスチェック制度は、労働安全衛生法第66条の10に規定されています。正式名称は「心理的な負担の程度を把握するための検査等」で、一般的に「ストレスチェック」と呼ばれています。50人以上の労働者を雇用する事業場では、年に1回、労働者に対してストレスチェックの実施が義務付けられています。
ストレスチェックの主な目的は以下のとおりです。
- 労働者のストレスへの気づきを促す
- メンタルヘルス不調の未然防止を図る
- 職場環境改善につなげる
ストレスチェックは、労働者自身のストレス状況を客観的に把握する機会となるだけでなく、事業者にとっては職場環境の問題点を把握し、改善策を講じるための重要なツールとなります。
【関連記事:メンタルヘルス×組織開発で生産性向上!企業の成長を促す最強戦略】
ストレスチェックの法的な位置づけ(50人未満事業場の場合)
労働安全衛生法では、50人未満の労働者を雇用する事業場においては、ストレスチェックの実施は義務ではありません。しかし、努力義務とされており、厚生労働省は実施を推奨しています。また、50人未満の事業場であっても、職場環境によってはストレスチェックの実施が必要となるケースもあります。
近年、従業員数の少ない事業場でもストレスチェックが実施されることが増えており、メンタルヘルス対策の重要性が高まっていることを示しています。
事業場規模とストレスチェックの実施率
厚生労働省の調査をもとに、事業場(事業所)規模別のストレスチェック実施率をまとめました。
| 事業所規模 | 実施率 |
|---|---|
| 50人未満 | 34.6% |
| 50~99人 | 74.5% |
| 100~299人 | 91.7% |
| 300~499人 | 97.5% |
| 500~999人 | 99.2% |
| 1000人以上 | 99.9% |
なお、50人未満の事業場(事業所)についてさらに細かく区分した実施率は以下のとおりです。
- 10~29人:33.1%
- 30~49人:41.8%
事業場規模が大きくなるにつれて、ストレスチェックの実施率が高くなる傾向が見られます。これには、大規模事業場ほど、労働安全衛生法の遵守意識が高いだけでなく、安全衛生に関するしくみを設けやすいことが関係していると考えられます。人的・経済的リソースが充実しており、組織的なメンタルヘルス対策を行いやすいのです。
一方で、50人未満の事業場では実施率が高くはないものの、実施するケースが増加傾向にあります。メンタルヘルス対策への関心の高まりがうかがえます。
【関連記事:ストレスチェックの受検を従業員に拒否されたら?受検率を高めるポイントを解説】
50人未満の事業場においてもストレスチェック義務化の流れ

従業員50人未満の事業場におけるストレスチェックは、現在、法的義務ではなく努力義務とされています。しかし、近年、メンタルヘルス対策の重要性が高まる中で、50人未満の事業場においてもストレスチェックを義務化すべきかどうかの議論が活発に行われています。義務化に向けた流れと現状、今後の展望について解説します。
厚生労働省検討会の議論
厚生労働省では、「ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会」を複数回開催し、50人未満の事業場へのストレスチェック義務化についても議論が重ねられています。検討会では、小規模事業場の実態を踏まえ、実施体制の確保や費用負担などの課題についても検討されています。
(参考:ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会|厚生労働省)
検討会では、ストレスチェックの効果について学術的な効果検証が行われました。「ストレスチェックの実施に加え、結果の集団分析及び職場環境改善の取り組みによって、労働者の心理的ストレス反応の改善等が見られた」、すなわち、ストレスチェックと集団分析を行い、職場改善を行うことは、従業員のストレスケアにつながると確認されたのです。
そのため、十分な支援体制の整備等を図ったうえで、「ストレスチェックの実施義務対象を50人未満の全ての事業場に拡大することが適当」とされ、ゆくゆくは義務化される流れであると考えられます。積極的にストレスチェックを行えるよう議論がなされています。
50人未満の事業場(事業所)では産業医の選任も義務ではない(努力義務)
50人未満のほとんどの事業場では、産業医の選任も義務ではなく、努力義務となっています。ストレスチェックの実施に際しては、医師による面接指導が必要となる高ストレス者への対応が課題となります。
産業医の選任が努力義務である50人未満の事業場では、外部機関への委託などを活用することで、高ストレス者への適切な対応が可能になり、従業員がより積極的にストレスチェックを受けやすく、本音を吐き出しやすくなると考えられます。
【関連記事:ストレスチェックと産業医の役割|企業のメンタルヘルス対策を徹底解説】
【関連記事:中小企業の「産業医がいない」問題を解決!費用を抑えた導入方法と注意点】
プライバシー確保のため、ストレスチェック外部委託を推奨
上記の検討会でも、50人未満の事業場では、従業員数が少ないため、個人情報保護の観点から、ストレスチェックを外部機関に委託することが推奨されています。
小規模の事業場(事業所)においては、プライバシー保護のために「外部委託を推奨する」という指摘もあり、受検時や回収時、集計時において外部機関やツールを活用することによる配慮を行うことが望ましいといえます。
適切なツールを用いることや外部委託によって、実施事務の負担軽減だけでなく、プライバシー保護の徹底、専門家による客観的な分析と助言を受けることが可能となります。
50人未満の事業場におけるストレスチェック義務化は、まだ決定事項ではありませんが、避けられないものと考えられます。
従業員の健康管理は企業にとって重要な責務です。義務化の流れを注視しつつ、従業員のメンタルヘルス対策に積極的に取り組むことが重要です。
「事業場」と「企業」の違い―ストレスチェック制度の注意点

ストレスチェック制度において、「事業場」と「企業」は異なる概念です。この違いを理解していないと、制度の運用で思わぬミスにつながる可能性があります。50人未満の事業場の場合、とくに注意が必要です。
事業場=企業(法人)ではない
法律上、「事業場」とは、一定の場所で事業を行う場所を指します。一方、「企業」は、事業を行う主体を指し、多くの場合、株式会社や合同会社などの法人組織を意味します。一つの企業が複数の事業場(本社・工場・支店など)を持つこともあれば、一つの事業場だけで運営される企業もあります。
ストレスチェック制度は、事業場単位で実施することが求められています。そのため、企業規模が大きくても、事業場ごとに従業員数が50人未満であれば法律上の実施義務はありませんが、現実には企業内で人事異動があり得たり、全社的な人事計画を立てたりするために、小規模の事業場についてもストレスチェックが行われるのが一般的です。
前傾のストレスチェック実施率に関する統計を「企業規模ごと」「事業場(事業所)規模ごと」に見てみましょう。
| 企業規模 | 実施率 |
|---|---|
| 10~29人 | 10.6% |
| 30~49人 | 16.1% |
| 事業所規模 | 実施率 |
|---|---|
| 10~29人 | 33.1% |
| 30~49人 | 41.8% |
事業場(事業所)規模別でみた場合に比べ、企業規模別でみた場合は実施率が低くなっています。上記のとおり、50人以上の規模の事業場を抱える企業の小さな事業場については、全社的な動きに合わせてストレスチェックを行う傾向があり、そのために統計上の実施率が引き上げられていることが推測されます。
本社・本店に加え、営業所・支店・支社・工場などを持つ企業の場合は、ストレスチェックを実施するのがスタンダードになってきていると考えても良いでしょう。
ストレスチェックは法人単位で実施のしくみを揃えておく
事業場単位で実施義務の有無が決まるストレスチェックですが、前述のとおり、組織全体で統一した実施体制を構築しておくことが望ましいでしょう。これは、従業員の異動や事業規模の変動に対応しやすく、また、企業全体のメンタルヘルス対策を効果的に進めるうえで重要となります。
法人規模が大きくても事業場規模が小さいケース
たとえば、全国に複数の支店を持つ企業の場合、各支店がそれぞれ50人未満の事業場だったとしても、法人全体でストレスチェック実施のためのルールや手順を統一しておくことで、効率的な運用が可能になります。ストレスチェックツールの選定、実施時期、高ストレス者への対応方法などを、全社的に統一することで、混乱を防ぎ、スムーズな実施につながります。
法人規模・事業場規模ともに小さいケース
従業員数が少なく、事業場も一つだけの小規模企業の場合でも、将来的に事業規模が拡大する可能性を考慮し、あらかじめストレスチェックの実施体制を整えておくことが重要です。
また、小規模企業であっても、従業員のメンタルヘルス対策は重要です。ストレスチェックを導入することで、従業員のメンタルヘルス不調の早期発見・予防につながり、結果的に生産性向上や離職率低下といった効果が期待できます。
従業員のメンタルヘルス不調の早期発見・予防
ストレスチェックの最大の目的は、従業員のメンタルヘルス不調の早期発見・予防です。50人未満の事業場では実施義務はありませんが、従業員の健康を守り、より良い職場環境を作るためには、ストレスチェックの実施を検討することが重要です。
以下の表は、事業場規模別のストレスチェック実施状況と、実施によるメリット・デメリットをまとめたものです。
| 事業場規模 | ストレスチェック実施義務 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| 50人以上 | 義務 | 法令遵守、組織的なメンタルヘルス対策が可能、従業員の健康管理の意識向上、生産性向上、離職率低下、企業イメージ向上 | 実施費用、時間、労力の負担(ツールでで労力を下げて実施可能) |
| 50人未満 | 努力義務(義務化の可能性大) | 従業員のメンタルヘルス不調の早期発見・予防、生産性向上、離職率低下、企業イメージ向上、経営基盤の安定・向上 | 実施費用、時間、労力の負担(ツールでで労力を下げて実施可能) |
50人未満の事業場では、費用や時間などの負担を軽減するために、簡単に操作・実施できるストレスチェックツールを利用するなどの工夫も可能です。従業員の状況に合わせて、最適な方法を選択しましょう。
50人未満の事業場がストレスチェックを実施する3つのメリット

現在は努力義務であるといっても、50人未満の事業場でもストレスチェックを実施することには多くのメリットがあります。ここでは、主なメリットを3つご紹介します。
メリット1:小さな事業場ほど影響が大きい、従業員の抱えるストレスへの早期対処
従業員数が少ない事業場では、一人ひとりの従業員が担う役割や責任が大きくなる傾向があります。そのため、一人が休職や退職に至った場合の影響は、大規模事業場に比べて深刻です。また、少人数であるがゆえに、人間関係のトラブルや仕事の負担の偏りなどが発生しやすく、従業員のストレスを増大させる可能性があります。
ストレスチェックを実施することで、従業員のストレス状態を早期に把握し、適切な対策を講じることが可能になります。これにより、休職や退職の予防、ひいては事業の安定的な運営につながります。
前掲の厚生労働省の調査でも、メンタルヘルス不調により退職した労働者数の割合は、事業場の規模を問わずほぼ一定です。しかしながら、小規模事業場の場合、退職者が発生することのインパクトはきわめて大きくなります。このことからも、小規模事業場におけるストレスチェックの重要性がうかがえます。
(参考:令和5年 労働安全衛生調査(実態調査)|厚生労働省)
メリット2:生産性向上と離職率低下
ストレスチェックによって従業員のストレス要因を特定し、職場環境の改善や個別のケアを行うことで、従業員のモチベーション向上、ひいては生産性向上につながることが期待できます。
また、従業員が安心して働ける環境を作ることは、離職率の低下にもつながります。とくに、優秀な人材の確保が難しい昨今、既存の従業員の定着は事業継続において重要な要素です。ストレスチェックは、従業員満足度を高め、離職防止につなげるための有効なツールと言えるでしょう。
【関連記事:【企業必見】ストレスチェックでわかる退職リスク!離職防止のための具体的な対策と活用事例】
メリット3:企業イメージの向上と社会的責任の履行
従業員の健康管理に積極的に取り組む企業姿勢を示す「ウェルビーイング経営」は、企業イメージの向上につながります。ストレスチェックを実施することは、従業員の健康と安全を重視する企業であることを対外的にアピールする効果があります。
ウェルビーイング経営は、優秀な人材の採用や取引先との良好な関係構築にもプラスに働きます。また、ストレスチェックの実施は、企業の社会的責任(CSR)を果たすうえでも重要な取り組みです。従業員の健康を守り、働きやすい環境を提供することは、企業の責務と言えるでしょう。
| メリット | 詳細 |
|---|---|
| 従業員満足度の向上 | 安心して働ける環境が提供されることで、従業員の満足度が向上する。 |
| 優秀な人材の確保 | 健康経営に力を入れている企業として認知され、優秀な人材の確保に有利に働く。 |
| 投資家からの評価向上 | ESG投資の観点からも、従業員の健康管理に積極的に取り組む企業は高く評価される。 |
| 企業価値の向上 | 企業イメージの向上は、企業全体の価値向上につながる。 |
近年、ESG投資の観点からも、従業員の健康管理に積極的に取り組む企業は高く評価されています。ストレスチェックの実施は、企業の持続的な成長に不可欠な要素と言えるでしょう。
【関連記事:ウェルビーイング経営の事例解説:日本でのウェルビーイング施策とは?】
【関連記事:ウェルビーイング採用とは?企業と従業員の幸福度を高める戦略】
50人未満の事業場がストレスチェックを実施する方法

従業員のメンタルヘルス対策としてストレスチェックを行うメリットは大きく、推奨されています。ここでは、50人未満の事業場がストレスチェックを実施するための具体的な方法をステップごとに解説します。
ストレスチェック実施手順
ストレスチェックの実施手順は以下のとおりです。それぞれのステップで考慮すべきポイントをくわしく見ていきましょう。
- 計画策定:ストレスチェックの実施時期、対象者、実施方法(紙実施またはWeb実施)、予算、担当者などを検討します。実施時期は業務の繁忙期を避け、対象者は正社員、契約社員、パート、アルバイトなど、雇用形態に関わらず就業しているすべての労働者が含まれることを確認しましょう。
- 実施事務の検討:ストレスチェックの実施で必要なことを洗い出し、事務作業の必要な部分を確認します。ここで作業にかかる時間を見積もっておき、最終的な実施方法やツールについての検討に活かしましょう。すべて手作業で行った場合の残業代等を考慮し、ツール導入の可能性があれば稟議の用意を始めます。
- ストレスチェックツールの選定:ストレスチェックツールは、厚生労働省が定めた基準を満たしている必要があります。実施方法やスマホ対応など、事業場の状況に合ったツールを選びましょう。
- 周知・説明:ストレスチェックの実施目的、実施方法、個人情報の保護等について、従業員に事前に周知・説明を行いましょう。実施への協力を得られるよう、ストレスチェックの意義を丁寧に説明することが重要です。
- 実施:選択したツールを用いて、ストレスチェックを実施します。実施にあたっては、プライバシーに配慮した環境で行うことが重要です。未実施の従業員への受検勧奨のしやすいツールを選んでおきましょう。
- 集計・分析:回答結果を集計・分析します。集団分析によって、職場環境の問題点を把握することができます。集計・分析には通常多くの時間がかかるため、集計や集団分析に対応したツールを選ぶのがおすすめです。
- 結果通知:高ストレス者と医師による面接指導が必要と判断された労働者には、速やかに結果を通知します。ストレスチェックの結果は本人にのみ通知され、事業場には集団的な分析結果のみが提供されます。
- 面接指導:高ストレス者で医師による面接指導を希望する労働者には、面接指導を実施します。面接指導の結果、就業上の措置が必要と医師が認めた場合は、事業者に対して意見を述べます。
- 職場環境改善:集団分析の結果を参考に、職場環境の改善に取り組みます。長時間労働の是正、ハラスメント対策、コミュニケーションの活性化など、具体的な対策を検討・実施しましょう。
【関連記事:職場環境改善の鍵!ストレスチェックで高ストレス者に対応するための3ステップ】
【関連記事:ストレスチェック集団分析結果の見方は?部署・年代・階層別の傾向と対策を解説】
ストレスチェックツール選定のポイント
ストレスチェックツール選定のポイントは、以下のとおりです。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 厚生労働省の基準適合 | 厚生労働省が定めた基準を満たしているか確認しましょう。 |
| 質問項目数 | どのような設問で構成されているか、選択したツールの妥当性を検討しましょう。自社独自の質問を作成できる機能があれば、自社特有の事情をあぶり出すこともできます。 |
| 実施方法 | Webツール、紙媒体など、事業場の状況に合った実施方法を選択しましょう。Webツールの場合は、社外でも実施できるものやスマホ対応しているものを選べば、小規模事業場だからこそ守りたいプライバシーに配慮できます。 |
| 費用 | ツール費用、実施費用、分析費用など、全体的なコストを考慮しましょう。 |
| サポート体制 | ツール提供事業者のサポート体制を確認しましょう。操作方法の問い合わせ、結果分析のサポートなど、充実したサポート体制があると安心です。 |
| 多言語対応 | 外国人労働者がいる場合は、多言語対応のツールも検討しましょう。 |
高ストレス者への対応
高ストレス者への対応は、以下の点を踏まえて行うことが重要です。
- プライバシー保護:高ストレス者のプライバシーに配慮し、結果の取り扱いには十分注意しましょう。結果を本人にのみ通知し、事業場には集団的な分析結果のみを提供します。
- 面接指導の勧奨:高ストレス者には、医師による面接指導を勧奨します。面接指導は、労働者の健康状態を把握し、必要な措置を検討するために重要な機会です。
- 就業上の措置:医師の意見を踏まえ、就業上の措置が必要な場合は、労働者と相談の上、適切な措置を講じます。休職、配置転換、作業内容の変更など、労働者の健康状態に配慮した対応が必要です。
- 相談窓口の設置:高ストレス者だけでなく、すべての労働者が気軽に相談できる窓口を設置しましょう。産業医、人事担当者、外部相談機関など、複数の相談先を用意することで、より安心して相談できる環境をつくることができます。
50人未満の事業場でも、これらの手順とポイントを踏まえることで、効果的なストレスチェックを実施し、従業員のメンタルヘルス対策を推進することができます。ストレスチェックの実施は、従業員の健康を守り、生産性を向上させるだけでなく、企業イメージの向上にもつながります。ぜひ、積極的に取り組んでいきましょう。
【関連記事:プレゼンティーズムで損をするのは誰?企業と従業員双方を守るための対策】
50人未満の事業場でもいち早くストレスチェック導入を

50人未満の事業場におけるストレスチェック実施について、そのメリット、方法、法的な位置づけなどを解説しました。
ストレスチェックは、従業員50人以上の事業場では義務ですが、50人未満の事業場では努力義務とされています。しかし、厚生労働省の検討会では、50人未満の事業場への義務化も議論されており、今後の動向に注意が必要です。
規模の小さな事業場では、従業員のストレスが事業全体に与える影響が大きいため、メンタルヘルス対策はとくに重要です。ストレスチェックの実施は、生産性向上や離職率低下、企業イメージ向上につながり、結果として企業の成長に貢献します。実施方法は、ストレスチェックツールの選定、実施手順、高ストレス者への適切な対応などが重要です。ツールを活用することで、プライバシー保護や専門的な対応をスムーズに行うことができます。
50人未満の事業場でも、従業員の健康を守り、より良い職場環境をつくるために、ストレスチェックの実施を積極的に検討しましょう。