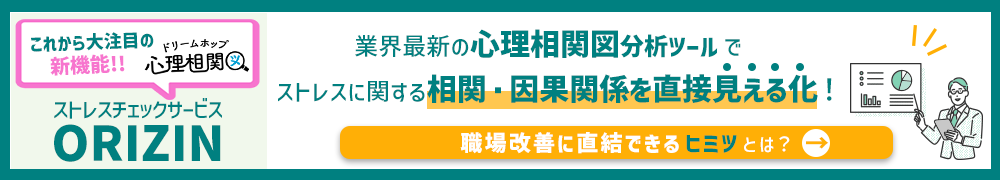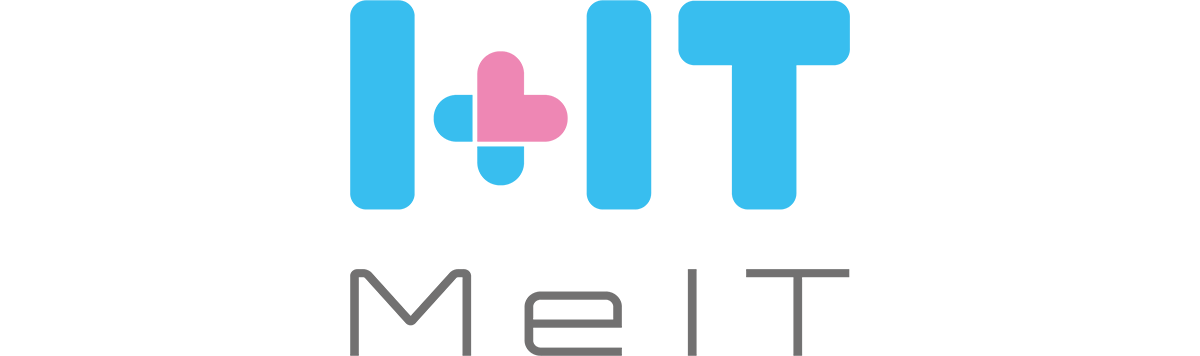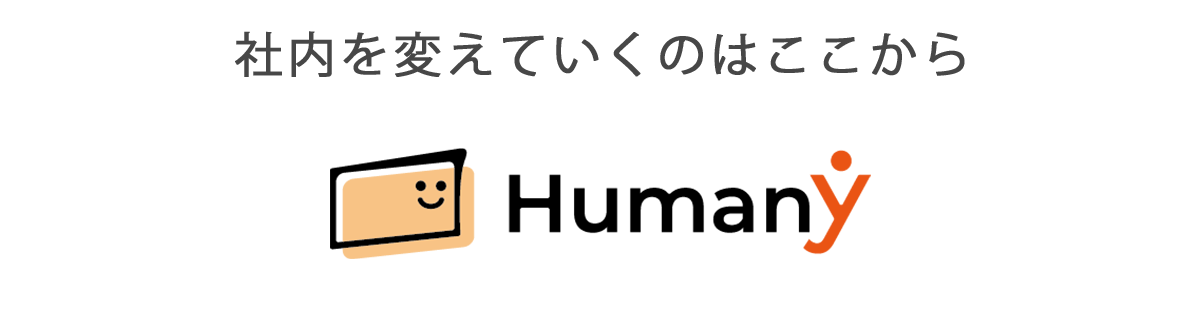ストレスチェックの運用ガイド|効果的な実施と活用で職場環境を改善
更新日:2025/04/03

法令対応に実施管理など、ストレスチェックの運用に課題を感じている人は少なくありません。
本記事では、ストレスチェック制度の概要から、実施手順、結果の活用方法まで、職場環境改善につながる効果的な運用方法を網羅的に解説します。実施時期の決定やストレスチェックツールの選定、高ストレス者への対応など、具体的なポイントを押さえることで、法律遵守だけでなく、従業員のメンタルヘルス不調の予防や生産性向上につなげられます。
ストレスチェックを「やらされ仕事」から、戦略的な組織運営のツールへと転換するための道筋を見つけましょう。
ストレスチェック制度の概要

ストレスチェック制度は、労働安全衛生法に基づき、職場における従業員のメンタルヘルス不調を予防することを目的とした制度です。定期的なストレスチェックの実施と、その結果に基づいた適切な対応を通じて、従業員の健康を守り、生産性の高い職場環境づくりを目指します。
ストレスチェック制度とは?
ストレスチェック制度の正式名称は、「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度」です。50人以上の労働者を雇用する事業場では、年に1回以上、全ての労働者を対象にストレスチェックを実施することが義務付けられています。ストレスチェックは、労働者のストレスの状況を把握し、メンタルヘルス不調のリスクを早期に発見するためのものです。
2025年3月の閣議決定により、近い将来50人未満の事業場でもストレスチェックが義務化される見通しとなっています。
【関連記事:50人未満の事業場におけるストレスチェック:実施するメリットと方法】
ストレスチェック制度の法的根拠
ストレスチェック制度は、労働安全衛生法第66条の10に規定されています。この法律に基づき、厚生労働省は「ストレスチェック制度実施マニュアル」を策定しています。
参考:ストレスチェック等の職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策等|厚生労働省
ストレスチェックの対象者
ストレスチェックの対象者は、以下のとおりです。
- 正社員、契約社員、派遣社員、パートタイマー、アルバイトなど、雇用形態にかかわらず、当該事業場で労働契約を締結している全ての労働者
- 休職者、在籍出向者なども対象に含まれる(ただし、長期休暇中の労働者などは対象外となる場合がある)
ストレスチェックの具体的な内容
ストレスチェックは、一般的に、労働者が質問票に回答する形式で行われます。質問票の内容は、厚生労働省が定めた標準的な質問票を使用するか、事業場の実情に合わせて作成した独自の質問票を使用するかのいずれかを選択できます。
ストレスチェックでわかることは、大きく分けて以下の3点です。
- 仕事のストレス要因:仕事の量、質、人間関係、役割など、仕事に関連するストレス要因
- 心身のストレス反応:イライラ、不安、抑うつ、身体症状など、ストレスによる心身の反応
- 周囲のサポート:上司や同僚、家族など、周囲からのサポートの程度
ストレスチェックの結果は、個々の労働者にフィードバックされ、高ストレス者と判定された労働者には、医師による面接指導が推奨されます。また、事業者はストレスチェックの結果を集団分析し、職場環境の改善に役立てることが求められます。
ストレスチェックの結果を用いて集団分析を行うと、上記の情報に加えて組織の課題がつかめるようになります。
ストレスチェックの目的と期待される効果

ストレスチェックは単なる義務として行うだけでなく、企業と従業員双方にとって多くのメリットをもたらすものです。大きく分けて、従業員個人への効果と、組織全体への効果が期待できます。
従業員のメンタルヘルス不調の予防
ストレスチェックの最も重要な目的は、従業員のメンタルヘルス不調を予防することです。早期発見・早期対応によって、重症化を防ぎ、休職や離職のリスクを低減します。ストレスチェックを受けることで、自分自身のストレス状態を客観的に認識し、セルフケアの必要性や具体的な方法を考えるきっかけにもなります。
また、高ストレス状態にある従業員には、医師による面接指導を受ける機会が提供されます。医師のアドバイスを受けることで、適切な対応策を検討し、健康状態の改善につながります。メンタルヘルス不調は回りまわって組織の生産性低下にも関係するため、従業員個人の問題であるだけなく、職場の課題でもあるのです。
未然防止
ストレスチェックは、メンタルヘルス不調の未然防止にも役立ちます。定期的に自身のストレス状態を把握することで、不調のサインにいち早く気づき、対処することができます。また、ストレスの原因を特定し、生活習慣の改善やストレス対処法の実践など、具体的な対策を講じることができます。
【関連記事:プレゼンティーズムで損をするのは誰?企業と従業員双方を守るための対策】
早期発見・早期対応
ストレスチェックによって高ストレス状態が判明した場合、医師の面接指導を受けることができます。医師との面談では、ストレスの原因や症状、対処法などについて相談することができます。必要に応じて、医療機関への受診や専門家によるカウンセリングなどの適切なサポートを受けることも可能です。
【関連記事:職場環境改善の鍵!ストレスチェックで高ストレス者に対応するための3ステップ】
職場環境の改善
ストレスチェックの結果は、職場環境の改善にも活用されます。集団分析によって、職場全体のストレス要因を特定し、職場環境改善計画を策定・実行することで、より働きやすい職場づくりが始められます。
具体的な改善策としては、労働時間の適正化、休暇取得の促進、コミュニケーションの活性化、ハラスメント対策などが挙げられます。ストレスチェックを継続的に実施することで、職場環境改善のPDCAサイクルを回し、効果的な改善を図れるでしょう。
職場環境改善計画の策定と実行
ストレスチェックの結果に基づき、職場環境改善計画を策定し、実行することが重要です。計画には、具体的な改善目標、実施時期、担当者などを明確に記載します。
また、計画の実施状況を定期的に評価し、必要に応じて見直しを行うことで、より効果的な職場環境改善ができます。
| ストレス要因の例 | 具体的な改善策 |
|---|---|
| 長時間労働 | ノー残業デーの設定、業務効率化の推進 |
| 休暇取得の難しさ | 休暇取得の推奨、計画的な休暇取得の支援 |
| 人間関係の悪化 | コミュニケーション研修の実施、相談窓口の設置 |
| ハラスメント | ハラスメント防止研修の実施、相談窓口の設置 |
生産性向上と組織活性化
従業員のメンタルヘルスが良好な状態に保たれることで、生産性向上や組織活性化にもつながります。ストレスが軽減され、仕事へのモチベーションが向上することで、業務効率やパフォーマンスが向上します。
また、従業員同士の良好なコミュニケーションが促進され、チームワークの向上や組織全体の活性化にも寄与します。結果として、企業の業績向上にもつながるため、ストレスチェックは経営戦略としても重要な位置付けとなります。
従業員エンゲージメントの向上
ストレスチェックは、従業員エンゲージメントの向上にも貢献します。従業員エンゲージメントとは、従業員が組織に対して愛着や誇りを感じ、積極的に貢献しようとする意欲のことです。
ストレスチェックを通じて、従業員の健康状態や職場環境への意識を把握し、改善策を講じることで、従業員のエンゲージメントを高めることができます。
【関連記事:エンゲージメントとは?意味や種類、向上させるメリット・方法を解説】
ストレスチェック運用の実践的なポイント

ストレスチェック制度を効果的に運用するためには、計画的な実施と結果に基づいた適切な対応が不可欠です。以下、実践的なポイントを解説します。
実施手順とスケジュール管理
ストレスチェックの実施は、綿密な計画とスケジュール管理が成功の鍵となります。実施時期、方法、周知方法などを事前に決定し、スムーズな運用を目指しましょう。
ストレスチェック実施時期の決定
ストレスチェックは、毎年1回以上実施することが法律で義務付けられています。実施時期は、業務の繁閑や従業員の状況などを考慮し、適切な時期を選定しましょう。
たとえば、期末や決算期など繁忙期を避ける、新年度が始まって職場環境の変化が落ち着いた時期に行う、などの工夫が考えられます。時期選定の際には、従業員との協議も重要です。
実施方法の選択(紙媒体・Webツール)
ストレスチェックの実施方法には、紙媒体とWebツールの2種類があります。それぞれにメリット・デメリットがあるため、自社の状況に合わせて適切な方法を選択しましょう。
| 実施方法 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 紙媒体 | IT環境が整っていない職場でも実施可能 回答しやすいと感じる従業員もいる | 集計作業に時間がかかる データの入力ミスが起こりやすい |
| Webツール | 集計作業が自動化され、効率的 データ分析機能が充実している場合が多い | IT環境が必要 回答に抵抗を感じる従業員もいる可能性がある |
周知・啓発活動
ストレスチェック制度の目的や実施方法、プライバシー保護について、従業員にしっかりと周知・啓発することが重要です。実施前に説明会を開催したり、資料を配布したりするなど、従業員の理解と協力を得られるよう努めましょう。
ストレスチェックは強制ではなく、受検は任意であることを伝えることも大切です。矯正するのではなく、実施の結果から職場改善を行うこと、集団分析の結果を共有することで、従業員に「働きやすさを高めるためにストレスチェックが行われている」と実感してもらう工夫が必要です。
【関連記事:ストレスチェックの受検を従業員に拒否されたら?受検率を高めるポイントを解説】
ストレスチェックツールの選定
ストレスチェックツールを選ぶ際には、自社のニーズに合ったツールを選ぶことが重要です。さまざまな観点から比較検討し、最適なツールを選びましょう。
実施者業務を担ってもらえるか
ストレスチェックの実施は、事業者自身で行うことも、外部機関(ストレスチェックツール提供業者)に委託することも可能です。ストレスチェックツールの導入によって、実施者としての業務を担ってもらえるかを確認しましょう。
ストレスチェックの実施事務を代行してもらえるだけでなく、実施後の集団分析や職場環境改善に向けたアドバイスなども提供してくれる業者もあります。ツールを導入することで、担当者の負担を軽減し、より効果的なストレスチェック運用が可能になります。
【関連記事:中小企業の「産業医がいない」問題を解決!費用を抑えた導入方法と注意点】
導入時の負担はどうか
ストレスチェックツールの導入には、費用だけでなく、システムの導入や操作方法の習得など、さまざまな負担がかかります。導入時の負担が少ないツールを選ぶことで、スムーズな運用開始を実現できます。無料トライアルやデモ版などを活用して、使い勝手や機能を事前に確認することが重要です。
【関連記事:IT導入補助金でストレスチェックツール導入!従業員のメンタルヘルス対策と離職防止に効果的な方法を解説】
プライバシーの保護ができるか
ストレスチェックは、従業員のプライバシーに関わる重要な情報を取り扱うため、適切なプライバシー保護対策が必須です。個人情報保護法に基づいた安全管理措置が講じられているか、データの保管場所やアクセス権限の設定などが適切かを確認しましょう。プライバシーマークやISMS認証を取得している業者を選ぶことも、安全性の指標となります。
多言語対応しているか
外国人従業員が増加している昨今、多言語対応のストレスチェックツールは必須と言えるでしょう。従業員の母語でストレスチェックを受けることができるようにすることで、正確な回答を促し、より効果的なストレスチェックを実施できます。
ストレスチェックの目的からみて、実施だけではなく、その後のフィードバックまで母語でできることが重要です。
外国人従業員も同じようにきめ細やかなストレスケアができるしくみをつくり、組織全体で働きやすさを高めていきましょう。
スマホ利用ができるか
従業員がいつでもどこでもストレスチェックに回答できるように、スマートフォンやタブレット端末に対応しているツールを選ぶと便利です。従業員の出張や外出が多い企業ではもちろんのこと、プライバシー保護のために、自宅など職場外で気軽に受検できることにもつながります。
設問の追加・編集ができるか
標準的な設問に加えて、自社独自の設問を追加・編集できる機能があると、より詳細なストレス状況を把握できます。たとえば、職種特有のストレス要因や、ハラスメントに関する設問などを追加することで、より精度の高い分析が可能になります。
集団分析がしやすいか
ストレスチェックの結果は、個人の結果だけでなく、集団分析を行うことで職場全体のストレス状況を把握し、職場環境改善に役立ちます。集団分析機能が充実しているツールを選ぶことで、効率的な分析作業が可能です。グラフ表示やレポート作成機能などが充実しているツールを選ぶと、分析結果を分かりやすく可視化できます。
【関連記事:ストレスチェック集団分析結果の見方は?部署・年代・階層別の傾向と対策を解説】
労基署への報告書作成が簡単にできるか
ストレスチェックの実施後は、労働基準監督署への報告が義務付けられています。報告書作成機能が搭載されているツールを選ぶことで、報告業務を効率化できます。ツールによっては、自動で報告書を作成してくれる機能もあるため、事務作業の負担を大幅に軽減できます。
【関連記事:ストレスチェック報告書の書き方・労基署への提出方法・提出期限を徹底解説!】
ストレスチェック結果の活用
ストレスチェックを実施するだけでは意味がありません。結果を適切に活用し、職場環境の改善につなげることが重要です。
集団分析の実施と結果の解釈
ストレスチェックの結果は、集団分析を行うことで、職場全体のストレス状況を把握することができます。部署別、年齢別、職種別など、さまざまな切り口で分析することで、より詳細な状況把握が可能になります。
分析結果を正しく解釈し、職場環境改善につなげるための具体的な対策を検討しましょう。必要に応じて、専門家の助言を受けることも有効です。
【関連記事:ストレスチェック集団分析結果の見方は?部署・年代・階層別の傾向と対策を解説】
高ストレス者への対応
ストレスチェックの結果、高ストレス者と判定された従業員には、医師による面接指導を受ける機会を提供することが義務付けられています。面接指導は、従業員のプライバシーに配慮しながら、丁寧に実施することが重要です。面接指導の結果を踏まえ、必要な場合は、就業場所の変更や作業の転換、休業などの措置を検討しましょう。
また、高ストレス者本人だけでなく、周囲の従業員へのケアも重要です。高ストレス者が安心して相談できる体制を整備し、職場全体でサポートしていくことが大切です。
【関連記事:ストレスチェックと産業医の役割|企業のメンタルヘルス対策を徹底解説】
職場環境改善計画の策定と実行
集団分析や高ストレス者への対応を踏まえ、職場環境改善計画を策定し、実行することが重要です。計画には、具体的な対策とその実施時期、担当者などを明確に記載しましょう。
また、計画の実施状況を定期的にモニタリングし、必要に応じて修正していくことも大切です。職場環境改善では、継続的な取り組みが必要です。従業員の声を聞きながら、より働きやすい職場づくりを目指しましょう。
正しく効果的なストレスチェック運用で、経営も上向きに

ストレスチェック制度は、従業員のメンタルヘルス不調の予防と職場環境の改善を目的とした重要な制度です。本記事では、ストレスチェック制度の概要から、運用における実践的なポイントまでを解説しました。効果的なストレスチェック運用のためには、適切なスケジュール管理、ツール選定、そして結果に基づいた職場環境改善が不可欠です。
実施時期は、業務の繁忙期を避け、従業員が落ち着いて受検できる時期を選定することが重要です。ツール選定においては、プライバシー保護、多言語対応、スマホ対応、集団分析機能など、自社のニーズに合った機能を備えているかを確認しましょう。また、ストレスチェック実施後の集団分析では、部署ごとのストレス要因を特定し、職場環境改善につなげることが重要です。高ストレス者に対しては、医師や産業カウンセラーなど専門家への相談窓口を設けるなど、適切なフォローアップ体制を構築しましょう。
ストレスチェック制度を適切に運用することで、従業員の健康を守り、生産性向上や組織活性化にもつなげることが期待できます。本記事を参考に、自社に最適なストレスチェック運用を実施し、より良い職場環境づくりを目指しましょう。