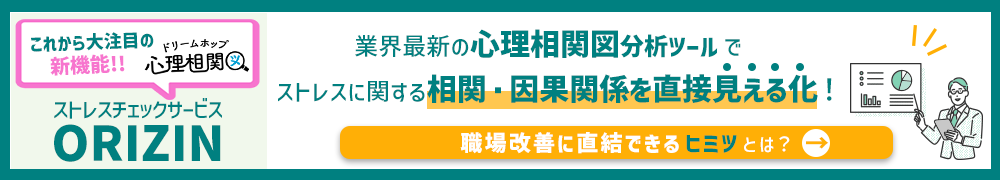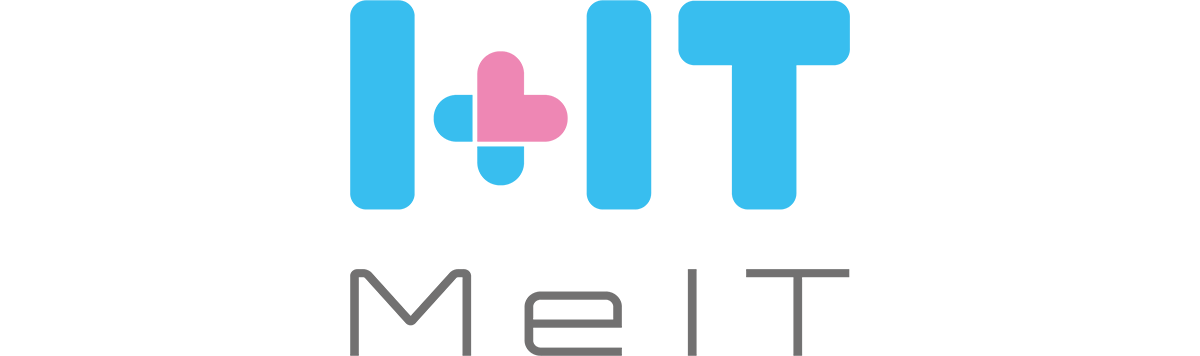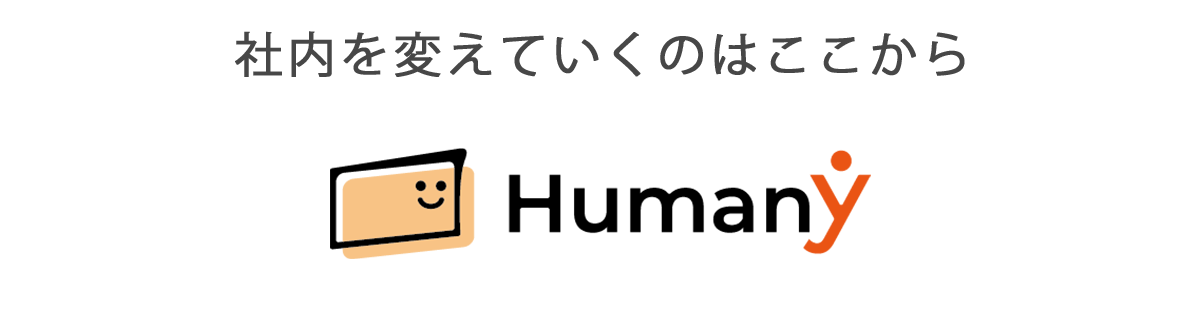ストレスチェックの実施状況を徹底解説|最新データから見る課題と企業の対策
公開日:2024/06/25
更新日:2025/11/04

「自社のストレスチェック実施率は、他社と比べて高いのか低いのか」「義務だから実施しているが、本当に意味があるのか形骸化していないか」このような疑問や課題を抱える人事・労務担当者の方も多いのではないでしょうか。この記事では、厚生労働省が公表する最新データに基づき、日本国内におけるストレスチェックの実施状況を企業規模別・業種別にくわしく解説します。
結論として、制度導入は進んでいるものの「中小企業における実施率の低さ」「従業員の受検率の伸び悩み」「実施後のフォローアップ不足」という根深い課題が存在します。本記事を読めば、日本の現状と自社の立ち位置を客観的に把握できるだけでなく、データから見える課題を乗り越え、ストレスチェックを真に有効なメンタルヘルス対策、そして職場環境改善へとつなげるための具体的な施策まで理解することができます。
まずは基本から|ストレスチェック制度とは?
ストレスチェック制度は、定期的に自身のストレス状況を把握し、メンタルヘルス不調を未然に防ぐことを目的とした制度です。
制度の目的と義務化の背景
ストレスチェック制度は、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止すること(一次予防)を主な目的としています。労働者が自らのストレス状態に気づき、セルフケアを行うきっかけを提供するとともに、事業者が職場全体のストレス要因を把握し、職場環境の改善につなげることも重要な狙いです。
ストレスチェック制度は、仕事による強いストレスが原因で精神障害を発症し、労災認定されるケースが増加したことを背景に、2014年6月に改正された労働安全衛生法に基づき、2015年12月1日から施行されました。
【関連記事:ストレスチェック基本の「き」がわかる!導入手順・実施方法・注意点まとめ】
対象となる事業者と労働者
ストレスチェックの実施は、2025年5月交付の改正法により、労働者数50人未満の事業場を含めたすべての事業場について義務化されました。
制度の対象となる労働者の具体的な範囲は以下のとおりです。
| 対象者 | 詳細 |
|---|---|
| 常時使用する労働者 | 正社員のほか、以下の要件を満たすパートタイムやアルバイト、契約社員なども対象
|
| 派遣労働者 | 派遣労働者については、派遣元の事業主に実施義務がある |
企業の役員や、労働時間の短いパートタイム労働者などは原則として対象外となりますが、集団分析を行う関係上、実施しておくのがおすすめです。集団分析については後述します。
ストレスチェック実施から職場環境改善までの流れ
ストレスチェック制度は、検査を実施して終わりではありません。結果を活かして職場環境を改善するまでが一連の流れとなります。
- 準備段階
事業者は、ストレスチェック制度の実施方針を表明し、衛生委員会などで実施体制や方法について調査審議します。 - ストレスチェックの実施
質問票を用いて、労働者のストレスの原因、心身の自覚症状、周囲からのサポート状況などを調査します。 - 結果の通知とセルフケア
結果は実施者(医師、保健師など)から直接本人に通知され、事業者が本人の同意なく結果を閲覧することは禁じられています。労働者は結果を通じて自身のストレス状態に気づき、セルフケアにつなげます。 - 医師による面接指導
検査結果で「高ストレス者」と判定された労働者から申し出があった場合、事業者は医師による面接指導を設定しなければなりません。 - 就業上の措置
面接指導後、医師の意見を聴取し、必要に応じて労働時間の短縮や作業内容の変更といった就業上の措置を講じます。 - 集団分析と職場環境の改善
部署や課ごとにストレスチェックの結果を集計・分析し、職場全体のストレス傾向を把握します。その分析結果に基づき、具体的な職場環境の改善策を計画し、実行します。
このように、個人へのケアと組織全体へのアプローチを両輪で進めることが、ストレスチェック制度を効果的に活用する鍵となります。
【最新データ】日本のストレスチェック実施状況
2015年12月に義務化されたストレスチェック制度は、日本の職場におけるメンタルヘルス対策の重要な柱となっています。ここでは、厚生労働省が公表している最新の「労働安全衛生調査(実態調査)」などに基づき、国内のストレスチェック実施状況を多角的に見ていきましょう。
事業者による実施率の推移と現状
ストレスチェックの実施率は、制度開始以来、高い水準で推移しています。とくに、実施が義務付けられてきた常時50人以上の労働者を使用する事業場においては、その傾向が顕著です。
企業規模別の実施状況
最新の調査によると、労働者50人以上の事業場におけるストレスチェック実施率は8割を超えており、制度が広く浸透していることがうかがえます。企業規模別に見ると、規模が大きいほど実施率が高い傾向は依然として続いており、1,000人以上の大企業ではほぼ全ての事業場で実施されています。
| 事業場規模 | 実施率 |
|---|---|
| 50~99人 | 84.7% |
| 100~299人 | 96.7% |
| 300~999人 | 98.0% |
| 1,000人以上 | 100.0% |
業種別の実施状況(抜粋)
業種によっても実施状況には差が見られます。「金融業、保険業」や「電気・ガス・熱供給・水道業」などでは高い実施率を示す一方、「医療、福祉」や「製造業」「建設業」などでは、全体の平均を下回る傾向にあります。これは、業種ごとの労働環境や組織体制の違いが影響していると考えられます。
| 業種 | 実施率 |
|---|---|
| 金融業、保険業 | 83.2% |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 76.3% |
| 情報通信業 | 51.7% |
| 学術研究、専門・技術サービス業 | 40.1% |
| 運輸業、郵便業 | 49.5% |
| 卸売業、小売業 | 43.4% |
| 医療、福祉 | 38.0% |
| 製造業 | 37.3% |
| 建設業 | 25.4% |
従業員の受検率と伸び悩む理由
事業場での実施率が高い一方で、従業員個人の受検率についてはどうでしょうか。
厚生労働省の資料「ストレスチェック制度の効果的な実施と活用に向けて」によれば、受検対象となる労働者のうち、実際に受検した労働者の割合が約8割を超える事業場は 77.5%です。
受検率が伸び悩む背景には、「結果が会社に知られるのではないか」というプライバシーへの懸念や、「高ストレスと判定された場合に不利益な扱いを受けるかもしれない」といった不安感、あるいは多忙な業務の中で受検する時間的・心理的余裕がないことなどが挙げられます。
参考:ストレスチェック制度の効果的な実施と活用に向けて|厚生労働省
【関連記事:ストレスチェックの受検を従業員に拒否されたら?受検率を高めるポイントを解説】
高ストレス者への面接指導の実施状況
ストレスチェック制度の最も重要な目的のひとつは、高ストレス状態にある労働者を早期に発見し、適切なケアにつなげることです。しかし、上記の厚生労働省の調査によれば、高ストレス者と判定された労働者のうち、実際に医師による面接指導を受けたいと申し出た人の割合は依然として非常に低い水準にとどまっています。
面接指導の申し出に対する心理的なハードルの高さや、事業場における受け入れ体制が十分に整備されていないことなどが原因と考えられます。
データから見えるストレスチェック制度の3つの課題
ストレスチェック制度は多くの事業所で導入が進んでいますが、制度の活用において依然として大きな課題が存在します。ここでは、統計データに基づき、3つの主要な課題を掘り下げて解説します。
課題①:中小企業・小規模事業場における実施率の低さ
第一の課題は、従業員数が少ない事業場における実施率の低さです。厚生労働省の「令和6年 労働安全衛生調査(実態調査)」によると、従業員1,000人以上の事業場での実施率が100%であるのに対し、50〜99人規模では78.1%、10~49人規模となると33.5%に留まっています。50人未満事業場での実施義務にはまだ対応しきれていないのが現状です。
この背景には、中小企業が抱える特有の問題があります。具体的には、産業医の選任義務がないための実施体制の構築の難しさ、人事担当者のリソース不足、そしてコスト面での負担などが挙げられます。企業規模が小さいほど実施へのハードルが高いことがうかがえます。
【関連記事:中小企業の「産業医がいない」問題を解決!費用を抑えた導入方法と注意点】
【関連記事:IT導入補助金でストレスチェックツール導入!従業員のメンタルヘルス対策と離職防止に効果的な方法を解説】
課題②:受検率が頭打ちになる原因
第二に、従業員の受検率が先に紹介したように伸び悩んでいるという課題があります。ストレスチェックの実施は事業者の義務ですが、従業員に受検義務はありません。そのため、本人の意思によって受検しない選択が可能であり、これが受検率が頭打ちになる一因となっています。
従業員が受検をためらう主な理由としては、以下のような点が考えられます。
- プライバシーへの懸念:「結果が会社に知られてしまい、人事評価などで不利益な扱いを受けるのではないか」という不安感
- 多忙な業務:日々の業務が忙しく、回答する時間を確保できない
- 当事者意識の欠如:ストレスチェックの重要性や目的を十分に理解しておらず、「自分には関係ない」と感じてしまう
受検率が低ければ、集団分析の結果が職場全体の実態を正確に反映しづらくなるため、職場環境改善の効果が限定的になる可能性があります。
【関連記事:50人未満の事業場におけるストレスチェック:実施するメリットと方法】
課題③:形骸化する実施後のフォローアップ
第三の課題は、ストレスチェック実施後のフォローアップが形骸化している点です。とくに深刻なのが、高ストレス者に対する医師の面接指導の実施率の低さです。制度開始当初からこの割合は極めて低く、平成29年の調査ではわずか0.6%でした。近年の調査でも、高ストレス者と判定された人のうち、実際に面接指導に至る割合は低い水準で推移していると指摘されています。
また、努力義務とされている「集団分析」の活用も十分とは言えません。集団分析は、部署ごとのストレス要因を特定し、職場環境の改善につなげるための重要なプロセスです。しかし、分析を実施しても具体的な改善策に結びついていない「やりっぱなし」の状態に陥っているケースが少なくありません。これでは、個人のセルフケアを促すだけに留まり、制度が本来目指す「メンタルヘルス不調の未然防止」という目的を十分に果たしているとは言えない状況です。
ストレスチェックを効果的に活用するための具体的施策
ストレスチェック制度を単なる義務の消化で終わらせず、従業員のメンタルヘルス不調の予防や生産性の向上につなげるためには、結果を組織的に活用する視点が不可欠です。ここでは、制度を形骸化させないための具体的な施策を多角的に解説します。
従業員の受検率を高めるための工夫
ストレスチェックの有効性は、多くの従業員が受検してこそ担保されます。しかし、従業員の中には「結果が評価に影響するのではないか」「プライバシーは守られるのか」といった不安から受検をためらうケースも少なくありません。従業員が安心して受検できる環境を整えることが、受検率向上の第一歩です。
周知方法とプライバシー保護の徹底
従業員の不安を払拭し、制度の重要性を理解してもらうためには、丁寧な周知活動が鍵となります。朝礼やグループウェア、メールなどを通じて、以下の点を繰り返し伝えましょう。
- ストレスチェックの目的(セルフケアと職場環境改善)
- 個人の結果は本人の同意なく会社に提供されないこと
- 受検や結果によって不利益な扱いを受けることは一切ないこと
とくに、個人情報の取り扱いに関する透明性の確保は、従業員の信頼を得るうえで極めて重要です。実施者(医師、保健師など)には守秘義務があること、人事権を持つ役職員は個人の結果に関与しないことを明確に規程し、周知することが求められます。
経営層からのメッセージ発信
トップマネジメントが従業員のメンタルヘルスを重視する姿勢を明確に示すことも、受検率向上に効果的です。経営層から「従業員の心身の健康が会社の成長の基盤である」というメッセージを直接発信することで、従業員は会社が本気で取り組んでいると感じ、安心してストレスチェックを受けることができます。全社的な方針として衛生委員会などで審議し、組織全体で取り組む姿勢を示すことが大切です。
結果を活かす「集団分析」の進め方
ストレスチェックのもう一つの重要な目的は、個人のケアだけでなく、職場全体のストレス要因を把握し、環境改善につなげることです。そのために不可欠なのが「集団分析」です。
集団分析で職場環境の課題を可視化する
集団分析とは、個人の結果を特定できないように処理したうえで、部署やチームといった一定の集団ごとにストレスの傾向を分析する手法です。この分析により、「どの部署で」「どのようなストレス要因が高いのか」といった課題を客観的なデータに基づいて可視化できます。
分析結果に基づく職場環境改善の具体例
集団分析によって明らかになった課題に対しては、具体的な改善策を検討・実行することが重要です。職場環境の改善は、一度きりで終わるものではなく、PDCAサイクルを回していくことが求められます。以下に、分析結果から考えられる課題と改善策の例を挙げます。
| 課題(考えられるストレス要因) | 職場環境改善の具体例 |
|---|---|
| 仕事の量的負担が大きい |
|
| 上司や同僚との支援が少ない |
|
| 仕事のコントロール度が低い |
|
【関連記事:「優秀な人ほど辞めていく」現象をデータで裏付け。離職を防ぐ本当のポイント【調査結果】】
高ストレス者への面接指導を促す体制づくり
ストレスチェックの結果、高ストレス者と判定された従業員に対しては、医師による面接指導を受けるよう促すことが事業者の義務です。しかし、面接指導の申し出には心理的なハードルが伴うため、従業員が利用しやすい体制を整える必要があります。
面接指導の申し出を促進するためには、申し出や面接指導を受けたことによる不利益な取り扱いがないことを改めて保証し、従業員が安心して相談できる環境を整備することが不可欠です。具体的な工夫としては、以下のようなものが挙げられます。
- 相談先の多様化:事業場の産業医だけでなく、外部のEAP(従業員支援プログラム)機関と連携し、相談先の選択肢を増やす。
- オンライン面談の導入:対面に抵抗がある従業員のために、オンラインでの面接指導も可能にする。
- プライバシーへの配慮:面談の予約方法や実施場所を工夫し、他の従業員の目を気にせず利用できるようにする。
高ストレス者からの申し出があった場合、事業者は概ね1ヶ月以内に面接指導を設定する義務があります。面接指導後は、医師の意見を聴取し、必要に応じて労働時間の短縮や業務内容の変更といった就業上の措置を講じる必要があります。
【関連記事:EAP(従業員支援プログラム)を徹底解説!導入のメリット・デメリット、具体的な内容とは?】
【関連記事:産業医の選任:基本と探し方、トレンドを解説】
ストレスチェックを目的から捉え直そう
本記事では、厚生労働省の最新データをもとに、日本国内におけるストレスチェックの実施状況、そこから見える課題、そして企業が取るべき具体的な対策についてくわしく解説しました。事業者による実施率は年々向上しているものの、依然として多くの企業が制度の有効活用に至っていないのが現状です。
データ分析から明らかになったのは、①中小企業における実施率の低さ、②プライバシーへの懸念などからくる従業員の受検率の伸び悩み、③結果を活かせず形骸化している実施後のフォローアップ、という3つの大きな課題です。これらは、ストレスチェックが単なる義務の遂行で終わってしまっている企業が多いことを示唆しています。
これらの課題を乗り越え、ストレスチェックを真に価値あるものにするためには、経営層からのメッセージ発信やプライバシー保護の徹底による受検率向上策が不可欠です。さらに、結果を「集団分析」によって職場ごとの課題として可視化し、具体的な職場環境の改善アクションへとつなげるサイクルを確立することが重要となります。また、高ストレス者に対しては、産業医と連携し、安心して面接指導を受けられる体制を整える必要があります。
ストレスチェックは、法律で定められた義務であると同時に、従業員のメンタルヘルス不調を未然に防ぎ、誰もが働きやすい職場環境を構築するための重要な経営ツールです。本記事で紹介したポイントを参考に、自社の取り組みを見直し、従業員の健康と企業の持続的な成長につなげてください。