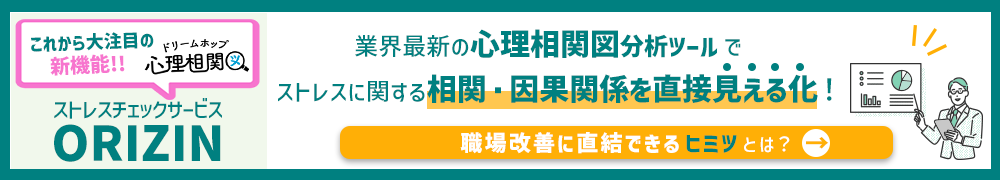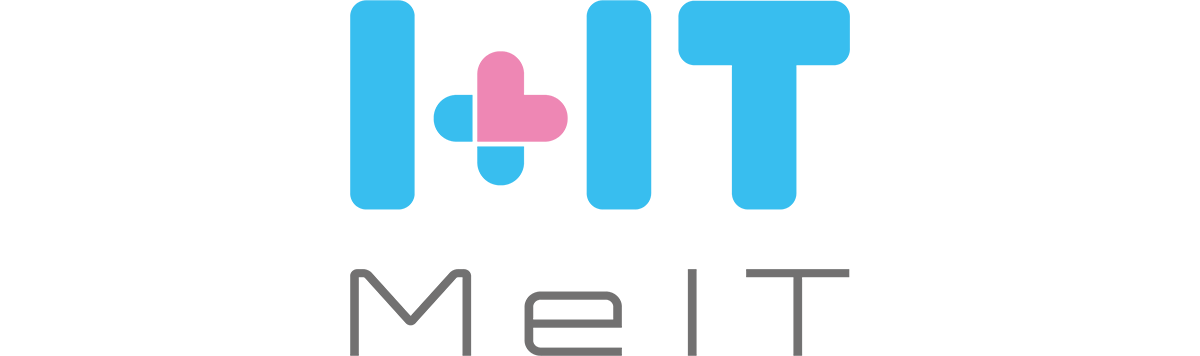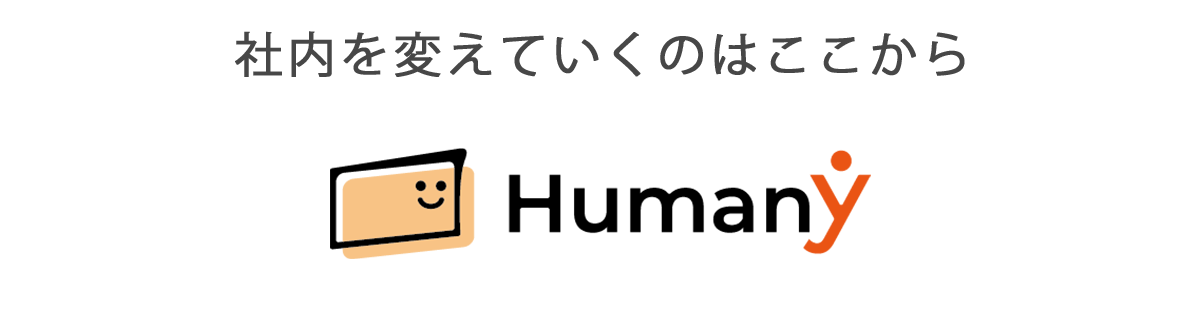ストレスチェックで職場改善を成功させる!データ活用の具体的なステップとポイント
公開日:2019/09/13
更新日:2025/08/01

ストレスチェックを「実施するだけ」で終わらせていませんか。
本記事では、ストレスチェックの集団分析データを最大限に活用し、職場課題を明確にする具体的な方法から、効果的な改善策の立案、そしてその定着まで、成功に導くロードマップを徹底解説します。データに基づいたアプローチで、従業員エンゲージメントと生産性を高めていきましょう。
ストレスチェックと職場改善の重要性

ストレスチェックは単なる義務ではなく、職場改善を推進し、企業の持続的な成長を実現するための重要なツールとして注目されています。
ストレスチェックの目的と義務化の背景
ストレスチェック制度は、従業員のメンタルヘルス不調を未然に防ぎ、快適な職場環境を形成することを主な目的としています。企業には、年1回以上、全従業員に対してストレスチェックを実施することが義務付けられています。
義務化の背景には、過重労働や人間関係の複雑化などによる労働者の精神的な健康問題が増加したことがあります。個人のストレス状況を把握するだけでなく、その結果を匿名で集計・分析する「集団分析」を通じて、職場のストレス要因を特定し、組織的な改善活動につなげることを強く推奨しています。
【関連記事:ストレスチェック基本の「き」がわかる!導入手順・実施方法・注意点まとめ】
職場改善が企業にもたらすメリット
ストレスチェックの結果を活用した職場改善は、企業に多岐にわたるメリットをもたらします。単に従業員の健康を守るだけでなく、企業の生産性向上や競争力強化にも直結する投資と捉えることができます。
具体的には、以下のようなメリットが挙げられます。
| メリットの側面 | 具体的な効果 |
| 従業員の健康と活力 | メンタルヘルス不調の予防、心身の健康維持、ワークエンゲージメントの向上 |
| 生産性の向上 | 集中力・モチベーション向上、業務効率化、創造性の促進 |
| 離職率の低下・定着率の向上 | 従業員満足度向上、従業員エンゲージメント強化、優秀な人材の流出防止 |
| 企業イメージの向上 | 「働きやすい職場」としての評価確立、採用競争力の強化、社会的信頼の獲得 |
| 法令遵守とリスク低減 | 労働安全衛生法等の遵守、過労死・ハラスメント等の労務リスク回避 |
アナログ的な判断に頼りがちだったこれまでの職場改善とは異なり、データに基づく客観的なアプローチは、より効果的で具体的な対策を可能にします。
ストレスチェックの「集団分析」とは?

ストレスチェックの「集団分析」とは、従業員個々のストレスチェック結果を、部署やチーム、あるいは会社全体といった集団単位で集計し、その集団のストレス状況を分析することです。
集団分析で何がわかるのか
集団分析を通じて、特定の部署やチームに共通して見られるストレス要因や職場環境の課題を客観的に把握できます。ストレスを単なる個人の問題として捉えるのではなく、組織全体として改善すべき点を発見し、具体的な対策を講じることが可能になります。
集団分析から把握できる職場環境の課題は多岐にわたり、たとえば以下のような要素が含まれます。
- 仕事の量的負担(業務量や労働時間)
- 仕事のコントロール度(業務における裁量権や意思決定の自由度)
- 職場の作業環境(温度、照明、騒音、安全性など)
- 上司や同僚からの支援(人間関係、コミュニケーション、サポート体制)
- 個人のストレス反応や心身の状態
これらのデータを可視化することで、どこに問題の根源があるのかを特定し、効果的な職場改善へとつながるのです。
57項目と80項目の違いと活用法
ストレスチェックの設問の組み方にはある程度の自由度があり、代表的なものに「57項目」と「80項目」などのパターンがあります。両者の主な違いと活用法を以下の表にまとめました。
| 項目 | 57項目 | 80項目 |
|---|---|---|
| 特徴 | 厚生労働省が推奨する標準的な検査項目 | 57項目に加えて、より詳細な分析が可能な検査項目 |
| 分析尺度 | 19の尺度(ストレス要因、ストレス反応など) | より多くの尺度(組織の公正性、キャリア開発、ハラスメント、ワークエンゲージメントなど) |
| 可視化できる内容 | 仕事の量的負担、仕事のコントロール度、人間関係、個人のストレス反応など、基本的なストレス要因 | 57項目の内容に加え、従業員のイキイキ度、職場の一体感、経営層との信頼関係、ハラスメントの有無など、職場の良い点や組織文化に関する詳細な情報 |
| 活用シーン | ストレスチェックを初めて実施する企業や、基本的な職場課題の把握を目指す企業 | より詳細な職場課題や組織文化の把握、従業員エンゲージメント向上、継続的な職場改善の指標として活用したい企業 |
【関連記事:80項目版ストレスチェックで職場環境を改善!57項目版との違いや実施方法を解説】
集団分析データから職場課題を発見する

ストレスチェックの集団分析データから把握できる職場環境の側面は多岐にわたります。たとえば、労働時間や仕事量、仕事の裁量や働きがい、職場の作業環境(温度、照明、騒音など)、上司や同僚との人間関係、さらには従業員の体調の状態まで、幅広い情報が含まれています。これらのデータを総合的に分析することで、漠然とした課題ではなく、具体的な改善ポイントを特定できるようになります。
データから仮説を立てる方法
集団分析データは、職場課題の「兆候」を示しますが、それだけでは具体的な「原因」を特定できません。そこで重要となるのが、データから仮説を立て、その仮説を検証していくプロセスです。
仮説を立てる際のステップは以下のとおりです。
- データから傾向を把握する
- 可能性のある原因を洗い出す
- 仮説を検証するための情報を収集する
まずは、とくに数値が悪い指標や、全国平均と比べて乖離が大きい指標に注目します。たとえば、「仕事の量的負担」が高い部署はどこか、特定の年代や性別で「上司の支援」が低い傾向があるかなど、詳細なセグメントで分析することで、より具体的な傾向が見えてきます。
傾向が把握できたら、「なぜそのような傾向が出ているのか」という問いを立て、考えられる原因を複数洗い出します。たとえば、仕事の量的負担が高い部署であれば、「人員不足」「業務プロセスの非効率」「特定の業務への負荷集中」などが考えられます。人間関係の悪化であれば、「コミュニケーション不足」「ハラスメントの発生」「評価制度への不満」などが挙げられます。
立てた仮説が正しいかを検証するために、追加の情報を収集します。これには、該当部署の従業員へのヒアリング、管理職へのインタビュー、アンケート調査、勤怠データや人事評価データとの突合などが有効です。たとえば、勤怠データから実際の残業時間を検証したり、ヒアリングで具体的な業務内容や人間関係の実態を聞き取ったりすることで、仮説の確度を高めます。
このプロセスを通じて、データが示す表面的な課題の奥にある真の原因を特定し、具体的な改善策を立案するための土台をつくりましょう。
職場改善の具体的な進め方と対策

ストレスチェックの集団分析によって職場課題が明確になったら、いよいよ具体的な改善策の実行段階へと移行します。
早期発見・早期介入の原則
集団分析データから問題点を早期に発見し、迅速に対応することが職場改善の成功には不可欠です。課題が顕在化してからでは対応が遅れ、従業員の心身の不調や離職につながるリスクが高まります。 産業医や保健師といった専門職に速やかに相談し、早期に対処を行うことが非常に重要です。
具体的な介入の例としては、以下のようなものがあります。
- 特定の部署やチームでストレスが高い場合、その原因を深掘りするためのヒアリングやアンケートの実施
- 高ストレス者への個別の面談指導や、必要に応じた医療機関への受診勧奨
- 職場環境改善に向けた部署単位でのワークショップ開催
量的負担・業務量改善の具体策
「仕事の量的負担」が高いと判明した場合、労働時間管理の厳格化と業務量の適正化が急務です。具体的な改善策としては、以下の点が挙げられます。
| 改善策のカテゴリ | 具体的な施策例 | 期待される効果 |
|---|---|---|
| 労働時間管理の徹底 |
|
|
| 業務プロセスの見直し |
|
|
| 人員配置・体制の見直し |
|
|
労働時間の削減だけでなく、業務の質を落とさずに効率を上げる工夫が求められます。
仕事の裁量・モチベーション向上策
「仕事のコントロール度」が低い場合、従業員のモチベーション低下や離職につながる可能性があります。アメリカの心理学者エドワード・デシの研究でも、仕事の裁量とモチベーションには密接な関係があることが示されています。従業員が自身の仕事に一定の責任と範囲を持ち、自律的に決定できると感じられる職場環境を構築することが重要です。
内発的動機を引き出し、活気のある職場にするための具体的な施策は以下のとおりです。
| 改善策のカテゴリ | 具体的な施策例 | 期待される効果 |
|---|---|---|
| 権限委譲と意思決定 |
|
|
| フィードバックと成長機会 |
|
|
| 目標設定と評価制度 |
|
|
従業員一人ひとりが「自分ごと」として仕事に取り組める環境が、組織全体の生産性向上にもつながります。
人間関係・ハラスメント対策
「上司の支援」や「同僚の支援」の数値が低い場合、職場で従業員が孤立している可能性や、マネジメントが機能していない、あるいはハラスメントが発生している可能性が考えられます。
人間関係の悪化原因(忙しさによる希薄化、ハラスメントなど)を特定し、適切な打ち手を実行していくことが求められます。
| 改善策のカテゴリ | 具体的な施策例 | 期待される効果 |
|---|---|---|
| コミュニケーション活性化 |
|
|
| ハラスメント対策の強化 |
|
|
| 心理的安全性向上 |
|
|
人間関係の改善は一朝一夕にはいきませんが、継続的な取り組みが従業員の定着率向上に直結します。
職場改善を継続・定着させるために

ストレスチェックの結果を活用した職場改善は、一度実施して終わりではありません。持続的な効果を生み出し、企業の競争力を高めるためには、改善活動を継続し、企業文化として定着させることが不可欠です。
改善策の効果測定と見直し
職場改善の取り組みが実際に効果を発揮しているかを客観的に評価し、必要に応じて軌道修正を行うことが重要です。PDCAサイクルを繰り返し回すことで、改善活動の質を高め、より効果的な職場環境を構築できます。
効果測定のためのKPI設定
改善策の効果を定量的に把握するためには、具体的なKPI(重要業績評価指標)を設定し、定期的に測定することが不可欠です。
| 指標カテゴリ | 具体的なKPI例 | 測定方法・データ源 |
|---|---|---|
| 健康・メンタルヘルス | ストレスチェックにおける高ストレス者率の低下 | ストレスチェック集団分析データ |
| 仕事のストレス判定図の改善(とくに「仕事の量的負担」「仕事のコントロール度」などの指標) | ストレスチェック集団分析データ | |
| 従業員エンゲージメント・満足度 | 従業員エンゲージメントスコアの向上 | 従業員エンゲージメントサーベイ、従業員満足度調査 |
| 組織活力度や職場の一体感の向上 | ストレスチェック80項目(該当項目)、従業員アンケート | |
| 生産性・パフォーマンス | 一人あたりの労働生産性の向上 | 業績データ、人事データ |
| 平均残業時間の削減 | 勤怠データ | |
| 定着率 | 離職率の低下 | 人事データ |
| コミュニケーション | ハラスメント相談件数の減少 | 相談窓口記録 |
これらのKPIを定期的に追跡し、目標達成度を評価することで、実施した改善策が職場にどのような影響を与えているかを可視化し、次の打ち手を検討する材料とします。
定期的なデータ分析とフィードバック
ストレスチェックの集団分析データは職場課題発見の重要な起点となりますが、これに加えて勤怠データ、健康診断データ、従業員アンケート、人事評価データなど、複数の情報を統合的に分析することで、より多角的な視点から職場の状況を把握できます。
分析結果は、経営層、管理職、そして従業員全体に分かりやすくフィードバックすることが重要です。とくに、改善策の実施後に再度ストレスチェックやアンケートを実施し、その変化を共有することで、従業員の改善活動への理解と協力を深められます。
企業文化としての定着
職場改善を単なる一時的なプロジェクトで終わらせず、企業のDNAとして根付かせるためには、組織全体での意識改革と継続的な努力が求められます。
経営陣のコミットメントとリーダーシップ
職場改善を成功させるには、経営層の強いコミットメントとリーダーシップが不可欠です。経営層が職場改善の重要性を深く認識し、その方針を明確に打ち出し、必要な資源(予算、人員、時間)を確保することで、組織全体にそのメッセージが浸透します。
経営層に対し、職場改善の進捗を報告し、成功事例を積極的に評価・共有することも、職場改善を企業文化として定着させるうえで欠かせません。
管理職の役割と教育
管理職は、従業員と経営層の橋渡し役として、職場改善において極めて重要な役割を担います。管理職がストレスチェックの結果を適切に理解し、自身の部署の課題を認識し、具体的な改善策を実行できるよう、定期的な研修や情報提供を行うことが重要です。
たとえば、部下との効果的なコミュニケーションスキル、ハラスメントの予防と対応、メンタルヘルス不調者への適切な初期対応など、具体的なマネジメント能力の向上を継続的に支援します。
従業員の主体的な参加とエンゲージメント
職場改善は、従業員一人ひとりの主体的な参加があってこそ真の成果を生み出します。以下のように、従業員の参画機会を増やしましょう。
- 意見表明の機会の提供:定期的な意見交換会、目安箱、匿名アンケートなどを通じて、従業員が安心して意見や提案を出せる場を設ける
- 改善活動への参画:小規模な改善チームへの参加を促したり、部署単位での改善活動を推進させたりすることで、従業員の当事者意識を高める
- 成功体験の共有:小さな改善でも成功事例を積極的に共有し、称賛することで、他の従業員のモチベーション向上につなげる
ストレスチェックの一連の流れを職場改善につなげよう

ストレスチェックは単なる義務ではなく、データに基づいた職場改善のための重要なツールです。とくに集団分析データを活用し、職場の具体的な課題を明確にすることで、効果的な改善策を立案できます。量的負担の軽減、仕事の裁量拡大、良好な人間関係の構築など、多角的な視点から具体的な対策を実行しましょう。
改善は一度きりではなく、効果測定と見直しを継続し、企業文化として定着させることが成功の鍵です。これにより、従業員エンゲージメントの向上、生産性向上、ひいては企業の持続的な成長へとつながるでしょう。