請求書の書き方完全ガイド!初心者でも完璧な請求書を作成できるテンプレート&例文集
更新日:2025/04/29

日々の業務の中でも欠かせない「請求書作成」。書き方に悩むこともあるかもしれません。
本記事では、請求書の書き方を初心者の方にもわかりやすく、網羅的に解説します。請求書に関するよくある質問にもお答えしているので、疑問を解消し、スムーズな取引を実現しましょう。効率的な請求書作成で、ビジネスを円滑に進めましょう。
請求書とは
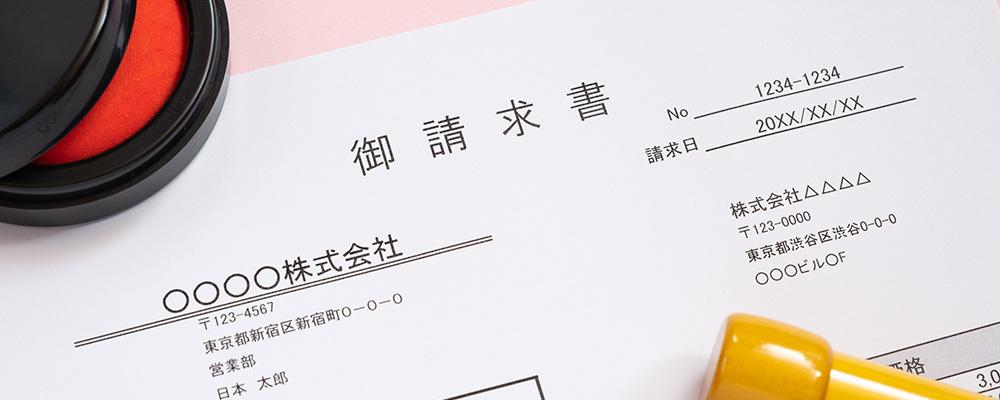
請求書とは、商品やサービスを提供した側(売主・請負人など)が、提供を受けた側(買主・注文者など)に対して、代金の支払いを請求するための書類です。ビジネスにおいて、取引の証拠となる重要な書類であり、金銭の授受を明確にする役割を担っています。
正式な書類であり、一定の形式や記載事項が求められます。口約束だけではトラブルに発展する可能性があるため、請求書を発行することで、取引内容を明確化し、双方の認識の齟齬を防いでいます。また、後々のトラブル発生時にも、請求書は重要な証拠となります。
請求書は、売掛金や買掛金の管理、会計処理にも不可欠です。請求書に基づいて売上や費用を計上し、財務諸表が作成されます。税務調査の際にも、請求書は重要な資料となります。適切な請求書を発行することは、健全な事業運営に欠かせない要素と言えるでしょう。
【関連記事:証憑とは? 種類や保存期間、電子化のメリットを確認】
請求書の目的・役割

請求書は、取引先に対して商品の販売やサービスの提供を行った際に、その対価を請求するための重要な書類です。ビジネスにおける金銭のやり取りを明確化し、円滑な取引を実現するために欠かせない役割を担っています。具体的には、以下の目的と役割があります。
- 取引内容の明確化
- 代金回収の促進
- 会計処理の根拠
- 仕入税額控除の資料
- 取引に関する証拠能力
取引内容の明確化
請求書には、取引の内容(品目、数量、単価、金額など)が詳細に記載されます。これにより、取引の当事者間で認識の齟齬を防ぎ、後々のトラブルを未然に防ぐことができます。ビジネスにおける信頼関係を築くうえでも非常に重要な点です。
代金回収の促進
請求書は、取引先に対して支払いを促す役割も担っています。支払期日や振込先などを明確に記載することで、スムーズな代金回収につなげます。また、未払いが発生した場合にも、請求書が重要な証拠資料となります。
会計処理の根拠
請求書は、企業の会計処理においても重要な役割を果たします。売上や費用の計上、消費税の計算など、会計処理の根拠となる資料として利用されます。
適格請求書(インボイス)と消費税の仕入税額控除
2023年10月1日より、適格請求書保存方式(インボイス制度)が開始されました。これにより、仕入税額控除を受けるためには、取引先から適格請求書(インボイス)を受け取ることが必要となりました。適格請求書には、登録番号や適用税率などの記載が義務付けられています。
【関連記事:インボイス制度Q&A Vol.1】
【関連記事:消費税の仕入税額控除とは?インボイス制度での変更点も解説】
請求書の法的効力
請求書自体は、それだけで法的拘束力を持つものではありません。しかし、裁判になった場合などに取引の内容や金額などを証明する重要な証拠資料となります。具体的には、売買契約や業務委託契約などの契約書と合わせて、取引の証拠として用いられます。
請求書作成の前に確認しておくべき事項

請求書をスムーズに作成し、取引先との良好な関係を維持するためには、作成前にいくつかの事項を確認しておくことが重要です。確認を怠ると、後々トラブルに発展する可能性もありますので、しっかりと確認を行いましょう。
取引先情報の確認
請求書の宛先は、取引先の正式名称で記載します。個人事業主の場合は氏名に加えて屋号も確認しましょう。また、部署名や担当者名、郵便番号、所在地(住所)なども正確に記載することが重要です。メールで送る場合も多いため、メールアドレスについてはとくに慎重に確認してください。
契約内容の確認
請求金額は、契約内容に基づいて算出します。契約書や発注書などを確認し、単価、数量、消費税率、源泉徴収税の有無、割引の有無などを確認しましょう。口頭での契約の場合は、書面に残しておくことが重要です。また、作業内容や納品物の詳細など、請求内容に関する事項も事前に確認し、齟齬がないようにしましょう。
請求書の発行日と支払期限
請求書の発行日は、実際に商品を納品した日、またはサービスを提供した日以降となります。支払期限は、取引先との契約に基づいて設定します。一般的には、月末締め翌月末払いなどがよく利用されますが、取引先によって異なる場合があるので、事前に確認しておきましょう。支払期限を明確にすることで、入金遅延を防ぎ、スムーズな資金回収につながります。
その他
上記以外にも、取引先によって特別な要件がある場合があります。
たとえば、毎回見積書や納品書を求められることも珍しくありません。また、官公庁との取引の場合や掛け取引がある場合などに、特定のフォーマット(指定請求書)での請求書提出が求められることもあります。
取引先に確認し、必要な書類等を準備しておきましょう。
| 確認事項 | 内容 |
|---|---|
| 取引先情報 | 正式名称、部署、担当者名、住所など |
| 契約内容 | 単価、数量、消費税、源泉徴収税、割引など |
| 請求書の発行日 | 商品納品日またはサービス提供日 |
| 支払期限 | 取引先との契約に基づく |
| その他 | 取引先独自の要件など |
【関連記事:経理業務の基礎知識】
請求書の種類

請求書の種類を確認しましょう。具体的な書き方は別の章でお伝えします。
適格請求書(インボイス)
適格請求書(インボイス)は、インボイス制度に則り、仕入税額控除を受けるために必要な記載事項が盛り込まれた請求書です。
具体的には以下の項目を記載する必要があります。
- 適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号(Tから始まる13桁の番号)
- 取引年月日(納品日)
- 取引内容(軽減税率の対象であれば、その旨)
- 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)および適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
- 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称(宛名)
適格請求書を発行できるのは、消費税の課税事業者であり、かつ適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者のみです。
なお、インボイス制度の開始に伴い、区分記載請求書は廃止されています。
【関連記事:インボイス制度とは?その目的や事業者の対応の基本を解説】
適格簡易請求書(簡易インボイス)
インボイスを発行できる事業者が以下の業種にあてはまる場合、適格簡易請求書(簡易インボイス)を発行することもできます。
- 小売業
- 飲食店業
- 写真業
- 旅行業
- タクシー業
- 駐車場業(不特定かつ多数の者に対するものに限る)
- その他これらの事業に準ずる事業で不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業
その他の請求書
適格請求書以外の請求書には、以下のような種類があります。取引の内容や状況に応じて使い分けられます。
請求明細書
複数の取引をまとめて請求する場合に用いられることが多い請求書です。 個々の取引内容を明細として記載し、合計金額を請求します。請求明細書は、請求書と併用して発行される場合もあります。
請求書兼領収書
請求と同時に支払いが完了するような、主に個人に対する請求の際に用いられる形式です。適格請求書の形式を満たしていれば適格請求書として利用できます。領収書を兼ねているため、気をつけなければならないポイントもあります。
請求書の記載事項

請求書に記載する項目を押さえていきましょう。
宛名
請求書の送付先となる企業名または個人名を記載します。法人格も省略せずに正確に記載しましょう。担当者名もわかれば併記するとスムーズです。
なお、宛名(書類の交付を受ける事業者の氏名または名称)は、適格請求書(インボイス)では記載必須事項ですが、適格簡易請求書(簡易インボイス)では省略できます。
件名
「請求書」「御請求書」など、この書類が請求書であるとわかる件名を大きく書きます。
また、請求内容がひと目でわかるように、何に対する請求書なのかを簡潔に記載する欄を設けても良いでしょう。案件名や契約IDなどを併記することで、相手が請求内容を特定しやすくなります。
発行者情報
請求書の発行者である企業(事業者)名、所在地、電話番号、メールアドレスなどを記載します。店舗名だけでなく、正式な会社名を記載しましょう。
適格請求書等発行事業者登録番号
適格請求書を発行する場合、登録番号を記載する必要があります。登録番号は、税務署から交付される13桁の番号です。適格請求書発行事業者は必ず登録番号を記載しましょう。
事業者名と登録番号は、適格請求書(インボイス)と適格簡易請求書(簡易インボイス)いずれにも記載しなければなりません。
【関連記事:インボイス制度Q&A Vol.2】
請求日
請求書を作成した日付を記載します。請求日は、請求の効力が発生した日付を示します。
請求書番号
請求書を識別するための番号です。発行するごとに異なる番号を割り振ります。一連の番号で管理する場合のほかに、取引内容やカテゴリーごとに区分するなどのパターンがあります。
品目・単価
提供した商品やサービスの内容、数量、単価を記載します。品目は具体的に記載し、どのような商品・サービスを提供したのかが明確にわかるようにしましょう。
納品日
商品を納品した日、またはサービスを提供した日を記載します。一定期間の代金をまとめて1枚の請求書で記す場合、同じ商品を複数回納品したときは、納品日ごとにわけて記載します。
納品日(取引年月日)は、適格請求書(インボイス)と適格簡易請求書(簡易インボイス)いずれにも記載しなければなりません。
小計・消費税・合計金額
適用税率ごとに、商品・サービスの金額を合計した小計と消費税額を記載します。そして小計と消費税額の合計金額を記載します。消費税額が適用税率ごとに記載されていれば、小計は税抜・税込いずれで記載してもかまいません。
なお、適格請求書(インボイス)では小計の時点で適用税率をそれぞれ記載しなければなりませんが、適格簡易請求書(簡易インボイス)では省略できます。
また、適格請求書(インボイス)では適用税率ごとに消費税額を記載しなければなりませんが、適格簡易請求書(簡易インボイス)では税額の代わりに適用税率を書いても問題ありません。
源泉徴収税額
法人からの請求では源泉徴収されることはほぼありませんが、源泉徴収の対象となる取引の場合は、源泉徴収税額を記載します。源泉徴収がある場合、合計金額から差し引いた金額を請求します。
振込先
請求金額の振込先となる金融機関名、支店名、口座の種類(普通預金、当座預金など)、口座番号、口座名義を記載します。
支払(振込)期日
請求金額の支払期限を記載します。トラブルを避けるためにも必ず記載しましょう。
備考
その他、必要な情報を記載します。たとえば、振込手数料の負担、割引の適用、追加の依頼事項などです。備考欄は、請求に関する補足情報を記載する際に活用しましょう。
請求書の発行時期
請求書の発行時期は、取引の内容や契約によって異なりますが、一般的には以下のタイミングで発行します。
商品の販売・サービスの提供
商品を販売したり、サービスを提供したりした後に請求書を発行するのが一般的です。具体的には、以下のタイミングが考えられます。
商品の場合
- 商品を発送した日
- 商品が納品された日
サービスの場合
- サービス提供が完了した日
- サービス提供期間の終了日
商品やサービスを提供した直後に請求書を発行することで、スムーズな入金につながります。 また、取引内容が鮮明なうちに請求書を作成すれば、記載漏れや誤りを防ぐことができます。
継続的な取引の場合
継続的な取引の場合、毎月または一定期間ごとに請求書を発行します。たとえば、月額制のサービスを提供している場合は、毎月末に翌月分の請求書を発行するなど、以下のように請求のタイミングを取り決めておくのが一般的です。
| 取引の種類 | 請求書の発行時期(例) |
|---|---|
| 月額制サービス | 毎月末(翌月分) |
| 四半期ごとのサービス | 四半期末(翌四半期分) |
| 年額制サービス | 年末(翌年分) |
契約内容による発行時期
契約書に請求時期が明記されている場合は、契約内容に従って請求書を発行します。たとえば、「月末締め翌月末払い」と契約している場合は、月末に締め処理を行い、支払処理に余裕が持てるよう、翌月初旬を目処に請求書を発行します。
請求日と支払期日の関係
請求書には、請求日と支払期日を記載します。請求日は、請求書を発行した日付です。支払期日は、取引先が支払うべき期限です。支払期日は、請求日から1ヶ月後や2ヶ月後など、取引先との合意に基づいて設定します。
請求日と支払期日を明確にすることで、入金遅延を防ぐことができます。
早期入金のための工夫
早期入金を促すためには、以下のような工夫が有効です。
- 早期入金割引を設定する
- 支払方法を複数用意する(銀行振込、クレジットカード決済など)
- 請求書に振込先情報を明確に記載する
これらの工夫をすることで、取引先にとって支払いがしやすい環境を整えることができます。
請求書の書き方 手書き(アナログ)編

手書きで請求書を作成する機会はほとんどなくなっていますが、基本事項を押さえていきましょう。
手書き請求書のメリット・デメリット
手書き請求書には、デジタル作成に比べて柔軟性が高いというメリットがあります。フォーマットにとらわれず、必要な情報を自由に記載できるため、特殊な取引にも対応しやすいでしょう。また、特別なソフトや機器を必要としないため、導入コストがかかりません。
一方で、手書きは時間がかかり、修正が難しいというデメリットもあります。字が汚いと相手に失礼な印象を与えてしまう可能性もあるでしょう。さらに、保管や管理の面でもデジタルデータに比べて劣ります。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 柔軟性が高い | 時間がかかる |
| 導入コストがかからない | 修正が難しい |
| 特殊な取引に対応しやすい | 保管・管理が煩雑 |
手書き請求書に必要なもの
手書きで請求書を作成するために必要なものは以下のとおりです。
- 請求書用紙(市販のもの、または自作のフォーマットを印刷したもの)
- ペン(黒または青色のインクを使用)
- 電卓(計算ミスを防ぐため)
- 印鑑(請求書に印鑑が必要な場合)
- 収入印紙(必要な場合)
手書き請求書の書き方手順
具体的な書き方の手順を以下に示します。
日付の書き方
請求書を発行した日付を西暦で記載します。
例:2025年1月1日
取引先情報(宛名)の書き方
取引先の正式名称と部署名、担当者名を記載します。「株式会社」などの法人格も省略せずに記載します。
発行者情報の書き方
自身の会社名、住所、電話番号、代表者名などを記載します。適格請求書・適格簡易請求書の場合は登録番号を忘れずに記載しましょう。
件名の書き方
「請求書」「御請求書」などのほかに、請求内容が簡潔にわかるように記載します。
例:「〇〇制作費」
品目・金額の書き方
提供した商品やサービスの内容、数量、単価、金額を明記します。品目や金額が複数ある場合は、それぞれを明確に区別して記載することが重要です。
記載事項の章も再度確認しながら、適切に記載してください。
消費税・源泉徴収税の書き方
消費税額と源泉徴収税額を計算し、それぞれを明記します。消費税の計算を間違えないように注意しましょう。
振込先の書き方
振込先の金融機関名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義を正確に記載します。
印鑑は必要なのか
法的に印鑑は必須ではありませんが、取引先によっては印鑑を求められる場合があります。取引先の慣習に合わせて対応しましょう。
印紙の取り扱い
請求書には、基本的に印紙は不要です。請求書兼領収書の形を取る場合に、印紙が必要となることがあります。
収入印紙が必要な場合は、所定の金額の印紙を貼付します。
なお、デジタルデータで請求書を発行する場合は印紙は不要です。記載ミスや金額・消費税額等の計算の手間を考え、デジタルデータの請求書を作成することが主流になっていますが、紙ではなくデジタルデータで発行するメリットは印紙の必要性にも関係しているといえるでしょう。
請求書の書き方 パソコン(デジタル)編

パソコンで請求書を作成するほうが、現代では一般的な方法となっています。効率化だけでなく、正確性も向上するため、積極的に活用していくべきでしょう。
記載事項は手書きと同じ
デジタルで請求書を作成する場合でも、記載事項は手書きの場合と基本的に変わりません。宛名、件名、発行者情報、請求日、請求書番号、品目・単価、納品日、小計・消費税・合計金額、源泉徴収税額、振込先、支払期日、備考など、必要な情報を漏れなく記載しましょう。
とくに、適格請求書(インボイス)を発行する場合は、登録番号の記載が必須となります。記載漏れがあると、受け取ったお客さまが仕入税額控除の適用が受けられない可能性があるため、注意が必要です。
デジタルの場合収入印紙は必要ない
デジタルデータで請求書兼領収書を発行する場合、収入印紙は不要です。印紙税法の基本通達において、電子計算機を使用して作成された請求書については印紙税が非課税とされています。
ただし、作成した請求書を印刷して相手に渡す場合は、印紙税の課税対象となるため、印紙を貼付する必要があります。
デジタル請求書を作成するメリット・デメリット
デジタル請求書には、多くのメリットがあります。たとえば、修正が容易であること、データで管理できるため検索性が高いこと、郵送コストがかからないことなどが挙げられます。また、テンプレートを利用することで、作成時間を大幅に短縮できる点も大きなメリットです。
一方で、デメリットも存在します。デジタル請求書を作成する場合、セキュリティ対策に注意する必要があります。また、取引先によってはデジタルデータでの請求書を受け付けていない場合もあるため、事前に確認が必要です。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 修正が容易 | セキュリティ対策が必要 |
| 検索性が高い | 取引先によっては受け付けていない場合がある |
| 郵送コストがかからない | |
| 作成時間を短縮できる |
請求書作成ツールの種類
デジタル請求書を作成するためのツールは、さまざまな種類があります。
Excel・Wordなどオフィスソフト
Microsoft ExcelやWordなどのオフィスソフトは、比較的簡単に請求書を作成できるため、広く利用されています。テンプレートも豊富に用意されているため、初心者でも手軽に始めることができます。
無料の請求書作成ツール
インターネット上には、無料で利用できる請求書作成ツールが多数公開されています。これらのツールは、基本的な機能を備えているため、コストを抑えたい場合に利用すると良いでしょう。機能が限定的な場合もあり、注意が必要です。
クラウド請求書作成サービス
クラウド型の請求書作成サービスは、インターネット上で請求書の作成・管理・送付までを一元的に行えるサービスです。データのバックアップやセキュリティ対策も万全であるため、安心して利用できます。インボイスを発行する場合はサービスを導入するのが現実的です。
請求書作成ツールの選び方
請求書作成ツールを選ぶ際には、自社の業務内容や規模、予算などを考慮することが重要です。小規模事業者であれば、無料のツールやオフィスソフトで十分な場合も多いでしょう。一方、大規模事業者や複雑な請求業務を行う場合は、クラウド型のサービスを導入するほうが合理的です。
また、操作性やサポート体制も重要な選定基準となります。無料トライアルなどを活用して、実際に使い勝手を試してから導入を決定することをおすすめします。
コピペで使える請求書テンプレート&例文集

この章では、すぐに使える請求書テンプレートと、具体的な例文集をご紹介します。業種や状況にあわせて、適宜修正してご活用ください。
パターン別・請求書テンプレート
よくある2つのパターンにわけて請求書のテンプレートをご紹介します。お使いのフォーマットに貼り付けたり、適宜編集したりしてご利用ください。
適格請求書(インボイス)として利用する場合は、適格請求書発行事業者登録番号の記載が必須です。
物品販売の請求書
【宛名】
株式会社〇〇
〇〇様
【件名】
御請求書
(請求内容を取りまとめて書く欄を設ける場合:◯◯代金)
【発行者情報】
株式会社△△
〒100-0000 東京都千代田区〇〇
TEL:03-xxxx-xxxx
適格請求書発行事業者登録番号:Txxxxxxxxxxxxx
【請求日】
2025年1月31日
【請求書番号】
20250101-001
【納品日・品目・単価】
| 納品日 | 品目 | 数量 | 単価 | 金額 | 適用税率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/10 | 商品A | 10 | 1,000円 | 10,000円 | 10% |
| 1/15 | 商品B | 5 | 2,000円 | 10,000円 | 8%(軽減税率) |
【小計】
10%対象 10,000円
8%対象 10,000円
【消費税】
10%消費税 1,000円
8%消費税 800円
【合計金額】
21,800円
【振込先】
〇〇銀行 〇〇支店 普通 〇〇〇〇〇〇〇〇
株式会社△△
【支払期日】
2025年2月28日
【備考】
振込手数料は貴社負担でお願いいたします。
サービス提供の請求書
【宛名】
株式会社〇〇
〇〇様
【件名】
御請求書
(請求内容を取りまとめて書く欄を設ける場合:ランディングページ制作・管理費用 ◯月分)
【発行者情報】
株式会社△△
〒100-0000 東京都千代田区〇〇
TEL:03-xxxx-xxxx
適格請求書発行事業者登録番号:Txxxxxxxxxxxxx
【請求日】
2025年1月31日
【請求書番号】
20250101-002
【納品日・品目・単価】
| 納品日 | 品目 | 数量 | 単価 | 金額 | 適用税率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 | ランディングデザイン | 1式 | 200,000円 | 200,000円 | 10% |
| 1/16 | コーディング | 1式 | 100,000円 | 100,000円 | 10% |
| 1/31 | ランディングページ管理(2025年1月分) | 1ヶ月 | 30,000円 | 30,000円 | 10% |
【小計】
10%対象 330,000円
8%対象 0円
【消費税】
10%消費税 33,000円
8%消費税 0円
【合計金額】
363,000円
【振込先】
〇〇銀行 〇〇支店 普通 〇〇〇〇〇〇〇〇
株式会社△△
【支払期日】
2025年2月28日
【備考】
振込手数料は貴社負担でお願いいたします。
品目・項目の書き方ポイント
品目や項目は、取引内容が明確にわかるように具体的に記載することが重要です。あいまいな表現は避け、誤解が生じないように注意しましょう。
似たような品目がある場合は区別できるように書く
似たような品目がある場合は、「商品A」と「商品B」といったシンプルな品名ではなく、「商品A(赤)」、「商品B(青)」のように、色やサイズなどの具体的な特徴を追記して区別しましょう。
セットの場合は含まれるものを書く(備考欄でも可)
セット商品を販売する場合は、セットに含まれる商品を具体的に記載することで、取引内容の透明性を高めます。たとえば、「商品セットA(商品C、商品D、商品Eを含む)」のように記載するか、備考欄に「商品セットAの内訳:商品C×1、商品D×2、商品E×1」のように記載しましょう。
サブスク形式の場合は対象の期間を書く
サブスクリプションサービスを提供する場合は、請求対象期間を明記しましょう。たとえば、「〇〇サービス利用料(2025年1月分)」のように記載します。
備考欄の例文集
備考欄には、請求書本文に記載しきれなかった補足事項や、取引先への連絡事項などを記載します。以下に、具体的な例文をいくつか紹介します。
振込手数料の取り扱いを備考欄に書く場合
「振込手数料は貴社負担でお願いいたします。」
「振込手数料は弊社にて負担いたします。」
セットの内訳や商品・サービスに含まれるものを備考欄に書く場合
「商品セットAの内訳:商品C×1、商品D×2、商品E×1」
「ランディングページ管理費には、セキュリティ管理および解析ツールの分析費用を含みます。」
これらの例文はあくまでも一例です。自社の状況に合わせて適宜修正してご利用ください。
請求書の送り方

請求書は、正しく相手に届いて初めてその役割を果たします。そのため、送り方にも注意を払う必要があります。主な送り方は郵送とデータ送信の2種類です。それぞれの方法についてくわしく見ていきましょう。
郵送する場合
請求書を郵送で送る場合は、以下の点に注意しましょう。
- 封筒の種類:請求書在中とわかる窓付き封筒が便利です。プライバシー保護のため、内容物が透けて見えないように配慮しましょう。
- 宛名の書き方:会社名、部署名、担当者名を正確に記載します。敬称は「御中」または「様」を使用します。
- 送付状の有無:金額が大きかったり、初めて取引をしたりする場合は、送付状を同封すると丁寧です。送付状には、請求書の送付目的、金額、支払期日などを記載します。
- 郵送方法:一般的には普通郵便で問題ありませんが、重要な請求書や期日が迫っている場合は、簡易書留や速達を利用することを検討しましょう。配達状況の確認ができるため、安心です。
- 折り方:三つ折りにして、宛名が読める向きで封筒に入れます。
郵送の場合、相手に届くまでに時間がかかるため、余裕を持って送付することが大切です。とくに月末月初は郵便物が多くなる傾向があるので、注意が必要です。また、郵送中に紛失するリスクもあるため、控えを必ず保管しておきましょう。
データで送る場合
データで送る場合は、PeppolによるデジタルインボイスかPDF形式が一般的です。内容が改ざんされるリスクを減らすことができ、多くのデバイスで閲覧できます。
デジタルインボイスを利用すれば、電子文書をネットワーク上でやり取りするための標準仕様で作成された請求書データが作れます。請求書を単なる電子ファイルとしてではなく直接データとして送受信するため、請求書データを社内システムに手作業で入力する必要がなくなります。発行者だけでなくお客さまにとっても事務効率が格段に向上するため、大変喜ばれます。
【関連記事:Peppol(ペポル)とは?】
PDF形式の場合は通常のメールで送付する方法のほか、請求書作成ツール経由でメール送信できることもあります。
データで請求書を送る際の注意点としては、以下の点が挙げられます。
- ファイル形式:PeppolによるデジタルインボイスかPDF形式が一般的です。編集可能な形式での送付は避けましょう。
- ファイル名:請求書番号や日付などを含め、一目で内容がわかるファイル名にしましょう。例:「請求書_20240101_001」
- メール本文:件名と本文には、請求書を送付した旨と、支払期日などを簡潔に記載しましょう。また、請求書ファイルがあることを明記することも忘れずに行いましょう。
- セキュリティ:請求書をファイル添付してメールを送ると、相手の設定次第で受信できないことがあります。また、ウイルス対策等の観点から、近年ではクラウドストレージにアップロードするなどして、添付ファイルを利用しないケースがほとんどです。送付時には、情報保護の観点から、パスワード設定や、暗号化して送付することも検討しましょう。
- ウイルス対策:メール送信前に、ウイルスチェックソフトでスキャンを行いましょう。
ツール経由でメール送信できる
請求書作成ツールの中には、作成した請求書をツール経由でメール送信できる機能が搭載されているものがあります。これらのツールを利用することで、本文作成の手間を省き、メールへファイルを添付するリスクを減らせます。また、送信履歴の管理も容易になるため、業務効率化につながります。
発行した請求書(請求書控え)の保管方法と保管期間

請求書は発行した後に控えを保管しておく必要があります。これは、取引内容の証明や税務調査の際に必要となるためです。適切な保管方法と保管期間を守ることで、トラブルを未然に防ぎ、スムーズな事業運営につなげましょう。
請求書控えの保管方法
請求書控えは、原本と同様に大切に保管する必要があります。紛失や破損を防ぐために、以下の方法を参考に適切な保管方法を選びましょう。
電子データでの保管
PDFなどの電子データとして保管する方法です。検索が容易で、場所も取らないため、近年主流となっています。データのバックアップを複数作成しておき、万が一のデータ消失に備えましょう。外部ストレージやクラウドサービスの利用も有効です。
紙媒体での保管
印刷した請求書をファイリングして保管する方法です。ファイリングの際は、日付や取引先などで整理しておくと、必要な請求書をすぐに探し出せます。湿気や直射日光を避け、適切な環境で保管しましょう。
| 保管方法 | メリット | デメリット | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 電子データ | 検索が容易、場所を取らない、バックアップが容易 | 記録媒体によってはデータ消失のリスク | 複数箇所にバックアップを取る、クラウドツールを利用する |
| 紙媒体 | 物理的な証拠として残る | 場所を取る、検索の手間、紛失・破損のリスク | ファイリングして整理する、適切な環境で保管する |
請求書控えの保管期間
請求書控えの保管期間は、法律によって定められています。主な関連法規と保管期間は以下のとおりです。保管期間は、確定申告書の提出期限の翌日から起算します。
| 法規 | 保管期間 |
|---|---|
| 法人税法 | 7年 |
| 所得税法 | 7年 |
| 消費税法 | 7年 |
| 電子帳簿保存法 | データ保存の場合は7年、スキャナ保存の場合は原本保存期間に準ずる |
上記に加えて、法人の青色繰越欠損金は10年間繰り越しができるため、実際には10年保存が原則と覚えておくと良いでしょう。
これらの法規以外にも、個別の契約で保管期間が定められている場合もあります。保管期間が重複する場合は、最も長い期間を適用する必要があります。また、税務調査や訴訟などに備えて、必要に応じて保管期間を延長することも検討しましょう。
請求書に関するよくある質問
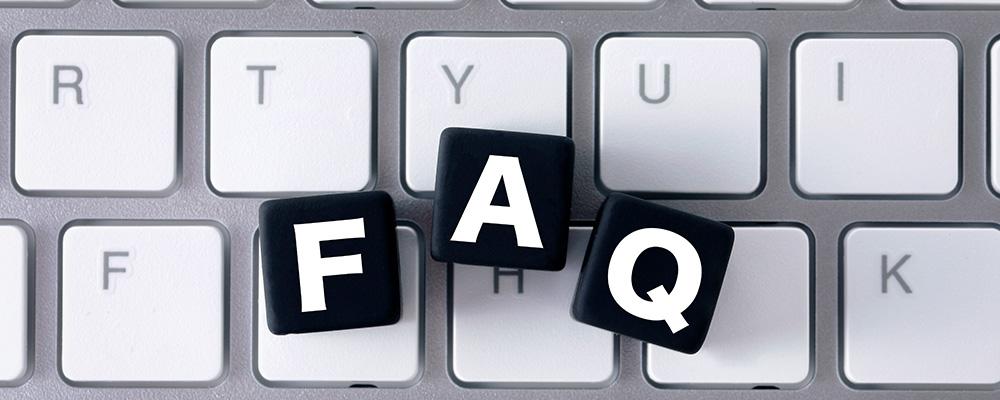
請求書に関するよくある質問をまとめました。記載内容に不安がある場合や、トラブルが発生した場合などは、以下の内容を参考にしてください。
請求書の再発行方法は?
請求書の再発行は、原本と同じ内容で作成し、「再発行」と明記するのが一般的です。発行日も再発行した日付を記載します。元の請求書の発行日を併記する場合もあります。電子データで保管している場合は、同じファイルを再送しても構いませんが、再発行であることを相手に伝えるようにしましょう。万が一、元の請求書と異なる内容で再発行する場合は、相手にその旨をきちんと説明し、同意を得ることが重要です。
請求書の訂正方法は?
請求書の訂正は、金額や数量など、軽微な誤りの場合は、二重線で誤りを消し、訂正印を押したうえで正しい内容を記載します。訂正箇所が多い場合や、重要な項目の誤りの場合は、再発行するのが望ましいでしょう。電子データの場合は、訂正版を作成し、バージョン番号を付けるなどして管理しましょう。また、訂正した内容については、相手に必ず連絡し、確認してもらうようにしてください。
請求書があれば、納品書や領収書は不要?
請求書、納品書、領収書はそれぞれ異なる役割を持つ書類です。請求書は代金の請求、納品書は商品の納入、領収書は代金を受け取ったことの証明となります。そのため、請求書のみで納品書や領収書の役割を果たすことはできません。取引の内容や相手方の要望に応じて、必要な書類を発行するようにしましょう。
代金と引き換えに商品を提供するときなどは、請求書に領収書の代わりとなる文言を記載することで、領収書を省略できる場合があります。具体的には、「本書をもって領収書に代えさせていただきます。」といった文言を記載します。ただし、取引内容によっては、3つの書類すべてを発行することが望ましい場合もあります。
| 書類 | 発行者 | 受領者 | 目的 |
|---|---|---|---|
| 請求書 | 商品・サービスの提供者 | 商品・サービスの受領者 | 代金の請求 |
| 領収書 | 代金を受け取った者 | 代金を支払った者 | 代金受領の証明 |
| 納品書 | 商品・サービスの提供者 | 商品・サービスの受領者 | 商品・サービスの納入を証明 |
適格請求書発行事業者の場合、納品書や領収書にも登録番号の記載が必要?
適格請求書発行事業者の場合、適格請求書(インボイス)には登録番号の記載が必須です。しかし、納品書や領収書には登録番号の記載は必須ではありません。ただし、取引先が適格請求書発行事業者である場合は、登録番号を記載することで、相手方の仕入税額控除の手続きがスムーズになります。そのため、可能な限り登録番号を記載することが推奨されています。
なお、納品書に適格請求書の記載事項を記入している場合は、適格請求書として利用することが可能です。
スムーズ・適切な請求書作成で取引先との信頼関係UP
この記事では、請求書の書き方について、初心者の方にもわかりやすく解説しました。請求書の種類、必須記載事項、手書きとデジタルそれぞれでの作成方法、テンプレート、送り方、保管方法など、網羅的に説明しました。請求書はビジネスにおける重要な書類です。正しく効率的に作成し、取引先との信頼関係を築きましょう。






