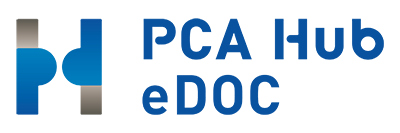証憑とは? 種類や保存期間、電子化のメリットを確認
更新日:2023/07/11
証憑とは? 種類や保存期間、電子化のメリットを確認


企業活動において、取引の正当性・妥当性を証明するには“証拠”が必要です。この証拠となる書類を「証憑」や「証憑書類」ともいいますが、証憑にはどのような種類があるのでしょうか?
ここでは、証憑の概要や種類、法で定められた保存期間について解説します。また証憑を電子化するメリットについてもご紹介していますので、合わせてお読みください。
証憑とは? 読み方や証票・帳票との違い
証憑は「しょうひょう」と読み、『企業が取引を行った証拠になる書類』を意味します。
企業では契約、代金の支払い、労働に関する取り交わしや企業経営など、さまざまなシーンで「履行したことの証明になる書類」を発行します。
【証憑の代表的な例】
- 契約書、請求書、領収書
- 発注書、納品書、見積書、検収書
- 雇用契約書、給与支払証明書、賃金台帳、業務委託契約書など
証憑の必要性
契約そのものは口頭(口約束)でも成立しますが、その“証拠”を残していないと「言った・言わない」のトラブルに発展することがあります。また、証憑を残していれば、円満かつスムーズな取引ができます。それぞれの認識の違いが生じていても、証憑が「根拠」となるため、正確な内容を確認できます。
その他、“税務申告を正しく行っている根拠”としても証憑は必要不可欠であり、証憑が揃っていないと「虚偽申告を行っている」として修正、追徴課税等のペナルティを求められることもあります。
「ビジネスに関する取引、約束、申告を正しく行う証明書類」として、証憑は欠かせないものなのです。
証憑と証票・帳票の違いとは?
証憑と混同されがちな言葉に「証票」「帳票」があります。
証票
証票は「しょうひょう」と読みます。
証憑と読み方は同一ですが、証憑が『取引の証拠になる書類』であるのに対し、証票は『何かを証明する紙片や札、書きつけ』という意味です。
よって証憑=書類だけではなく、資格証などのカード、会社の看板なども「証票」に含まれます。
帳票
帳票(ちょうひょう)は、帳簿や伝票のことで、さらにくわしく言えば、取引や会計といった、経営に関する“お金の動き”を記録した書類です。
【帳簿】
- 仕訳帳
- 総勘定元帳
【伝票】
- 売上伝票
- 仕入伝票
- 出金伝票
- 経費精算伝票
- 振替伝票
なお仕訳帳・総勘定元帳など、取引が発生するたびに記入する帳簿は「主要簿」といいます。
一方、それ以外の補助的な記録帳簿を「補助簿」と呼んでいます。主要簿や補助簿を作成するもとになる書類=個々の取引を記録したものが「伝票」です。
証憑の種類
冒頭で証憑に含まれる書類の代表例をご紹介しましたが、これらは大きく4種類に分類できます。
売上関連
売上関連の証憑は、“売上の根拠”として取引・売買を行ったことの証明になる書類です。
【売上関連の証憑の代表例】
- 見積書……商品・サービスの提供対価を概算し、提示する書類。企業や個人の依頼によって発行される。
- 納品書……納品する商品の明細が記された書類。商品提供側(納品者)が発行する。
- 売買契約書……商品やサービスに対する売買契約を結んだことを証明する書類。
- 請求書……商品・サービスの対価として金銭を請求する書類。
- 領収書……商品・サービスを受け取り、代金を支払ったことを証明する書類。
売上関連の証憑を残すことは企業の売上やお金の出入りを証明することでもあります。
よってこれらは特に重要性が高く、厳重な管理が必要です。
仕入関連
企業では仕入に関する証憑を扱う機会が多々あります。
【仕入関連の証憑の代表例】
- 見積書……商品・サービスの提供対価を概算し、提示した書類。企業や個人の依頼によって発行される。
- 発注書……取引の際の注文内容を記した書類のこと。
- 納品書……納品された商品の明細が記された書類。商品提供側(納品者)が発行する。
- 受領書……「商品やサービスを受領したこと」を証明する書類。
- 検収書……商品を検収した(発注品が品質・数量・仕様に合っていると確かめ受け取った)証明となる書類。
- 棚卸表……在庫商品の数量・金額をカウントし、一覧化した表
売上に関連する証憑と重複するものもありますが、発行する立場と受領する立場が入れ替わります。
商品の仕入では発注書、納品書をもとに個数調整を行われるケースが多く、在庫管理にも役立ちます。
商品の仕入は、提供元と仕入側が「仕様」「単価」「個数」を話し合い、契約合意をしたうえで行われます。
万が一契約内容にそぐわない内容(仕様が違う、単価が違うなど)で納品された場合でも、証憑があれば返品や交換を要求しやすくなるでしょう。
経費精算関連
領収書は「売上に関する証憑」のひとつですが、経費精算において「支払を証明する証憑」としても用いられます。
【経費精算関連の証憑の代表例】
- 領収書……商品・サービスの対価として金銭を支払った証明となる書類
- レシート、クレジットカードの支払証明書……領収書と同じく、支払の証明になる。
経費精算においては、レシート、クレジットカードの支払証明書なども重要な証憑です。
証憑が「経営に関与する支出があったこと」の証明となるため、経費精算、ひいては税務管理の正当性が保たれます。
給与・人事関連
給与・人事関連の証憑には、以下のとおり従業員の給与や雇用契約、業務委託契約に関する書類があてはまります。
【給与・人事関連の証憑の代表例】
- 賃金台帳……従業員の給与支払い状況を記録した書類
- 給与支払証明書(給与明細)……従業員に発行される「給与の総額および控除額」等を通知する書類
- 雇用契約書……雇用主と従業員との雇用契約を明示する書類
- 業務委託契約書……外注業者との業務委託契約を締結するための書類
給与関連の証憑は、企業側が従業員に対し適切な給与を支払っているかを証明するものです。給与の未払いなどのトラブルが発生した場合、「労働の対価を払っている」という正当性を示す根拠として使えます。
また、雇用契約書は「どのような条件で雇用契約を結んだか」を証明する証憑です。従業員または企業のいずれかで契約内容違反が生じた場合、この雇用契約書を“契約内容の根拠”としてトラブル解決を目指すことになるのです。
証憑の保存期間
証憑は法律で保存期間が決められています。その期間は法人税法、会社法によって異なり、勝手に捨てることは禁じられています。
法人税法、会社法それぞれの証憑保存期間を把握しておきましょう。
(法人)税法での期間
所得税や法人税など、「税法」における証憑の保存期間は、確定申告の提出期限翌日から5~7年となっています。この保存期間は紙、電子データ共通です。
また、保存期間については証憑の種類、および前々年の所得によっても変わります。
| 保存が必要な帳簿・証憑 | 法定保存期間 | ||
|---|---|---|---|
| 帳簿 |
|
7年 | |
| 書類 | 決算関係書類 |
|
7年 |
| 現金預金取引等関係書類 |
|
7年 ※前々年分所得が300万円以下の事業者は5年 |
|
| その他の書類 | 取引に関して作成し、又は受領した上記以外の書類 | 5年 | |
ちなみに、青色申告において「青色繰越欠損金が生じた事業年度」、および「災害損失欠損金額が生じていて、かつ青色申告書を提出していない年度」については、帳簿・証憑の保存期間が10年間に延長されます。
| 証憑の種類 | 保存期間の起算日 | 保存期間 |
|---|---|---|
| 株主総会議事録 | 株主総会の開催日から | 10年間 |
| 取締役会議事録 | 取締役会の開催日から | |
| 決算書、財務諸表、計算書類 | 作成日から | |
| 会計書類 | 帳簿閉鎖時から | |
| 会計参与報告定時 | 株主総会開催日の1週間前 ※取締役会設置会社は2週間前 |
5年間 |
| 臨時計算書類 | 作成日から | |
| 株主総会に関する文書 (代理権の証明、議決権行使) |
株主総会の開催日から | 3ヶ月間 |
国税関係の証憑との違いは、保存期間の「起算日(保存がスタートする日)」がそれぞれ異なる点です。
証憑は電子化できる! 電子化のメリットとは?

ビジネスにおいて証憑は長らく紙ベースでの発行、管理が行われてきました。しかし近年は電子帳簿保存法の改正により、要件を満たせば電子データ形式での保存が認められています。
電子帳簿保存法の改正で電子化しやすくなった
電子帳簿保存法とは、ビジネスにおける国税関係書類の「電子保存」に関する法律です。
また日本においてはより幅広い書類の電子保存を認める「e-文書法」という法律もあり、時代の変化とともに改正が重ねられてきました。
電子帳簿保存法ではデータ検索ができることなどを条件に、電子帳簿等保存(PC等で作成した電子データを記録媒体等に保存する)やスキャナ保存(紙の証憑等をスキャンし、電子データ化して保存する)などの保存方法が認められています。
また、企業間等で書類データをやり取りする際には、タイムスタンプの付与などを施したうえで「電子取引」をすることも認められています。
2023年には改正が行われ、一定の要件を満たす事業者に対し、条件付きで“検索要件”が不要となりました。また同法における「電子取引でも証憑をプリントアウトし、保存していれば電子データの保管とみなす」といった措置が、2023年12月31日をもって廃止されます。
つまり企業においては、証憑を含む文書・帳簿等の電子化を進めることが実質的に推奨されているのです。
証憑を電子データ化するメリット
証憑を電子化すると、さまざまな恩恵が受けられます。
- ペーパーレス化が進み、コスト削減につながる
- 検索性が上がり、業務効率アップにつながる
- 証憑の保存期間がわかりやすく、管理も楽になる
- テレワークの促進につながる
- 書類持ち出しなどの漏洩リスクを低減できる
特に大きなメリットは「コスト削減」「業務効率アップ」が両立できる点でしょう。
紙の証憑の場合、「プリントアウトのためのインク代・紙代」「保管のためのファイリング・収納・場所代」といったさまざまなコストが必要です。一方、電子化してしまえばPCで管理ができ、紙などのコストが発生することもありません。保管のための物理スペースが不要になれば、オフィスを縮小するなどしてさらなるコストダウンをはかることもできます。
また、電子データ化して一元管理をすることで、証憑の検索性もアップします。探したいデータがすぐに見つかれば業務効率がアップしますし、業績にも良い影響が表れる可能性が高いでしょう。
電子データであれば「いつ作成・保存した書類なのか」が明確なので、作成から保存・廃棄といった管理も楽です(電子帳票管理ツールの中には、保存期限が終了間近になると自動削除してくれるものもあります)。
そのほか、証憑を電子化すると「テレワークの促進」「紙の書類持ち出し・紛失などによる漏洩リスクの低減」といった効果も期待できます。回覧による回収までのタイムラグやハンコによる押印の手間、持ち出しの可能性といった“紙ならではのデメリット”が解消されるのは、企業にとっても大きなメリットといえるでしょう。
まとめ
取引の根拠となる「証憑」は、円滑な企業経営を行う上で必要不可欠なものです。法律でも保存期間が定められているため、法人はもちろん個人事業においても適切な期間の保存、廃棄を徹底しましょう。
また、証憑は電子化することで多数のメリットが得られるようになります。一部証憑については紙での発行・保存が義務付けられているものもありますが(事業用借地権設定契約書、棚卸表など)、それ以外は電子保存が認められているもののほうが多いです。
このような事情やメリットを把握したうえで、まだ電子化に至っていない企業については電子化を検討してみてはいかがでしょうか。
『PCA Hub eDOC』なら電子帳簿保存法(電子取引やスキャナ保存)に必要な機能を搭載しており、大きな費用をかけることなく、簡単に始めることができます。『PCA会計シリーズ』をご利用でないお客様も『PCA Hub eDOC』をお使いになることができますが、『PCA会計シリーズ』をご利用の場合は取引と仕訳を紐づけることができ、さらに便利にご活用いただけます。