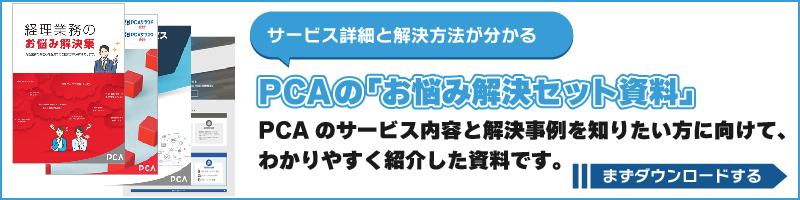グループ会社・子会社・関連会社の違いとは?言葉の定義や会計処理の方法を解説
更新日:2025/08/29

「グループ会社」「子会社」「関連会社」「関係会社」—これらの言葉の定義や違いは、さまざまな届け出や手続きなどの際に気になるものですね。本記事では、会社法や金融商品取引法、会計処理の観点から、それぞれの言葉が指す範囲と具体的な取り扱いを徹底解説します。結論として、「グループ会社」は包括的な概念であり、「子会社」や「関連会社」はその中に位置づけられます。曖昧だった企業間の関係性を整理し、ビジネスシーンでの適切な理解と判断ができるように最後までご覧ください。
グループ会社・子会社・関連会社・関係会社の定義
「グループ会社」「子会社」「関連会社」「関係会社」という言葉は日常的に使われますが、それぞれの言葉が持つ意味や法的な定義、会計上の取り扱いは異なります。
「支配の程度」「資本関係」「組織図から見る関係性」に注目
企業間の関係性を理解するうえで重要なのは、「支配の程度」、すなわちある会社が別の会社に対してどれだけの意思決定権や影響力を持っているかです。これに加えて、「資本関係」(出資比率や議決権の保有状況)、そして「組織図から見た関係性」という視点からそれぞれの言葉の定義を見ていくことで、より明確に違いを把握できます。
グループ会社とは
グループ会社とは、法的な定義があるわけではなく、一般的に親会社と子会社、あるいは関連会社を含む企業集団全体の総称として使われる言葉です。親会社が中心となり、複数の子会社や関連会社を傘下に持つことで、事業の多角化や効率化を図るケースが多く見られます。「○○グループ」といった呼称は、このグループ会社という概念に基づいています。
グループ会社は、必ずしもすべての会社が連結会計の対象となるわけではなく、会計上の「連結子会社」や「持分法適用会社」とは異なる、より広範な意味合いで用いられることが多いのが特徴です。
子会社とは
子会社とは、他の会社(親会社)に「支配されている」会社を指します。その定義は、会社法や会計基準(企業会計基準)によって定められています。
親会社に「支配されている」会社(会社法における定義)
会社法においては、ある会社が他の会社の議決権の過半数を保有している場合、その会社は子会社と定義されます。これは、親会社が子会社の株主総会の決議を支配し、その経営方針を決定できる状態にあることを意味します。
議決権の過半数を保有する場合
最も一般的な子会社の定義は、親会社がその会社の議決権の過半数(50%超)を保有している場合です。これにより、親会社は子会社の株主総会における意思決定権を確保し、取締役の選任や事業計画の承認など、重要な事項をコントロールできます。
実質的な支配力基準とは
議決権の過半数を保有していなくても、実質的にその会社を支配していると認められる場合にも子会社とみなされることがあります。これを「実質的な支配力基準」と呼び、主に会計基準において適用されます。
具体的には、以下のような状況がある場合、議決権の保有割合にかかわらず子会社と判断される可能性があります。
- 他の会社の役員の過半数を自己または自己の子会社、あるいは自己と密接な関係にある者が占めている場合
- 他の会社の重要な財務・営業または事業の方針決定を支配する契約等が存在する場合
- 他の会社の資金調達額の過半について融資を行っている場合
- その他、他の会社を支配していると認められる事実がある場合
関連会社とは
関連会社とは、他の会社(親会社)に「重要な影響を受けている」会社を指します。子会社のように完全に支配されているわけではありませんが、親会社の意向がその会社の経営に大きく反映される関係性です。
親会社に「影響を受けている」会社
関連会社は、親会社がその会社の財務および営業または事業の方針決定に対して、重要な影響を与えることができる会社として定義されます。これは、主に会計上の概念であり、連結決算において「持分法」が適用される対象となります。
議決権の20%以上50%以下を保有する場合
関連会社と判断される最も一般的な基準は、親会社がその会社の議決権の20%以上50%以下を保有している場合です。この範囲の議決権保有は、通常、その会社の意思決定に重要な影響を与える力があるとみなされます。
財務・営業・事業の方針決定に重要な影響を与える場合
議決権の保有割合が20%未満であっても、以下のような状況がある場合、実質的に重要な影響力があると判断され、関連会社とみなされることがあります。
- 他の会社の役員または従業員を派遣し、その会社の財務および営業または事業の方針決定に関して重要な影響を与えることができる場合
- 他の会社の重要な融資元である場合
- 他の会社との間に重要な技術提携、販売契約等の継続的な契約が存在する場合
- その他、他の会社に対して重要な影響を与えることができると認められる事実がある場合
関係会社とは
関係会社とは、金融商品取引法等に関連する広範な概念です。子会社と関連会社の両方を含むだけでなく、親会社自身や、親会社が子会社や関連会社を介して間接的に支配・影響を及ぼす会社なども含まれることがあります。
金融商品取引法と関係会社の定義
関係会社は、主に上場企業が作成する有価証券報告書などの開示書類において用いられます。金融商品取引法関連法令では、親会社、子会社、関連会社、およびこれらの会社と密接な関係にある会社を総称して「関係会社」と定義しています。これは、投資家が企業の全体像を把握できるよう、より広い範囲の企業グループ情報を開示することを目的としています。
参考:財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則|eGoV 法令検索
以下に、各会社の定義と主な特徴をまとめます。
| 区分 | 定義・特徴 | 主な判断基準(議決権比率) | 法的・会計上の根拠 |
|---|---|---|---|
| グループ会社 | 親会社・子会社・関連会社を含む企業集団の総称。法的な定義なし。 | - | 一般的な呼称 |
| 子会社 | 親会社に「支配されている」会社。 | 議決権の過半数(50%超)を保有、または実質的な支配力がある場合。 | 会社法、企業会計基準 |
| 関連会社 | 親会社に「重要な影響を受けている」会社。 | 議決権の20%以上50%以下を保有、または実質的な影響力がある場合。 | 企業会計基準 |
| 関係会社 | 子会社、関連会社、および親会社を含む広範な企業集団の総称。 | - | 金融商品取引法関連法令 |
グループ会社と子会社・関連会社・関係会社との違い
ここでは、「グループ会社」と、具体的な定義を持つ「子会社」「関連会社」「関係会社」がどのように異なるのかを、それぞれの設立目的や企業としての働き方に焦点を当てて解説します。
グループ会社と子会社との違い
グループ会社は、親会社とその子会社、さらには関連会社など、資本関係や人的関係によって結びついた企業群全体の総称です。一方、子会社は、親会社に「支配されている」という明確な法的・会計的定義を持つ会社を指します。
設立目的の違い
| カテゴリー | グループ会社 | 子会社 |
|---|---|---|
| 設立目的 | 経営戦略上の概念として、事業多角化、リスク分散、シナジー効果の創出、ブランド力強化などを目指し、複数の会社を一体的に運営する。 | 親会社が特定の事業活動を行うために設立・買収し、その事業を専門化・効率化させる。親会社の事業拡大や地域戦略の実行手段となる。 |
グループ会社は、あくまで経営上の戦略的な概念であり、個々の会社が持つ具体的な目的とは異なります。子会社は、親会社の特定の事業目的を達成するための「実行部隊」としての役割を担うことが多いでしょう。
働き方の違い
| カテゴリー | グループ会社 | 子会社 |
|---|---|---|
| 働き方 | グループ全体として連携・協力しながら、各社が独立性を保ちつつ、グループ全体の目標達成に向けて活動する。 グループシナジーを追求する。 | 親会社の経営方針や戦略に従い、その指示・監督の下で事業活動を行う。 親会社の意向が事業運営に直接的に反映される。 |
子会社は、親会社からの支配を受けているため、その経営判断や事業運営は親会社の意向に左右されることもあります。これに対し、グループ会社という概念の中では、各社が独立性を保ちながらも、グループ全体の利益を最大化するための協力関係が重視されます。
グループ会社と関連会社との違い
関連会社は、親会社が「重要な影響を与えることができる」会社を指し、子会社のような「支配」の関係にはありません。
設立目的の違い
| カテゴリー | グループ会社 | 関連会社 |
|---|---|---|
| 設立目的 | 経営戦略上の概念として、事業多角化、リスク分散、シナジー効果の創出、ブランド力強化などを目指し、複数の会社を一体的に運営する。 | 親会社が特定の事業分野で連携・協力関係を築くため、または事業投資の目的で出資する。 支配ではなく、事業上の協業や情報共有を通じて相互にメリットを追求する。 |
関連会社は、親会社にとって完全に支配下に置かれるものではありません。事業活動が自社に影響を与える可能性がある場合に、親会社が戦略的なパートナーシップとして出資するケースもあります。これにより、技術提携や販路拡大など、双方にとって有益な関係を築くことを目指します。
働き方の違い
| カテゴリー | グループ会社 | 関連会社 |
|---|---|---|
| 働き方 | グループ全体として連携・協力しながら、各社が独立性を保ちつつ、グループ全体の目標達成に向けて活動する。 グループシナジーを追求する。 | 親会社から独立した経営を行いながらも、親会社の経営方針に重要な影響を受ける。 親会社との協業や情報共有を通じて、相互にメリットを追求する。 |
関連会社は、子会社と異なり、親会社からの直接的な支配は受けません。しかし、議決権の保有や役員の派遣などを通じて、親会社がその経営に「重要な影響を与える」ことができるため、緩やかな連携の中で事業活動を行います。
【関連記事:人手不足の時代は「仲間」の領域が広がる】
グループ会社と関係会社との違い
グループ会社は経営上の集合体であるのに対し、関係会社は法的な開示義務を伴う概念です。
設立目的の違い
| カテゴリー | グループ会社 | 関連会社 |
|---|---|---|
| 設立目的 | 経営戦略上の概念として、事業多角化、リスク分散、シナジー効果の創出、ブランド力強化などを目指し、複数の会社を一体的に運営する。 | 金融商品取引法に基づき、企業の財務状況や事業活動の透明性を確保するため、親会社、子会社、関連会社など、特定の関係にある会社を包括的に定義し、情報開示の対象とする。 |
関係会社は、企業が投資家や市場に対して適切な情報を提供するための法的な枠組みであり、特定の事業目的を持って設立されるものではありません。あくまで、企業間の関係性を明確にし、開示義務を課すための概念です。
働き方の違い
| カテゴリー | グループ会社 | 関連会社 |
|---|---|---|
| 働き方 | グループ全体として連携・協力しながら、各社が独立性を保ちつつ、グループ全体の目標達成に向けて活動する。グループシナジーを追求する。 | 関係会社という概念自体が特定の働き方を規定するものではない。 個々の関係会社(子会社、関連会社など)の定義に基づき、それぞれの働き方をする。法的な情報開示義務を負う点が共通する。 |
関係会社という言葉は、あくまで法律上の分類であり、個々の会社がどのように事業を行うかを示すものではありません。子会社であれば親会社の支配下で、関連会社であれば親会社の影響を受けながら、それぞれの役割を果たすことになります。
会計処理におけるグループ会社・子会社・関連会社の取り扱い
企業グループの会計処理は、個々の会社の独立した会計処理とは異なり、企業集団全体の実態を正確に把握するための特別なルールが存在します。とくに、子会社や関連会社の存在は、連結会計という考え方に基づいて処理されます。
連結会計の基本と目的
連結会計とは、親会社と子会社を一つの企業集団とみなし、それらの財務諸表を合算して作成する会計処理のことです。これにより、個々の会社では見えにくい企業グループ全体の財政状態や経営成績を明らかにできます。
連結会計の主な目的は以下のとおりです。
- 企業集団の実態把握:親会社が子会社を支配している場合、子会社の業績は実質的に親会社の業績に影響する。連結会計により、グループ全体の事業活動を包括的に捉えられる。
- 投資家保護:投資家や債権者などの利害関係者は、企業グループ全体の情報を知ることで、より的確な投資判断や融資判断が可能となる。
- 多角化する事業への対応:事業の多角化やグローバル展開が進む中で、連結会計は複雑な企業構造を透明化するうえで不可欠。
子会社と連結決算の関係
子会社は、親会社に「支配されている」会社であり、原則として連結決算の対象となります。連結決算では、親会社と子会社の資産、負債、収益、費用を合算し、グループ内での取引(相殺消去)などを調整することで、あたかも一つの会社であるかのような財務諸表を作成します。
子会社には、連結の対象となる「連結子会社」と、特定の理由により連結の対象とならない「非連結子会社」があります。
連結子会社と非連結子会社
連結子会社は、親会社がその意思決定機関を支配していると認められる子会社を指します。具体的には、議決権の過半数を保有している場合や、役員の過半数を派遣している場合などが該当します。
一方、非連結子会社は、子会社であるにもかかわらず、連結決算の対象とならない会社です。これは、企業会計基準によって定められた特定の条件に合致する場合に限られます。
| 定義・条件 | 会計処理上の取り扱い | |
|---|---|---|
| 連結子会社 | 親会社に「支配されている」子会社(議決権の過半数保有、実質的な支配力基準など) | 原則として連結財務諸表に含めて合算処理(連結範囲) |
| 非連結子会社 | 重要性が乏しい子会社(連結財務諸表に与える影響が軽微)、含み損がない会社、一時的な支配の子会社など | 連結財務諸表には含めず、親会社の単体決算では「投資有価証券」として計上。ただし、重要性が乏しい場合を除き、持分法を適用することがある。 |
【関連記事:「敬意」が非財務情報を形成し、財務情報に連動する】
関連会社と持分法適用会社
関連会社は、親会社に「影響を受けている」会社であり、連結決算の対象とはなりませんが、「持分法」という会計処理が適用されることがあります。持分法とは、投資会社(親会社)が被投資会社(関連会社)に対して重要な影響を与えている場合に、その投資勘定を被投資会社の純資産の変動に応じて増減させる会計処理方法です。
具体的には、親会社が関連会社の議決権の20%以上50%以下を保有している場合や、議決権保有比率が20%未満であっても役員派遣などで財務・営業・事業の方針決定に重要な影響を与えている場合に、持分法が適用されます。
持分法を適用する関連会社は「持分法適用会社」と呼ばれ、親会社の連結損益計算書には、関連会社の当期純利益のうち親会社の持分相当額が「持分法による投資損益」として計上されます。
グループ会社の独立した会計処理
連結会計は企業集団全体の実態を表すものですが、グループ内の個々の会社は、法的には独立した法人です。そのため、親会社、子会社、関連会社それぞれが、税務申告などの目的で個別の「単体決算」(個別財務諸表)を作成する必要があります。
単体決算では、各会社が独立した事業体として、その会社自身の取引のみを記録し、財務諸表を作成します。連結会計は、これらの単体決算をベースに、グループ間の取引を消去したり、子会社の財務諸表を合算したりして作成される二次的な財務情報という位置づけになります。
親会社の単体決算における扱い
親会社の単体決算では、子会社や関連会社への投資は、原則として「投資有価証券」として資産に計上されます。これは、親会社が子会社や関連会社の株式を保有していることを意味します。
子会社から親会社へ配当金が支払われた場合、親会社の単体決算では、その配当金は「受取配当金」として収益に計上されます。連結決算では、グループ内の配当金は相殺消去されますが、単体決算では個別の収益として認識される点が異なります。
このように、単体決算と連結決算では、子会社や関連会社への投資の表示方法や、グループ内取引の取り扱いが大きく異なります。それぞれの目的と役割を理解することが重要です。
【関連記事:経費精算とは?経費の対象となる費用や基本的な流れ、業務効率化のポイントを解説】
グループ会社のバックオフィス業務を効率的にするには
複数の会社で構成されるグループ経営において、バックオフィス業務の効率化は、グループ全体の生産性向上とコスト削減に直結する重要な課題です。各社が独立して業務を行うことで生じる非効率や重複を解消し、最適な運営体制を構築することが求められます。
属人化を防ぐ
グループ会社では、子会社ごとに異なるシステムや業務フローが導入されていることが多く、特定の担当者しか業務内容を把握していない「属人化」が発生しがちです。業務が属人化していると、担当者の退職や異動時に業務が滞るリスクが高まります。
属人化を解消するためには、グループ全体で業務プロセスの標準化を進め、共通のシステムやツールを導入することが有効です。たとえば、経費精算システムや会計システムを統一し、マニュアルを整備することで、誰でも業務を遂行できる体制を構築できます。これにより、業務の継続性を確保し、品質の均一化も図れます。
【関連記事:請求書の電子化とは?発行側・受取側のメリットと導入時のポイントを解説】
作業の遅れにつながる心理的負担解消
グループ会社間での複雑な連携や承認フローは、担当者の心理的な負担を増大させ、作業の遅延を招く原因となることがあります。とくに、複数の子会社をまたがる承認やデータ連携が必要な場合、担当者はミスを恐れて慎重になりすぎたり、コミュニケーションコストが増大したりします。
この負担を軽減するためには、自動化が有効です。自動化ツールを導入すれば、承認プロセスが可視化され、自動で次のステップに進むため、担当者の確認作業が減り、精神的なプレッシャーが軽減されます。結果として、業務スピードが向上し、より創造的な業務に時間を割けるようになります。
【関連記事:経理におけるAIの活用は?活用状況や経理の仕事がなくなると言われる理由を解説】
ペーパーレス・リアルタイム化
紙ベースの書類管理は、物理的な保管スペースを必要とし、情報共有に時間がかかるだけでなく、検索性も低いという課題があります。とくにグループ会社間での書類のやり取りが多い場合、郵送やFAXなどの手間がかかり、リアルタイムでの情報共有が困難になります。
これを解決するためには、クラウドベースの文書管理システムや電子契約システムの導入を進め、ペーパーレス化を徹底することが不可欠です。これにより、必要な情報にいつでもどこからでもアクセスできるようになり、グループ会社間での情報共有がリアルタイムで可能になります。また、物理的な保管コストの削減や、リモートワークへの対応力強化にもつながります。
【関連記事:請求書の書き方完全ガイド!初心者でも完璧な請求書を作成できるテンプレート&例文集】
コスト削減
グループ会社がそれぞれ独立してシステムを導入したり、バックオフィス部門を抱えたりすると、重複投資や非効率な人員配置が生じ、グループ全体としてのコストが増大する可能性があります。
コスト削減を実現するためには、グループ共通の基幹システムを導入し、バックオフィス業務を集約することが効果的です。たとえば、経理、人事、総務といった機能を集約することで、専門性の高い人材を効率的に配置し、システムのライセンス費用や運用コストを削減できます。また、定型業務を自動化することも、人件費の抑制に寄与します。
グループ会社の違いを理解して効率的な会計処理をするなら「PCAクラウド会計」
本記事では、「グループ会社」「子会社」「関連会社」の定義と、それぞれの明確な違いを解説しました。とくに子会社は親会社に「支配」され、関連会社は「影響」を受けるという資本関係や実質的な支配力が判断基準となります。これらの違いは、連結決算や持分法適用といった会計処理にも大きく影響します。
企業間の関係性を正しく理解し、適切な経営戦略の立案や、グループ全体のバックオフィス業務効率化を行っていきましょう。20,000法人の導入実績を持つPCAクラウド会計シリーズなら、ワークフローや自動化ツールを利用でき、複雑な会計処理や法令対応に悩まされることなく、年間約432時間もの業務削減が可能です。
以下のボタンから体験のお申し込みをして、ぜひ機能を実感してください。