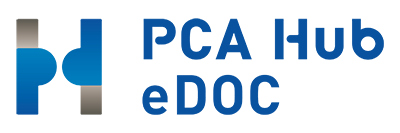経理におけるAIの活用は?活用状況や経理の仕事がなくなると言われる理由を解説
更新日:2025/05/20
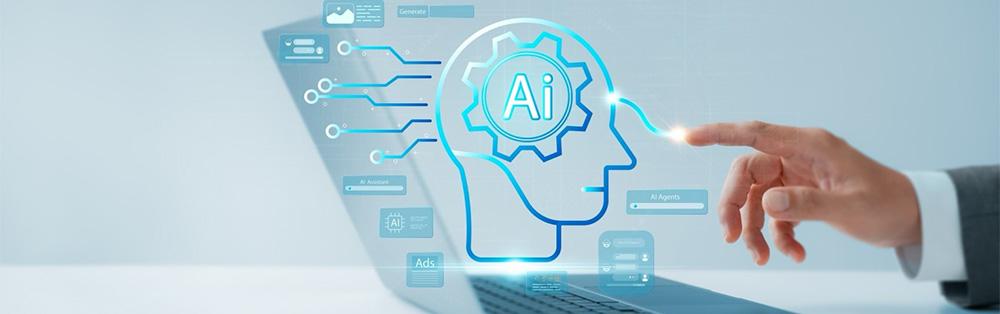
近年、AI(人工知能)の急速な進化により、さまざまな業務が自動化されつつあります。そのなかでも特に注目されているのが経理業務です。
「経理の仕事は将来AIに取って代わられるのではないか」といった不安を耳にすることもありますが、実際にはどうなのでしょうか。
本記事では経理分野におけるAIの活用現状や、導入が進む背景、AIによって変わる業務内容などを具体例とともに解説します。
これからの経理担当者に求められるスキルについてもご紹介しますので、業務改革やキャリア形成の参考にしてみてください。
経理におけるAI活用の現状
経理業務におけるAIの導入は、すでに多くの企業で始まっています。
特に会計処理の自動化やデータの読み取り、請求書処理、仕訳作業といったルーティン業務への適用は積極的に進んでおり、業務効率の向上や人的ミスの削減に貢献しています。
また経理分野でのAI導入は、大企業だけでなく中小企業にも広がりつつあります。
AIを搭載したクラウド型会計ソフトや、AI-OCR(手書き文字や印刷文書を読み取る技術)など、手軽に導入できるツールも多く登場しています。
これにより、「経理=手作業中心」の時代から、「経理=テクノロジー活用による戦略的業務」への転換が進みつつあるのが現状です。
経理でAIの導入が進む3つの背景
経理業務にAIが導入される背景には、3つの大きな要因があります。
- 人手不足の深刻化
少子高齢化の影響で、経理人材の確保が難しくなっています。
特に年次決算などの繁忙期に人員が不足することも多く、業務効率化の必要性が高まっています。
- 働き方改革・残業削減への対応
経理は繁忙期の残業が多くなりがちな部門です。AIを活用して定型業務の処理スピードを上げることで、長時間労働の削減にもつながります。
- 膨大なデータの処理と分析が求められる時代
経理業務に求められる役割が「単なる記録」から「経営判断のためのデータ提供」へと変わってきており、その変化に対応するにはAIの力が不可欠です。
経理業務におけるAIとRPAの違い
AIと混同されやすい技術に「RPA(Robotic Process Automation)」がありますが、両者には明確な違いがあります。
| 比較項目 | AI(人工知能) | RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション) |
|---|---|---|
| 概要 | 学習・判断・予測ができる | 手順を定型化して自動実行する |
| 主な活用範囲 | 非定型業務(仕訳判断、予測分析など) | 定型業務(データ入力、ファイル転送など) |
| 学習能力 | 自律的に学習して改善する | 学習機能はない(人が操作ルールを定義) |
RPAはあらかじめ決められたルールに従って動作します。一方AIは、過去のデータから学習し、状況に応じて自動的に判断を下すことができます。
AIがよく活用されている経理業務
AIが導入されやすい業務には共通する特徴があります。
それは以下の3点です。
①ルールが明確
②繰り返しが多い
③大量のデータを扱う
経理業務の業務では、精度とスピードが求められる一方で人の判断が不要なケースが多く見られます。以下の業務についてはAIとの親和性が高く、特に活用が進んでいます。
領収書や請求書のデータ化(AI-OCR)
取引先ごとに形式が異なる帳票も、AI-OCRが自動で読み取り、クラウド会計ソフトに連携することで入力ミスや業務負担を大幅に削減。勘定科目や金額などをAIが自動で仕訳し、大量の伝票処理も短時間で完了します。
経費精算の自動処理
社員の申請内容をAIがチェックし、規定に沿って自動承認または差し戻しを判断するシステムも登場。不正な経費やミスをAIが検知し、申請内容を自動でフラグ付けするなどの活用も進んでいます。審査業務の時間短縮に効果があります。
売掛・買掛金管理
支払い予定や入金状況をAIがモニタリングし、異常や遅延の兆候を早期に検知。債権管理の効率化にも貢献しています。
予算管理・シミュレーション
過去の実績データと現在の取引をもとに、AIが将来の資金繰りや予算超過のリスクを予測。経営判断に資する情報提供が可能になります。
AIに置き換えられない経理業務
AIの導入が進む一方で、人にしかできない経理業務も存在します。
それは「例外への対応」や「判断の根拠を説明する力」「細やかなコミュニケーション」が必要な業務です。
以下のような業務についてはAIと人間の役割を明確に分け、専門スキルを有する人材が担当することで、より高度な処理が可能となるでしょう。
新規取引先との契約に関わる財務リスクの評価
新規の取引先と契約を結ぶ際には、与信管理や支払条件の妥当性を判断する必要があります。
AIは過去の取引データや公開情報を分析することはできますが、企業の経営方針や業界動向、担当者の信頼性といった“定量化しにくい要素”まで考慮するのは困難です。
また、契約交渉においては、相手企業の状況や関係性、取引全体の文脈を踏まえた柔軟な判断が求められます。取引額の大きさやリスクの複雑さによっては、経験に基づく直感や先読みが欠かせません。
このように、データでは測れないリスクを見極める力は、人間にしか担えない重要な役割です。
社内意思決定における資料作成や調整業務
経営層への報告資料や意思決定支援のための資料作成では、単にデータを集計するだけでなく、その背景や意図、今後の影響まで含めた説明が求められます。
AIは数値の差異や傾向を提示することは得意でも、「なぜこの数字が重要か」「経営判断にどうつながるか」までを論理的に語ることはできません。
さらに、部門をまたいだ調整や合意形成には、細やかな対人コミュニケーションやタイミングの見極めが必要です。たとえば、コスト削減の資料一つをとっても、内容の出し方や順序によって受け止め方が変わることがあります。
こうした“空気を読む”ような配慮や調整の巧みさは、AIには再現できない領域です。
法令改正への対応や制度理解
税制や会計基準は、毎年のように改正が行われます。
新たな制度を正確に読み解き、自社の業務に落とし込むには、法律の文言を単に読解するだけでなく実務上の影響を想像し、業務への適用方法を設計する力が必要です。
たとえば、同じ法改正でも業種や企業規模によって対応内容は異なりますし、例外規定が存在することもあります。AIは法文の読み込みはできても、それを会社の実態にどう適用すべきか、他部門とどう連携すべきかといった判断まではできません。
このような“法令と実務の橋渡し”を行う判断力は、依然として人間の役割として残り続けるでしょう。
業務フローや経理体制の再構築
企業の成長や事業再編、グループ会社との統合などに伴って、経理部門の業務フローや体制の見直しが必要になることがあります。
新たな会計処理の設計やシステム変更に伴う運用設計など、“全体最適の視点から構造を再編する力”はAIの得意分野ではありません。
業務再設計には法的な正しさに加え、現場での実行可能性や部門間の連携、経営方針との整合性などの多面的な判断が求められます。
また関係者への説明や意見調整も発生するため、単なる論理だけではなく、人間関係や社内文化に配慮した調整力も不可欠です。
このように、「経理をどう回すか」を構築・調整する役割は、テクノロジーだけでは完結できない、人にしか担えない重要な仕事です。
経理でAIが活用されている事例

ここでは、実際に経理部門で活用されているAI技術の代表例を4つご紹介します。
AI-OCR
AI-OCRは、紙の請求書・領収書・納品書などの書類をスキャンし、AIが文字を自動認識・抽出してデータ化する技術です。これにより、これまで人が手入力していた伝票内容や請求金額を、瞬時にデジタルデータに変換できます。
最近のAI-OCRは読み取り精度が格段に向上しており、手書きの文字やレイアウトが不規則なフォーマットにも対応可能な製品が登場しています。多くの企業では会計システムや経費精算ソフトと連携させることで、請求書の突合作業や入力ミスの削減を実現しています。
AI-OCRを業務に取り入れると、「取引先から届いた紙の請求書をスキャンするだけで、仕訳データの下書きが自動で作成される」といった形で、人手による単純作業の大幅な削減が期待できます。
電子帳簿保存法に対応したスキャナ保存とも相性がよく、ペーパーレス化と法令対応を同時に進められるのも大きなメリットです。
仕訳の自動作成
仕訳の自動作成は、AIによる経理業務の中でも特に導入効果が高い分野です。
銀行口座の入出金データやクレジットカードの利用明細を取り込み、AIが取引内容を解析。過去の仕訳履歴や勘定科目のパターンを学習し、自動で仕訳案を提案します。
ミスの少ない仕訳入力が可能になることで、月次決算のスピードアップや経理業務の平準化にもつながります。
AIは学習を重ねることで次第に精度が上がるため、使えば使うほど“経理チーム専用のアシスタント”のような存在へと成長します。
仕訳作業が効率化されれば、経理担当者は数値の分析や報告業務といった「より戦略的な業務」に時間を使えるようになります。
データ分析
AIによるデータ分析機能は、経理を「処理部門」から「経営参謀」へと変える力を持っています。
財務データや取引データをもとに、売上の傾向やコストの異常値をAIが自動で検出し、視覚化されたレポートを提示します。
これを活用すれば、「今月の広告費が前年比で急増している」「特定の取引先の支払いが遅延傾向にある」といった兆候を自動的に知らせることが可能です。
さらに予算と実績の乖離分析や、営業データと連携した収益性分析などもAIが担えるようになっています。
このような分析結果は、経営判断や事業戦略に直結する重要な材料となります。従来は分析に数日かかっていた作業も、AIなら数分で完了。経理担当者はその結果をもとに、経営層や各部署へのアドバイスを行うことができます。
上手に活用できれば未来を見通す“レーダー”のような存在として、経理の付加価値を高められるでしょう。
チャットボット
チャットボットは、経費精算や申請に関する社内問い合わせを自動で対応するAIツールです。
多くの企業では「この領収書は経費精算できるの?」「交通費の上限は?」といったよくある質問に対し、即座に回答できる仕組みとして導入が進んでいます。
このような対応を人手で行うと、担当者の業務を中断する必要があり効率が悪くなりがちです。チャットボットなら24時間365日対応可能で、社内業務の属人化を防ぎながら、問い合わせ対応を効率化できます。
また使い方によっては、従業員教育にも活用可能です。
たとえば、新入社員に向けて「交通費精算のルールを簡単に確認できるチャットガイド」などを提供することで、マニュアルよりも身近なサポートツールとして機能します。
さらにチャットボットの応答履歴を分析することで、「よくある質問」や「ルールが曖昧な箇所」を可視化でき、経理業務そのものの見直しにもつながります。
AIで経理の仕事がなくなると言われる理由
「経理の仕事はなくなる」という言説が出る背景には、いくつかの社会的な潮流があります。
- 経理=ルーティンワークという先入観
伝票入力や請求書処理など、反復的な業務の比重が大きかったため、「AIにとって代わられる」と感じやすい側面があります。
- 会計ソフトの進化と自動化の加速
クラウド会計ソフトが「仕訳提案」「残高チェック」「税務申告連携」まで担うようになり、「人の手を介さない経理処理」が現実化してきました。
- テレワーク推進による業務の見直し
コロナ禍をきっかけに、紙と人に依存していた経理体制の見直しが進みました。結果として、AIやRPAの導入が急加速しました。
ただし、多くの企業で導入されているAIツールは、「業務を補助する存在」であって、「すべてを代替する存在」ではありません。
どちらかといえば“仕事がなくなる”のではなく、“業務の質が変化すること”が本質であるといえるでしょう。
これからの経理担当者にとって求められるスキルとは
今後の経理担当者に求められるのは、「自動化された世界で何ができるか」という視点です。
言い換えれば「データを読み、意味を伝え、業務を変える力」ともいえるでしょう。
具体的に以下の4スキルは、今後必須となるスキルです。
- プロセス設計力
- 非財務データへの理解
- 会計と経営の橋渡しスキル
- 変化に対応するマインドセット
プロセス設計力
AI導入時には単にツールを使いこなすのではなく、どの業務をどこまで自動化するか、社内のフロー設計に関与できる視点が必要です。
AIやRPAを導入する際には、既存の業務をただ置き換えるのではなく、業務全体の流れを見直し、どの部分をどのように自動化すべきかを設計する力が求められます。
よって経理フロー全体を理解し、関係部門と調整しながら最適なプロセスを描ける人材は、今後重宝されるでしょう。
非財務データへの理解
近年は、ESG(環境・社会・ガバナンス)や人的資本だけでなく、「非財務情報」全般が重視される時代です。よってこれからの経理担当者には、定量・定性の両方を扱う力が求められます。
例えば気候変動リスクや人的資本、ダイバーシティといった非財務領域の情報などは、企業の価値評価に直結する時代です。
会計データと組み合わせて活用するには、定性情報の背景を理解し、経営に活かせる視点を持つことが重要になります。
会計と経営の橋渡しスキル
経理部門は経営判断を支える「数字の翻訳者」としての役割がますます求められます。よって経営層に対して「会計数値をわかりやすく伝える力」がある人材は、今後ますます重宝されます。
例えば専門用語をかみ砕いて説明する力や、データをグラフや可視化資料に落とし込み、的確に提案するプレゼン力はその最たる例です。
変化に対応するマインドセット
AIや制度改正など、経理の業務環境は大きく変わり続けています。このような状況では、新しい知識を自ら学び、実務に柔軟に取り入れる姿勢が不可欠です。
よって経理の業務では、変化を前向きに捉え、自らキャッチアップしていける柔軟性もキャリアの武器になります。
まとめ
経理業務におけるAIの活用は、すでに業務標準になりつつあります。事実、多くの企業ではルーティンワークの自動化を行い、経理担当者の役割はより高度で創造的なものへとシフトしています。
AIに仕事を奪われるのではなく、AIと共存しながら自らの業務を進化させていくことが今後のカギです。
「変化はチャンスである」と捉え、AI-OCR 搭載の会計ツールや経費精算システムなどのAIツールをうまく活用していきましょう。
それと合わせてより高度な経理業務に携われるスキルを磨いていけば、相乗効果で企業の発展や成長にもつながっていくはずです。