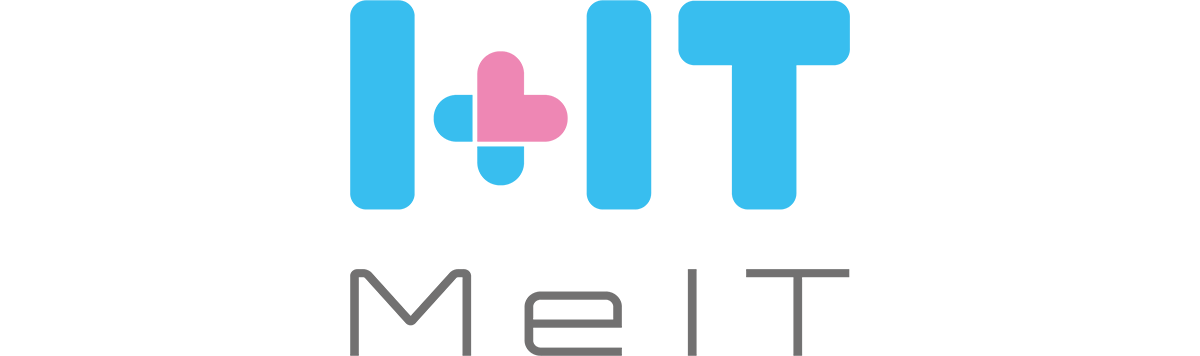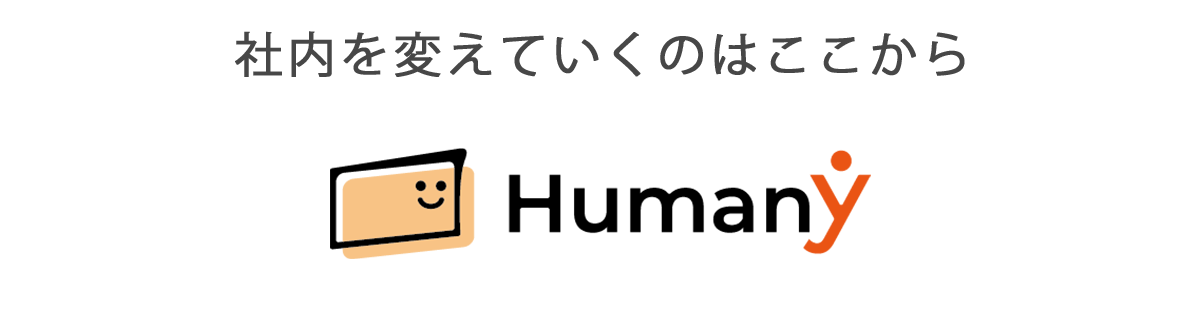【中小企業向け/専門家監修】離職を防ぐ従業員相談窓口の構築と運用ポイント
更新日:2025/07/07

「従業員向け相談窓口」の設置は、中小企業にとって離職率の低下、ハラスメント対策、従業員のメンタルヘルス維持に不可欠です。
本記事では、内部・外部それぞれの相談窓口の種類と特徴、具体的な構築・運用方法、そして効果的な活用ポイントを解説します。従業員が安心して働ける環境を整備し、企業の信頼性と生産性を高めるための具体的なステップを押さえましょう。
従業員相談窓口とは?その目的とメリット

従業員相談窓口とは、従業員が職場におけるさまざまな悩みや問題を安心して相談できる社内外の窓口を指します。ハラスメント、人間関係、メンタルヘルスに関する不調、キャリアの不安、待遇への疑問など、従業員が抱える幅広い問題に対応することを目的としています。
従業員相談窓口は、単に相談を受け付けるだけでなく、相談内容に応じて適切な解決策を模索したり、必要に応じて関係部署と連携して問題解決を図ったりする役割を担います。また、相談を通じて得られた情報を分析し、職場環境全体の改善に活かすことで、より健全で働きやすい職場づくりに貢献します。
従業員相談窓口の目的とメリットをみてみましょう。
従業員相談窓口の主な目的
従業員相談窓口の主な目的は以下のとおりです。
- 従業員の悩みやプライベートにおける問題の早期発見と解決
- ハラスメントやメンタルヘルス不調の予防と適切な対応
- 法令遵守(とくにハラスメント対策関連法規)
- 健全な職場環境の維持・向上
- 従業員の安心感とエンゲージメントの向上
企業側のメリット
従業員相談窓口を設けると企業には以下のようなメリットがあります。
- 法的リスクの低減:ハラスメントや労務問題に関する訴訟リスク、行政指導のリスクを軽減する
- 離職率の低下:従業員の不満や不安を早期に解消することで、離職を防ぎ、定着率を高める
- 生産性の向上:ストレスや問題が軽減され、従業員が安心して業務に集中できるため、生産性が向上する
- 企業イメージの向上:従業員を大切にする企業としての評判が確立され、採用活動や取引先からの信頼にもつながる
- 潜在的な問題の早期発見:表面化していない職場の課題や職場が手を出しづらいプライベートで生じるさまざまなリスクを事前に察知し、大規模な問題になる前に対策を講じることが可能である
- 従業員満足度(ES)の向上:安心して働ける環境を提供することで、従業員の会社に対する満足度とエンゲージメントが高まる
従業員側のメリット
従業員相談窓口を設け、利用することで、従業員には以下のようなメリットがあります。
- 精神的負担の軽減:安心して相談できる場所があることで、精神的な負担が軽減される
- 孤立感の解消:問題解決への道筋が見え、孤立感を解消できる
- 従業員エンゲージメントの向上:企業への信頼感が高まり、安心して長く働き続けられると感じられる
- 相談しづらいプライベートに関する相談リソースの獲得:社会的な孤立を防ぎ、労働に対するコミットメントが向上する
ハラスメント対策関連法令対応
従業員相談窓口の設置は、とくにハラスメント対策における企業の法的義務として、その重要性が高まっています。
2020年6月1日(中小企業は2022年4月1日)に施行された改正労働施策総合推進法(パワハラ防止法)により、企業には職場におけるパワーハラスメントに関する相談対応を含めた防止措置を講じることが義務付けられました。大きくわけて以下の措置が求められています。
- 事業主の方針の明確化と周知・啓発
- 相談に応じ、適切に対応するための体制整備(相談窓口の設置)
- 職場におけるハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
- その他、プライバシー保護や不利益取扱いの禁止など
相談窓口の設置は、この中でもとくに「相談に応じ、適切に対応するための体制整備」の中核をなすものです。相談窓口があることで、従業員はハラスメントの被害に遭った際や、ハラスメントを目撃した際に、企業にその事実を伝え、適切な対応を求めることができます。
相談窓口があることで、企業側ではハラスメント事案を早期に把握し、迅速な事実確認、被害者への配慮、加害者への適切な措置、再発防止策の実施といった対応が可能になります。
法令遵守は、単に罰則を避けるだけでなく、企業の社会的責任(CSR)を果たすうえでも不可欠です。ハラスメント事案への不適切な対応は、従業員の離職、企業イメージの失墜、訴訟リスクの増大など、企業経営に甚大な影響を及ぼす可能性があります。相談窓口は、これらのリスクを未然に防ぎ、健全な企業運営を支えるための重要なリスクマネジメントツールとしての役割も果たします。
【関連記事:パワハラとは?パワハラ防止法と一緒に知りたいその定義を解説】
中小企業における従業員相談窓口の必要性

従業員相談窓口は、大企業だけでなく、リソースが限られがちな中小企業にとってこそ、経営を安定させ、持続的な成長を実現するために不可欠な存在です。
中小企業では、従業員一人ひとりの存在が大きく、その離職やメンタルヘルスの不調が事業運営に与える影響は計り知れません。相談窓口は、従業員の小さな不満や悩みを早期にキャッチし、深刻な問題に発展する前に解決へと導くための重要なインフラとなります。
離職防止と従業員相談窓口の関係
中小企業にとって、従業員の離職は事業継続に直結する大きなリスクです。とくに優秀な人材の流出は、ノウハウの喪失、生産性の低下、採用コストの増大など、多岐にわたる負の影響をもたらします。従業員相談窓口は、このような離職リスクを未然に防ぐうえで極めて有効な手段となります。
従業員が抱える不満やストレス、人間関係の悩み、キャリアに関する不安などは、放置されるとやがて離職へとつながります。相談窓口があることで、従業員は安心して悩みを打ち明けることができ、企業側は問題を早期に把握し、適切な対応を取ることが可能になります。従業員のエンゲージメントを高め、職場への定着を促すうえでも鍵を握る部分です。
相談窓口の離職防止に対する具体的な効果は以下のとおりです。
| 効果 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 不満の早期発見と解決 | 従業員が抱える不満やストレスが深刻化する前に、相談窓口を通じて吸い上げ、適切な解決策を講じることで、離職の引き金となる要因を取り除く |
| 従業員満足度・エンゲージメント向上 | 「会社が自分の声に耳を傾けてくれる」という安心感は、従業員の会社への信頼感を高め、満足度やエンゲージメントの向上につながる |
| 良好な職場環境の維持 | 相談内容から職場内の課題を特定し、組織全体の改善に活かすことで、風通しの良い、働きやすい職場環境を構築・維持できる |
| 人材定着率の向上 | 上記の効果が複合的に作用することで、従業員が長期的に安心して働ける環境が整い、結果として人材の定着率が向上する |
メンタルヘルス対策としての従業員相談窓口
現代社会において、従業員のメンタルヘルスは企業経営の重要な課題となっています。ストレス社会と言われる中で、メンタルヘルス不調による休職や離職は、企業の生産性低下、医療費負担の増加、そして企業イメージの悪化に直結します。中小企業においても、従業員のメンタルヘルスケアは看過できない問題です。
従業員相談窓口は、メンタルヘルス不調の早期発見と早期対応に大きな役割を果たします。従業員が気軽に悩みを相談できる場があることで、心身の不調のサインを見逃さずに済み、専門機関への紹介や適切なサポートを速やかに提供することが可能になります。
メンタルヘルス対策としての相談窓口の具体的な効果は以下のとおりです。
| 効果 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 不調の早期発見 | 従業員がストレスや不安を感じた際に、気軽に相談できる場があることで、メンタルヘルス不調の初期段階で問題を把握し、適切な介入ができる |
| 専門機関との連携 | 相談内容に応じて、産業医、カウンセラー、医療機関などの専門機関へスムーズにつなぐことで、従業員が適切な専門的支援を受けられるようサポートする |
| 休職・復職支援 | 休職中の従業員への定期的な連絡や、復職時の職場環境調整など、休職から復職までのプロセスをきめ細やかに支援し、スムーズな職場復帰を促す |
| 職場全体のストレス軽減 | 相談内容から得られた情報をもとに職場環境の改善や業務の見直しを行うことで、従業員全体のストレスを軽減し、健康的な職場づくりを目指す |
中小企業においても、従業員のメンタルヘルス対策は企業の社会的責任として重要であり、相談窓口の設置は「健康経営」を推進するための第一歩となります。限られた経営資源を最大限に活かし、中小企業が成長していくうえで欠かせない観点です。
相談窓口の種類と特徴

従業員が抱える悩みや問題を解決するための相談窓口には、大きく分けて企業内に設置する「内部相談窓口」と、外部の専門機関に委託する「外部相談窓口」の2種類があります。
それぞれに特徴があり、企業規模や目的、予算に応じて最適な選択をすることが重要です。ここでは、それぞれの相談窓口の具体的な内容と、メリット・デメリットについて詳しく解説します。
内部相談窓口
内部相談窓口とは、企業が自社の従業員の中から担当者を指名し、社内に設置する相談窓口のことです。一般的には、人事部門の担当者や、特定の部署の責任者、あるいは兼任で窓口業務を行う従業員が担当します。
企業文化や組織の状況を熟知している担当者が対応するため、迅速な状況把握や、企業の実情に即した解決策の検討が期待できます。
内部相談窓口のメリット・デメリット
内部相談窓口には、以下のようなメリットとデメリットがあります。
| 項目 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| コスト | 比較的低コストで設置・運用が可能。新たな費用発生を抑えられる | 担当者の人件費や研修費が発生する |
| 迅速性・情報共有 | 組織内の状況を把握しやすく、迅速な対応や解決策の実行が可能。社内での情報共有がスムーズ | 相談内容が企業内部に留まるため、情報漏洩への不安や公平性への疑問が生じやすい |
| 企業文化への理解 | 企業独自の文化や慣習、人間関係を理解したうえで対応できるため、実情に即したアドバイスが可能 | 担当者が「会社側の人間」と見なされやすいため、従業員が相談をためらうことがある |
| 公平性・信頼性 | (難しい) | とくに上司や同僚に関する相談の場合、公平性が保たれないと感じられ、従業員からの信頼を得にくい場合がある |
| 専門性 | (難しい) | ハラスメント、メンタルヘルス、法律問題など、専門的な知識や経験が不足している場合がある |
| 心理的ハードル | (メンタルヘルスの問題については難しい) | 身近な人が担当者であるため、相談しにくいと感じる従業員もいる |
| 人的リスク | 社内人材で対応できる | 担当者の離職による引き継ぎや担当人材自体の適性の有無が課題 |
外部相談窓口
外部相談窓口とは、企業が独立した第三者機関に委託して設置する相談窓口のことです。EAP(従業員支援プログラム)もここに含まれます。
企業から独立した立場であるため、公平性・中立性が高く、従業員が安心して相談できる環境を提供できます。また、専門的な知識を持つプロフェッショナルが対応するため、複雑な問題にも適切に対処できる点が大きな特徴です。
外部相談窓口のメリット・デメリット
外部相談窓口には、以下のようなメリットとデメリットがあります。
| 項目 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 公平性・中立性 | 企業から独立しているため、公平かつ中立的な立場で相談に応じられ、従業員からの高い信頼を得やすい | 企業側へのフィードバックにタイムラグが生じることがある |
| 専門性 | 法律、心理、医療など、多岐にわたる専門知識を持つプロフェッショナルが対応。複雑な問題にも適切に対処できる | 提供されるサービス内容や専門分野が外部機関によって異なるため、自社のニーズに合ったサービスを選ぶ必要がある |
| 匿名性・プライバシー保護 | 相談内容が企業に直接知られる心配が少なく、匿名での相談も可能。従業員が安心して利用できる | 提供されるサービスの情報保護レベルを確認する必要がある |
| 心理的ハードル | 企業内部の人間に相談するよりも、心理的な抵抗が少ない | 内部窓口に比べて導入・運用コストが高い傾向がある |
| レピュテーション向上 | 外部窓口の設置自体が、企業が従業員を大切にしている姿勢を示すことになり、対外的な評価(レピュテーション)を高める | 外部相談窓口を設けておくことで、さらに外部からの評判が向上する |
| 人的リスク | 外部機関が担保する | 外部機関の体制次第 |
内部相談窓口の構築方法

従業員相談窓口を社内に設置する内部相談窓口は、従業員が日々の業務や人間関係で抱える悩み、ハラスメントの相談などを気軽にできる環境を整えるうえで非常に重要です。単に窓口を設けるだけでなく、実効性のある仕組みを構築し、従業員が安心して利用できる体制を整えることが成功の鍵となります。とくに中小企業では、限られたリソースの中で最大限の効果を発揮するための工夫が求められます。
内部相談窓口の設置例
内部相談窓口の設置にあたっては、従業員が利用しやすい形態を検討することが重要です。自社の規模や文化、従業員の特性に合わせて最適な組み合わせを検討しましょう。
| 項目 | 主な選択肢 | 備考 |
|---|---|---|
| 相談窓口担当者 | 人事担当者、総務担当者、役員、管理職、特定の指名された従業員 | 公平性・中立性を保てる人物の選定が重要。複数人体制も有効 |
| 相談方法 | 専用メールアドレス、専用電話番号、社内チャットツール、Webフォーム(グループウェア)、対面での面談(予約制) | 従業員が匿名で相談できる選択肢を用意すると、利用のハードルが下がる |
| 相談場所 | 人事部内、総務部内、個室の会議室、休憩スペースの一部 | プライバシーが守られ、他人の目を気にせず話せる場所が望ましい |
これらの例を参考に、自社に最適な内部相談窓口の形態を具体的にイメージし、構築を進めていきましょう。
相談しやすい窓口の設置場所や方法の検討
従業員が安心して相談できる環境を整えるためには、相談窓口の設置場所や相談方法を慎重に検討することが不可欠です。物理的な場所だけでなく、心理的なハードルを下げる工夫も求められます。
まず、物理的な相談場所は、プライバシーが確保され、他人の目を気にせず話せる個室や区切られたスペースが理想的です。人事部や総務部の執務室の一角ではなく、専用の面談スペースや、予約制で利用できる会議室などを活用すると良いでしょう。また、相談場所へのアクセスが容易で、人目につきにくい場所を選ぶことも重要です。
次に、相談方法については、従業員が自分の状況や好みに合わせて選べるよう、複数のチャネルを用意することが望ましいでしょう。たとえば、以下の方法が考えられます。
- 専用メールアドレス:時間や場所を問わず、自分のペースで相談内容を整理して送れる。匿名での相談も可能にしやすい
- 専用電話番号:緊急性が高い場合や、文字では伝えにくいニュアンスを伝えたい場合に有効
- 社内チャットツール:日常的に使用しているツールであれば、より気軽にアクセスしやすい
- Webフォーム(グループウェア):匿名性を確保しやすく、相談内容を体系的に収集できる
- 対面での面談:複雑な相談や、直接話すことで安心感を得たい場合に適している
とくに、匿名での相談を可能にする仕組みは、ハラスメントなどのデリケートな問題について、従業員が不利益を恐れずに声を上げやすくするために非常に重要です。相談受付時間や対応可能な曜日を明確に周知し、従業員が「いつでも、誰でも、安心して」相談できるというメッセージを伝えることが、利用促進につながります。
窓口担当者の選定と研修・ルール設定
内部相談窓口の機能性を高めるうえで、担当者の選定、適切な研修、そして明確なルール設定は極めて重要です。これらが不十分だと、せっかく設置した窓口が形骸化したり、かえって従業員の不信感を招いたりする可能性があります。
窓口担当者の選定
窓口担当者には、相談内容を公平かつ中立な立場で傾聴し、守秘義務を徹底できる人物を選定することが不可欠です。以下の資質を持つ人材が望ましいでしょう。
- 傾聴力と共感力:相談者の話を最後まで聞き、感情に寄り添うことができる
- 公平性と中立性:相談者や関係者の立場に偏らず、客観的に事実を把握しようと努める
- 守秘義務の徹底:相談内容や個人情報を厳重に管理し、許可なく第三者に漏らさない
- 問題解決能力:相談内容に応じて適切な解決策を提案したり、関係部署と連携したりできる
- 法令知識:ハラスメント関連法規、個人情報保護法など、関連する法令の基礎知識がある
中小企業の場合、人事担当者や総務担当者が兼任することがありますが、複数人体制にすることで、相談内容や相談者の性別・立場に応じて選択肢を提供でき、より安心して相談できる環境が生まれます。また、相談担当者自身が責任を抱え込みすぎないよう、定期的なサポート体制も検討しましょう。
研修内容
選定された担当者には、相談対応に必要な知識とスキルを習得させるための研修が必須です。具体的な研修内容の例は、以下のとおりです。
- ハラスメントの種類と対応:パワハラ、セクハラ、マタハラなど、各種ハラスメントの定義、具体例、企業の法的責任、対応フロー
- メンタルヘルスに関する基礎知識:ストレスチェック制度、精神疾患の基礎知識、休職・復職支援の基本
- カウンセリングスキル:傾聴、質問技法、共感、ラポール形成など、相談者が話しやすい雰囲気を作るスキル
- 個人情報保護法と守秘義務:相談内容の取り扱い、個人情報の保護、情報漏洩のリスクと対策
- 危機管理と緊急対応:自殺リスクのある相談への対応、緊急時の連絡体制
- 関連法規の理解:労働施策総合推進法(パワハラ防止法)、男女雇用機会均等法などの関連法規
これらの研修は、社内で行うだけでなく、外部の専門機関が提供する研修プログラムやセミナーを活用することも非常に有効です。定期的なスキルアップ研修や情報共有の場を設けることで、担当者の質の維持・向上を図りましょう。
ルール設定のポイント
相談窓口の運用にあたっては、明確なルールを文書化し、社内に周知することが不可欠です。これにより、相談者、担当者、会社全体の行動規範が明確になり、トラブルを未然に防ぐことができます。主なルール設定のポイントは以下のとおりです。
- 相談受付から解決までのフロー:相談受付、事実確認、関係者へのヒアリング、解決策の検討・実施、フィードバック、記録・保管といった一連の流れを具体的に定める
- 守秘義務の徹底:相談内容や相談者の個人情報は厳重に管理し、本人の同意なく第三者に開示しないことを明記する
- プライバシー保護:相談者のプライバシーを最大限尊重し、個人が特定できる情報が不必要に拡散されないよう配慮する
- 匿名相談への対応方針:匿名相談の場合でも、可能な範囲で事実確認を行い、職場改善につなげるための対応方針を定める
- 相談者への不利益取り扱いの禁止:相談したこと、あるいは事実関係の確認に協力したことを理由に、相談者や協力者が不利益な取り扱いを受けないことを明確に規定し、周知する
- 就業規則やハラスメント防止規定との連携:相談窓口が、既存の就業規則やハラスメント防止規定に則って運用されることを明確にする
- 記録の取り方と保管方法:相談内容の記録方法、アクセス権限、保管期間、廃棄方法を具体的に定める
これらのルールは、社内規定として明文化し、従業員全員に周知徹底することで、相談窓口への信頼感を高め、安心して利用してもらう土台を築きます。
相談内容の管理と情報保護
従業員相談窓口で受け付けた相談内容は、極めてデリケートな個人情報を含むため、その管理と情報保護には最大限の注意を払う必要があります。適切な情報管理体制を構築することは、相談者の信頼を得るうえで不可欠です。
記録の重要性
相談内容の記録は、以下の目的のために非常に重要です。
- 事実の把握と経緯の追跡:相談内容、対応状況、解決策、その後の経過などを詳細に記録することで、問題解決のプロセスを明確にし、再発防止策の検討に役立てる
- 傾向分析と職場改善:複数の相談から共通の課題や傾向を抽出し、組織全体の職場環境改善につなげるためのデータとなる
- 相談者との共通認識:対話内容やどのように問題を取り扱っていくかを適切に記録することで、相談者との齟齬を防ぐプラットフォームになる
- 法的対応:万が一、法的な問題に発展した場合に、自社が適切に対応したことを示す証拠となる
記録する際は、個人が特定されないように配慮しつつ、必要な情報を網羅することが重要です。匿名相談の場合でも、相談のあった日時、相談内容の概要、対応状況などは記録し、傾向分析に活用できるようにします。
厳格な情報保護体制
相談内容の記録や関連情報は、個人情報保護法や労働施策総合推進法(パワハラ防止法)などの法令を遵守し、厳格に管理する必要があります。具体的な情報保護体制の構築ポイントは以下のとおりです。
- アクセス権限の厳格化:相談内容にアクセスできる担当者を限定し、権限のない者が閲覧できないように厳重に管理する。物理的な記録は施錠可能なキャビネットに保管し、デジタルデータはパスワード保護やアクセス制限を設ける
- 守秘義務の徹底:相談窓口担当者だけでなく、相談内容に関わる可能性のある全ての関係者(経営層、人事担当者など)に対し、守秘義務の重要性を徹底し、誓約書などを取り交わすことも検討する
- 個人情報の匿名化・符号化:傾向分析などでデータを利用する際は、個人が特定できないよう匿名化したり、符号化したりする工夫を凝らす
- 保管期間と廃棄方法:記録の保管期間を明確に定め、期間経過後は適切かつ安全な方法で廃棄する。デジタルデータは完全に消去し、紙媒体はシュレッダーにかけるなど、情報漏洩のリスクを排除する
- 定期的な監査と見直し:情報管理体制が適切に運用されているか、定期的に監査を行い、必要に応じて見直しや改善を行う
情報保護を徹底することで、相談者は自身の情報が適切に扱われると信頼し、安心して相談窓口を利用できるようになります。情報保護の徹底は、相談窓口の信頼性を確立し、その実効性を高めるうえで不可欠な要素です。
【監修者からのコメント】
監修者は内部と外部の両方の相談窓口を担当した経験があります。両方の経験から挙げられる違いとして、以下のものがあります。
内部:相談者の人事情報や業務内容にアクセスしやすいため、相談者のサポートがトータルでできる。一方で企業組織の指揮系統や利害関係に強く影響を受ける。
外部:アクセスできる情報に制限が多い。一方で相談内容を担当部署に対して直接伝えることができる。
【関連記事:「優秀な人ほど辞めていく」現象をデータで裏付け。離職を防ぐ本当のポイント【調査結果】】
外部相談窓口の活用方法

従業員相談窓口として外部機関を活用することは、とくに中小企業にとって多くのメリットをもたらします。内部資源が限られる中小企業では、専門的な知識や公平な視点を持つ外部の専門家に相談業務を委託することで、質の高い相談対応と、より客観的な職場環境改善へのアプローチが可能になります。
外部相談窓口の活用例
外部相談窓口は、従業員が企業に直接言いにくい問題や、デリケートなハラスメント、メンタルヘルスに関する相談など、多岐にわたる課題に対応できる専門性を持っています。具体的な活用例としては、以下のようなケースが挙げられます。
- ハラスメント相談:パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、カスタマーハラスメントなど、従業員が内部では相談しにくいと感じる内容に対して、中立的な立場で話を聞き、適切なアドバイスを行う
- メンタルヘルス相談:ストレスやうつ病などのメンタルヘルス不調に関する相談に対し、専門のカウンセラーや産業医が対応し、必要に応じて医療機関への受診勧奨や休職・復職支援を行う
- 人間関係の悩み:職場内の人間関係のトラブルや、部署間の連携に関する問題など、従業員が抱える個人的な悩みに寄り添い、解決に向けたサポートを行う
- キャリアや処遇に関する相談:キャリアパスの不安、評価への不満、労働条件に関する疑問など、従業員のキャリア形成や処遇に関する相談にも対応し、客観的な視点からの助言を行う
- プライベートに関する悩み:職場で話しづらい家族関係やプライベートの問題に関して心理的なサポートを行う
MeITのような従業員支援プログラム(EAP: Employee Assistance Program)を提供する専門サービスでは、カウンセリング、法律相談、健康相談など、幅広い分野をワンストップで受けられることもあります。匿名性が高く、従業員が利用しやすい体制が整っています。従業員の匿名性を守りつつ、専門的な知見に基づいた公平な対応を行うことで、内部では解決が難しい問題へのアプローチが可能です。
フィードバック情報から職場改善を図る
外部相談窓口は、単に相談を受けるだけでなく、その相談内容から得られる情報を企業にフィードバックし、具体的な職場改善につなげる重要な役割を担います。このフィードバックは、個別の相談内容が特定されないよう匿名化され、傾向や課題として報告されます。
フィードバックされる情報と、それを用いた職場改善の例は以下のとおりです。
| フィードバック情報の種類 | 活用による改善例 |
|---|---|
| 相談件数と内容の傾向 | 特定の部署からの相談が多い、ハラスメント関連の相談が増加傾向にある、といった情報を把握し、問題のある部署への重点的な介入や、特定のハラスメント防止策の強化につなげる |
| 匿名化された具体的な相談事例 | 個人が特定されない範囲で、どのような問題が発生しているのかの具体的な事例を共有することで、類似の問題の再発防止策を検討したり、マネジメント層への注意喚起を行ったりする |
| 専門家からの提言・アドバイス | 相談内容や企業の状況を客観的に分析し、就業規則の改定、研修の実施、人事制度の見直し、コミュニケーション改善策など、具体的な改善策を提言することもある |
これらのフィードバックをもとに、継続的な職場環境改善に努めることが重要です。経営層や人事担当者がフィードバック内容を真摯に受け止め、改善計画を策定・実行することで、従業員が安心して働ける環境を構築できます。
外部相談窓口があることがレピュテーションを高める
外部相談窓口の設置は、単なる法令遵守やリスク回避のためだけではありません。企業が従業員の声を真摯に受け止め、健全な職場環境づくりにコミットしているというメッセージを内外に発信し、企業のレピュテーション(評判)を高める効果があります。
- コンプライアンス体制の強化:ハラスメント防止対策やメンタルヘルス対策を含むコンプライアンス体制が整っていることで、取引先や投資家からの信頼獲得にもつながる
- 採用競争力の向上:求職者は、企業の働きやすさや従業員への配慮を重視する傾向にある。外部相談窓口があることは、安心して働ける職場環境が整備されていることを示し、優秀な人材の確保に有利に働く
- 従業員エンゲージメントの向上:困ったときに相談できる場所があることで、従業員満足度やエンゲージメントの向上につながり、結果として生産性の向上や離職率の低下につながる
- 企業イメージ・ブランド価値の向上:従業員を大切にする企業としてのイメージは、社会全体からの評価を高め、企業のブランド価値を向上させる
中小企業においても、外部相談窓口の導入は、「従業員を大切にする企業」としてのポジティブな企業文化を醸成し、長期的な視点での経営安定化に貢献する重要な戦略的投資と言えるでしょう。
【監修者からのコメント】
監修者が経験した実際の外部相談窓口活用事例やメリットなどをご紹介します。
・内部の人事担当者・管理部門担当者が相談対応をする場合、説得力に欠けたり、手落ちになったりする部分を、外部相談窓口ならカバーできる
・従業員からの相談対応をはじめとする人事部門の業務は答えや確かなモデルがないため、対応に迷いや不安が生じる。外部相談窓口があることで、それらに対するひとつの指針が得られる。
・内部に相談窓口があったが、担当者の問題で情報が筒抜けになってしまった。外部であれば、間違いなくそういったところが守ってもらえるのでここに連絡すれば安心と窓口チラシが出回っている。
【関連記事:ウェルビーイング採用とは?企業と従業員の幸福度を高める戦略】
従業員相談窓口の運用ポイント

従業員相談窓口は、設置するだけでなく、適切に運用されることで初めてその真価を発揮します。形骸化させず、従業員が安心して利用でき、かつ組織改善につながる運用を行うためのポイントを解説します。
周知と利用のしやすさ
せっかく相談窓口を設置しても、従業員にその存在が知られていなかったり、利用しにくいと感じられたりすれば意味がありません。従業員が「困ったときに頼れる場所」だと認識し、心理的なハードルなく利用できる環境を整えることが重要です。
効果的な周知方法
相談窓口の存在を従業員全員に確実に知らせるための具体的な方法を、複数組み合わせることがおすすめです。
| 周知方法 | 具体的な内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 社内広報媒体での掲示・掲載 | 社内掲示板、社内報、グループウェア、社内SNSなど | 定期的に情報を更新し、目につきやすい場所に掲示する。デジタル媒体ではアクセスしやすいよう工夫する |
| 就業規則への明記 | 就業規則や関連規程に相談窓口の設置と利用方法を明記する | 法的根拠を示し、従業員の権利として位置づける |
| 入社時研修・定期研修 | 新入社員研修や全従業員向け研修で、相談窓口の目的、利用方法、秘密保持について説明する | 対面での説明は理解度が高まり、質問の機会も提供できる |
| 名刺サイズのカード配布 | 相談窓口の連絡先や利用方法を記載したカードを全従業員に配布する | 手元に常に情報があることで、いざというときに利用しやすい |
| 経営層からのメッセージ | 経営者や役員が、従業員相談窓口の重要性や利用促進についてメッセージを発信する | 経営層のコミットメントを示すことで、従業員の安心感を高める |
利用しやすい窓口にするための工夫
従業員が安心して相談できると感じるための環境づくりが不可欠です。
- 相談方法の複線化:電話、メール、Webフォーム、対面など、従業員が選択できる複数の相談チャネルを用意する
- 匿名性の確保:とくにハラスメントなどデリケートな相談の場合、匿名での相談を可能にすることで心理的ハードルを下げることができる
- 相談時間の柔軟性:勤務時間内だけでなく、事前に予約すれば勤務時間外でも相談できるよう配慮するなど、従業員の状況に合わせた対応を検討する
- 相談員の専門性と信頼性:相談員が守秘義務を遵守し、公平・中立な立場で対応することの周知。専門知識を持つ人材を配置することで、より的確なアドバイスが可能となる
相談内容への適切な対応
相談窓口の信頼性は、相談内容に対してどれだけ適切かつ迅速に対応できるかにかかっています。不適切な対応は、従業員の不信感を招き、問題の悪化や離職につながりかねません。
対応の基本原則
相談員は以下の原則に基づき、丁寧かつ慎重に対応する必要があります。
| 原則 | 内容 | 留意点 |
|---|---|---|
| 傾聴と共感 | 相談者の話を遮らず、最後まで耳を傾け、感情に寄り添う | 安易な助言や決めつけは避け、相談者の気持ちを最優先する |
| 秘密保持の徹底 | 相談内容や相談者の個人情報は、本人の同意なく第三者に開示しない | 違反は信頼失墜に直結する |
| 公平・中立な立場 | 特定の個人や部署に偏らず、客観的な視点で対応する | 相談員自身の感情や先入観を排除する |
| 迅速な対応 | 相談受付から問題解決に向けたアクションまで、速やかに対応する | 放置は相談者の不安を増大させ、問題の長期化を招く |
| 二次被害の防止 | 相談者が不利益な取り扱いを受けないよう、細心の注意を払う | 相談内容が漏洩したり、報復を受けたりしないよう厳重に管理する |
| 問題解決への道筋提示 | 相談者の意向を尊重しつつ、具体的な解決策や選択肢を提示する | 必要に応じて、専門部署(人事、法務など)や外部機関への連携を促す |
相談対応の具体的なフロー例
事前に明確なフローを定めておくことで、対応の質を一定に保ち、迅速な問題解決につながります。
- 相談受付:電話、メール、対面など、設定されたチャネルで相談を受け付ける。相談日時、相談者の希望(匿名希望の有無、解決希望の有無など)を正確に把握する
- 傾聴・事実確認:相談内容を丁寧に聞き取り、必要に応じて事実関係を整理する。この段階で安易な判断はせず、情報収集に徹する
- 対応方針の検討:相談内容に基づき、個人情報保護に配慮しつつ、必要な調査の範囲や、関係部署・専門家(産業医、弁護士など)との連携の要否を検討する
- 問題解決に向けた実行:相談者の意向を踏まえ、加害者への指導、配置転換、研修実施、関係部署への是正勧告など、具体的な解決策を実行する
- 経過報告・結果報告:相談者に対し、対応の進捗状況や最終的な結果を定期的に報告する。解決に至った場合でも、再発防止策の実施状況などを伝える
- アフターフォロー:問題解決後も、相談者の状況を確認し、必要に応じて継続的なサポートを行う
その場の対応だけでなく職場改善に活かす
従業員相談窓口の最も重要な役割のひとつは、個別の問題解決に留まらず、そこから得られた情報を組織全体の職場環境改善につなげることです。同様の問題の再発防止、従業員満足度の向上、ひいては企業の生産性向上を目指します。
フィードバックループの構築
相談窓口に寄せられた情報を経営改善に活かすためには、体系的なフィードバックの仕組みが必要です。
- 相談内容のデータ化と分析:個人が特定できない形(匿名化、統計化)で、相談の種類(ハラスメント、人間関係、メンタルヘルスなど)、発生部署、時期、解決に要した期間などをデータとして蓄積・分析
- 傾向の把握と課題の特定:分析結果から、特定の部署で問題が多発している、特定のハラスメントが多い、特定の時期に相談が増えるなどの傾向を把握し、組織が抱える潜在的な課題を特定
- 経営層・人事部門への報告:分析結果と特定された課題に改善提案を添えて、経営層や人事部門、関連部署に定期的に報告
- 改善策の検討と実行:報告された課題に基づき、具体的な職場改善策を検討し、実行
- 効果測定と見直し:実施した改善策の効果を定期的に測定し、必要に応じて見直しを行う
具体的な職場改善策の例
相談窓口からのフィードバックに基づき、以下のような改善策を検討・実施することができます。
- 研修の実施:ハラスメント防止研修、アンコンシャスバイアス研修、管理職向けコーチング研修、メンタルヘルス研修など、課題に応じた研修を実施する
- 就業規則・規程の見直し:相談窓口の利用促進、ハラスメントの定義、懲戒規定などをより明確にし、実効性のあるものにする
- 人事評価制度・人事制度の改善:公平で透明性の高い評価制度の導入、キャリアパスの明確化、適切な人員配置の見直しなど
- コミュニケーション活性化策:部署間の交流促進、定期的な1on1ミーティングの推奨、社内イベントの企画など
- 職場環境の物理的改善:休憩スペースの確保、照明・空調の改善、フリーアドレスの導入など、従業員が快適に働ける環境を整備する
従業員相談窓口は、単なるリスクマネジメントツールではなく、従業員の声を吸い上げ、組織の健康状態を把握し、持続的な成長を促すための「経営改善のセンサー」として機能します。中小企業こそ、このセンサーを最大限に活用し、従業員のエンゲージメントと生産性の向上につなげるべきです。
中小企業こそ相談窓口で経営改善を図る

従業員相談窓口は、単なるハラスメント対策やメンタルヘルスケアの手段にとどまりません。とくに中小企業においては、経営改善を促進し、持続的な成長を支える強力なツールとなり得ます。
従業員の声に耳を傾け、それを経営に活かすことで、企業全体の生産性向上、リスク低減、そして採用競争力の強化を目指しましょう。

株式会社ドリームホップ
HRtech事業本部 運用支援グループ
臨床心理士・公認心理師
大学院終了後、東日本大震災の被災自治体にて自治体人事課業務、全国自治体派遣職員の生活援助、職員の安全衛生、健康管理、カウンセリング、メンタルヘルス対策等の業務を経験し、株式会社ドリームホップ入社。
現在は、年間100~200組織のストレスチェック、カウンセリング、研修等に携わりながら、企業のメンタルヘルス対策・組織改善にかかわるプロダクト開発・学術研究に従事している。