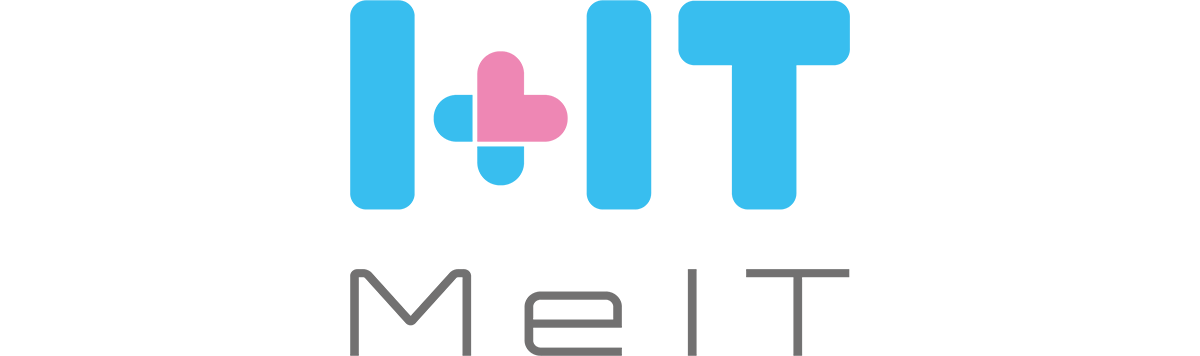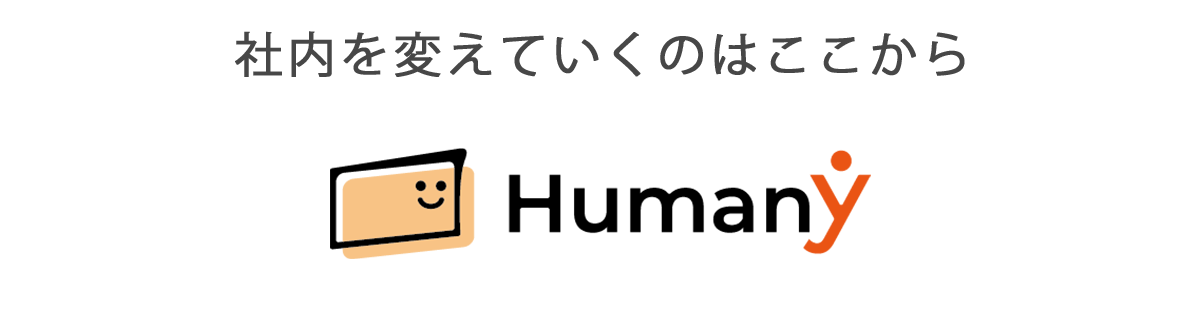ハラスメント相談窓口の設置・運用ガイド|企業が取るべき対策と注意点
公開日:2021/12/03
更新日:2025/07/03

ハラスメント相談窓口の設置は、企業にとって単なる義務ではなく、健全な職場環境を築き、リスクを低減するための重要な経営戦略です。
本記事では、パワハラ防止法に代表されるハラスメント対策の義務化の背景から、社内・外部相談窓口の具体的な設置方法、適切な運用、担当者の役割、そしてハラスメントを未然に防ぐための効果的な取り組みまで、企業が取るべき対策と注意点を網羅的に解説します。ハラスメントリスクを管理し、従業員が安心して働ける職場をつくりましょう。
なぜハラスメント相談窓口が今、企業に求められるのか

現代の職場において、ハラスメントは従業員の心身の健康を害し、企業の生産性やブランドイメージに深刻な影響を与える喫緊の課題です。かつては個人の問題として扱われがちでしたが、法改正や社会意識の変化により、企業が積極的に対策を講じることの重要性が増しています。
ハラスメント対策義務化の背景と企業の責任
職場におけるハラスメントは、長年にわたり労働問題として認識されてきました。厚生労働省が2016年に行った「職場のパワーハラスメントに関する実態調査報告書」では、過去3年以内にパワハラを受けた経験がある人が全体の約3割に上るという結果が示され、その深刻さが浮き彫りになりました。また、都道府県労働局に寄せられるいじめや嫌がらせに関する相談件数も増加の一途をたどり、2018年度には8万件を超えるなど、社会全体で職場ハラスメントへの関心が高まりました。
このような状況を受け、2019年には「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」(通称:労働施策総合推進法/パワハラ防止法)が改正され、企業に対して職場におけるハラスメント防止のための措置を講じることが義務化されました。
この法律により、企業は以下の具体的な措置を講じる責任を負います。
| 義務の内容 | 具体的な措置 |
|---|---|
| ハラスメントに対する方針の明確化と周知・啓発 | 就業規則等にハラスメントを行ってはならない旨を規定し、その内容を従業員に周知する |
| 相談に応じ、適切に対応するための体制整備 | ハラスメント相談窓口を設置し、相談への対応方法を定める |
| 職場におけるハラスメントに関する事後の迅速かつ適切な対応 | 事実関係の迅速な確認、被害者・加害者への適切な措置、再発防止策の実施 |
| プライバシー保護等の措置 | 相談者・行為者のプライバシー保護、相談を理由とした不利益な取扱いの禁止 |
これらの義務を怠った場合、直ちに罰則が科されるわけではありませんが、厚生労働大臣による指導や勧告の対象となり、悪質な場合は企業名が公表される可能性があります。
相談窓口設置がもたらす企業へのメリット
ハラスメント相談窓口の設置は、単なる法的義務の履行に留まらず、企業経営において多岐にわたるメリットをもたらします。主なメリットは以下のとおりです。
- 法的リスクの低減
ハラスメントが発生した場合、企業は民事訴訟や行政指導のリスクに直面する。相談窓口を通じて問題を早期に把握し、適切に対応することで、訴訟に発展する可能性を低減し、多額の賠償金や弁護士費用といった経済的損失を防げる - 企業イメージ・レピュテーションの向上
ハラスメント問題が表面化し、対応が不適切であった場合、企業のブランドイメージや社会的信用は大きく損なわれる。相談窓口の設置と適切な運用は、従業員だけでなく、顧客や取引先、求職者に対しても「従業員を大切にする企業」というポジティブなメッセージを発信し、企業価値を高められる - 従業員の定着率・生産性の向上
ハラスメントは従業員のモチベーション低下、ストレス、精神疾患の原因となり、結果として離職や休職につながる。相談窓口があることで、従業員は安心して悩みを打ち明けられるようになり、心理的安全性が確保される。これにより、エンゲージメントが高まり、集中力や創造性が向上し、組織全体の生産性向上につながる - 早期発見・早期解決による問題の深刻化防止
ハラスメントは放置されるとエスカレートし、取り返しのつかない事態に発展することがある。相談窓口は、問題の芽を早期に摘み取るための重要なセンサーとして機能する。迅速な対応により、被害の拡大を防ぎ、加害者への適切な指導や処分、再発防止策の実施へとつながる - コンプライアンス体制の強化
ハラスメント対策は、企業のコンプライアンス(法令遵守)体制の中核。相談窓口の設置と運用は、企業が社会規範や倫理観を尊重し、健全な組織運営を行っていることの証となる
ハラスメントの種類と具体的な定義

職場におけるハラスメントは多岐にわたり、その定義や具体例を正しく理解することが、適切な対策を講じるうえで不可欠です。ここでは、主要なハラスメントの種類とその具体的な定義、判断基準について解説します。
職場におけるパワハラの定義と判断基準
職場におけるパワーハラスメント(パワハラ)は、厚生労働省の指針において、以下の3つの要素をすべて満たす行為と定義されています。
- 優越的な関係を背景とした言動:職務上の地位や人間関係など、加害者側の優位性を利用した言動を指す。上司から部下への行為だけでなく、先輩・後輩間、同僚間、さらには専門知識や経験が豊富な部下から上司への行為も該当する場合がある
- 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの:業務の適正な範囲を超えて行われる言動を指す。業務上の指示や指導、注意・叱責であっても、その目的や態様が不適切である場合、パワハラに該当する可能性がある
- 労働者の就業環境が害されるもの:業務の適正な範囲を超えて行われる言動により、労働者が身体的または精神的な苦痛を感じ、業務を遂行するうえで看過できない程度の支障が生じることをいう
パワハラの判断基準は、「平均的な労働者の感じ方」が採用されます。これは、特定の労働者の主観的な感じ方だけでなく、社会一般の労働者が就業できないほどの苦痛と感じる言動かどうかという客観的な視点から判断されるということです。
パワハラは、具体的な行動類型として以下の6つに分類されます。
| 類型 | 概要 | 具体例 |
|---|---|---|
| 身体的な攻撃 | 暴行や傷害など、身体に直接的な危害を加える行為 | 殴る、蹴る、物を投げつける、胸ぐらを掴む |
| 精神的な攻撃 | 脅迫、名誉毀損、侮辱、ひどい暴言など、精神的に苦痛を与える行為 | 大勢の前での叱責、人格否定の発言、無視、SNSでの誹謗中傷 |
| 人間関係からの切り離し | 隔離、仲間外し、無視など、人間関係を阻害する行為 | 一人だけ別室に隔離する、会議や連絡から意図的に外す |
| 過大な要求 | 業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害 | 新入社員に達成不可能なノルマを課す、休日出勤の強要 |
| 過小な要求 | 業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと | 管理職の経験がある社員に単純作業のみをさせる、雑用しか与えない |
| 個の侵害 | 私的なことに過度に立ち入ること | 個人情報(病歴、交友関係など)を執拗に聞き出す、監視する |
これらの類型に該当する行為は、業務上の指導との線引きが難しいため、日頃からコミュニケーションを密にし、指導の目的と必要性を明確にすることが重要です。
【関連記事:<休職中対応>社員が休職の原因はパワハラだと言っている。】
セクシュアルハラスメントの理解と対応
セクシュアルハラスメント(セクハラ)は、職場において行われる性的な言動に対する労働者の対応により、その労働者が労働条件について不利益を受けたり、性的な言動により就業環境が害されたりすることを指します。男女雇用機会均等法に基づき、事業主は防止措置を講じることが義務付けられています。
セクハラには大きく分けて以下の2つの種類があります。
- 対価型セクシュアルハラスメント:労働者の意に反する性的な言動に対し、労働者が拒否や抵抗をしたことで、解雇、降格、減給、配置転換などの不利益な取り扱いを受けること
- 環境型セクシュアルハラスメント:労働者の意に反する性的な言動により、職場の就業環境が不快になり、労働者の能力の発揮に重大な悪影響が生じること
セクハラは、行為者の意図に関わらず、受け手が不快に感じた場合に成立する可能性があります。また、被害者・加害者の性別を問わず、同性間でも発生し得るものです。職場における性的な言動とは、業務遂行中に限らず、休憩時間、懇親会、出張先など、業務に関連するあらゆる場所での言動が含まれます。
妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント(マタハラ)
妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント(マタハラ)は、職場において行われる妊娠・出産等に関する言動により、女性労働者の就業環境が害されたり、妊娠・出産・育児休業等の利用に関する言動により、男女労働者の就業環境が害されたりすることを指します。
育児介護休業法および男女雇用機会均等法に基づき、事業主は防止措置を講じることが義務付けられています。
マタハラは、主に以下の2つの種類に分類されます。
- 制度等利用への嫌がらせ型:育児休業や介護休業、時短勤務などの制度利用を阻害するような言動
・「育休を取るなら辞めてもらう」と脅す
・育休申請を却下する、取得を妨害する
・制度利用を理由に不当な配置転換や降格を行う
- 状態への嫌がらせ型:妊娠・出産、育児等に関する状況(つわり、体調不良、子の病気など)に対する嫌がらせ
・「妊娠は病気じゃない」と心ない言葉をかける
・「どうせすぐ辞めるんだろ」と嫌味を言う
・体調不良を訴えているのに無理な業務を強いる
マタハラは、女性だけでなく、男性が育児休業を取得しようとした際に受けるハラスメント(パタニティハラスメント、通称パタハラ)も含まれます。また、上司や同僚だけでなく、顧客からの言動もマタハラの対象となる場合があります。
多様化するハラスメント(リモートハラスメント、カスハラなど)
社会や働き方の変化に伴い、ハラスメントの種類も多様化しています。ここでは、近年とくに問題視されているハラスメントについて解説します。
リモートハラスメント(リモハラ)
リモートハラスメント(リモハラ)は、リモートワークやオンラインでのコミュニケーション環境下で発生するハラスメントです。
- 過度な監視・管理:オンラインツールの利用状況を常に監視する、不必要な頻度で進捗報告を求めるなど
- プライベートへの過度な干渉:業務時間外の連絡、プライベートな空間(自宅)の背景や家族への言及など
- オンライン会議での差別的扱い:特定の参加者だけを無視する、発言機会を与えない、意図的にミュートにするなど
- 情報格差の発生:リモートワーク中の社員に重要な情報を共有しない、必要な連絡を怠るなど
リモハラは、コミュニケーション不足や相手の状況が見えにくい環境が背景にあることが多く、企業はガイドラインの整備や適切なツールの利用を促す必要があります。
カスタマーハラスメント(カスハラ)
カスタマーハラスメント(カスハラ)は、顧客や取引先から、従業員に対して行われる著しい迷惑行為を指します。企業の従業員が、顧客からの不当な要求や言動によって精神的・肉体的な苦痛を受けるケースが増加しており、従業員を守るための対策が求められています。
- 暴言・威圧的な態度:大声で怒鳴る、長時間にわたる説教、侮辱的な言葉を浴びせるなど
- 不当な要求:本来提供されないサービスの要求、過剰な金銭的補償の要求、土下座の強要など
- セクシュアルハラスメント:性的な冗談、身体への不必要な接触、執拗な交際要求など
- SNS等での誹謗中傷:事実と異なる内容を拡散する、個人情報を晒すなど
企業は、カスハラに対する方針を明確にし、従業員への周知、対応マニュアルの作成、法的措置の検討など、従業員が安心して働ける環境を整備する義務があります。
その他の多様なハラスメント
上記以外にも、現代社会ではさまざまなハラスメントが認識されています。代表的なものを挙げてみましょう。
| ハラスメントの種類 | 概要 | 具体例 |
|---|---|---|
| アルコールハラスメント(アルハラ) | 飲酒に関する嫌がらせ行為 | 飲酒の強要、イッキ飲みの煽り、飲めない人への配慮不足、酔ったうえでの暴言や暴力 |
| モラルハラスメント(モラハラ) | 精神的な暴力や嫌がらせ行為 | 無視、仲間外れ、人格否定、不機嫌な態度で威圧、プライベートへの干渉 |
| スメルハラスメント(スメハラ) | 体臭や香水、タバコ臭など、匂いによる嫌がらせや不快感を与える行為 | 香水や柔軟剤の匂いがきつい、体臭が強い、喫煙後の匂いが残る |
| ロジカルハラスメント(ロジハラ) | 正論や論理を振りかざし、相手を追い詰める行為 | 相手の感情を無視して正論でねじ伏せる、反論の余地を与えない |
| テクノロジーハラスメント(テクハラ) | IT機器やデジタルツールに不慣れな人に対する嫌がらせ | ITスキル不足を嘲笑する、PC操作を教えずに放置する |
| ジェンダーハラスメント(ジェンハラ) | 性別に基づく固定観念や差別的な言動 | 「男だから」「女だから」といった決めつけ、性別役割の押し付け |
これらのハラスメントは、従業員の心身の健康を損ね、生産性の低下や離職につながる可能性があるため、企業は包括的なハラスメント対策を講じる必要があります。
ハラスメント相談窓口の設置義務と具体的な措置

2019年に労働施策総合推進法が改正され、すべての企業に対し、職場におけるハラスメント防止のための措置を講じることが法律で義務付けられました。これは通称「パワハラ防止法」とも呼ばれ、職場でのハラスメント行為を未然に防ぎ、労働者が安心して働ける環境を整備することを目的としています。
企業が講ずべき具体的な措置は、主に以下の4つの項目です。
- 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
- 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
- 職場におけるハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
- その他、職場におけるハラスメントと併せて講ずべき措置
このうち「相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備」において、ハラスメント相談窓口の設置が義務付けられています。相談窓口の設置を怠った場合、直接的な罰則規定はありません。しかし、労働基準監督署からの指導や勧告の対象となる可能性があり、改善が見られない場合には企業名が公表されることもあります。
相談窓口の設置方法と選択肢
ハラスメント相談窓口の設置方法は、主に「内部相談窓口」と「外部相談窓口」の2つがあります。それぞれの特徴を理解し、自社の規模や状況、従業員のニーズに合わせて最適な方法を選択することが重要です。
内部相談窓口と外部相談窓口の主なメリット・デメリットを以下の表にまとめました。
| 項目 | 内部相談窓口 | 外部相談窓口 |
|---|---|---|
| メリット |
|
|
| デメリット |
|
|
外部委託先を選定する際は、実績、専門分野、費用、報告体制、個人情報保護体制などを総合的に評価し、信頼できる機関を選ぶことが重要です。
相談窓口の周知とプライバシー保護の徹底
ハラスメント相談窓口は、設置するだけでなく、従業員がその存在を知り、安心して利用できる環境を整えることが極めて重要です。また、相談者のプライバシーを厳重に保護し、不利益な取扱いをしないことを明確にすることも不可欠です。
相談窓口の周知方法には、以下が挙げられます。
- 就業規則・社内規程への明記:ハラスメント防止規程や就業規則に相談窓口の設置、利用方法、対応フロー、秘密保持、不利益取扱いの禁止などを明確に記載し、全従業員に周知する
- 社内掲示・イントラネット・社内報:相談窓口の連絡先、利用時間、対応可能な相談内容などを、グループウェア、社内イントラネット、社内報などで定期的に周知する。視覚的に分かりやすいポスターやチラシの活用も効果的
- 研修会の実施:全従業員を対象としたハラスメント防止研修の中で、相談窓口の役割や利用方法について説明する時間を設ける。相談窓口の認知度を高めるとともに、ハラスメントに対する意識向上を促す
- 入社時の説明:新入社員に対して、入社時にハラスメント防止に関する方針や相談窓口の存在を説明し、安心して働ける職場であることを伝える
また、相談者が安心して相談できる環境を築くためには、プライバシー保護が不可欠です。プライバシー保護のポイントを見てみましょう。
- 秘密保持義務の徹底:相談窓口の担当者や関係者は、相談内容や相談者の個人情報について厳重な秘密保持義務を負うことを明確にする。相談者の同意なく、不必要な範囲で第三者に情報を開示することは絶対に避ける必要がある
- 不利益取扱いの禁止:相談したこと、または事実関係の確認に協力したことを理由として、相談者や関係者が解雇、配置転換、減給などのいかなる不利益な取扱いも受けないことを明確に定め、徹底する
- 匿名相談の検討:相談者の心理的負担を軽減するため、匿名での相談も受け付ける体制を検討する
- 情報管理の徹底:相談記録や関連資料は厳重に管理し、アクセス権限を限定するなど、情報漏洩のリスクを最小限に抑える措置を講じる
従業員への周知とプライバシー保護の徹底は、相談窓口が機能するための土台となります。
社内相談窓口の運営と担当者の役割

社内相談窓口は、ハラスメントの早期発見と解決、そして健全な職場環境の維持において極めて重要な役割を担います。その効果的な運営には、適切な担当者の選任と、明確な対応プロセスの確立が不可欠です。
相談担当者の選任と必要なスキル
ハラスメント相談窓口の担当者は、相談者が安心して心の内を打ち明けられるよう、高い専門性と倫理観が求められます。人事部門や総務部門の担当者が兼任するケースがよくみられますが、相談しやすい環境を整えるためには、複数の担当者を配置し、性別や役職などに配慮することも重要です。また、外部の専門家(弁護士、臨床心理士など)と連携できる体制を構築することも有効です。
相談担当者に求められる主なスキルは以下のとおりです。
| スキル項目 | 内容 |
|---|---|
| 傾聴力・共感力 | 相談者の話を遮らず、最後まで耳を傾け、感情に寄り添う姿勢。相談者の苦痛や悩みを理解し、共感を示すことで信頼関係を築く |
| 守秘義務の遵守 | 相談内容や個人情報を厳重に管理し、許可なく第三者に漏らさないこと。相談者のプライバシー保護は最も重要な原則 |
| 公平性・中立性 | 相談者、行為者、関係者のいずれに対しても偏見なく、客観的な視点で事実確認を行い、判断すること |
| 法律・社内規定の知識 | 労働施策総合推進法(パワハラ防止法)をはじめとする関連法規や、自社の就業規則、ハラスメント防止規定などを正確に理解していること |
| メンタルヘルスに関する基礎知識 | ハラスメントが相談者の心身に与える影響を理解し、必要に応じて産業医や外部カウンセラーへの連携を促せる知識 |
| 記録作成能力 | 相談内容や事実確認の結果を正確かつ詳細に記録する能力 |
これらのスキルについて、定期的な研修を通じて習得・向上させることが推奨されます。とくに、相談対応の経験が少ない担当者に対しては、実践的なロールプレイング研修などを実施し、対応力を高めることが重要です。
相談対応マニュアルの整備
相談窓口の運営を円滑かつ適切に行うためには、詳細な相談対応マニュアルの整備が不可欠です。マニュアルは、相談担当者が一貫した対応を行うための指針となり、対応漏れや判断ミスを防ぐ役割を果たします。また、相談者にとっても、どのようなプロセスで問題が解決されるのかが明確になり、安心感につながります。
マニュアルには、少なくとも以下の項目を盛り込みましょう。
- 相談受付から解決までの具体的なフローチャート(受付、ヒアリング、事実確認、認定、措置検討、解決、再発防止策まで)
- 守秘義務、プライバシー保護、不利益取り扱いの禁止に関する明確な規定
- 相談者の希望(解決を望むか、情報提供のみかなど)の確認方法
- ヒアリング時の質問例や留意事項(傾聴の姿勢、共感の示し方、誘導尋問の禁止など)
- 事実確認の方法(行為者・第三者からのヒアリング、客観的証拠の収集)と注意点
- ハラスメントの認定基準(厚生労働省のガイドラインに準拠しつつ、自社の状況に合わせた判断基準)
- ハラスメント認定後の措置の種類(行為者への処分、被害者へのケア、配置転換など)と、それぞれの措置を決定する際の基準
- 再発防止策の検討と実施に関する項目
- 産業医、弁護士、外部相談窓口など、関係機関との連携方法
- 相談記録の作成方法、保管方法、保管期間に関する規定
- 緊急時(相談者が心身に重大な影響を受けている場合など)の対応手順
このマニュアルは、一度作成したら終わりではなく、法改正や社会情勢の変化、あるいは社内で発生した事案の教訓などを踏まえ、定期的に見直し、更新していく必要があります。
相談者へのヒアリングと事実確認の進め方
相談窓口の対応は、まず、担当者が相談者の話をじっくりと聞くことから始まります。この際、担当者は詰問するような態度ではなく、相談者に寄り添うような気持ちで、安心感を与えることが非常に大切です。相談者が繰り返し体験を語ることが一層苦痛となるおそれがあるため、初回面談で可能な限り正確な情報を引き出すよう努めます。一般的に、1回の相談時間は50分程度に設定し、内容が多岐にわたる場合は日を改めて面談を行うと良いでしょう。
ヒアリングでは、相談者の精神的負担に配慮しつつ、以下の点を明確に把握することを目指します。
- いつ、どこで、誰が、何を、どのように、なぜ、結果どうなったか、という具体的な事実関係
- ハラスメント行為が継続しているか、過去の出来事か
- 相談者が具体的にどのような解決を望んでいるのか(行為者への処分、謝罪、配置転換、再発防止策、情報提供のみなど)
- ハラスメント行為を示す客観的な証拠(メール、SNSのやり取り、録音、写真、診断書など)の有無
相談時の記録の重要性
相談時の記録は、事実関係を正確に把握し、その後の対応の根拠となるため、極めて重要です。繰り返し相談内容を尋ねることで相談者にさらなる精神的負担をかけることを避けるためにも、初回から詳細な記録を作成する必要があります。記録は、単なるメモではなく、以下の項目を含んだ形で作成し、適切に保管します。
| 記録項目 | 内容 |
|---|---|
| 相談日時・場所 | 面談を行った正確な日時と場所 |
| 相談者情報 | 相談者の氏名、所属部署、連絡先 |
| 担当者情報 | 相談対応を行った担当者の氏名、所属部署 |
| 相談内容の要約 | ハラスメント行為の具体的な内容、発生日時、場所、関係者、相談者が受けた影響などを詳細に記述 |
| 相談者の希望 | 相談者が会社に求める具体的な対応内容 |
| 今後の対応方針 | 会社として今後どのように対応を進めるか、相談者に伝えた内容 |
| 添付資料 | 相談者が提出した証拠資料(メール、診断書など)の有無と内容 |
記録は、客観的な事実に基づき、感情的な記述を避けるように心がけます。また、記録は個人情報を含むため、厳重な管理体制のもとで保管し、アクセス権限を限定するなど、情報漏洩のリスクを最小限に抑える必要があります。可能であれば、相談者にも記録内容を確認してもらい、誤りがないことを確認するプロセスを設けることも信頼性向上につながります。
関係者からの情報収集
相談者からのヒアリングだけでは事実関係が不明確な場合や、行為者からの反論が予想される場合などには、客観的な事実確認のために、行為者や第三者からの情報収集が必要となります。このプロセスも、公平性とプライバシー保護に最大限配慮して進めましょう。
- 行為者からのヒアリング:相談者の許可を得たうえで、行為者にも事実関係について説明を求める。この際、行為者にも弁明の機会を十分に与え、一方的な決めつけをしないことが重要
- 第三者からのヒアリング:ハラスメント行為の目撃者や、状況を知る可能性のある同僚など、第三者からも情報収集を行う。情報提供を依頼する際には、協力を求めるとともに、守秘義務を徹底し、情報提供者が不利益を被らないよう細心の注意を払う必要がある
- 客観的証拠の収集:メール、チャット履歴、業務日報、出勤記録、防犯カメラの映像など、客観的な証拠となり得るものを収集・確認する。これらの情報収集は、プライバシー侵害や名誉毀損とならないよう、細心の注意を払って行う
これらの情報収集を通じて、多角的に事実関係を検証し、ハラスメントの有無や程度を客観的に判断するための材料を揃える
ハラスメント認定後の措置と再発防止策
収集した情報に基づき、ハラスメントの有無や内容が確認された場合、企業は速やかに適切な措置を講じる必要がある。被害者の保護と行為者への対応、そして再発防止の三つの意味合いがある。人事労務担当者や行為者の上司とも連携を取りながら、就業規則やハラスメント防止規定に則って慎重に検討を進める
- 行為者への措置:ハラスメントの事実が認定された場合、行為者に対しては、就業規則に基づき懲戒処分を検討する。懲戒処分の種類は、ハラスメントの態様、悪質性、被害の程度などによって異なるが、戒告、減給、出勤停止、降格、諭旨解雇、懲戒解雇などが考えられる。また、配置転換や業務内容の変更、ハラスメント防止研修の受講義務付けなども有効な措置。行為者には、認定された事実と措置の内容を明確に伝え、再発防止を強く促す
- 被害者への措置:被害者の心身の回復と、安心して働ける環境の確保が最優先される。産業医や外部カウンセラーとの連携による精神的ケア、必要に応じた配置転換や休職、業務内容の変更などが挙げられる。また、行為者からの謝罪や、名誉回復のための措置を講じることも重要。被害者の意向を最大限尊重し、不利益な取り扱いがないよう配慮する
- 再発防止策:個別の事案への対応だけでなく、組織全体としてハラスメントの再発を防止するための取り組みも不可欠。以下が再発防止策の例
- 全従業員に対するハラスメント防止方針の明確な周知と啓発活動
- 定期的なハラスメント防止研修の実施(とくに管理職層への意識改革研修を強化)
- 社内規定や就業規則の見直しと、従業員への周知徹底
- 風通しの良い職場環境づくりの推進(コミュニケーションの活性化、意見表明の場の確保など)
- 定期的なストレスチェックやパルスサーベイの実施による、職場のハラスメントリスクの早期発見
- 相談窓口の継続的な運用と、その存在・利用方法の周知
外部相談窓口の活用と選び方のポイント

ハラスメント相談窓口の設置は企業の義務ですが、社内リソースだけでは対応が難しい場合や、より中立的・専門的な対応が求められる場合に、外部の専門機関に相談窓口業務を委託するという選択肢があります。外部相談窓口は、従業員が安心して相談できる環境を提供し、企業のリスクマネジメントにも貢献します。
主な外部相談窓口の種類
ハラスメントに関する外部相談窓口には、さまざまな専門性を持つ機関があります。それぞれの特徴を理解し、自社のニーズに合った窓口を選ぶことが大切です。
- 弁護士事務所:
ハラスメントが法的な問題に発展する可能性がある場合や、法的な助言が必要な場合に強みを発揮する。ハラスメントの定義、証拠収集、損害賠償請求、懲戒処分など、法律に基づいた対応やリスク管理について専門的なアドバイスが得られる。訴訟リスクを考慮した対応策を検討する際にとくに有効 - 社会保険労務士事務所:
労務管理の専門家として、就業規則やハラスメント防止規定の整備、社内調査の進め方、行政機関(労働局など)への対応について専門的なサポートを行う。法改正への対応や、実務的な労務管理の観点からのアドバイスが期待できる - 産業カウンセラー・臨床心理士等による専門機関:
ハラスメントによる精神的苦痛を抱える相談者に対し、心理的ケアやカウンセリングを提供する。ハラスメントが確定する前の段階でのメンタルヘルスサポートや、二次被害防止に有効 - EAP(従業員支援プログラム)サービス提供会社:
従業員のメンタルヘルスやハラスメント問題だけでなく、キャリア、育児、介護、生活習慣病など、従業員の幅広い悩みに対応する総合的な支援プログラムを提供する。専門のカウンセラーが対応し、電話やWeb、対面など多様な方法で相談を受け付ける。ハラスメント相談だけでなく、従業員のウェルビーイング向上を包括的にサポートしたい企業におすすめ - 公的機関:
厚生労働省が設置している総合労働相談コーナーなど、無料で利用できる相談窓口もある。ただし、企業への直接的な介入は限定的であり、企業の具体的なハラスメント対策を継続的にサポートする役割とは異なる
外部委託先の選定基準
外部相談窓口を委託する際には、以下の選定基準を参考に、自社の状況やニーズに最も合致するパートナーを選ぶことが成功の鍵となります。
| 選定基準 | 具体的な確認事項 |
|---|---|
| 専門性と実績 |
|
| 守秘義務とプライバシー保護体制 |
|
| 対応範囲とサービス内容 |
|
| 費用体系の明確さ |
|
| 企業文化への理解と連携体制 |
|
これらの基準を総合的に評価し、自社にとって最適な外部相談窓口を選ぶことで、ハラスメント対策の実効性を高め、従業員が安心して働ける職場づくりが進むでしょう。
ハラスメントを未然に防ぐための取り組み

ハラスメントは一度発生すると、被害者の心身に深刻な影響を及ぼすだけでなく、職場の士気低下、生産性の悪化、企業イメージの損害など、組織全体に多大な悪影響をもたらします。そのため、ハラスメントが発生してから対処するだけでなく、未然に防止するための積極的な取り組みが不可欠です。
ハラスメント防止方針の明確化と周知
企業がハラスメント対策に取り組むうえで、最も基本となるのが「ハラスメントは許されない行為である」という明確な方針を打ち出し、それを全従業員に徹底的に周知することです。これにより、企業としての毅然とした態度を示し、従業員一人ひとりの意識改革を促します。
具体的な取り組み
- トップメッセージの発信:経営層がハラスメント防止への強い決意を表明し、全従業員に周知
- 就業規則等への明記:就業規則や服務規律にハラスメント行為を明確に禁止する旨を記載し、違反した場合の懲戒処分についても具体的に定める
- ハラスメント防止規程の策定:ハラスメントの種類、定義、相談窓口、相談後の対応プロセス、プライバシー保護、不利益取扱いの禁止などを明記した規程を策定し、従業員に配布またはグループウェア・社内ポータルサイト等で公開する
- 周知の徹底:入社時研修での説明、定期的な社内研修、グループウェア、社内報、社内ポータルサイトなどを活用し、従業員がいつでもハラスメントに関する情報にアクセスできるよう工夫する。とくに、相談窓口の存在とその利用方法については、繰り返し周知することが重要
従業員への啓発活動と研修の実施
ハラスメントの未然防止には、従業員一人ひとりのハラスメントに対する正しい理解と意識の向上が不可欠です。定期的な啓発活動と研修を通じて、ハラスメントの発生リスクを低減します。
研修の目的と内容
研修では、単に知識を伝えるだけでなく、参加者がハラスメントを「自分ごと」として捉え、行動変容を促す内容とすることが重要です。
| 対象者 | 主な目的 | 研修内容例 |
|---|---|---|
| 全従業員 | ハラスメントの正しい理解を深め、加害者にも被害者にも傍観者にもならない意識を醸成する |
|
| 管理職・リーダー層 | ハラスメント防止の責任と役割を認識し、適切なマネジメントスキルを習得する |
|
研修実施のポイント
- 定期的な実施:一度きりではなく、年1回など定期的に実施することで、知識の定着と意識の維持を図る
- 多様な形式:eラーニング、集合研修、グループディスカッション、ロールプレイングなど、飽きさせない工夫を凝らす。とくに、具体的な事例を用いたディスカッションは、参加者の当事者意識を高める
- 外部講師の活用:専門的な知識を持つ外部講師を招くことで、客観的かつ質の高い研修を提供できる
- アンケートによる効果測定:研修後にはアンケートを実施し、理解度や満足度を測り、次回の研修内容に反映させる
ストレスチェック・パルスサーベイの活用
従業員のストレス状況や職場の雰囲気を定期的に把握することは、ハラスメントの発生リスクを早期に察知し、対策を講じるうえで有効な手段です。ストレスチェックやパルスサーベイといったツールを積極的に活用しましょう。
ストレスチェックをハラスメント防止に活用するポイント
- 個人のストレス状況だけでなく、部署やチームごとの集団分析結果から、ハラスメントの温床となりやすい職場環境の問題点(例:過重労働、人間関係の悪化など)を特定し、改善策を検討する
- 高ストレス者が多い部署や特定の人間関係に起因するストレス要因が見られる場合、ハラスメントの潜在的なリスクが高いと判断し、早期の介入や調査につなげる
【関連記事:ストレスチェック基本の「き」がわかる!導入手順・実施方法・注意点まとめ】
パルスサーベイをハラスメント防止に活用するポイント
- 人間関係の満足度や上司への信頼度など、ハラスメントにつながりやすい項目を定期的にモニタリングすることで、ハラスメントの兆候や職場の人間関係の悪化を早期に察知する
- 匿名性を確保し、従業員が安心して本音を回答できる環境を整えることで、表面化しにくい潜在的な問題を拾い上げる
- 結果を迅速にフィードバックし、PDCAサイクルを回すことで、継続的な職場環境改善につなげる
【関連記事:パルスサーベイとは?ストレスチェックとの違い、メリット・デメリット、活用事例まで徹底解説】
ストレスチェックやパルスサーベイを活用すれば、従業員の健康管理だけでなく、ハラスメントを含む職場の潜在的なリスクを可視化し、先行対策を講じるための重要なデータが得られます。
風通しの良い職場環境づくり
ハラスメントは、閉鎖的でコミュニケーションが不足しがちな環境で発生しやすい傾向があります。日頃から風通しの良い、心理的安全性の高い職場環境を構築することが、ハラスメントの根本的な防止につながります。
具体的な取り組み
- コミュニケーションの活性化
- 1on1ミーティングの推奨:上司と部下が定期的に一対一で対話する機会を設け、業務の進捗だけでなく、キャリアや悩みについても話しやすい関係性を築く
- オープンな対話の促進:部署や役職の垣根を越えた交流イベントや、ランチミーティングなどを企画し、非公式なコミュニケーションを促す
- フィードバック文化の醸成:ポジティブな点も改善点も、建設的に伝え合う文化を育む
- 心理的安全性の確保
- 従業員が「自分の意見や質問、懸念を表明しても、罰せられたり、恥をかいたりすることはない」と感じられる環境を目指す
- 失敗を恐れずに挑戦できる雰囲気、多様な意見や価値観を尊重する姿勢を組織全体で育む
- 管理職は、部下の発言を傾聴し、否定せずに受け止める姿勢を示す
- 多様性の尊重とインクルージョンの推進
- 性別、年齢、国籍、障がいの有無、性的指向、価値観など、あらゆる多様性を受け入れ、それぞれの個性が尊重される職場を目指す
- 多様な視点を取り入れることで、ハラスメントにつながる無意識の偏見や固定観念を解消し、より創造的で働きやすい環境を創出する
- 経営層・管理職のリーダーシップ
- 経営層や管理職が自ら模範となり、ハラスメント防止に対する強いコミットメントを示すことが、組織全体の意識を変える原動力となる
- 「いつでも相談してほしい」「ハラスメントは絶対に許さない」というメッセージを日頃から発信し、従業員が安心して働ける環境をリードしていく責任がある
これらの取り組みは、ハラスメント防止だけでなく、従業員満足度の向上、生産性の向上、離職率の低下など、企業の持続的な成長にもつながるものです。
相談窓口の活用は経営課題

ハラスメント相談窓口の設置は、パワハラ防止法により企業の義務となりました。これは単なる法的要件に留まらず、従業員が安心して働ける環境を整備し、企業の健全な成長を支えるうえで不可欠な要素です。
適切な窓口の設置と運用は、ハラスメントの早期発見・解決を促し、従業員のエンゲージメント向上に寄与します。また、企業イメージの向上や訴訟リスクの低減にもつながり、持続可能な企業経営を実現するための重要な投資と言えるでしょう。ハラスメントを未然に防ぎ、誰もが働きやすい職場環境を築くため、継続的な取り組みが求められます。