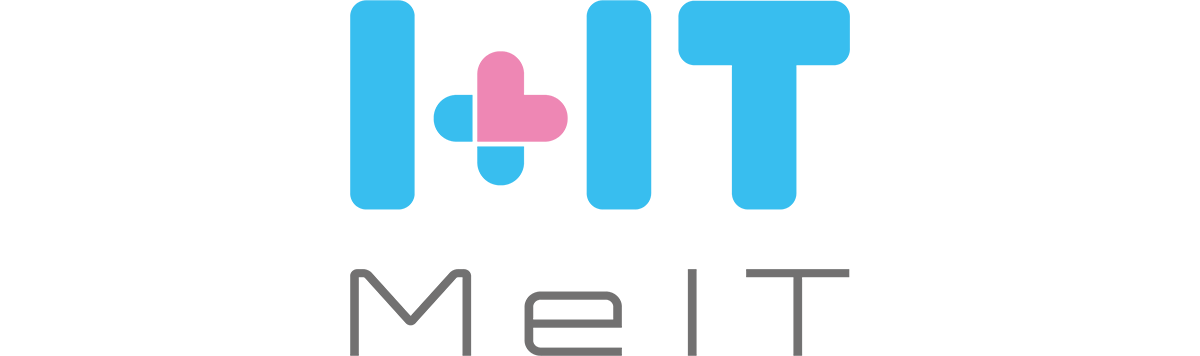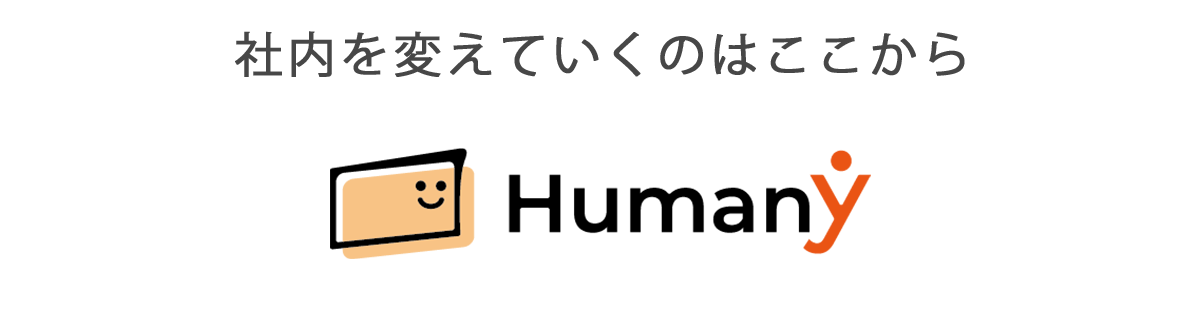カスハラ対策の義務化、あなたの会社は大丈夫?すぐに実践できる具体的対策と相談窓口設置のポイント
更新日:2025/10/07

カスハラ対策は、労働施策総合推進法(パワハラ防止法)による企業の法的義務です。本記事では、事業主の責務に触れながら、自社の対応状況がわかるチェックリスト、方針の明確化や相談窓口設置といった具体的な対策の進め方、そして義務を怠った際の企業リスクまでを網羅的に解説します。従業員と会社を守るために今すぐ何をすべきか、確認しましょう。
カスハラ対策は企業の義務 法律で定められた事業主の責務とは
「お客様は神様」という言葉は、もはや過去のものです。近年、顧客や取引先からの度を越したクレーム、いわゆるカスタマーハラスメント(カスハラ)が深刻な社会問題となっており、従業員を守るための対策は、今や企業に課せられた法的な義務と言えます。直接的に「カスハラ防止法」という名称の法律は存在しませんが、関連する法律によって、事業主は従業員のために適切な措置を講じる責務を負っています。
この章では、なぜカスハラ対策が企業の義務なのか、その法的根拠と事業主が果たすべき責務の全体像をくわしく解説します。
パワハラ防止法で強化された企業のハラスメント対策義務
カスハラ対策の法的な根拠として最も重要なのが、2020年6月から大企業、2022年4月から中小企業にも適用が拡大された改正労働施策総合推進法(通称:パワハラ防止法)です。この法律では、職場におけるパワーハラスメント対策を事業主に義務付けていますが、その対象は社内の関係に留まりません。
この改正に絡み厚生労働省が定めた指針(事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針)でも、顧客や取引先などからの著しい迷惑行為(カスハラ)についても言及されていました。
2025年法改正によるカスハラ対策義務化・カスハラの定義
2025年には、労働施策総合推進法がさらに改正され、カスハラの定義が示されたうえで、カスハラ対策が全企業の義務となりました。具体的には、事業主はカスハラから従業員を守るため、相談体制の整備など「雇用管理上の配慮」をすることが望ましいと明記されています。
カスハラは以下の3要素をすべて満たすものとされています。
- 顧客、取引先、施設利用者その他の利害関係者が行う
- 社会通念上許容される範囲を超えた言動による
- 労働者の就業環境を害すること
そして、以下の措置が事業主の義務となりました。
- 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
- 相談体制の整備・周知
- 発生後の迅速かつ適切な対応・抑止のための措置
参考:令和7年の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(労働施策総合推進法)等の一部改正について|厚生労働省
さらに、労働契約法第5条では、企業は従業員が安全で健康に働けるように配慮する「安全配慮義務」を負うと定められています。カスハラによって従業員が精神的・身体的な健康を損なうことがないよう、職場環境を整備することは、この安全配慮義務を果たすうえでも不可欠です。
厚生労働省が示す事業主が講ずべき措置の3つの柱
企業は具体的にどのような対策を講じるべきなのでしょうか。厚生労働省が公表している「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」では、事業主が講ずべき対策の枠組みが示されています。これらは大きく3つの柱に整理できます。
| 対策の柱 | 具体的な措置の内容 |
|---|---|
| 1.方針の明確化と周知・啓発 | カスハラを許さないという企業姿勢を明確にし、就業規則等に規定を設ける。どのような行為がカスハラに該当するのかを具体的に示し、従業員だけでなく、顧客や社会に対してもその方針を表明する。 |
| 2.相談体制の整備 | 従業員がカスハラの被害に遭った際に、一人で抱え込まずに安心して相談できる窓口を設置し、その存在を全従業員に周知する。相談者が不利益な扱いを受けないことを保証することも重要。 |
| 3.事後の迅速かつ適切な対応 | 実際にカスハラが発生した場合の対応フローをあらかじめ定めておく。被害を受けた従業員のケアを最優先し、事実関係の確認、加害者への対応、再発防止策の検討などを迅速かつ適切に行う体制を構築する。 |
これらの措置は、パワハラ防止法で義務付けられている雇用管理上の措置と多くの点で共通しています。カスハラ対策は、パワハラやセクハラと同様に、企業が取り組むべきハラスメント対策全体の一部として捉え、一体的に進めていくことが極めて重要です。
あなたの会社は大丈夫?義務化に対応するカスハラ対策チェックリスト
従業員が安全かつ健康に働ける職場環境を整えることは、事業主の義務です。以下のチェックリストを使い、自社のカスハラ対策が十分かを確認してみましょう。
| カテゴリ | チェック項目 | 確認のポイント |
|---|---|---|
| 方針・体制整備 | カスハラに対する方針を明確に定めているか | 「カスハラは許さない」という企業の姿勢を文章で定義し、経営トップがメッセージを発信しているか。 |
| 就業規則等にカスハラに関する規定があるか | 相談・懲戒に関する規定や、従業員を守るための方針が明記されているか。 | |
| 方針を全従業員に周知・啓発しているか | ポスター掲示、社内報、グループウェアなどを活用し、いつでも確認できる状態になっているか。 | |
| カスハラに関する研修を実施しているか | 全従業員向け、管理職向けなど、対象者に合わせた研修を定期的に行っているか。 | |
| 相談体制の整備 | 相談窓口を設置し、従業員に周知しているか | 相談窓口の場所、担当者、連絡先(電話、メール等)が明確に案内されているか。 |
| 相談しやすい環境が整備されているか | プライバシーが保護される面談室の確保や、オンラインでの相談など、複数の選択肢を用意しているか。 | |
| 相談担当者が適切な研修を受けているか | 守秘義務や傾聴スキル、カスハラに関する知識など、担当者に必要な教育を行っているか。 | |
| 外部の相談窓口(EAPなど)と連携しているか | 社内の担当者には相談しにくい従業員のために、外部の窓口も用意しているか。 | |
| 事後の対応 | 相談後の対応フローがマニュアル化されているか | 事実確認、被害者への配慮、行為者への対応、再発防止策といった一連の流れが定められているか。 |
| 悪質なクレームと正当な要求を見極める基準があるか | 現場の従業員が判断に迷わないよう、具体的な判断基準を共有しているか。 | |
| 従業員を守るための具体的な対応策があるか | 複数人での対応、録音・録画の許可、対応の中断・退出のルールなどが決められているか。 | |
| 警察や弁護士など外部専門機関との連携体制があるか | 脅迫や暴力など、悪質な事案が発生した際に、速やかに相談できる体制が構築されているか。 |
もしチェックが付かない項目があれば、それは企業の安全配慮義務違反につながる可能性があります。次の章を参考に、早急な対策の実施をご検討ください。
企業が今すぐ取り組むべきカスハラ対策の具体的な進め方
カスハラ対策の義務化に対応するためには、場当たり的な対応ではなく、体系的かつ計画的に対策を進めることが不可欠です。ここでは、企業が今すぐ着手できる具体的な対策を3つのステップに分けて解説します。「方針の明確化」「相談体制の整備」「事後の対応フロー構築」という流れで進めることで、実効性のある対策を社内に根付かせることができます。
ステップ1 方針の明確化と社内への周知啓発
まず最初に取り組むべきは、企業として「カスハラを断固として許さない」という明確な方針を定め、それを全従業員に周知徹底することです。
カスハラ対策規定の作成例とポイント
自社の毅然とした姿勢を示すために、就業規則や個別の規定でカスハラへの対応方針を明文化しましょう。規定を作成することで、対応の属人化を防ぎ、一貫性のある対応が可能になります。規定には、以下の項目を盛り込むことが重要です。
| 項目 | 内容のポイント |
|---|---|
| カスハラの定義 | 自社における「カスハラ」がどのような行為を指すのかを具体的に定義する |
| 禁止行為の明記 | 暴言、威嚇、土下座の要求、長時間の拘束など、具体的な禁止行為を列挙 |
| 企業の基本方針 | 従業員の人格や尊厳を守り、安全な職場環境を提供することを宣言。 |
| 相談・対応窓口 | 誰が、どこで相談を受け付けるのかを明確に記載。 |
| 対応フロー | カスハラ発生時の報告から解決までの流れを定める。 |
| 加害者への対処 | 加害者への対処 悪質な要求を繰り返す顧客等に対し、取引停止や法的措置を含む厳しい対応を取る方針を示す。 |
現状把握にストレスチェック・パルスサーベイ活用
効果的な対策を講じるためには、まず自社の現状を正確に把握することが欠かせません。従業員がどのような状況でストレスを感じているのか、カスハラの潜在的なリスクはどこにあるのかを可視化するために、ストレスチェックやパルスサーベイといったツールが有効です。これらの調査結果から、とくに負担の大きい部署や業務を特定し、重点的な対策を講じることができます。
全従業員を対象とした研修の実施
カスハラに対する全社的な意識と対応スキルを向上させるため、定期的な研修を実施しましょう。研修は、役職や職務内容に応じて内容を最適化することが重要です。
- 管理職向け研修:部下がカスハラ被害に遭った際の対応方法、相談を受けた際の傾聴スキル、二次被害の防止策など、マネジメント層としての役割を学ぶ。
- 一般従業員向け研修:カスハラの定義、具体的な対応手順、エスカレーションの基準、自身のメンタルヘルスを守る方法などを学ぶ。
- 相談窓口担当者向け研修:プライバシー保護の重要性、相談者への適切な対応方法、事実確認の進め方など、より専門的な知識とスキルを習得。
ステップ2 相談体制の整備と相談窓口の設置
従業員がカスハラの被害に遭った際、一人で抱え込まずに安心して相談できる体制を整えることは、問題の早期発見と解決に直結する極めて重要な要素です。パワハラ防止法でも相談体制の整備は義務付けられており、カスハラ対策においても同様に必須の取り組みです。
相談しやすい窓口の条件とは
形だけの窓口では意味がありません。従業員が「ここに相談すれば大丈夫だ」と思える、実効性のある窓口を設置する必要があります。相談しやすい窓口には、以下のような条件が求められます。
- アクセスの多様性:対面だけでなく、電話、メール、オンライン面談など、複数の相談手段を用意する。
- 担当者の多様性:人事部、コンプライアンス部門など複数の部署に窓口を設けたり、男女双方の担当者を配置したりして、相談者が話しやすい相手を選べるように配慮する。
- プライバシーの厳守:相談内容や相談者の個人情報が厳格に保護され、相談したことで不利益な扱いを受けないことを明確に保証する。
- 外部窓口の設置:社内の人間には相談しづらいケースを想定し、外部相談窓口も併設する。
【関連記事:【中小企業向け/専門家監修】離職を防ぐ従業員相談窓口の構築と運用ポイント】
ステップ3 事後の迅速かつ適切な対応フローの構築
実際にカスハラ事案が発生してしまった場合に、組織として迅速かつ適切に対応するための具体的なフローをあらかじめ定めておくことが重要です。対応が遅れたり、担当者によって対応が異なったりすると、従業員の不信感を招き、問題を深刻化させるおそれがあります。
悪質なクレームと正当な要求の見極め方
顧客からの要求が、正当なクレームか、あるいは行き過ぎた要求(カスハラ)なのかを見極めることは、対応の第一歩です。この判断基準を社内で共有しておく必要があります。
| 判断基準 | 正当なクレーム・要求 | 悪質なクレーム・要求(カスハラ) |
|---|---|---|
| 要求内容の妥当性 | 商品やサービスの瑕疵に対する補償など、社会通念上、相当な範囲の要求。 | 金品の過剰な要求、土下座の強要など、社会通念を逸脱した不当な要求。 |
| 要求の手段・態様 | 冷静かつ論理的な指摘。 | 暴言、脅迫、威嚇、名誉棄損、人格否定、長時間の拘束、執拗な繰り返し。 |
この見極めが難しい場合は、一人で判断せず、上司や相談窓口に速やかに報告・相談するルールを徹底しましょう。
警察や弁護士との連携体制を整える
企業内の対応だけでは解決が困難な悪質なケースも想定し、外部の専門機関との連携体制を事前に構築しておくことが、従業員と会社を守るうえで不可欠です。
- 警察との連携:従業員の身体に危険が及ぶような暴力行為や脅迫、器物損壊など、明らかに犯罪行為に該当する場合は、ためらわずに警察(110番通報)に連絡します。事前に所轄の警察署に相談しておくことも有効です。
- 専門家との連携:法的な対応が必要になった場合に備え、いつでも相談できるハラスメント対策の専門家や顧問弁護士などを見つけておきましょう。対応方針に関する助言、相手方との交渉など、専門的な見地からサポートを受けることができます。
社内だけで抱え込まず、早期に専門家へ相談することが、結果的に被害の拡大を防ぎ、迅速な解決につながります。
カスハラ相談窓口設置で失敗しないためのポイント
単に窓口を設けるだけではカスハラ対策には不十分です。従業員が「何かあっても、あそこへ行けば大丈夫」と心から信頼し、安心して利用できる実効性のある窓口でなければ意味がありません。ここでは、従業員を守り、企業の義務を果たすための相談窓口設置における3つの重要なポイントを解説します。
ポイント1 相談者のプライバシー保護を徹底する
従業員が相談をためらう最大の理由は、「相談したことが原因で、職場で不利益な扱いを受けるのではないか」という不安です。この不安を払拭し、安心して声を上げられる環境を整えるためには、プライバシー保護の徹底が不可欠です。
具体的には、以下の措置を講じ、全従業員に明確に周知する必要があります。
- 守秘義務の厳守:相談内容や相談者の個人情報は、本人の同意なく他者へ共有しないことを徹底する。
- 不利益な取り扱いの禁止:相談したこと、あるいは事実確認に協力したこと等を理由として、解雇、降格、異動、嫌がらせなどの不利益な取り扱いを行うことを明確に禁止し、その旨を就業規則等に規定。
- 情報の厳格な管理:相談記録は施錠できる場所に保管したり、アクセス制限を設けたシステムで管理したりするなど、相談者や関係者のプライバシーが守られるよう、物理的・技術的な安全管理措置を講じる。
相談者が報復や不利益をおそれることなく、安心して第一歩を踏み出せる環境を整備することが、相談窓口を機能させるための大前提となります。
ポイント2 相談担当者の選任と教育
相談窓口の信頼性は、担当者の対応スキルに大きく左右されます。担当者には、人事や労務に関する知識だけでなく、高い倫理観とコミュニケーション能力が求められます。誰を担当者にするか、そしてどのように教育するかは極めて重要な課題です。
担当者には、次のような資質やスキルが求められます。
- 傾聴力と共感力:相談者の話に真摯に耳を傾け、不安な気持ちに寄り添う姿勢。
- ハラスメントに関する知識:カスハラと正当なクレームとの違いを客観的に判断できる知識。
- 中立性と公正さ:予断や偏見を持たず、事実関係を客観的に確認しようとする姿勢。
- 高い倫理観:守秘義務やプライバシー保護の重要性を深く理解し、遵守できること。
担当者に対しては定期的な研修を実施し、知識とスキルの向上を図りましょう。担当者が一人で問題を抱え込まないよう、複数の担当者を置いたり、産業医や心理の専門家などと連携したりするサポート体制を築くことも、担当者自身のメンタルヘルスを守るうえで重要です。
ポイント3 外部相談窓口を設けておく
社内窓口だけでは、「上司や同僚に知られたくない」「社内の人間関係がこじれるのが怖い」といった理由で相談しにくいケースも少なくありません。とくに、相談内容が社内の有力者に関わる場合、内部窓口では公正な対応が難しい可能性もあります。そこで有効なのが、外部相談窓口の設置です。
EAP(従業員支援プログラム)提供企業などの専門機関に委託することで、従業員は社内の人間関係を気にすることなく、安心して相談できます。内部窓口と外部窓口にはそれぞれメリット・デメリットがあるため、両方を設置し、従業員が状況に応じて選択できるようにすることが理想的です。
| 窓口の種類 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 内部相談窓口 |
|
|
| 外部相談窓口 |
|
|
相談の選択肢を複数用意し、従業員が最も利用しやすい方法を選べるようにすることが、問題の早期発見と解決につながります。
カスハラ対策を怠った場合の企業リスクと罰則の有無
ここでは、対策を怠った場合に想定される具体的なリスクを解説します。
従業員からの安全配慮義務違反による損害賠償請求
2025年改正の時点では、労働施策総合推進法によるカスハラ対策の罰則規定はありません。しかし、企業には、労働契約法第5条に基づき、従業員が安全で健康に働けるよう配慮する「安全配慮義務」が課せられています。顧客からのハラスメントを放置し、従業員が精神疾患を発症したり、休職・退職に追い込まれたりした場合、この義務を怠ったと判断される可能性があります。
その結果、従業員から、安全配慮義務違反を理由として、治療費や休業損害、慰謝料などを含む損害賠償請求訴訟を起こされるリスクがあります。裁判では、企業がカスハラを認識しながら適切な対策を講じなかったことが厳しく問われ、高額な賠償金の支払いを命じられるケースも少なくありません。
企業イメージの低下と採用活動への悪影響
カスハラが放置されているという事実は、SNSや口コミサイトを通じて瞬く間に拡散される可能性があります。一度「従業員を守らない会社」「ブラック企業」という評判が広まってしまうと、そのイメージを払拭するのは容易ではありません。
このような企業イメージ(レピュテーション)の低下は、事業活動のさまざまな側面に深刻な悪影響を及ぼします。
| リスクの種類 | 具体的な悪影響 |
|---|---|
| 採用への影響 | 応募者数の減少、優秀な人材からの敬遠、内定辞退率の上昇 |
| 従業員への影響 | 従業員のモチベーション低下、メンタルヘルス不調の増加、離職率の上昇 |
| ブランド・売上への影響 | SNS等でのネガティブな情報の拡散、顧客や取引先からの信頼失墜、売上の減少 |
とくに、人材獲得競争が激化する現代において、採用活動への悪影響は致命的です。カスハラ対策の不備は、単なる労務問題に留まらず、企業の持続的な成長を阻害する重大な経営リスクであると認識する必要があります。
【関連記事:ウェルビーイング採用とは?企業と従業員の幸福度を高める戦略】
カスハラ対策を効果的に進めよう
カスハラ対策は、パワハラ防止法の趣旨にも含まれる企業の法的義務です。従業員の心身の健康を守る安全配慮義務を果たすため、企業には「方針の明確化と周知」「相談窓口の設置」「事後の迅速かつ適切な対応」を柱とした体制構築が求められます。対策を怠れば、従業員からの損害賠償請求や企業イメージの悪化といった深刻なリスクにつながります。本記事で解説した具体的な進め方やチェックリストを参考に、従業員が安心して働ける職場環境を整備し、自社の持続的な成長を実現しましょう。