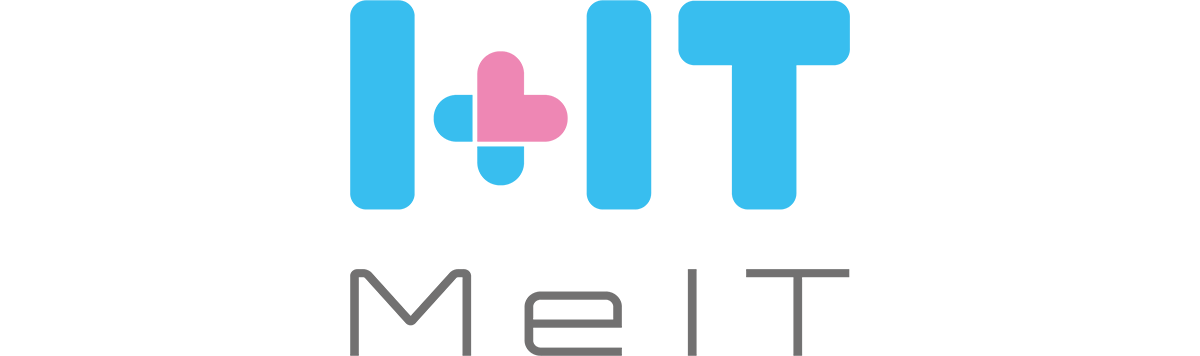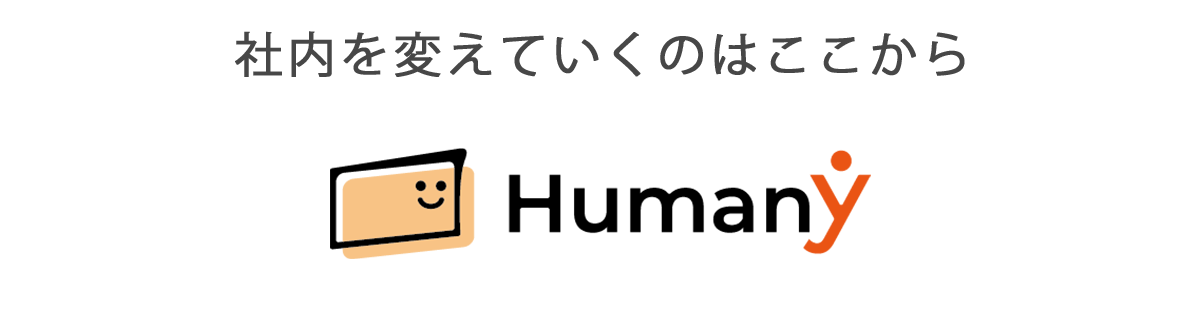厚労省パワハラ指針を読み解く!企業が講ずべきパワハラ防止措置と実務対応 第1回
更新日:2021/11/26


令和4年4月以降、中小事業主を含む全ての事業主は、パワハラ防止措置を講じる法的義務を負います。
この点、厚労省パワハラ指針(正式名称は「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(令和2年1月15日厚生労働省告示第5号)は既に公表されていますが、これを実務にどう落とし込めば良いかが分からない、という経営者や企業担当者は少なくありません。
そこで、本コラムでは、全3回にわたって、パワハラ指針のうち、企業が講ずべきパワハラ防止措置にスポットを当てて、わかりやすく解説します(無料DL書式例あり)。
1 パワハラ防止措置と本コラムの構成
パワハラ指針では、職場におけるパワーハラスメントの無いよう、雇用管理上講ずべき措置(以下、「パワハラ防止措置」といいます。)につき、次のⅠ〜Ⅳを挙げています。
本コラムではⅠを取り上げます。
なお、事業主がパワハラ防止措置義務を履行していない場合、厚生労働大臣による助言、指導、勧告、(勧告に従わなかった場合に)企業名公表がなされる可能性があります。
パワハラ防止措置と本コラムの構成

2 はじめに:企業がパワハラ問題に取り組む必要性
⑴ ハラスメント撲滅は経営課題であること
関係図

「職場のハラスメントに関する実態調査報告書(概要版)(令和3年3月)」(以下、「実態調査報告書」といいます。)によると、31.4%の労働者が過去3年間にパワハラを一度以上経験したことがあると回答しています。
昨今は、SNS等を通じて容易に発信できますので、社内でパワハラ問題が発生し、これが外部に発信された場合、世間から厳しい批判の目に晒されることは容易に想像できます。
令和における経営者及び企業担当者は、パワハラを含むハラスメントの問題を単なる個人間や社内の問題であると軽視するのではなく、ハラスメント撲滅は経営課題であることを認識する必要があります。
⑵ 企業にも取り組む意義があること
企業の取り組み姿勢としても、「法的義務だから、実施する」というのではなく、この機会を積極的に捉えて、社内のエンゲージメントを高めるチャンスと捉えることが重要です。
例えば、前掲・実態調査報告書には、ハラスメントの予防・解決のための取組を進めたことによる副次的効果として、「職場のコミュニケーションが活性化する/風通しが良くなる」(35.9%)と回答している企業の割合が最も高く、職場の生産性が高まるという回答(13.3%)もあります。
ハラスメント対策への取り組みは、企業の活力を好循環させるメリットがありますので、企業にも取り組む意義があります。
⑶ 職場のハラスメント対策について
職場のハラスメント対策について、既にセクシュアルハラスメントや妊娠・出産・育児休業・介護休業等のハラスメントを防止するための雇用管理上の措置義務が企業に課せられています。
これらの内容は、基本的にはパワハラ防止措置と同内容ですので、ハラスメント対策の問題は、今に始まったことではないことに留意が必要です。
3 パワハラ指針が定める企業が講ずべき措置(テーマⅠ)
⑴ パワハラ指針の内容(Ⅰ事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発)
ア ①パワハラの内容及びパワハラを行ってはならない旨の方針を明確化し、労働者に周知・啓発すること
パワハラ指針によると、①パワハラの内容及びパワハラを行ってはならない旨の方針を明確化し、労働者に周知・啓発することが必要です。
パワハラ指針で、上記①を講じている例として挙げているのは、次の3つです。
a 就業規則等に、パワハラを行ってはならない旨の方針を規定し、内容及びその発生の原因や背景を労働者に周知・啓発すること。
b 社内報等に方針を記載し、配布等すること。
c パワハラ研修、講習等を実施すること。
イ ②行為者については、厳正に対処する旨の方針及び対処の内容を就業規則等に規定し、労働者に周知・啓発すること
パワハラ指針によると、②行為者については、厳正に対処する旨の方針及び対処の内容を就業規則等に規定し、労働者に周知・啓発することが必要です。
パワハラ指針で、上記②を講じている例として挙げているのは、次の2つです。
a 就業規則等に行為者に対する懲戒規定を定め、その内容を労働者に周知・啓発すること
b 行為者は、現行の就業規則等において定められている懲戒規定の適用の対象となる旨を明確化し、これを労働者に周知・啓発すること
⑵ 解説
ア ①について
上記①及び②の企業が講ずべきパワハラ防止措置は、事前の防止策です。
まず、パワハラを行ってはならない旨の方針について、企業のトップが従業員に向けて、メッセージを発することが考えられます(本コラム特典として、無料DL書式例あり<後述参照>)。
トップが直接メッセージを発することにより、仮にハラスメント問題が生じた場合、従業員が、ハラスメント相談窓口への相談を含め、問題点の指摘や発言をしやすい職場環境を作ることができます。
次に、定期的に社内報等に、上記メッセージやハラスメント相談窓口の案内等を掲載することが考えられます。
さらに、パワハラ防止のためには、従業員の理解と協力が重要です。企業によっては、弁護士、社会保険労務士、コンサルタント等を講師として、研修を実施しています。従業員の役職等によって視点が異なるため、研修では、経営層、管理者層、相談窓口担当者、一般従業員層などの階層別に分け、かつ、研修内容も階層別に応じて変えながら行うことが効果的です。
他にも、匿名の社内アンケートにより、ハラスメントの実態を把握することも考えられます。
イ ②について
就業規則等に行為者に対する懲戒規定を整備することが挙げられます。
この点は、次の項目で具体例とともに解説します。

4 実務対応:就業規則の整備
⑴ 就業規則の整備
就業規則の規定例は、次のものが考えられます。
(職場のパワーハラスメントの禁止)
第●条 職務上の地位や人間関係などの職場内の優越的な関係を背景とした、業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により、他の労働者の就業環境を害するようなことをしてはならない。
(懲戒の事由)
第●条 労働者が次のいずれかに該当するときは、情状に応じ、けん責、減給又は出勤停止とする。
① (中略)
② 第●条(職場のパワーハラスメントの禁止)に違反したとき。
③ (中略)
2 労働者が次のいずれかに該当するときは、懲戒解雇とする。ただし、平素の服務態度その他情状によっては、第●条に定める普通解雇、前条に定める減給又は出勤停止とすることがある。
① (中略)
② 第●条(職場のパワーハラスメントの禁止)に違反し、その情状が悪質と認められるとき。
③ (中略)
⑵ 解説
これまで、就業規則の懲戒事由にパワハラ行為が明記されていなかったとしても、懲戒事由に包括条項(例:「その他前各号に準ずる行為があったとき」)が規定されていれば、その他の懲戒事由の規定内容にもよりますが、これらを根拠に懲戒処分を行っているケースもあったと思います。
しかし、パワハラ指針では、上記②aのとおり、行為者に対する懲戒規定を就業規則等に定めることを例として挙げていますので、これを明記した上で、労働者に周知・啓発することに意義があります。
したがって、事前の防止策として、就業規則等の規定内容を整備することが重要です。
なお、企業には、パワハラ防止のための措置義務だけではなく、セクハラ防止のための措置義務(均等法11条)、妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関する防止のための措置義務(均等法11条の3、育児・介護休業法25条)が課せられていますので、これらのハラスメント行為を禁止する規定及びこれらを懲戒事由に定めておくことも必要です。

弁護士
多湖・岩田・田村法律事務所。第一東京弁護士会所属。第一東京弁護士会労働法制委員会(基礎研究部会副部会長)。経営法曹会議会員。使用者側から労働問題を取り扱う。労働法務に関するセミナー講師も務める。
著書に、『詳解 働き方改革関連法』(共著、労働開発研究会、2019年)、『Q&A労働時間・休日・休暇・休業トラブル予防・対応の実務と書式』(共著、新日本法規、2020年)、『新しい働き方に伴う非正規社員の処遇-適法性判断と見直しのチェックポイント-』(共著、新日本法規、2021年)、『改訂版 実用会社規程大全』(共著、日本法令、2022年)、『対応ミスで起こる 人事労務トラブル回避のポイント』(共著、新日本法規、2022年)、「4訂補訂版 標準実用契約書式全書」(共著、日本法令、2024年)、『三訂版 企業労働法実務入門』(共著、日本リーダーズ協会、2024年)。
URL:http://www.tamura-law.com/