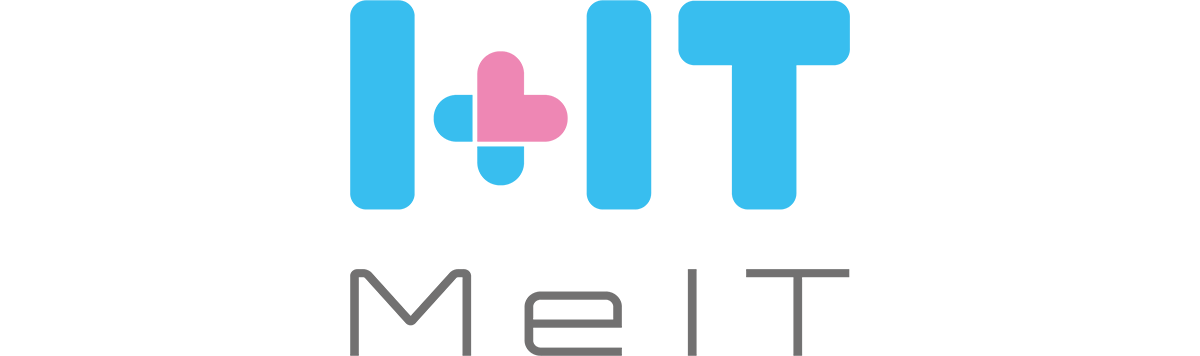第9回健康経営トレーニングクイズ
更新日:2025/07/15


昨今、健康経営が注目されていますがまだまだ知識に不安のある方もいらっしゃるかもしれません。
健康経営についてもっと知りたい人事・総務のご担当者様にお役立ていただけるよう、健康経営にまつわる問題をクイズ形式でご用意しました。
こちらの問題で自分の知識を確認してみましょう。
問1 更年期と職場対応
更年期は閉経前後に起こるホルモンバランスの変動期であり、身体的・精神的な不調が出やすくなります。女性だけでなく、男性にも年齢によるホルモン変化が生じるケースがあり、職場としては適切な理解とサポートが求められます。では、次のうち、更年期の社員に関する職場対応として望ましいものはどれでしょうか?
- 「更年期は個人の問題だから、人事評価には一切影響を与えない」と明言するのみで十分
- 「更年期で体調を崩す人は単なる甘え」と認識し、業務量や勤務時間の変更はしない
- 暑さ寒さへの配慮や休憩室の整備など環境調整を行い、必要に応じて休業や時短勤務なども検討する
問2 デジタル・デトックス
スマートフォンやタブレットなどのデジタル機器を長時間利用することは、視力低下や睡眠障害などの身体的リスクだけでなく、情報過多によるストレス増大や集中力の低下などの精神的リスクも指摘されています。そこで「デジタル・デトックス」が注目され、職場でも導入する企業が増えています。次のうち、このデジタル・デトックスに関する正しい内容はどれでしょうか?
- 一切のデジタル機器を使わせず、連絡はすべて口頭や紙ベースに戻すことが理想的
- 業務中は自由に使わせるが、業務終了後や休日に会社からの連絡は原則禁止にするなど、メリハリを付ける取り組みがデジタル・デトックスの一例
- デジタル機器利用に制限をかけると業務効率が必ず低下するので、デジタル・デトックスは経営にマイナス
問3 神経多様性(Neurodiversity)と職場のインクルージョン
ADHDや自閉スペクトラム症など、いわゆる「発達特性」を持つ人々を含む神経多様性(Neurodiversity)への関心が高まっています。多様な認知特性を排除することなく活かす取り組みが、イノベーション創出や従業員の満足度向上につながるとも言われます。以下のうち、神経多様性への理解を深める取り組みとして適切なのはどれでしょうか?
- 周囲の社員に「特定の発達障害の特性」について研修を行い、必要な配慮や強みの活かし方を学ぶ
- 作業手順やコミュニケーション手段を一律に定め、すべての従業員に同じ対応を求める
- あえて特性を隠すように促し、業務に差が出ないよう配慮する
この記事の執筆者
社会保険労務士法人 未来経営(ESコモンズ メンバー)
長野県松本市に拠点を置き、それぞれ専門分野を持つ5名の社会保険労務士が在籍しています。私たちのビジョンである「元気な会社作りのお手伝い」を実現するため、母体である税理士法人未来経営ともに、人事労務分野に積極的に携わり、トータルな企業経営サポートを実現しています。
ESコモンズ主宰 有限会社人事・労務 URL:https://www.jinji-roumu.com/