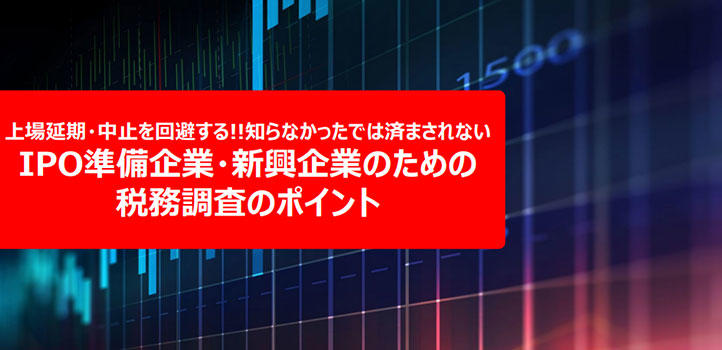失敗しないIPO 第7回「コンプライアンス強化の必要性」
更新日:2020/04/17
失敗しないIPO 第7回「コンプライアンス強化の必要性」


1.法務対応の必要性
前回「第6回.あるべき労務管理」においては労働関連法規を中心にコンプライアンスの重要性を解説しましたが、法治国家である我が国においては、違法行為は倫理に関係なく損害賠償責任その他の責任に問われる可能性があります。一方で法律の条文がおかしいから守らなくても良いという解釈は、法改正が行われない限り違法行為に該当することに変わりはありませんので、いずれにおいても社会性を求められる上場企業において不適格という烙印を押されることとなります。
また、とりわけここ数年IPO申請企業の法令遵守状況について証券取引所は厳しく審査されており、審査の過程で法令違反が発見された場合において、
- 深刻な法令違反の場合
即時に審査手続が中止されて、再開されない場合がある
- 深刻な違反ではない場合
このような場合でも法令違反が解消するまでは、他の審査手続も停止する場合がある
- 法令違反状態が解消された後
解消された後においても「法令遵守体制の整備」を求められ、その体制が適切に運用されるか一定期間を掛けて検証することが求められる
といったように、法令違反は深刻でなくてもIPO準備及びスケジュールに深刻なダメージを与えることとなります。
2020年3月18日付の日本経済新聞において、新型コロナウィルスの蔓延状況に鑑み、東京証券取引所がIPOの基準を緩和する検討に入ったことが報道されていましたが、ご留意頂きたいのは全てにおいて緩和されているということではなく、緩和するのはあくまでも収益性の部分であるということです。今回触れる法令遵守体制をはじめ、健全性、コーポレートガバナンスの状況については緩和の対象とはなっておらず、この部分については従前どおり厳格に審査されると理解しなければなりません。
一方で、IPO準備企業、とりわけベンチャー企業にカテゴライズされる企業においては、法務面・法令遵守体制に関して脆弱である場合が多く、総務部門において法務専従者が在籍していないケースが多くみられます。また、一定の顧問弁護士と顧問契約を締結しているものの、企業法務やその企業の事業の特殊性に精通していないというケースも見受けられます。とりわけ、弁護士の方々は総じて法律の適用や解釈について知見を有している職業ではありますが、上場申請との関係で法律の適用や解釈がどのような意味を持つのかアドバイス出来ている弁護士は限られています。
例えばCEOにおいて利益相反取引が行われようとする場合、
- 取締役会での承認
- 特別利害関係人の取締役会決議からの排除
については弁護士の方々の殆どはアドバイスできるものの、この利益相反取引自体が存在することによる証券取引所における審査上の影響をアドバイス出来る方が限られる、というところです。
IPO準備における法務対応は、適法性の有無に加えてIPO審査における影響までをカバーできる社内体制とこれに精通する弁護士の協力が必要となるのです。
2.IPO準備において留意すべき法律
前回の労働関連法規の他に、IPO準備において特に留意しなければならない法律について説明します。
(1)会社法
株式会社は会社法に基づき設立され、その条文の通りに運用されることが期待されていますが、設立時、M&A、解散などステークホルダーが多く絡む場合を除き、非上場段階では会社法の条文に沿って運営していないケースが多々見られます。例えば以下のケースです。
①取締役会の開催
取締役会設置会社においては、
- 開催する1週間前までに各取締役(監査役設置会社の場合は監査役にも)に招集通知を発送しなければならない(会社法368条1項)
- 代表取締役は3か月に1回以上、自己の職務執行の状況を取締役会に報告しなければならない(会社法363条2項)
という条文が定められているものの、IPOを検討しない段階で上記を遵守している企業は少ないです。
②株主総会の招集
株主総会は公開会社・非公開会社又は取締役会設置会社・非設置会社で期限が異なりますが、いずれの場合においても定められた期限に定められた方法により招集通知を行う必要がありますが、会社法で定められた招集方法に基づかず株主総会を開催しているケースが見受けられます。
これらいずれの場合においても本来は「法律違反」となりますが、IPOを検討しな い段階では、これらに違反することによる会社法上の罰則がなく、この違法状態により損害を被った人が損害賠償を提訴しない限りは問題が顕在化することはありません。しかし、IPOを検討する過程に入ったらこれらを含めて会社法のすべての条項に従った会社運営が求められます。
(2)会社法以外の法律
会社法及び労働基準法以外において、とりわけ昨今留意が必要な法律を以下に列挙します。
①個人情報保護法
個人情報を保有している事業者は、個人情報取扱事業者として個人情報保護法に定める義務が課せられます。これに違反すると是正勧告・命令が下され、企業活動が大きく制限されることとなります。
また、先般個人情報は非常にセンシティブになっていることから、漏洩が発覚してしまうと、社会的な信用問題ともなり損害賠償につながる恐れもあります。特に事業運営上個人情報を多く取り扱っている企業は、IPO審査において個人情報管理の整備・運用状況は重点的に審査されることになります。
予め個人情報管理に関する規程やマニュアルを整備し、個人情報関連の対応部署を定めて運用する、という体制を構築することが望まれます。
②下請代金支払遅延等防止法
一般には下請法と呼ばれるもので、発注者が一方的な都合で下請け業者への支払を不当に減額・遅延することを防止し、取引の公正化を図ることを目的としています。例えば
- 買いたたき
- 下請代金の下請け業者の責によらない減額
- 支払期日の60日を超えての支払
といった場合には、公正取引委員会から違反行為を中止するとともに減額分や遅延利息の支払いなどにより下請け業者が受けた不利益を回復させるよう文書で勧告を受けます。と同時に違反事実や勧告の概要が企業名と併せて公表されます。これは企業としては大きなイメージダウンとなるとともに会計上も損失処理をする状況が増加します。
下請け業者が介在する場合には下請法を熟読の上対応することが必要です。
③不当景品類及び不当表示防止法
一般的には景品表示法と呼ばれており、商品・サービスの品質、内容、価格などの偽った表示を規制することを目的としています。
この景品表示法による規制においてIPO準備において懸案となる可能性がある内容は次の2つです。
- 優良誤認表示
例えば「名古屋コーチン」として売り出していた鶏肉が実はそうではなかったといった、内容が優良であると顧客に誤認させるような場合や、予備校や国家資格受験専門学校で合格率の算定を過度に上昇させて比較上優良の程度が不透明になるような場合が挙げられます。 - 有利誤認表示
「今なら90%オフ」と表示していた商品が実はもともとその価格で販売されていたといったような、消費者が有利であると誤認するような表示を行うことを言います。
以上に違反事実が認められた場合、再発防止措置命令といった行政処分を受けるとともに課徴金が課せられる場合もあります。
また、措置・命令は消費者庁のホームページで公表されることとなっており、日常の営業活動に多大な影響が及びます。
下記リンク先のように具体的に措置・命令が出ておりますので、対岸の火事と思わず、どのようなケースで他社が処分されているかをお時間があるときに参照してみてください。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/release/2019/

株式会社サンライトコンサルティング 代表取締役CEO、公認会計士・税理士。
(株)ミズホメディー(現在東証二部)社外監査役、九州大学大学院非常勤講師。
その他IPO準備中の企業の社外役員、顧問、中小監査法人のパートナーを務める。
主な著書(共著) 会計が分かる事典(日本実業出版社)、7ステップで分かる株式上場マニュアル(中央経済社)
セミナー実績 名古屋・札幌・福岡各証券取引所のIPOセミナーを中心に講演多数
URL:https://www.slctg.co.jp/