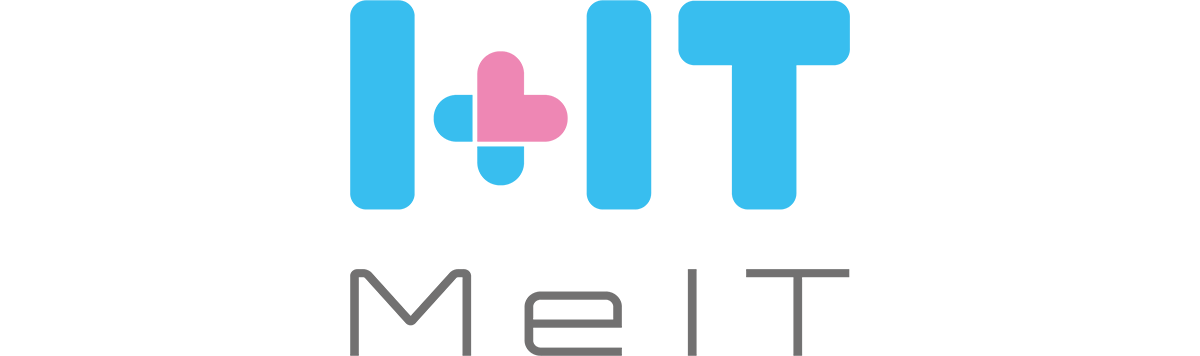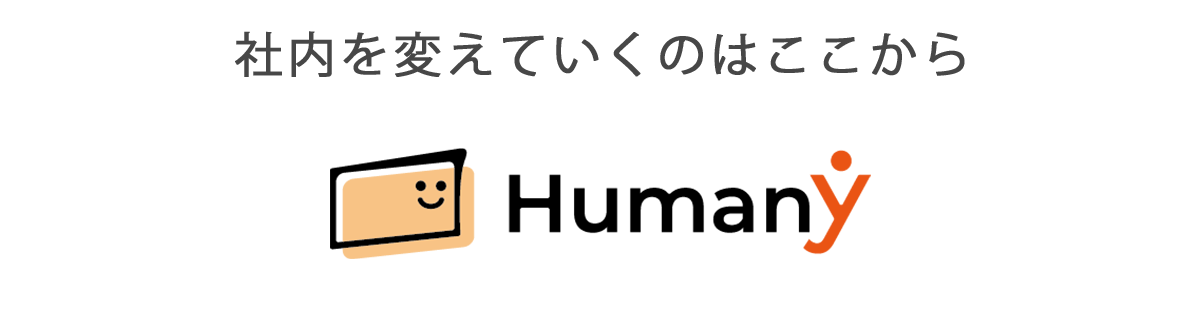第5回 「教育研修」における健康経営の視点と人事労務の要点
企業の健康経営への取り組みに必要な人事労務の知識と実践とは 中小企業が恐れのない職場を目指すための組織開発視点を解説
更新日:2023/07/21


このシリーズのテーマ「恐れのない職場」とは、言い換えると、痛みがなく安心・安全な空気感が高い職場のあり方ということになります。
「痛み」には、身体的・心理的・社会的・スピリチュアル(霊的)側面という四つの側面があると言われています。職場というフィールドに置き換えれば、体調不良気味だけど頑張って職場へ行かねば…という身体的な痛みだけではなく、「これはどうなっているんだろう(聴きたいけど聴きづらい…)」などモヤモヤ感のような心理的痛み、「もっと職場のメンバーとコミュニケーションを取りたい(でも話しかけづらい…)」といったつながりの薄さから来る社会的痛み、が無い・少ない状態を目指していくということです。
今回は、「教育研修」を取り上げて、考えていきます。
今、教育のあり方が模索されている
国が、リスキリングやリカレント教育に注力する方針を打ち出したことを受け、新たな教育体系の構築に着手している企業も多いのではないでしょうか。
「ひとは、社会に出てからも生涯成長・変容し続けることができる」というのは、成人発達理論で言われていることですが、生涯の多くの時間を過ごす「職場」でいかなる学びを得て自己を成長させていくか、一人ひとりが主体的に考え”選択”していけるような人事システムを考えていくことが重要です。
その人事システムの一つである教育体系に関しても、どのような種類の場を設けるのか、どのように実施するのか(リアル/オンライン等)、などこの時代の変化を捉えて見直していく必要があると思います。それは、個々の探求心や創造性を育み、人間性が花開く組織の土壌をつくるために、主体的に学べる環境を整えることでもあります。
いま教育界でも、主体性の重視等、子どもたちの新しい学びのあり方が模索されています。変化の激しい時代において「生きる力」を育むことを軸に、アクティブ・ラーニングや探求学習等によって”自ら考え対話しながら学んでいくこと”を大切にしているのです。新しい学習指導要領のもとで授業を実施している先生は、インタビューで「子供たちのおもいを引き出すことを大切にするが、それを誘導しないようにする。そして、そのおもいを引き出す質問に集中するようにしている。」と述べていました。
これまでの学校のように「こたえを持っている先生から一方的に学び理解する」スタイルではなく、先生や仲間とのコミュニケーションの中で主体的に考えこたえを導き出す過程から知識・技術だけではないしなやかに生きる力を育んでいくのが、学校という場になるわけです。そうなると、当然、そこでの「先生」の役割も、「一方的に教える」ことから「学び合いを促進するファシリテーター」へと変化してゆきます。
職場の学び方も変化していく必要がある
そして、そのような学びを得て成長してきた子ども・若者たちが社会へ出た時に、職場が”従来の学びのかたち”を重視した状態だと、必ずひずみが生じると言えます。例えば、上司は「リーダー・上司がこたえを持っていて、その指示・指導のもとで物事を動かしていく」というスタイルだけれども、新入社員の方は「学び合い」のスタイルが当たり前、と思っているケース。これだと、上司から伝えられたことに対して新入社員が何か自分の考えを伝えたり問い(質問)を返してばかりだと、「この部下は素直に指示通りに動かないから、やりづらいなあ」という印象を抱くかもしれません。あるいは新入社員としては、「伝えられた指示をこなすばかりで、何だか機械みたいだなあ」と感じ、業務の意義を見出だせずにやる気が低下するかもしれません。
「社会構造が変わると、教育が変わり、職場も変わる」。これはデジタルファシリテーターの田原真人さんの言葉ですが、まずは今の社会を生きるわたしたちが、社会の変化を捉え、今ある意識構造(正解重視、学びは先生から得るもの、等)を自己認識し、これからの未来を見据えた学びのかたちを職場に創り出していくことが重要であると言えます。
上司・部下間などで認識の違いが生じても、単に「世代の感覚の違い」で片付けるのではなく、それぞれにどんな世界観や「当たり前」がまとわりついているのか、対話をしながら丁寧に認識を深めていくことが大切なのです。
そのために、まずは経営者やリーダー、人事担当者が、ファシリテーター的な役割で職場の土壌を耕していくことです。「ファシリテート=促す」だけではなく、「介入」したり全体を「俯瞰」したり各所を「調整」したりするファシリテーターです。管理部門も、社長・リーダーも、いかにファシリテーター的なリーダーシップを発揮し、職場で生じる課題を見極め、解決のための働きかけを担えるか、という点が重要なのです。
そこには、「これを自分が担うんだ」「自分は愛着もってこのことに取り組むんだ」という使命感(ミッション)が必要になりますし、虫の目・鳥の目の両面をもったメタ認知力も重要でしょう。もちろん、会議や面談の進めかたなどファシリテーション技術も必要です。お互いの得意・苦手を認識し受け入れて他者との連携をはかるコラボレーション力も重要です。
このようなファシリテーター的リーダーシップを身に付けられるような学びの機会を、座学ではなく体感の場も含めて組み立てていくことが重要であると言えます。これは、議論して一度固めたら運用し続けられるシステムではないと思います。組織は機械ではなく「生き物」だからです。
身体知の習得も含めた新たな体感型の教育体系を構築し、まずは実践をしながら、対話してふりかえり・内省の時間を設ける。組織の状態の変化や個々の社員の成長度合いに応じて、フレキシブルに見直しをしていくことも重要であると言えます。
まとめ
コミュニケーションの問題、と一言で捉えがちな事象−、例えば「自分が大切におもうことが相手に伝わらない」「周りと異なっていることが受け入れられない」など表には見えづらい痛みの存在にまずは焦点をあて、自社の働き方や職場環境のあり方を再考する機会として、教育研修の場を活かしていくと良いでしょう。

有限会社人事・労務 ヘッドESコンサルタント。
厚生労働省認定CDA(キャリアデベロップメント・アドバイザー)。
一般社団法人 日本ES開発協会 代表理事。
福島大学行政社会学部卒業後、有限会社人事・労務にて、日本初のES(人間性尊重経営)コンサルタントとして、企業をはじめ、大学、商工団体で講師を務めるなど幅広く活動する。“会社と社員の懸け橋”という信念のもと、介護事業所や福祉施設、製造業、サービス業などさまざまな中小企業でのクレドづくり・ES組織開発に取り組む。また、「日本の未来の“はたらくカタチ”をつくる」をテーマに、社員一人ひとりが地域社会との接点を持ち共感資本を高めるための活動を推進。自律心高い越境人材の育成や地域活動プロジェクトの運営などに力を入れ、ESを軸にコミュニティ経営の視点を中小企業で実践し、高い評価を得る。
宮城県仙台市生まれ。「東北の土地の記憶を知ること」「働く犬の研究」がライフワーク。
【主な講演実績・著書等】
・社会によろこばれる会社のためのESを軸とした組織づくり (熊谷法人会、上尾法人会)
・キャリアデザイン入門 (日本大学法学部)
・シゴト選びのモノサシを変える!新しい一歩を踏み出すキャリアデザイン講座(東北芸術工科大学)
・『人財経営実践塾』愛社精神溢れる-体感経営~ES(従業員満足度)が会社を伸ばす~ (ふくいジョブカフェ)
・対話の習慣を軸とした自律型人材育成法/ESを軸につながりを大切にする経営/新任管理職の為のリーダーシップ強化セミナー(ヒューマンリソシア「定額制公開講座ビジネスコース」)
・イノベーションを巻き起こすES向上型人事制度 (ピーシーエー株式会社)
・千葉県指定工場協議会 第三ブロック向けセミナー~今日からすぐに始められる会社が元気になる7つの施策 (あいおいニッセイ同和損害保険株式会社)
・後継者向けESマネジメント研修 (あいおいニッセイ同和損害保険株式会社)
・人と環境と社会にやさしい社内体制の作り方セミナー~グレートスモールカンパニーが社会を変える!~ (日本ES開発協会)
・若手社員の採用と定着を上手に行う秘訣 (常陽産業研究所)
・ES型人事制度構築のポイント (淡路青年会議所)
・「共感資本時代のリーダーはここが違う」(株式会社USEN)・・・他
・『ニュートップリーダー』「はたらく個も、組織も輝く経営」(日本実業出版社)
・2013年7月号:「独自に定めた「旅籠三輪書」を軸に地域のつながりを重視した変革に挑む-HATAGO井仙」
・2013年8月号:「本業を通した社会貢献」を掲げ、地域のつながりの基点となる-株式会社大川印刷」
・「人材アセスメントの時代」連載 (フジサンケイビジネスアイ)
・『ESクレドを使った組織改革』(税務経理協会)
・「従業員のモチベーションアップに役立つ社内コミュニケーション」(日本経団連事業サービス)
・『ESコーチング&ESマネジメント 感動倍増組織のつくり方』(九天社)
・『儲けを生み出す人事制度7つの仕組み』(ナナブックス)
・『社員がよろこぶ会社のルール・規定集101』(かんき出版)
・『今から間に合う! 小さな会社の働き方改革対応版 就業規則が自分でできる本』(ソシム)1
・「人事労務のいろは」連載(東商新聞)
・『労務事情』「人事労務相談室」連載(株式会社産労総合研究所)
・『月刊総務』(株式会社ナナ・コーポレート・コミュニケーション)
・『ニュートップリーダー』「ES経営が会社を伸ばす」(日本実業出版社)
2010年2月号:「社員がここにいたいと思う会社にする-株式会社アドバネクス」
2009年12月号:「患者の立場に立ってよりよい病院づくりをしたい-医療法人井上整形外科」
2009年11月号:「印税を通して地域や社会に貢献したい-株式会社大川印刷」
・就活支援ジャーナル
2014年10月15日「秋の内定をこうして勝ち取る!!」「企業人の視点 地域密着を果たし、社会を良くする企業に出合おう!」