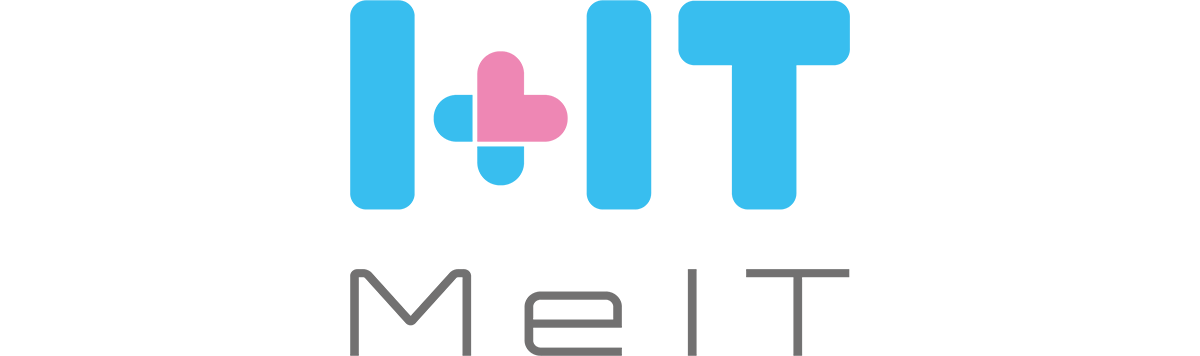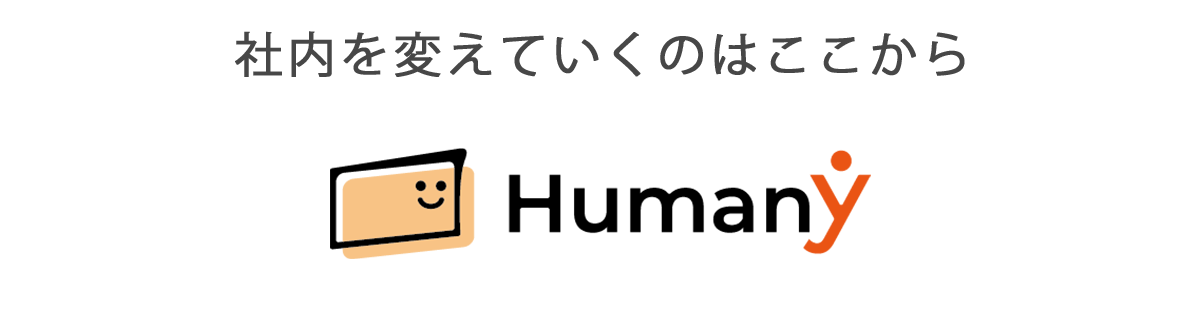第3回 「採用」における健康経営の視点と人事労務の要点
企業の健康経営への取り組みに必要な人事労務の知識と実践とは 中小企業が恐れのない職場を目指すための組織開発視点を解説
更新日:2022/11/22


このシリーズのテーマ「恐れのない職場」とは、言い換えると、痛みがなく心理的安全性が高い職場のあり方ということになります。「痛み」には、身体的・心理的・社会的・スピリチュアル(霊的)側面という四つの側面があると言われています。職場というフィールドに置き換えれば、「これはどうなっているんだろう(聴きたいけど聴きづらい…)」などのモヤモヤ感のような心理的痛み、「もっと職場のメンバーとコミュニケーションを取りたいけれども話しづらい」などのつながり意識の無さから来る社会的痛み、が無い状態で、エンゲージメント高く心身健やかに働いていくために、採用時においても健康経営の視点をおさえた取り組みが重要であると言えます。
近年、政府主導で取り組まれている「健康経営」とは、従業員の健康管理を経営的な課題と捉え、戦略的に取り組む手法のことを指します。健康経営を導入し、従業員がよりよい状態でパフォーマンスを上げていくことができれば、労働生産性の向上や離職率の低下にもつながるというものです。入社後の従業員の健康管理も健康経営の一つです。また採用活動を通して、新入社員の健康状態について知ることができれば、入社後の従業員の健康維持もスムーズに進めることができます。
そこで今回は、「健康経営」につながる面接における要点や、労働安全衛生法に基づく健康管理など企業が守るべきポイントについて解説していきます。
面接で法的に禁止されている質問とは?
面接では応募者の特性などを知るための能力・適正に関する質問を行います。応募者への質問の中に、健康面に関する要素を盛り込むことができれば事前に健康状態を把握することができます。
しかし面接では社会的差別につながるような質問は法的に禁止されています。
具体的には以下のような、基本的人権の尊重に関わる事項です。
<本人に責任のない事項の把握>
- 本籍・出生地に関すること (注:「戸籍謄(抄)本」や本籍が記載された「住民票(写し)」を提出させることはこれに該当します)
- 家族に関すること(職業、続柄、健康、病歴、地位、学歴、収入、資産など)(注:家族の仕事の有無・職種・勤務先などや家族構成はこれに該当します)
- 住宅状況に関すること(間取り、部屋数、住宅の種類、近郊の施設など)
- 生活環境・家庭環境などに関すること
<本来自由であるべき事項(思想信条にかかわること)の把握>
- 宗教に関すること
- 支持政党に関すること
- 人生観、生活信条に関すること
- 尊敬する人物に関すること
- 思想に関すること
- 労働組合に関する情報(加入状況や活動歴など)、学生運動など社会運動に関すること
- 購読新聞・雑誌・愛読書などに関すること
<採用選考の方法>
- 身元調査などの実施 (注:「現住所の略図」は生活環境などを把握したり身元調査につながる可能性があります)
- 合理的・客観的に必要性が認められない採用選考時の健康診断の実施
採用面接における質問の禁止事項には「応募者の過去の病歴や健康状態(既往歴)」は、明記されていないことが分かります。
しかし応募者の健康状態(既往歴)について、面接で質問をすることや採用合否の基準として用いることが一般的に許容されるのは「業務に必要な範囲に限定する」場合に限ります。
業務遂行可否や業務遂行上のリスクを把握するために必要と判断される場合に限り、健康状態(既往歴)についての質問をすることができます。具体的には仕事で機械操縦や自動車運転などを行う場合が該当します。
健康面での理解を図るための面接のポイントとは?
健康状態(既往歴)についての質問が業務上必要だと判断されない場合には、どのような質問であれば応募者の健康状態を知ることが出来るでしょうか。
- 趣味に関すること
- 休日の過ごし方
上記のような質問であれば、応募者のライフスタイルを知るヒントになります。
趣味として活動していることを知り、休みの日の過ごし方を知ることで、オンオフの切り替え方が分かります。
具体的な健康状態(既往歴)について質問することはできませんが、応募者自身の心身の健康に関するセルフケアの方法への理解が進みます。
採用基準として用いるのではなく、入社後の働き方をケアする目的で質問をするようにしましょう。
また採用者も自社の働き方含めた文化を面接時に正直に伝えていくことで、応募者が実際に業務を遂行できそうかの判断ができるように促すことも大切になります。
入社後に企業が行うべき健康診断とは?
採用面接時には健康状態に関する質問を業務上に関係なく行うことはできません。しかし入社後には企業・事業者は労働安全衛生法に基づき、労働者への「安全配慮義務」が課せられます。雇入れ時の健康診断を行うことが、事業者の講ずべき措置となります。
雇入時の健康診断とは、文字通り、労働者を雇い入れる際に行う健康診断のことで「常時使用する労働者」が対象です。
雇入時の健康診断の項目
- 既往歴及び業務歴の調査
- 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
- 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
- 胸部エックス線検査
- 血圧の測定
- 貧血検査(血色素量及び赤血球数)
- 肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP)
- 血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、血清トリグリセライド)
- 血糖検査
- 尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)
- 心電図検査
労働安全衛生規則第43条で定められた以下の11項目について、健康診断を行います。
また1年以内に1回、定期的に行う健康診断や「特定業務従事者」への健康診断も事業者の措置義務となります。「危険を伴う作業に従事する労働者」や「深夜労働をしている労働者」が、特定業務従事者に該当します。
雇入れ時に健康状態を知り、定期的な健康診断を行うことで従業員の健康維持につなげていくことができます。
そして労働安全衛生法では「ストレスチェックの実施」も50人以上の労働者のいる企業に義務化されています。メンタルヘルスの不調を未然に防止することを目的としています。
ストレスチェックや健康診断を上手に活用して、持続的な健康維持につなげていけるようにしましょう。組織の中に健康経営を推進する部署やチームを作ることで、具体的な取り組みを進めやすくなります。
まとめ
今回は採用と健康経営をテーマに、採用時から採用後の従業員の健康管理に関するポイントをご紹介しました。
「健康経営」と一言でいっても、取り組むことの出来ることが多岐にわたり何から始めるべきか迷いますよね。まずは採用という組織へ入る第一プロセスで、従業員の健康へ配慮したアプローチが出来ることで、長期的なスパンでの従業員の健康維持につなげることができます。
「健康経営」の目的は健全性のある組織づくりを行うことです。従業員一人ひとりの良い状態を保つことは、組織全体のパフォーマンスを上げるだけでなく、企業のイメージもアップしていきます。企業イメージがプラスになることは、採用活動にも良い作用をもたらし、好循環で「健康経営」を進めていくことができるでしょう。

ESコモンズ(有限会社人事・労務主宰) メンバー
明治大学経営学部卒業後アパレル会社を経て、組織づくりの根幹を支える仕事に携わるた め有限会社人事・労務へ入社。入社後は100名~500名ほどの会社の給与計算・社会保険 手続き・就業規則の整備の業務を中心に組織づくりを支援。現在は「人を軸にした組織づくり」を大切に、フリーランスとして企業の人事・組織デザインに携わる。
WEBサイト:https://www.jinji-roumu.com/