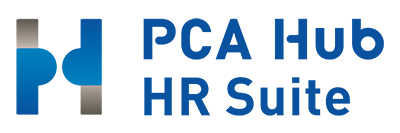病気の療養と就労の両立支援について
更新日:2020/11/27
病気の療養と就労の両立支援について


医療技術が発展し、病気と長く付き合いながら生きていく時代になりました。
2016年2月には、「事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン(厚生労働省)」が発表されました。これは、治療を必要とする従業員の就労継続による病状悪化を回避し、企業も適切な措置によって治療に対する配慮を行おう、という動きに関して参考としてまとめられたものです。更に同年9月には、働き方改革実現会議で、「病気の治療、子育てや介護と仕事の両立」の検討が表明され、その後、「働き方改革実行計画」の中で「病気の治療と仕事の両立」が掲げられました。
今回から二回にわたりこの療養と就労の両立支援について取り上げ、これからの持続的な暮らし方・働き方について考えていきたいと思います。
「びっくり離職」を増やさないために
「働き方改革実行計画」の中で掲げられた方針は、以下の三点です。
- 会社の意識改革と受入れ態勢の整備(経営陣・リーダー層の意識改革、柔軟な働き方に関する制度整備等)
- トライアングル型支援などの推進(主治医・会社・両立支援コーディネーターによる三者のサポート体制、マニュアル等の普及)
- 産業医・産業保健機能の強化
例えば現在、仕事をしながらがん治療をする人は約36万5千人にのぼると言います。
昨年実施された調査(内閣府)では、「がん治療や検査のために二週間に一度程度病院に通う必要がある場合、働き続けられる環境だと思いますか」という質問に対して、「そう思う」「どちらかと言えばそう思う」と答えた割合は、37.1%で、以前と比較して徐々に増えて来ました。
でも一方で、「びっくり離職」という言葉も出ていると言います。
がんの疑いとの説明を受けた時点でどんな治療を受けるのか分からない状況の中で離職を決めてしまう、というものです。最も多い理由は、「周囲に迷惑をかけたくない」「体力的に続ける自信がなくなった」の二点。がんであると確定した後の離職においても「周囲に迷惑をかけたくない」が多く、企業としてもさまざまなサポートが必要であることがうかがえます。
両立支援においてキモになるのが「企業側と医療機関側との連携」
ガイドラインが示す「両立支援を行なうための環境整備」には、以下の点が挙げられています。
- 事業者による基本方針等の表明と労働者への周知
- 研修等による両立支援に関する意識啓発
- 相談窓口の明確化等
- 休暇・勤務制度の整備=時間単位の年次有給休暇、傷病休暇・病気休暇などの休暇制度、短時間勤務制度、テレワーク、時差出勤制度、試し出勤制度などの勤務制度
治療を受ける患者さんが働き続ける上で大切なサポートとして、「企業側と医療機関との情報共有」があると言います。
企業としては、当事者である社員がどのような仕事ができ、周りは何に気を付ければ良いのかが分からない。医療機関としては患者さんがそれまでどんな仕事をしているのか具体的なところが見えない。そこにある隔たりを越えて情報交換を行なうことで、主治医からは必要な配慮を伝えることができ、企業側も、それを受けて、具体的な業務内容を考えたり、治療・通院のための配慮を決めたりすることができるわけです。
両立支援の進めかた
病気の療養と就労の両立支援の検討は、従業員の申し出から始まります。
- 本人の申出
まずは本人が支援を求める申し出がしやすい環境を整えることが重要です。 - 特徴を踏まえた対応
対象者は、入院、通院、療養のための時間の確保が必要になるだけでなく、病気の症状や治療の副作用・障害等によって、従業員自身の業務遂行能力が一時的に低下する場合もあります。
そのため、時間的制約に対する配慮だけでなく、本人の健康状態や業務遂行能力も踏まえた就業上の措置が必要です。 - 対象者・対応方法の明確化
会社として基本方針を定め、明文化および周知しておくことが重要です。同一労働同一賃金の観点から、ガイドラインは非正規労働者を除外するものではない、という点もおさえておきましょう。
- 個人情報の保護
両立支援には、症状・治療の状況等の疾病に関する情報が必要です。これらは本人の同意なく取得できません(労働安全衛生法に基づく健康診断において把握した場合を除く)。
※2019年4月に施行された改正労働安全衛生法では「健康情報取扱規定」を定めることが義務付けられ、同意取得の手続きが明確に。
- 両立支援にかかわる関係者間の連携
企業における関係者(経営者、人事担当者、上司・同僚、社会保険労務士、産業保健スタッフ等)、医療関係者(主治医、看護師、医療ソーシャルワーカー等)、地域関係者(産業保健総合支援センター、治療就労両立支援センター、保健師、社会福祉士等)、さらには労働者の家族など、関係者は多岐にわたります。
両立支援を行うための環境整備
以上の点を踏まえ、「両立支援の環境整備」を進めていきます。
それにあたり、まずは他社の事例なども集めながら、具体的にどのような対応を進めているのか把握し、自社としての方針を定めることが必要でしょう。
①経営者による基本方針等の表明と従業員への周知
:衛生委員会や特別プロジェクトなどの社内協議の場を活用します。
②研修等による両立支援に関する意識啓発
:誰もが当事者になり得るわけなので、管理職を含めた全員を対象に実施することが重要です。
③相談窓口の明確化
:実際に窓口へ相談が行われた場合の情報の取り扱い(誰が把握しどこで協議・判断するのか等)を明確にします。
④両立支援に関する制度・体制の整備
ア 休暇制度、勤務制度の整備:時間単位の年次有給休暇、傷病休暇・病気休暇、時差出勤制度、短時間勤務制度、在宅勤務(テレワーク)、試し出勤制度* など
イ 従業員から支援を求める申出があった場合の対応手順、関係者の役割の整理
ウ 関係者(会社、主治医など)間の円滑な情報共有のための仕組みづくり
エ 両立支援に関する制度や体制の実効性の確保★
オ 労使等の協力体制
*会社が自主的に設ける勤務制度。長期間休業していた社員が円滑に復職できるように支援するもので、勤務時間や日数を短縮して対応する。
管理職に対して、相談・申し出を受けた場合の対応方法や支援体制について研修を行なうなど
実際に病気があって心配事を抱えながら働いている社員が社内に既にいるかもしれません。
自社の方針を示し、面談等の対話の機会をつくることで、そのような心配事を共有しても良いという安心・安全な空気感を醸成することができるでしょう。
助成金制度の活用も
「治療と職業生活の両立支援」については、従業員が「持続的に働いていく」ことを目的として、障害や傷病の特性に応じた治療との両立のための施策等を整備した企業に対して、助成金制度も活用できます。
【環境整備助成】
両立支援制度を導入し、かつ、両立支援に関する専門人材を社内に配置した事業主に対して助成。
■支給対象措置
以下の2つを行った場合が支給対象となる。
- 両立支援制度(※)の導入
- 専門人材(企業在籍型職場適応援助者又は両立支援コーディネーター)の配置
■助成額
- 企業在籍型職場適応援助者を配置した場合 30万円
- 両立支援コーディネーターを配置した場合 20万円
【制度活用助成】
両立支援コーディネーターを活用し、両立支援制度を労働者に適用した事業主に対して助成
■支給対象措置
以下の2つを行った場合が支給対象となる。
- 両立支援コーディネーターの活用
- 両立支援制度(※)の労働者への適用
■助成額
- 対象労働者が有期契約の場合 20万円
- 対象労働者の雇用期間に定めのない場合 20万円
※ 両立支援制度の例:通院等に配慮した休暇制度、障害や傷病特性に配慮した短時間勤務制度、身体の負担に配慮した時差出勤制度など
※両立支援コーディネーター:独立行政法人労働者健康安全機構における養成研修を修了し認定を受けた人。企業の人事労務担当者、医療機関の医療従事者など。
医療機関のソーシャルワーカー等と連携し社会福祉面の情報を把握することで、より幅広い観点から「持続的な働き方」を検討することもできます。次号はそのあたりをご紹介したいと思います。
両立支援の方針を掲げることは、職場の心理的安全性を高めることにもつながる
中小企業における“治療と仕事の両立支援”の取り組みの多くに共通しているのが、「自社の社員が突然の病に倒れたことがきっかけで急遽制度をつくり、その後さらに整備を進めた」という点です。身近なところで起きたショックな出来事から自分ごと感が高まり、現場の声を聴きながら制度を整えていくというケース。
その制度整備もあって受診した健診で病気が判明し、自身も制度利用となったケース。自己の体験を踏まえて健診の大切さを皆に伝えているケース。他人事から自分事へと切り替わるできごとがあって教訓となり、その後の全社を挙げた対策へとつながっているのです。
今は「健康経営」という考え方もあります。両立支援のガイドラインにのっとった制度整備に取り組むことで「万が一のことがあっても働き続けることができる職場」という示しができ、社員の心理的安全性を高めることで、組織の生産性にも寄与すると言えます。

有限会社人事・労務 ヘッドESコンサルタント。
厚生労働省認定CDA(キャリアデベロップメント・アドバイザー)。
一般社団法人 日本ES開発協会 代表理事。
福島大学行政社会学部卒業後、有限会社人事・労務にて、日本初のES(人間性尊重経営)コンサルタントとして、企業をはじめ、大学、商工団体で講師を務めるなど幅広く活動する。“会社と社員の懸け橋”という信念のもと、介護事業所や福祉施設、製造業、サービス業などさまざまな中小企業でのクレドづくり・ES組織開発に取り組む。また、「日本の未来の“はたらくカタチ”をつくる」をテーマに、社員一人ひとりが地域社会との接点を持ち共感資本を高めるための活動を推進。自律心高い越境人材の育成や地域活動プロジェクトの運営などに力を入れ、ESを軸にコミュニティ経営の視点を中小企業で実践し、高い評価を得る。
宮城県仙台市生まれ。「東北の土地の記憶を知ること」「働く犬の研究」がライフワーク。
【主な講演実績・著書等】
・社会によろこばれる会社のためのESを軸とした組織づくり (熊谷法人会、上尾法人会)
・キャリアデザイン入門 (日本大学法学部)
・シゴト選びのモノサシを変える!新しい一歩を踏み出すキャリアデザイン講座(東北芸術工科大学)
・『人財経営実践塾』愛社精神溢れる-体感経営~ES(従業員満足度)が会社を伸ばす~ (ふくいジョブカフェ)
・対話の習慣を軸とした自律型人材育成法/ESを軸につながりを大切にする経営/新任管理職の為のリーダーシップ強化セミナー(ヒューマンリソシア「定額制公開講座ビジネスコース」)
・イノベーションを巻き起こすES向上型人事制度 (ピーシーエー株式会社)
・千葉県指定工場協議会 第三ブロック向けセミナー~今日からすぐに始められる会社が元気になる7つの施策 (あいおいニッセイ同和損害保険株式会社)
・後継者向けESマネジメント研修 (あいおいニッセイ同和損害保険株式会社)
・人と環境と社会にやさしい社内体制の作り方セミナー~グレートスモールカンパニーが社会を変える!~ (日本ES開発協会)
・若手社員の採用と定着を上手に行う秘訣 (常陽産業研究所)
・ES型人事制度構築のポイント (淡路青年会議所)
・「共感資本時代のリーダーはここが違う」(株式会社USEN)・・・他
・『ニュートップリーダー』「はたらく個も、組織も輝く経営」(日本実業出版社)
・2013年7月号:「独自に定めた「旅籠三輪書」を軸に地域のつながりを重視した変革に挑む-HATAGO井仙」
・2013年8月号:「本業を通した社会貢献」を掲げ、地域のつながりの基点となる-株式会社大川印刷」
・「人材アセスメントの時代」連載 (フジサンケイビジネスアイ)
・『ESクレドを使った組織改革』(税務経理協会)
・「従業員のモチベーションアップに役立つ社内コミュニケーション」(日本経団連事業サービス)
・『ESコーチング&ESマネジメント 感動倍増組織のつくり方』(九天社)
・『儲けを生み出す人事制度7つの仕組み』(ナナブックス)
・『社員がよろこぶ会社のルール・規定集101』(かんき出版)
・『今から間に合う! 小さな会社の働き方改革対応版 就業規則が自分でできる本』(ソシム)1
・「人事労務のいろは」連載(東商新聞)
・『労務事情』「人事労務相談室」連載(株式会社産労総合研究所)
・『月刊総務』(株式会社ナナ・コーポレート・コミュニケーション)
・『ニュートップリーダー』「ES経営が会社を伸ばす」(日本実業出版社)
2010年2月号:「社員がここにいたいと思う会社にする-株式会社アドバネクス」
2009年12月号:「患者の立場に立ってよりよい病院づくりをしたい-医療法人井上整形外科」
2009年11月号:「印税を通して地域や社会に貢献したい-株式会社大川印刷」
・就活支援ジャーナル
2014年10月15日「秋の内定をこうして勝ち取る!!」「企業人の視点 地域密着を果たし、社会を良くする企業に出合おう!」