第10回 人的資本経営にAIを活用する
更新日:2022/11/29
AIやITで、経理は本当になくなるのか?~共存する人とAIとIT~第10回 人的資本経営にAIを活用する
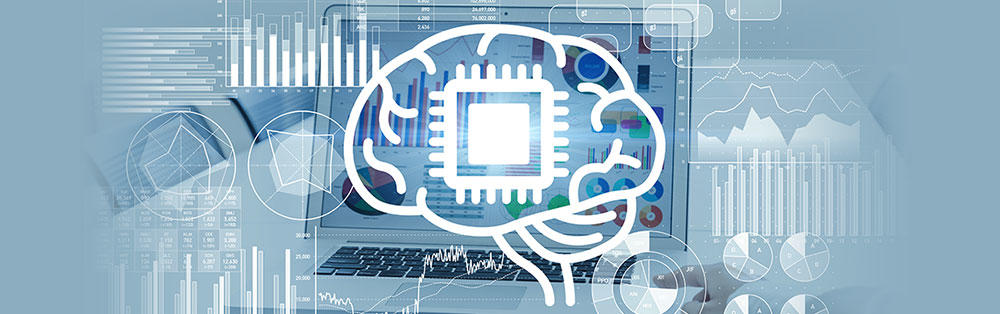
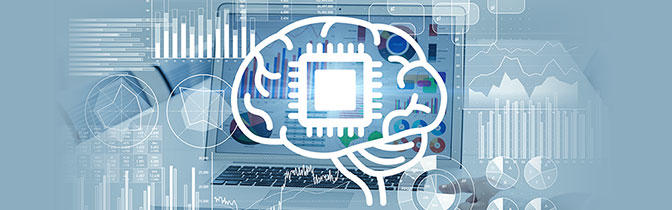
人的資本経営とは
2022年5月に経済産業省より「人材版伊藤レポート2.0」が発表されました。これは一橋大学の伊藤邦雄先生が座長となり、人的資本経営(人材を「資本」と捉え、その価値を最大限に引き出すことで、中長期的な企業価値向上につなげる経営のあり方)の実現に向けて検討した内容をまとめた報告書です。その中で私が特に印象に残ったのは「経営戦略と人材戦略を連動させるための取組」の重要性について述べられている点です。伊藤先生は経理の読者の皆さんならピンと来る人もいるかもしれませんが、『現代会計入門』など会計学に精通された先生です。つまり経営戦略と人材戦略を「連動」させる具体的なものの一つに「数字」があると私は理解しました。その「数字」を取りまとめることができるのは、もちろん経理部です。これからデジタル化が進み、経理部門がDX化した後、私は人的資本経営への参画が経理部のDX化後の仕事として有益ではないかと考えています。
人材を「資本」ととらえるというのは、人材を「投資の対象」とみなすということです。給与だけでなく、福利厚生や職場環境など、働く人材を取り巻く状況をよりよくすることで、それが結果的により多くの売上や利益を生みだすということです。
少し難しくなりましたが、身近な例を考えてみましょう。
たとえば会社の福利厚生といえば、伝統的なものでは社員旅行や保養施設の割引など、そして近年では職場でお菓子や飲み物などを無償提供したり、在宅勤務の環境をよりよくする手当の支給をしたり、働く環境がよくなる、社員満足度が上がる制度を実施している会社もあります。
社員満足度と売上・利益の相関性
ただ、私は以前から、福利厚生制度というものが、実際にどれくらい会社の売上や利益に寄与しているのか、それともしていないのか、データとして測定できたら面白いのになあ、と思っていました。というのも、「社員満足度が上がると、売上・利益も必ず上がる」とは限らないからです。
私はベンチャー企業を多く見てきているのですが、社員に優しすぎる福利厚生があるベンチャー企業というのは、その多くが途中で経営が立ちいかなくなることがあります。それは社員に対して「優しい」を通り越して「甘やかし」になってしまっているからだと思います。社員満足度はMAX上がっているのですが、それが悪い方向に転じて「怠惰、堕落」につながり、業績も下降線になっていきます。
一方で、福利厚生が全くない会社も、経営者が社員に対して「ヒト」ではなく「モノ」のようにとらえている傾向もあるため、総じて社員満足度が低く、人が定着せず、人材不足によって事業が立ちいかなくなることがあります。このように考えると、福利厚生は「ちょうどいい塩梅」があるはずで、それも会社ごとに、全て塩梅のレベルが違うのではないかと私は思います。
もしそれが、AIなどによって試算表分析をして、福利厚生の費用額が売上に対して何%、〇〇費に対して何%の時が、一番売上や利益がいいか、といった、私たちが想像つかない範囲の分析までしてくれると、とても興味深い結果が出てくる楽しみもあるかなと思います。
福利厚生費と離職率の相関性
先日、ある会社の社長さんと、社員の定着率を上げるためにはどのような費用の配分をしたらいいだろうかという話になりました。たとえば人件費の予算が月額一人30万円あるとしたら、給与30万円で福利厚生なしがいいのか、給与29万で福利厚生1万円がいいのか、給与28万円で福利厚生2万円がいいのか、それによっても定着率が変わってくるかもしれませんね、と話をしていました。
社員にとっては、現金をより多くもらえたほうがいいかもしれませんが、月給が1万円増えた時は「やったー!」という人もいるでしょうが、「ふーん、増えたんだ」というくらいの感想の人もかなりいると思います。それであれば、1万円の昇給を5000円に留めて、残りの5000円は「1か月に5000円までなら、リフレッシュのための費用として使っていい」という制度にしたほうが、周囲からも「いい会社だね」と言われるでしょうし、その人が転職を考えた時に、転職先に福利厚生が全くない会社だとわかった際、「確かに給料は今よりちょっといいけど、福利厚生が全くないってことは社員には冷たい会社かもしれないな。それに比べたらうちの会社は社員に親切な福利厚生制度がたくさんあるから、やっぱりここで働き続けたほうが自分にとってはいいのかな」と思うかもしれません。
福利厚生費をいくらかけた時が、離職率が一番低かったのか、また、人件費に対して何パーセントの福利厚生費をかけたときに離職率が低いのか、など、手計算でもできなくはないですが、AIなどで設定をしておけば一瞬のうちに結果が出ますから、そのようにして、試算表とさまざまな人事施策とをAIで結び付けて分析をし、それを経営戦略に活かす、そのような活用がAIにはとても有効ではないかと思います。
DX化後に経理の存在価値を示すには
経理のデジタル化が進みDX化された後、経理部門はこのような事例のように、AIなどのデジタルツールを活用して、自分達の得意な数字と人事施策に関する数字との相関性を分析するなどして人的資本経営に参画していくのが経理部門の新たな存在価値を示す一つの方法ではないかと思います。

流創株式会社代表取締役
エイベックスなど数社で管理業務全般に従事し、サニーサイドアップでは経理部長として株式上場を達成。その後中国・深センでの駐在業務の後、独立。現在は利益改善、コンプライアンス改善、社風改善の社員研修、コンサルティング、講演、執筆活動などを行っている。著書に『メンターになる人、老害になる人。』(クロスメディア・パブリッシング)、『社長になる人のための経理とお金のキホン』(日経BP 日本経済新聞出版)、他多数。






