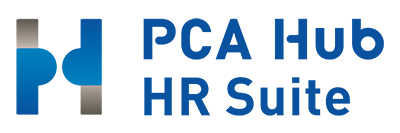労働災害が発生したらどのように申請したら良いの?労災について解説
更新日:2021/12/24
労働災害が発生したらどのように申請したら良いの?労災について解説


業務中や通勤中にケガをしたり、仕事が原因で病気になったりすることを「労災」と言います。「労災」と口にしたり、耳にしたりすることは多いと思いますが、実際に起こったらどうしたら良いか分からないといった方も見受けられます。そこで、労災が起こった際の給付の申請について、療養(補償)等給付を中心にご説明させていただきます。
1.労災(業務災害・通勤災害)とは
仕事中や通勤途中にケガをしてしまった際に「労災事故」という言葉は聞いたことがあると思います。労災事故は二つに分かれ、従事している仕事が原因で起きたケガや病気等を「業務災害」、通勤により被ったケガや病気等を「通勤災害」と言います。
業務災害として認められるには、ケガや病気などになってしまった労働者が労働契約に基づいて、事業主の支配下にある状態であることが必要です。このことを「業務遂行性」と言います。業務遂行性は、必ずしも業務中の事故というわけではなく、例えば、休憩中であったとしても、会社の施設の不備が原因で負傷した場合などは、業務遂行性に該当します。
また、ケガや病気が業務と一定の因果関係を認められる必要があり、これを「業務起因性」と言い、業務災害に該当するかどうかは、この「業務遂行性」と「業務起因性」の両方の条件を満たすかどうかにより判断されます。
次に、「通勤災害」についてですが、こちらは名前の通り、通勤中の事故が該当します。最も一般的なのが、住居と就業場所の往復中の事故になりますが、例えば、兼業をしている労働者が1つ目の就業場所から2つ目の就業場所に向かう途中の事故なども通勤災害に当たります。なお、通勤途中で通勤経路から逸れたり、通勤と関係ない行為を行うと、その後は原則として通勤とはなりませんが、日用品の購入、選挙権の行使、病院等での診察、要介護状態にある親族の介護等などの場合は、例外に当たり、その後、合理的な経路に戻った場合は、再び通勤となります。
2.労災事故が起きた場合は
労災事故が発生した場合には、労災事故として各種申請および請求を行う必要があります。ここでは、より分かりやすい「ケガをした」ケースで説明します。なお、申請における各種様式は、最寄りの労働基準監督署で入手できるほか、厚生労働省のホームページからもダウンロードすることができます。
療養(補償)等給付の手続き
療養(補償)等給付とは、業務災害や通勤災害によって発生する病院での治療費として支給される給付です。業務中の労災事故によりケガをした場合は、病院等の医療機関で治療を受けますが、この医療機関が指定医療機関の場合には、「療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の給付請求書」(様式第5号)(通勤災害の場合は、「療養給付たる療養の給付請求書」(様式第16号の3))を提出します。注意点として、労災事故は、健康保険で扱う事故ではないので、健康保険証を持参していても健康保険証を使用することはできません。
なお、指定医療機関以外で治療を受けた場合には、いったん治療費を負担して、あとで「療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の費用請求書」(様式第7号)(通勤災害の場合は、「療養給付たる療養の費用請求書」(様式第16号の5))を提出することにより、負担した費用の全額が支給されます。
様式第5号(通勤災害の場合は様式第16号の3)は、指定医療機関経由で労働基準監督署に提出されますが、様式第7号(通勤災害の場合は様式第16号の5)は、医療機関に証明してもらった後に、本人または会社から労働基準監督署に提出する必要があります。その他、既に療養の給付を受けている場合に、治療する指定医療機関を変更する場合は、療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届」(様式第6号)(通勤災害の場合は「療養給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届」(様式第16号の4))を変更後の医療機関経由で労働基準監督署に提出することにより、引き続き療養(補償)等給付を受けることができます。
休業(補償)等給付
労災事故によるケガによって会社を休んだ場合は、賃金の補填として休業(補償)等給付を受けることができます。この休業(補償)等給付を受給するためには、以下の3つの要件を満たす必要があります。
①労災事故による療養であること
②労働することができないこと
③賃金を受けていないこと
支給額は、休業日4日目から、休業1日につき給付基礎日額の80%(保険給付60%+特別支給金20%)が支給されます。なお、この「給付基礎日額」とは、原則として、原因となった事故直前3カ月分の賃金を歴日数で割った金額のことを言い、「平均賃金」の計算方法と同様です。なお、この休業日4日目からとは、継続断続問わず、4日目の休業日から支給されます。ここで注意点ですが、休業日3日目までは、休業(補償)等給付を受けることはできません。この3日間は、業務災害の場合は事業主が休業補償(1日につき平均賃金の60%)を行い、休業者に支給しなくてはなりません。この休業補償を行わない場合は、法違反となりますので必ず支給する必要があります。なお、通勤災害の場合は休業補償を行う義務はありません。
この休業(補償)等給付を請求するには、休業(補償)等給付支給申請書(様式第8法)(通勤災害の場合は「様式第16号の6」)を本人または会社から労働基準監督署に提出する必要があります。
3.その他の給付
その他、労災給付は、ケガや病気の症状等により各種給付を受けることができます。給付内容は以下の通りです。(厚生労働省:労災保険給付の概要より)
-
障害(補償)等年金・・・業務災害、複数業務要因災害または通勤 災害による傷病が治ゆ(症状固定)した後 に障害等級第1級から第7級までに該当 する障害が残ったとき
-
障害(補償)等一時金・・・業務災害、複数業務要因災害または通勤災害による傷病が治ゆ(症状固定)した後 に障害等級第8級から第14級までに該当する障害が残ったとき
-
遺族(補償)等年金・・・業務災害、 複数業務要因災害または通勤災害により死亡したとき
-
遺族(補償)等 一時金・・・(1)遺族(補償)等年金を受け得る遺族がないとき(2)遺族(補償)等年金を受けている人が 失権し、かつ、他に遺族(補償)等年金 を受け得る人がない場合であって、すで に支給された年金の合計額が給付基礎 日額の1000日分に満たないとき
-
葬祭料等(葬祭給付)・・・業務災害、 複数業務要因災害または通勤災害により死亡した人の葬祭を行うとき
-
傷病(補償)等年金・・・業務災害、複数業務要因災害または通勤 災害による傷病が療養開始後1年6か月を経過した日または同日後において次の各号のいずれにも該当するとき(1)傷病が治ゆ(症状固定)していないこと(2)傷病による障害の程度が傷病等級に該当すること
-
介護(補償)等給付・・・障害(補償)等年金または傷病(補償)等 年金受給者のうち第1級の者または第2級 の精神・神経の障害および胸腹部臓器の 障害の者であって、現に介護を受けているとき
- 二次健康診断等給付・・・事業主が行った直近の定期健康診断等(一次健康診断)において、次の(1)(2)のいずれにも該当するとき(1)血圧検査、血中脂質検査、血糖検査、胸囲またはBMI(肥満度)の測定のすべての検査において異常の所見があると診断されていること(2)脳血管疾患または心臓疾患の症状を有していないと認められること
4.労働者死傷病報告
労災事故が起きると、給付の請求ばかり気になってしまうと思いますが、給付以外にも労働基準監督署に提出しなくてはいけない書式があります。それが労働者死傷病報告です。労働者死傷病報告の提出が必要になる時は、以下の場合です。
(1)労働者が労働災害により、負傷、窒息又は急性中毒により死亡し又は休業したとき
(2)労働者が就業中に負傷、窒息又は急性中毒により死亡し又は休業したとき
(3)労働者が事業場内又はその附属建設物内で負傷、窒息又は急性中毒により死亡し又は休業したとき
(4)労働者が事業の附属寄宿舎内で負傷、窒息又は急性中毒により死亡し又は休業したとき
なお、様式および提出期限は休業が4日以上か4日未満かで変わります。
4日以上の場合は、様式23号を「遅滞なく」提出しなくてはなりませんが、4日未満の場合は、1月から3月、4月から6月、7月から9月、10月から12月の期間ごとに、それぞれの期間における最後の月の翌月末日前に様式第24号を提出することになります。例えば、8月1日に事故が起きた場合は、10月末日が提出期限です。休業が4日に及ぶということは労災事故も大きいため、提出期限も早いということになります。
労働者死傷病報告を提出しない場合は、「労災かくし」と見なされてしまう可能性もありますので、忘れず必ず提出するようにしましょう。

有限会社人事・労務 チーフ人事コンサルタント。
日本大学法学部卒業後、食品メーカーを経て現職。従業員が500名を超える会社から数名の会社まで幅広い企業のES向上型人事制度作成に数多く携わるほか、多くの労働基準監督署の是正勧告対応などの労務トラブルに対応し、その経験からリスク管理に長けた就業規則を作成するなど、中小企業の人事・労務に精通している。最近は、執筆や講演も精力的に行っている。
【主な執筆実績】
・小さな会社働き方改革 就業規則が自分でできる本(ソシム株式会社)
・Q&A 「労働基準法・労働契約法」の実務ハンドブック(セルバ出版)
・従業員満足ES向上型人事制度のつくり方(日本法令)
・Management Flash(みずほ総合研究所株式会社)
・HOTERES 週刊ホテルレストラン~物語で学ぶ労務管理~(株式会社オータパブリケイションズ)
・月刊遊技通信(株式会社遊技通信社)
・会社の経理を全自動化する本(執筆協力 株式会社翔泳社)
【主な講演実績】
・業員満足(ES)向上型人事制度のつくり方(中央職業能力開発協会)
・成長企業から学ぶ!ES(従業員満足)向上型人事制度(ヒューマンソリシア株式会社)
・第1回 人事・労務 勉強会 -ES 従業員満足施策-(一般社団法人組織内コミュニケーション協会)
・ここだけは押さえておきたい!トラブルを起こさない労務管理のポイント(キヤノンシステムアンドサポート株式会社)
・快適な職場作りを!~メンタルヘルス対策のための労務管理~(ディーアイエスソリューション株式会社)
・メンタル不調者の対応と労務管理(ピー・シー・エー株式会社)
・雇用保険・社会保険の実務ポイント(大分県商工会連合会)
・ここだけは押さえておきたい!「改正派遣法の概要とポイント」(富士ゼロックス群馬株式会社)
・マイナンバー制度の概要と実務(青森県青森商工会議所) ・マイナンバー制度開始に向けて企業が取り組むべき対応(応研株式会社)