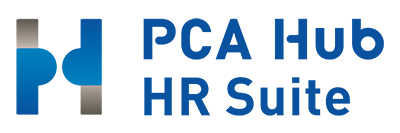育休法改正、企業は男性の育休にどう備える?
更新日:2021/10/22
育休法改正、企業は男性の育休にどう備える?


令和3年6月に、改正育児介護休業法 が成立しました。改正の背景には男性の育休取得を促す狙いがあり、規模を問わず全ての企業に対して、育休制度の説明義務と、育休取得の意向確認義務を課すことにした点がポイントとなります。義務違反の企業を、国は公表することができるようにもなります。
この記事では、男性従業員にとっての育休という観点から、育休制度の現状と育休中の収入面に関わる仕組みを解説した後、今回の法改正によって何が変わり、それに対して企業はどのように備えればよいのかについて解説していきます。
育児休業?育児休暇?
ところで皆さんは、「育休」といえば、「育児休業」と「育児休暇」のどちらを思い浮かべますか?そしてその違いをご存知でしょうか?
少しだけ、「休業」「休暇」という言葉にこだわって、育児介護休業法の中の育児に関する規程を見てみましょう。
- 従業員の「育児休業」と「子の看護休暇」の権利が、この法律の中で保障されています 。(※2)
- この法律の中に「育児休暇」という文言は出てきません。「育児目的で利用できる休暇制度」という文言はあります。企業にはその設置について努力義務が課されています 。(※3)
つまり、
- 「育児休業」は、国が法律で定めた従業員の権利です。
- 「育児休暇」は、企業ごとの判断で実施するいわば社内制度のことを指しており、これに法的な保障はありません。
育休制度の基礎知識
それでは、現行の育児休業制度について確認しておきましょう。
(1)育児休業とは?
企業や事務所で働く従業員が、子どもの1歳の誕生日前日までの間にとる育児のための休みのことをいいます。育休中は企業に給与支払い義務はありません。
(2)取得できるのは誰?
1歳未満の子を育てる従業員であれば、女性も男性も育休を取得することができます。パート、アルバイト、時短社員などの雇用形態を問わず取得できますが、有期契約で働いている場合には条件が付きます。その条件とは、1年以上勤務し、さらに子どもが1歳6か月になるまで雇用契約が続く見込みであることです。
(3)育休対象から除外することはできる?
労使協定があれば、企業は、①継続勤務期間が1年未満の従業員、②育休取得の申出をしてから1年以内に退職することが明らかな従業員、③1週間の勤務日数が2日以下の従業員について、育休の申出を拒むことができます。
(4)いつからいつまで?回数制限はある?
男性の場合は、出産予定日から1歳の誕生日前日までの間に、希望するひとまとまりの期間を1回限り、育休として取得できます。出産した女性の場合は、産後8週間は労働基準法に定められた「産後休業」となるので、育休の開始は産後休業が終了した翌日からとなります。この点は男性と異なりますが、その他は男性と同じです。
なお、子どもの1歳の誕生日前日に既に育休をとっていて、子どもを保育園に預けたいのに預けられないという公的な証明書があれば、1歳を超えて6か月ずつ、最長で2歳の誕生日前日まで、育休を延長することができます。
(5)取得回数の特例としての「パパ休暇」
1回しか取ることができない育休ですが、男性には2回に分けて取得できる特例があります。「パパ休暇」と呼ばれています。条件は、出産予定日から8週間の間に1回目の育休を開始し、そして終了していること。そうすれば、男性は子どもが1歳になるまでの間に2回目の育休を取ることができます。
(6)期限延長の特例としての「パパ・ママ育休プラス」
夫婦がふたり同時に、あるいは交代で、ともに育休を取得する場合には、原則は子どもが1歳になるまでのところ、1歳2か月になるまで、育休の終了日を延ばすことができる特例があります。「パパ・ママ育休プラス」と呼ばれる制度です。ただしこの場合も、夫婦それぞれが取得できる最大日数は(女性は産後休業を含めて)1年間ずつです。つまり、1歳ではなく、1歳2か月までの期限内に、夫婦ともに、それぞれ1年間の育休を取得することができるのです。
育休中は無給・・・でも!
ノーワークノーペイの原則で、企業は、育休中は無給として問題ありません。しかし、育休中の従業員には収入を支える仕組みが備えられています。社会保険料が免除され、育児休業給付が支給されることによって、実質的には育休開始から半年間は手取り額の約8割ほどが、その後は約6割ほどが補償されることになるのです。それでは育休中の収入を支える制度について確認していきます。
(1)社会保険料免除
育休中の健康保険料と厚生年金保険料は、本人負担分・企業側負担分ともに、育休開始月から「終了日の翌日が属する月の前月」まで免除されます。免除はされても引き続き加入しているとみなされますから、健康保険も使えますし、将来の公的年金額にも保険料を納めた期間として反映されることになっています。
なお、上記、免除期間についての法律(健康保険法、厚生年金法)の文言に注目してください。現行制度上は、月末の1日を含む期間を、あるいは月末のたった1日だけを、育児休業として取得すればその月の社会保険料が免除される仕組みとなっています。その月が賞与支給月であれば賞与にかかる保険料も免除されることになります。しかし、月途中からその月の月末にかからない形で育休期間を取得した場合には、その月の社会保険料は免除されません。この仕組みは、保険料の免除を受けたいがために、月末1日だけ、あるいは賞与月の月末に偏って育休を取得する例を多発させている可能性があります。この点については令和4年10月から改正されることになりました。後ほど解説します。
(2)雇用保険の育児休業給付
育休開始前2年間に、月11日以上の勤務月が12か月以上ある雇用保険の被保険者には、育児休業給付が支給されます。出生日以降、育休開始から180日目までは育休開始前賃金の67%、その後は50%が支給されることになります。ただし育児休業給付には上限額が定められている点に留意してください。(令和3年8月時点での月あたり上限額は、支給率67%で301,902円、支給率50%で225,300円です。)育児休業給付金は非課税なので、無給となった分に応じて所得税と翌年の住民税負担が軽くなります。
法改正で育休制度のどこが変わるのか?
ここからは、育児介護休業法の改正によって現行の育休制度のどこが変わるのか、企業はどのように備えればよいのかについて解説します。改正法は令和4年4月から3段階で施行されます。施行時期の順に法改正のポイントを紹介していきます。
(1)令和4年4月から施行
(ⅰ)育休制度について、個別の周知と意向確認を義務化
規模を問わず全ての企業には、子どもが生まれることを申し出た従業員に対して、個別に育休制度の説明をし、育休取得の意向を確認することが義務付けられます。これを受けて企業は、個別面談と、情報提供の体制を整えていく必要があります。具体的には、①出産予定を申し出た従業員に対する個別の面談を行う体制を整えること、②面談の際に渡す、育休制度の情報提供および育休取得の意向確認のための書類を準備すること、の2点です。なお個別周知の方法については、今後、厚労省の省令で複数の選択肢が示される予定となっています。
個別の周知と意向確認の義務化と併せて、企業には不利益取扱いが禁じられることになります。つまり、従業員に、育休を取りたいと表明すると何かしらの不利益を被ると感じさせ、申出自体を控えさせるような抑制力があれば、会社は違法性を問われることになるのです。育休取得に冷たい職場の雰囲気自体が問題になるということについて、今一度、職場全体での共通認識を醸成していっていただきたいと思います。
(ⅱ)育休を取得しやすい雇用環境整備の義務化
さらに全ての企業には、育休を取りづらい職場の雰囲気を解消するよう、雇用環境を整備する措置を講じることが義務付けられます。企業が今できることとしては、①従業員全員に向けて、育休に関する研修を実施する体制を整えること、②育休に関わる相談窓口の設置を準備すること、この2点の体制づくりを進めてください。なお雇用環境整備の具体的内容についても、今後、厚労省の省令で複数の選択肢が示される予定となっています。
(ⅲ)有期契約で勤務1年未満の従業員も育休の対象に
現行制度の下では、有期契約で働く従業員が育休を取得するためには、①勤務期間が1年以上あり、②子どもが1歳6か月になるまで雇用契約が続く見込み、という2つの要件を満たさなければいけません。しかし法改正によって①の要件は廃止されます。つまり、非正規雇用者にとっても育休は取得しやすくなるのです。しかし改正後も、労使協定があれば勤務期間が1年未満の従業員を育休の対象外とすることはできます。
(2)令和4年10月から施行
(ⅰ)新たな出生時育休制度としての「男性版産休」
男性従業員に向けては、現行制度に上乗せする形で「出生時育児休業制度」が新設されます。この制度を利用すれば、男性従業員は、出産予定日から8週間の間に、4週間以内の育休を取ることができます。しかもこの育休は2回に分割して取得することができます。
また、「出生時育児休業制度」を使っての育休中には就業することもできます。現行制度では育休中の就労は想定されておらず原則不可なのですが、新設の育休では、労使協定の締結が前提となりますが男性従業員は就業希望日を企業に申し出ることができ、企業側もそれを認めることができるようになります。省令で就業可能日の上限は設定される見込みですが、男性が出生時育休をとりながらも堂々と働くことができる、とされることで、今後、男性の育休取得にプラスの効果が期待されます。
(ⅱ)育休の分割取得が可能に
現行制度の下では分割して取ることができない育休ですが、令和4年10月からは2回までの分割取得が可能となります。したがって男性従業員は、前述の出生時育児休業制度の下で子どもの誕生から8週間の間に2回の育休を取った後にも、子どもが1歳になるまでに2回、合計4回の育休を、短期長期と柔軟に組み合わせて利用できるようになります。
(ⅲ)育休中の社会保険料免除要件の見直し
社会保険料免除を狙っての育休取得について、令和4年10月からは健康保険法等の一部改正法が施行されます。現行制度の下では、月途中に開始し終了する育休は全て免除の対象外でしたが、月途中の2週間以上の育休は、月末にかからなくても免除されることになります。そして1か月以下の育休では、賞与にかかる保険料は免除されないことになります。これで、育休が月末を含むか否かで保険料免除の有無が変わる不公平感は少しは解消されることになります。ただし月末1日のみの育休が保険料免除の対象となることについては改正後も変わりません。
(3)令和5年4月施行
(ⅰ)大企業には育休取得率公表の義務
従業員数1,000人超の大企業には、育休取得の状況について毎年公表することが義務付けられます。育休取得率の高さは企業の社会的評価や企業イメージの向上にもつながることから、男性も育休を取りやすい職場作りへの企業側の取り組みの深化が期待されます。
まとめ
最新の調査(※4)では 男性の育休取得率は12.65%です。初めて男性の育休取得率が1割を超えたとはいえ、それでも国際的に見れば低い水準にとどまっています。充実した育休制度も空しく、男性の育休取得がなかなか進まない理由は、育休についての情報不足や取得を言い出しにくい職場の雰囲気、収入減やキャリアの中断への不安に求められるのではないでしょうか。となると、企業と従業員、双方の意識に働きかける施策が必要です。
今回の育児休業法の改正によって、企業には、収入減を補う仕組みを含め、育休制度について従業員に十分に説明する義務が課され、男性が育休を取りづらく感じる企業風土を改善する取り組みが求められることになります。法改正に伴って就業規則の育児休業に関する規定を見直す必要がありますが、併せて、育休制度の周知体制を整え、従業員から長期間の育休を取りたいという申し出があった場合にはその希望を叶えることができるよう、誰が休んでも滞ることなく回る職場を目指して、柔軟性の高い雇用環境の実現に挑んでいただきたいと思います。
※1:正式名称は、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う従業員の福祉に関する法律」といいます。
※2:育児介護休業法5条、16条の二
※3:育児介護休業法24条
※4:厚生労働省「令和2年度雇用均等基本調査」
筆者プロフィール

荒木 志奈 (あらき しな)
- 有限会社 人事・労務チーフコンサルタント
- 特定社会保険労務士
- 大学付属研究機関の研究員として社会資本の経済評価プロジェクトに携わった後、地域コミュニティー活動に参加しながら育児を存分に楽しむ専業主婦となる。子育てに一段落ついてからは、社労士事務所に勤務し、後に独立。経営者の理念が共有され、人が育ち、組織が育ち、地域が育ち、次世代を担う子供たちが元気に育つ好循環に貢献したいという思いを胸に、学習する組織づくりを支援している。