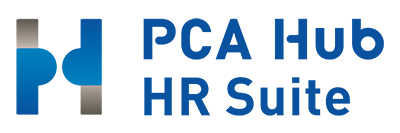短時間労働者に対する社会保険の適用拡大について
更新日:2021/08/20
短時間労働者に対する社会保険の適用拡大について


今回は、短時間労働者に対する社会保険の適用拡大についてです。
パートタイマーやアルバイトなどの短時間労働者が増えていることから、短時間労働者でも社会保険の適用を受けられるようにとのことで、一定の要件を満たす事業所(「特定適用事業所」と呼ばれます)に勤める短時間労働者も社会保険の適用対象とする制度があります。
この適用拡大自体は2016年から既に始まっているものですが、今回2022年10月より特定適用事業所の要件が変更となり、対象事業所が拡大されます。また、段階的に2024年10月にもさらに要件を変更し、対象事業所が増える見込みとなっています。
どのような事業所、短時間労働者が適用拡大の対象となるのか見ていきましょう。
特定適用事業所の要件について
まず、「特定適用事業所」の要件を確認していきます。
現在は、「社会保険の加入者が501人以上」の場合に特定適用事業所となります。この人数が、2022年10月からは「101人以上」、2024年10月からは「51人以上」となり、該当企業が一気に拡大されます。なお、支店など事業所が2つ以上ある場合は、合計数で判断します。
人数については、全従業員数で判断するわけではなく、「社会保険の加入人数」で判断します。直近12ヶ月のうち6か月以上上記の基準を超える場合は、特定適用事業所となりますので、会社でしっかりと毎月の被保険者数を把握しておく必要があります。
適用拡大となる短時間労働者について
続いて、適用拡大となる短時間労働者の要件を確認していきます。
そもそも、社会保険の適用対象となるのは、原則「週の所定労働時間および1か月の所定労働日数が常時雇用者(正社員)の4分の3以上」の労働者です。例えば、正社員の週の所定労働時間が40時間であれば、週に30時間以上働く労働者はパートでもアルバイトでも社会保険に加入させる必要があります。そもそもの話ではありますが、しっかりと押さえていただければと思います。
しかし、下記の要件を満たす短時間労働者は上記の要件に関わらず、社会保険の適用対象となります。
- 週の所定労働時間数が20時間以上であること
- 賃金月額が88,000円以上であること
- 雇用期間1年以上の見込みがあること(現行)
- 学生でないこと
1 週の所定労働時間が20時間以上であること
1つ目の要件は週の所定労働時間が20時間以上であることです。正社員の4分3以上の勤務がない場合でも、適用拡大となる短時間労働者として加入させる必要が出てくる可能性があります。
具体的に特に確認いただきたいのは、「雇用保険には加入しているが社会保険の適用対象とはなっていない従業員」です。雇用保険は週に20時間以上働く従業員は適用対象のため、雇用保険に加入している場合は、①の要件を満たしていると考えられます。
2 賃金月額が88,000円以上であること
基本給と諸手当の合計額が月額88,000円以上である場合は対象となります。
残業代等の割増賃金や、臨時的に支払われる賞与、通勤手当や家族手当・皆勤手当等の最低賃金に参入しないとされる手当はここには含まれません。
東京など最低賃金が比較的高額の地域では、①の要件ぎりぎりの時間数でない限りは、該当してくる可能性が高いと思われます。
3 雇用期間1年以上の見込みがあること
3つ目の要件は雇用期間が1年以上見込まれていることです。
ただし、これは現行の基準であり、2022年10月の改正で「2か月を超える雇用の見込があること」と要件が緩和されます。
注意点としまして、当初2か月以内で満了する予定の契約であれば③の要件は満たさないということになるのですが、その後方針の変更等で雇用契約を更新し、結果的に2か月を超える契約期間となった場合は③の要件を満たしていたものとし、遡及的に社会保険に加入させるように指導がなされる可能性があります。
4 学生でないこと
学生であれば、原則適用対象外となります。ただし、卒業見込証明書を有し、既に就職しており、卒業後も引き続きその会社で勤務する場合や、休学中の学生、夜間学部等の定時制の学生は適用対象となります。
表にまとめると、下記のようになります。
| 対象 | 要件 | 平成28年10月~(現行) | 令和4年10月~(改正) | 令和6年10月~(改正) |
| 事業所 | 事業所の規模 | 常時500人超 | 常時100人超 | 常時50人超 |
|---|---|---|---|---|
| 短時間労働者 | 労働時間 | 週の所定労働時間が20時間以上 | 変更なし | 変更なし |
| 賃金 | 月額88,000円以上 | 変更なし | 変更なし | |
| 勤務期間 | 継続して1年以上使用される見込み | 継続して2ヶ月を超えた使用される見込み | 継続して2ヶ月を超えた使用される見込み | |
| 適用除外 | 学生ではないこと | 変更なし | 変更なし |
最後に
適用拡大となる対象の事業所、短時間労働者については上記の通りです。
会社としては被保険者をしっかり把握・管理して、特定適用事業所に該当していないか確認しておく必要があります。また、短時間労働者が在籍しているのであれば、新たに適用対象とならないか確認しておく必要もあります。
そのため、シフト制などで所定労働時間数が正確に把握できていない場合は、労働時間をしっかり確認しておく必要があります。
また、パートで勤務している従業員の中には、配偶者等の扶養の範囲内で勤務したいという方がいるかと思います。週20時間以上勤務している方でそのような勤務にしたいという方がいる場合、まずは従来の勤務の仕方だと新たに社会保険の適用対象となるため、扶養から外れる必要があることを伝える、場合によっては勤務日数・時間数の見直すなど、該当従業員との対話の時間も必要です。
改正直前になって、対応が後手に回らないよう早めの準備をしていくことが求められるでしょう。

有限会社人事・労務 チーフコンサルタント。
行政書士。
中央大学法学部卒業後、早稲田大学大学院法務研究科を経て、有限会社人事・労務に入社。労働・社会保険手続き、給与計算、規則規程の整備などの業務を中心に企業の体制を整えるサポートに関わる。これからのより多岐に亘って求められる様々な働き方を実現し、個々の能力を十分に活かせる環境作りを支援していく中で、様々な新たな働き方を行うコミュニティカンパニーの設立支援に携わる。
【主な講演・執筆実績】
・講師 労働者協同組合法台東区役所庁内学習会
・コミュニティFM「鳥越アズーリFM『大ちゃん金ちゃんの ここ掘れワンワンスタジオ!』」ディレクター
・セミナー「働く個々の健康と育児介護・療養等に関わる人事労務の要点~恐れのない職場を目指して」
・セミナー「おさえておくべき法制度改正と人事労務面での対応」
・セミナー「職場のハラスメント対策」
・セミナー「働き方改革」の概要~パート労働法改正と同一労働同一賃金への取組み~
・書籍「小さな会社働き方改革 就業規則が自分でできる本」(ソシム株式会社)
・セミナー「第2回労務管理セミナー~中小企業の労働時間対策~」(ダイキンHVACソリューション東京株式会社・主催)
URL:https://www.jinji-roumu.com/