有給休暇義務化とは?ポイントや実際の対応方法についてご紹介
更新日:2020/06/02
有給休暇義務化とは?ポイントや実際の対応方法についてご紹介
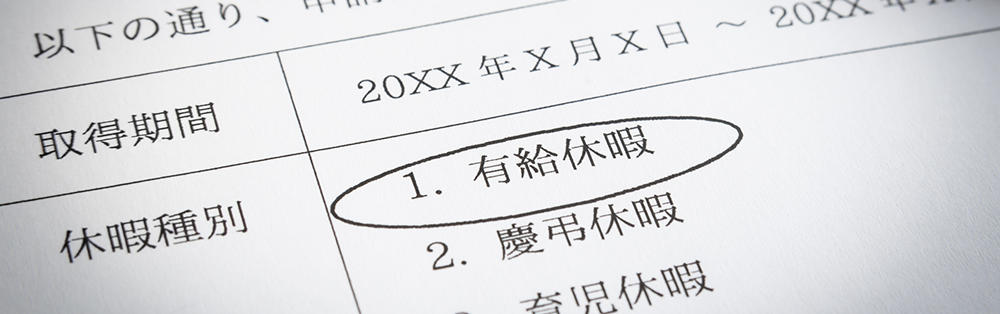
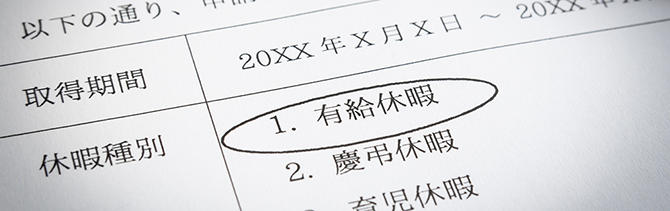
日本のビジネスで今大きなトピックになっているのは、「働き方改革」です。誰もが自分らしく健康に暮らせるよう、日本政府も本腰を入れて働き方改革を推進しています。
政府は働き方改革の一環として、「働き方改革関連法案」を成立させました。そして法案の中では、日本の労働環境で大きな問題になっている有給休暇消化の是正を行う「有給休暇義務化」が定められ、2019年4月から実施されています。
有給休暇義務化は始まったばかりの制度なので、理解が追い付かず混乱している方もいらっしゃるかもしれません。しかし有給休暇義務化の内容を理解しておかないと、罰金や懲役などを科される恐れもあるので注意したいところです。
今回は有給休暇義務化について、義務化のポイントや実際に義務化へ対応する方法などをご紹介していきます。
有給休暇が与えられる対象は?
有給休暇は正式名称を「年次有給休暇」と言い、「労働基準法第39条で定められた、賃金が発生する休暇」を指します。
- 労働者が雇用開始から6ヶ月以上継続勤務、労働日の8割以上出勤していると自動付与
- 1年6か月後には11日、2年6か月後には12日と取得できる日数があらかじめ決まっている
- 取得後2年経過すると、失効してしまうな
どが特徴となっています。
有給休暇が与えられる対象は、企業の正規雇用の方だけではなく、アルバイト・パート・派遣の方も付与の対象です。
ただしアルバイト・パート・派遣の場合は付与日が労働日数や時間によって決められ、
- 週間労働日4日、年間労働日169~216日:6ヶ月7日、1年6か月8日など
- 週間労働日3日、年間労働日121~168日:6ヶ月5日、1年6か月6日など
- 週間労働日2日、年間労働日73~120日:6ヶ月3日、1年6か月4日など
などと変化するので注意しましょう。
有給休暇に対する課題
有給休暇を消化する(実際に利用する)のは社員の権利で自由に行使できますが、日本社会では長らく有給休暇を上手く消化できない環境が続いています。
「エクスペディア」が公開している「有給休暇国際比較調査」では、有給休暇の世界各国取得率がデータ化されています(全体の支給日数を取得日数で割った数値を比較)。
結果としては
- ブラジル、フランス、スペイン、ドイツ・・・100%
- イギリス・・・96%
- 韓国、メキシコ、シンガポール・・・93%
- アメリカ・・・71%
- 日本・・・50%
と、日本が世界各国に対して大きく引き離されています。
同調査では日本人が有給休暇を取らない理由として、
1位・・・人手不足
2位・・・緊急時のために取っておく
3位・・・仕事をする気がないと思われたくない(世間体を気にする)
などが挙げられており、有給休暇取得の弊害になっているのが現状です。
有給休暇義務化とは
有給休暇を消費できない結果、「ライフワークバランス(プライベートと仕事の両立)」が崩れて健康を損ねては元も子もありません。そこでライフワークバランスを実現し、働き方改革を進める一環として政府が定めたのが有給休暇義務化です。
有給休暇義務化のポイントは、次のとおりです。
- 年次有給休暇が10日以上付与された場合、1年以内に5日間有休を取得させる必要がある
- 有休取得の申し出がなかった場合、期間内に時季指定を行い消化させる
- 義務化に違反した場合、30万円の罰金などが課される
年次有給休暇が10日以上付与された場合、1年以内に5日間有休を取得させる必要がある
年次有給休暇を10日以上付与された労働者に対し、使用者は必ず1年以内に最低5日、労働者に有給休暇を取得させないとといけません。
たとえば2020年4月1日に10日以上有給休暇を付与されたら、2021年3月31日までに5日消化できるよう準備をする必要があります。この決まりは正規雇用の方だけでなく、パート、アルバイト、派遣などあらゆる雇用形態が対象です。
有休の買取などでは消費扱いにならず、法律違反になるので注意しましょう。
有休取得の申し出がなかった場合、期間内に時季指定を行い消化させる
義務化された有給日数を労働者側が事前申告して消費してくれれば、会社側は何も対応する必要はありません。しかし実際にはさまざまな理由で、事前申告がなかなかできない労働者もいるでしょう。
企業は期限内に、申し出が行われていない義務日数分を消化できるよう時季指定を行う必要性が出てきます。
時季指定の手順は、
1.会社側が労働者に対し、有休を取得したい時季をヒアリングする
2.ヒアリングを優先しながら時期を調整し、消費する日を決定する
となっています。
義務化に違反した場合、30万円の罰金などが課される
もし義務日数の消化に失敗し法律に違反した場合、会社側には
・違反の発生した労働者一人につき30万円以下の罰金
・6ヶ月以下の懲役
などが課される恐れがあります。
30万円の罰金は積み重なると何百万、何千万にも膨れ上がる危険性があります。
有給休暇義務化は努力義務ではなく、罰則ありの厳しい決まりだと覚えておきましょう。
有給休暇義付与務化に対応する方法3つ
ここからは、有給休暇義務化に対応する方法を3つご紹介していきます。
- 企業自体が有給休暇にメリットがあると自覚し、推進を行う
- 有休を消化しやすい風土を作る
- 勤怠状況をツールで可視化して適切に管理する
企業自体が有給休暇にメリットがあると自覚し、推進を行う
有休ついて、下手に消化させてしまうと
- 労働力が減少する
- 社員が休んでいる間、コストが掛かる
などのデメリットが発生してしまうと感じている企業もいるかもしれません。
しかし有休を適切に消化できるようにすれば、
- リフレッシュできた社員のモチベーションが向上し、返って生産性が向上する
- 社員の離職率が減り、定着率が上がるので無駄な採用コストがなくなる
- 有給休暇が取りやすい企業として認知され、イメージアップを狙える
など、さまざまなメリットを見込めます。
有給休暇を消化させずに働かせることに、メリットはあまりありません。有給休暇消化を推進するには、まず企業側が有休にメリットを感じて積極的に広げていこうとする姿勢を取ることが重要です。
有休を消化しやすい風土を作る
有休を消化しやすい風土を作るには、次のような方法があります。
- 雇用者を増やしたり、ITツールで効率化を行ったりして労働不足を是正する
- 有給休暇義務化について、労働者全体に内容を詳しく説明する
- 娯楽施設の割引チケットを配布するなど、福利厚生を手厚くする
有給休暇を消化しにくいのは、「労働力が不足している」面が大きいでしょう。つまり労働力を安定して確保できれば無理に出社する必要はなく、有給休暇もそれだけ消化しやすくなります。
また有給休暇を社員が積極的に消化したいと思えるよう、割引チケットを配布したりと有給休暇を有効活用できる福利厚生制度を整えておくと将来的にも役立つでしょう。
勤怠状況をツールで可視化して適切に管理する
法律に違反せず社員に有休を消化してもらうには、社員一人一人の勤務状況や実際の有給休暇取得日数などを会社側で細かく管理する必要があります。しかし規模が多ければ多いほど、一人一人の勤務状況などを可視化して有休の消化状況を把握するのは難しくなるでしょう。
有給休暇消化状況の改善だけでなく労働環境自体の是正を行えるよう、勤怠管理ツールを導入して可視化を行える環境を作りましょう。
勤怠管理ツールを使えば、
- 出社、退社時間
- 出席、離席状況
- 自動計算された有給休暇日数
などが一目で分かるようになり、「誰をどれだけ休めないといけないか」の判断にも使えます。
有給休暇を時季指定する場合に適切なタイミングで社員が休めるよう、勤怠管理ツールを活用して一人一人の労働状況を把握しておきましょう。
勤怠管理ツールに予算を割きにくい中小企業には、クラウド勤怠管理ツールがおすすめです。多くの勤怠管理ツールがサービス内容を知ってもらうため、無料トライアルを行っています。
まずは無料トライアルでサービスの試験運用を行い、上手く有休の把握を含めて勤怠管理ができるようだと判断できれば本格的にお金を掛けて導入してみましょう。

まとめ
今回は有給休暇義務化のポイント、そして法律違反にならないようにするポイントなどをご紹介しました。
消化させる際は上手く日程調整なども行い、会社・社員双方が納得できるようにしましょう。
ぜひ有給休暇義務化をチャンスと捉え、積極的に働き方改革を推進してみてください。






