企業の本決算における決算整理の重要性
更新日:2019/12/03
企業の本決算における決算整理の重要性
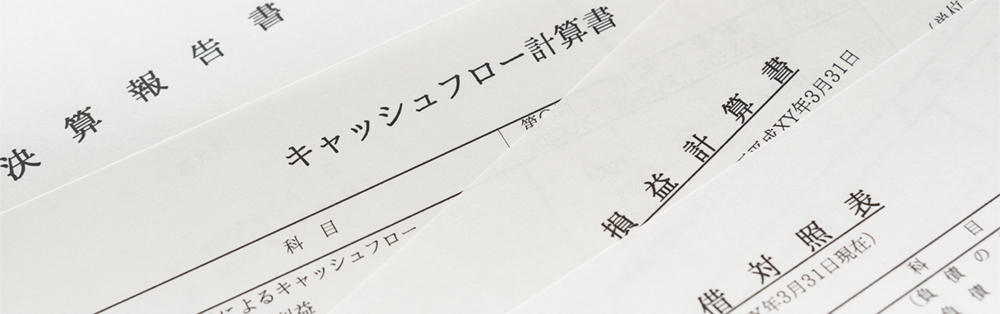
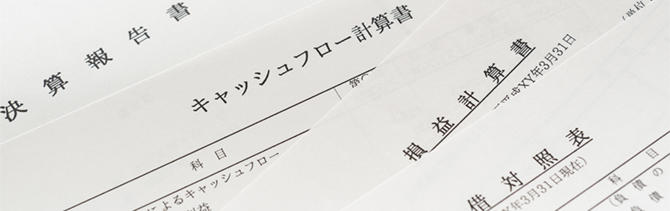
決算にはさまざまな種類がありますが、中でも1年間の活動をまとめる本決算は重要です。本決算のデータは株主への成果報告や与信管理だけでなく、確定申告にも使われます。本決算がしっかりしていないと株主などに迷惑をかけるだけではなく、本来払わなくてよかった税金を後々払わないといけない状況に陥る可能性もあります。
適切に本決算を行うためには、経理上の計上ずれなどを解消する決算整理をしっかり行っておく必要があります。
今回は決算整理とは何か、そして実行手順やポイントまで分かりやすく解説していきます。「経理担当者になったばかりで、本決算の意味や手順などがよくわからない」という方はぜひご覧ください。
決算整理とは
多くの企業では、経理担当者が月ごとに試算表を作り、そのデータを元に本決算を行うことが多いと思います。しかし試算表のデータはあくまで概要であり、1年間で見ると調整の必要がある部分が見えてきます。
例えば補充した在庫の代金を、来年度に入金する予定とします。このとき実際に支払いを行うのは来年度なので、来年度に費用を計上すればよいと考える可能性が出てきます。
しかし実際は現金の受け渡しが終わっていなくても取引が完了していればその時点で経費を計上しなければならないので、この場合は未払い分を今年度支払い分として計上する必要があります。
このように決算では「発生主義(取引の発生を基準に計上を行う主義)」に基づき計算をしなくてはいけないので、間違って今年度に入れるべき利益を来年度に繰り越してしまった場合は、正しいタイミングに修正する必要があります。
その他にも、修正を行うべきところはたくさん出てきます。そういった修正点を洗い出し、適切な状態に決算を調整する作業を決算整理と呼びます。
決算整理の手順
決算整理は、主に次のような手順で行われます。
- 毎月の試算表を集めて、決算整理用データのたたき台を作る
- 決算整理仕訳を行う
- 貸借対照表と損益計算書を完成させる
1.毎月の試算表を集めて、決算整理用データのたたき台を作る
まずは毎月の試算表を集めて、決算整理用データのたたき台を作っていきます。大量のデータが貯まっていると思いますので、この時点で抜け漏れがないよう注意してください。
2.決算整理仕訳を行う
次に決算整理で一番重要になる、決算整理仕訳を行っていきます。
決算整理仕訳では
- 見越し処理
- 繰延べ処理
- 減価償却費の計上
などを行っていきます。
見越し処理
未払いになっている費用や収益を、今年度分と判断して計上を行っていく処理を指します。
例えば先ほど説明した在庫仕入代金の入金が来年度になるケースも、すでに今年度取引が一旦完了しているとみなして費用計上を行います。
またクライアントとの取引で発生した報酬が来年度の支払いになる際も、取引自体は一旦今年度で終了しているので今年度分の報酬として計上を行います。
繰延べ処理
見越しとは逆に、来年度分として今年度支払った費用や収益を、来年度分として計上を行っていく処理です。
例えば土地を他社から借りている場合、半年分など先に発生する費用までまとめて支払いを行う場合もあります。その際前もって支払いした分が年度をまたぐ場合、またいだ分は別途来年度分経費として計上する必要があります。逆に自社が提供している商品やサービスにより、ユーザーから前もって来年度分の料金を徴収した場合も繰延べ処理が発生します。
来年度分までまとめて支払いが行われているので、単に試算表を見ただけでは見落とす可能性があります。決算整理の際には注意深く試算表内の日づけを見ながら、繰延べ処理に当たる取引が発生していないか確認する必要があります。
減価償却費の計上
会社で調達した設備の中には、何年にもわたって使い続けるものがあります。
- パソコン
- ソフトウェア
- 家具
こういったものはシャープペンシルやインクなどと違いすぐには消費されず、長い耐用年数を持っています。そのため調達額全額を1度に計上すると、実際は来年度も使っているはずなのに1年で使い切って使えなくなったような計上の仕方になります。
そこで長期間使うことを前提とした資産を調達した場合、その調達額を年ごとに分けて計上し違和感のないよう調整する考えを減価償却と呼びます。減価償却は、企業内資産が現在どのくらいの価値を持っているのか評価する指標としても使われます。
決算整理仕訳においては、減価償却費も計算して記録する必要があります。
減価償却費は、「各資産の調達額/国が定めた耐用年数」で算出されます。
例として
- 事務机・・・15年
- パソコン・・・4年
- 社用車・・・5年
などとなっています。その他の耐用年数については財務省令の別表にまとめられているので、計算時の参考にしてください。
3.貸借対照表と損益計算書を完成させる
各決済整理仕訳を終わらせたら、算出された内容を元に成果物として貸借対照表と損益計算書を完成させます。
貸借対照表はバランスシートとも呼ばれ、社内資産や負債、そしてそこから導き出される純資産などを記載していきます。社内の資金のやりくりがどう行われているかを外部に公表するために作成されます。
損益計算書には企業収益やかかった費用、それに純利益などを記載します。指定期間内に、企業がどのくらいの利益を出しているかを外部から判断するのに使われます。
決算整理時に押さえておきたいポイント
ここからは、決算整理時に押さえておきたいポイントをご紹介します。
- できるだけ第三者が作った資料を基に確認を行う
- 仕訳は丁寧に行う
- 会計システムを活用する
できるだけ第三者が作った資料を基に確認を行う
決算整理の数値に間違いがあると確定申告時に税務署から指摘を受けるなど、トラブルが増える原因になります。そのため決算整理時に数値を確認する際は、できるだけ第三者が作成した資料を基にしましょう。
例えば
- 銀行の残高証明書
- 残高確認依頼書
- 公官庁関係の資料
このような自社以外で作成された書類を活用することで、決算で記載されている数値などのズレを少しでも防げます。
仕訳は丁寧に行う
当然のことではありますが、仕訳は丁寧に行いましょう。
- 現金勘定と現物にズレがないか
- 残高証明書と預金勘定にズレがないか
- 見越しや繰延べ処理に抜け漏れがないか
- 減価償却費として計上すべきものに抜け漏れがないか
- 未使用の消耗品は資産に変更しているか
こういった点も含めて、確実に仕訳を行っていきましょう。
会計システムを活用する
ここまで決算整理の手順などをご紹介してきましたが、手作業ではとても時間のかかる作業なのが文面からご理解いただけたと思います。「人手不足で決算整理にまで手が回らない・・・」という場合は、会計システムの活用も検討してみてください。
会計システムは経理に関する作業を自動化・可視化してくれるので、ミスを減らしながら経理作業の効率化を狙えます。決算整理にかかる手間と時間も短縮され、質の高い決算書ができあがるでしょう。
クラウドタイプであれば導入も簡単ですし、低コストで経理作業を効率化できます。まだ導入していない場合はぜひご検討ください。

まとめ
今回は本決算における決算整理の重要性、そして決算整理の手順やポイントも解説しました。
経理を行っていると、どうしても決算時記載にズレやミスが生じがちです。そのまま計上を行ってしまうと税金追納など余計な手間と費用がかかってしまうので、ぜひ決算整理を丁寧に行い決算書を適正化しましょう。
また決算整理など各経理作業に忙殺されている場合は、クラウドタイプなど会計システムの導入を検討してみてください。







