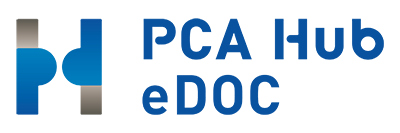電子帳簿保存法とは?保存方法や手続きについて解説
更新日:2019/10/08
電子帳簿保存法とは?保存方法や手続きについて解説


企業が業務を行う際は、大量の国税関係書類が必要になります。現金出納帳や仕訳帳、領収書など、あらゆる国税関係書類を紙で管理しようとすると膨大な手間と時間がかかります。そこで政府は企業のペーパーレス化を推進するために、「電子帳簿保存法」を制定しています。
この電子帳簿保存法、実は2000年以前から存在している法律ですが、当初は規約が多く実践しにくい企業が多いのが難点でした。しかし最近では規制緩和や電子化の方法が広がるなど、たくさんの企業で電子帳簿保存法が実践されるようになっています。あなたの会社が紙ベースで国税関係書類を整理しているのであれば、電子帳簿保存法に則って書類を電子化することでさまざまなメリットが得られます。
今回はそもそも電子帳簿保存法とは何か、そして対象となる書類、実際の保存方法や手続きの仕方まで初心者にも分かりやすいように解説していきます。「電子帳簿保存法とは何か知りたい」、「自社の紙書類が多いので、電子帳簿保存法を利用してペーパーレスな環境を実現したい」という方はぜひご覧ください。
電子帳簿保存法とは
電子帳簿保存法とは、1998年に制定された法律です。国税関係の書類をデジタルで管理し、保存できるようにその方法などを定めています。
従来の国税関係書類は、すべて紙で保存するように義務づけられていました。しかし書類はたくさんあればあるほどかさばりやすく、また管理しにくいものです。そして国税関係書類には実にさまざまな種類があり、これを分かりやすくバインダーやフォルダなどで管理して保存しておくのは骨の折れる作業です。
国税関係書類を電子化して管理できるようにすれば、そもそも電子化された書類にはかさばるという概念がないので、すっきり国税関係書類を整理できます。またソフトウェアの機能を使って分類なども自動化できます。このように電子帳簿保存法に則って国税関係書類を電子化することで煩雑な書類整理・保管業務時間の削減及び業務効率化などを狙えます。
制定当初は対象があらかじめコンピューターで作成された電子データを保存の対象としており、紙の書類をスキャンして保存する前提ではありませんでした。
2005年には電子帳簿保存法の改正により、従来対象ではなかった紙の書類をスキャンして電子データ化して保存するケースが対象になりましたが、それでも、その対象になる請求書・領収書は取引金額が3万円以上の場合は電子化できず、かつ電子署名が求められるなど厳しい規制がありました。
しかし、2015年には3万円以上の金額制限が緩和され、3万円を超える請求書・領収書でも電子データ化が可能になり、あわせて電子署名も不要になります。続けて翌2016年には、スマホの普及などITが進歩したことを受けて、デジタルカメラやスマホなどで撮影した書類を電子データとして保存可能になり、企業がより導入しやすい制度に変更されていっています。
そして、経済社会のデジタル化を踏まえ、経理電子化による生産性向上、テレワーク推進、記帳水準向上及び適正な課税の実現等の観点から、電子帳簿保存制度を抜本的に見直しが行われ、2020年10月の電子帳簿保存法の改正で要件が緩和されて、法人クレジットカードやSuicaなどの交通系ICの電子決済を利用した明細データが、紙の領収書に代わりになるように改正されました。これにより、これまで必要だったスマホなどの撮影やアップロードが不要になっています。
電子帳簿保存法で保存可能な書類
以前より規制が緩和された電子帳簿保存法ですが、注意点もいくつかあります。
具体的に電子帳簿保存法で保存可能な書類としては、
- 取引内容を明らかにする書類で、書類の真実性を補完する書類・・・契約書など
- 取引の中間過程で作成される、所得計算と直結・連動する書類・・・請求書など
- 資金や物の流れに直結・連動しない書類・・・見積書、検収書など
の3つです。基本的にあらゆる国税関係書類を電子化して保存できます。
ただし紙ベースの書類を機器で読み取って電子保存するスキャンの場合、保存できる書類と保存できない書類が分かれます。
具体的にスキャナで保存できない書類は、
- 帳簿・・・現金出納帳、仕訳帳、総勘定元帳など
- 決算関係書類・・・貸借対照表、損益計算表、棚卸表など
が挙げられます。「紙の書類をスキャナで保存して電子化したい」という場合は、上記書類は対応していないことに注意しましょう。またスキャナで保存できないだけで、上記書類も最初から電子化して管理しておけば保存可能なります。
電子帳簿保存法に沿って書類を電子化する方法
電子帳簿保存法に沿って書類を電子化するには、次の2つの方法があります。
- ソフトウェアで書類を電子化する
- 紙の書類をスキャナで保存・スマホなどで撮影する
ソフトウェアで書類を電子化する
「Excel」や業務システムを活用して、書類を最初から電子化して保存する方法です。最初から書類を電子化して作成してしまえば余計な手間がかからないので、多くの企業が実践している方法です。
電子帳簿保存法が適用される書類には
- 訂正、削除、入力履歴など作業の跡がしっかり把握できる状態であること
- 書類同士の関連性が分かりやすく把握できること
- システム操作説明書などのマニュアルを用意し、手順通りに書類を作成すること
- 日付や金額など、指定の条件で検索をかけられるようになっていること
- 書類内の文字がつぶれておらず、明瞭ではっきり見える状態であること
といった条件があります。
「Excel」を使っても電子書類を作成し、保存はできます。しかし「Excel」では複数人で内容を共有しにくい、柔軟に電子書類作成に対応できないなどのデメリットがあります。電子帳簿保存法をクリアした書類を自動作成できるシステムを導入すると、手間をかけずに簡単に国税関係書類を電子化できます。
紙の書類をスキャナで保存・スマホなどで撮影する
電子書類作成には、紙ベースの領収書だけでなく、請求書・納品書・契約書といった書類をスキャナで保存して電子化する方法も考えられます。2018年からはスマホなどの撮影機器で撮影した書類も認められるようになったので、外出先でも書類を電子化して保存可能です。
紙の書類を電子化するためには、上記の電子帳簿保存法が適用される条件に加えて
- 解像度が200dpi以上の状態で保存すること
- RGB(赤、緑、青)の階調がそれぞれ256以上
- 撮影した領収書などには対象データの作成と、改ざんがされてないことを証明するためタイムスタンプを付与すること
なども同時にクリアしている必要があります。
また、タイムスタンプは2020年10月の改正で、緩和されています。タイムスタンプの受け取り手が自由にデータを改変できない場合は、受け取りての付与が不要になっており、より利用しやすくなっております。
最初から電子化された書類とスキャナで保存して電子化した書類、この2つを併せて簡単に管理するには、電子帳簿保存法に準拠した業務システムと連携する業務システムを導入すると便利です。
スキャナ読み込みから電子化して自動でタイムスタンプを付与して、書類の電子保存に関するさまざまな機能を使って業務を効率化できます。ベンダーごとにさまざまなサービスが提供されているので、興味のある方はぜひ自社に最適なサービスを探して導入を検討してみてください。
電子帳簿保存法の手続きについて
電子帳簿保存法を導入するためには、あらかじめ税務署へ申請手続きを行う必要があります。ここからは電子帳簿保存法の手続きについて分かりやすく解説していきます。
- 必要な書類を用意する
- 税務署に申請する
- システム導入などの前準備を行う
1.必要な書類を用意する
まずは書類電子化申請に必要な書類を用意します。ここで注意したいのは、申請書類は1つではなく、電子化したい書類の種類や電子化の方法によって分かれている点です。
例えば「帳簿も書類も電子化したいし、スキャナも利用したい」という場合は、
- 国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等の承認申請
- 国税関係書類の電磁的記録等による保存の承認申請
- 国税関係書類の電磁的記録によるスキャナ保存の承認申請
と3つの申請が必要になってきます。ちなみに電子保存を取りやめたり変更したりする場合も、後日別途書類を提出する必要があります。
上記書類に加えて、
- 書類を電子化するシステムの概要について記載した書類
- 書類を電子化するときの処理手続きなどについて説明した書類
- 申告書などを保管するための書類
も必要です。必要な書類が多いので、余裕をもって準備をしておきましょう。
2.税務署に申請する
書類を準備した後は、実際に税務署に書類を提出します。申請期限は書類のスキャナ保存をする3ヶ月前までとなっており、スキャナ保存の運用をするにあたっては余裕をもって税務署へ書類を提出するようにしましょう。
3.システム導入などの前準備を行う
申請を終わらせたら、書類の電子化開始までにシステム導入やマニュアルなど、必要なものを前もって準備しましょう。システムは使い方を習得する必要があるので、事前に研修を行うなどしてスムーズに使えるように備えておいてください。

まとめ
今回は電子帳簿保存法の概要や保存可能な書類、そして実際の保存方法や手続きについてご紹介しました。
今後書類をペーパーレスにするのは、環境に優しい企業を目指してイメージアップを図るためにも重要になってきます。また書類電子化は社員の負担軽減や業務効率化にもつながるので、まだ実践していない場合はぜひ導入を進めていただければと思います。
ただし書類を電子化する際には電子帳簿保存法をよく理解した上で、しっかり準拠した内容で保存できるように前もって準備をしておきましょう。