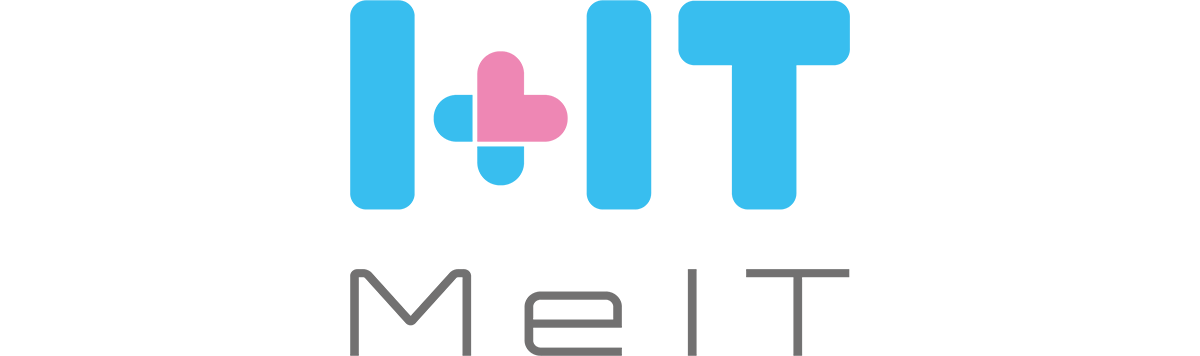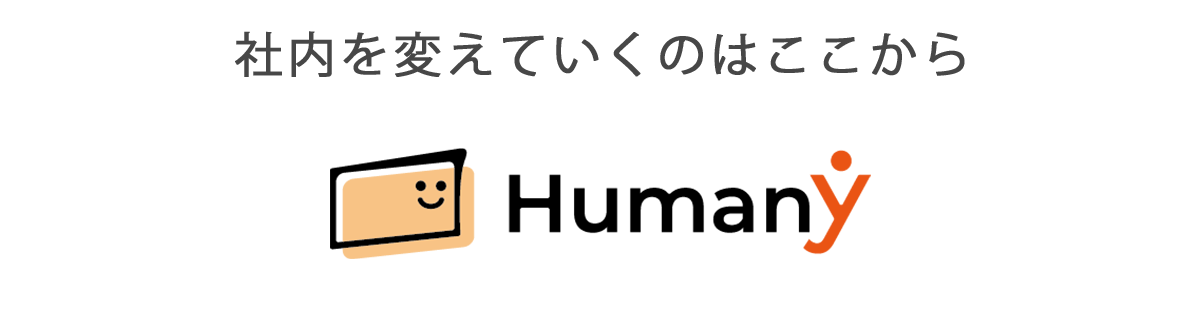ウェルビーイング経営と健康経営の違いとは?ウェルビーイング経営の取り組み事例を紹介
更新日:2023/06/16
ウェルビーイング経営と健康経営の違いとは?ウェルビーイング経営の取り組み事例を紹介


最近注目されている「ウェルビーイング経営」と「健康経営」。これらの取り組みとはどのようなものなのでしょうか。また、その違いについて解説します。そして、最後に「ウェルビーイング経営」の取り組み事例を挙げ、より深掘りしていきたいと思います。
「ウェルビーイング経営」とは?
ウェルビーイングとは?
ウェルビーイング(Well-being)とは、「身体的、精神的、社会的に、良好な状態であり、幸福に満たされた状態」を指す概念のことです。1946年にWHO(世界保健機構)が設立された際、憲章の一節に登場しており、近年再注目されているワードの一つです。
ウェルビーイング経営とは?
ウェルビーイング経営とは、ウェルビーイングの概念に基づき、誰もが働きやすいように組織の環境を整備し、従業員の健康増進や仕事への意欲向上を目的とした取り組みのことです。ウェルビーイング経営は「従業員の視点から施策を検討」します。ウェルビーイング経営を導入することで、働きやすく、明るい環境作りの実現に繋がります。それにより、様々なストレスが軽減され、従業員の満足度が高まります。その結果として、組織へのエンゲージメントが高まり、従業員の仕事に対するモチベーションやパフォーマンスの向上に繋がるのです。
「健康経営」とは?
「健康経営」とは、従業員の健康を企業の経営戦略の一環として位置づけ、企業の視点から施策を検討します。健康経営を導入することで、働きやすい環境を整え、従業員の心身の健康をサポートすることができます。そうすることで、生産性が上がり、結果として企業の成長に繋がります。
健康経営は、様々な企業に浸透しつつある取り組みです。また、健康経営に取り組む企業は、経済産業省の認証制度である「健康経営優良法人認定制度」に応募することができ、企業内外に働きやすさなどをアピールすることもできます。
「ウェルビーイング経営」と「健康経営」についてのまとめ
従業員の健康管理維持や改善を通じて、企業の生産性の向上を目的とする「健康経営」が浸透しつつありますが、近年では「健康」に留まらず、従業員のエンゲージメント向上や従業員の幸福度の向上なども含めた「ウェルビーイング経営」の概念に移行する傾向にあるようです。2020年以降のコロナ禍によりテレワークが普及したことや、価値観の変化、多様な働き方を望む声が多くなっている今、ウェルビーイング経営は非常に重要な取り組みになると言えるでしょう。
「ウェルビーイング経営」の取り組み事例
ここでは、心身の健康や労働環境、コミュニケーション関連、福利厚生といった面から、ウェルビーイング経営に向けた取り組み事例を紹介します。
心身の健康に関する取り組み事例
企業側は、従業員が自ら心身の健康状態を把握して改善・維持できるよう、セルフチェックやケアを行うなどの対応が重要です。また、ストレスチェックの実施、専門医との個別面談を実施するなど、メンタルヘルス対策も必要です。従業員が健康で、幸福度が高いことによって、仕事に対するパフォーマンスの向上などにも繋がります。
労働環境の改善に関する取り組み事例
現状を把握し、長時間労働や休日出勤といった、従業員に負担がかかるような労働環境であれば見直しが必要です。従業員の要望を取り入れ、対策を講じていくことが大切です。
【労働環境の改善例】
- 残業時間や休日出勤の見直し
- 有給を使用した休暇を申請しやすい職場の雰囲気作り
- テレワークなど、それぞれの働き方に合った環境作り など
このように、自社の状況や業務内容に合わせて、従業員が働きやすい環境を検討することが重要です。
コミュニケーションに関する取り組み事例
コミュニケーションを活性化させると、良好な人間関係を構築できる他、働きやすい環境作りやストレスの軽減にも繋がります。例えば、従業員同士が気軽にコミュニケーションを取れる場を作る、気軽に利用できるチャットやSNSツールを活用するなどです。従業員のコミュニケーションが円滑になれば、職場環境の改善、組織へのエンゲージメント向上にも繋がります。
福利厚生に関する取り組み事例
福利厚生を充実させることで、より働きやすい環境を作ることができます。
【具体例】
- 家賃補助や住宅手当の支給
- 社内食堂や食事面での補助
- 介護や育児と仕事との両立をサポートする制度や補助金の導入
- 資格取得の支援を行う など
活用できる福利厚生があっても、従業員が把握していないケースもあります。企業側は福利厚生に関する情報などを発信し、積極的に利用してもらえるようにすることが大切です。
ウェルビーイング経営に取り組み、組織全体の発展に繋げましょう!
現在は様々な価値観、働き方に関するニーズの多様化など、働く環境についての考える機会が多くなってきています。企業側は、労働環境などについて再確認することが必要となってくるのではないでしょうか。従業員の健康増進や仕事への意欲向上を目的とした「ウェルビーイング経営」を導入し、社内アンケートを活用するなど、従業員の声や要望を反映することで働きやすい環境作りを進め、組織全体の発展に繋げましょう。