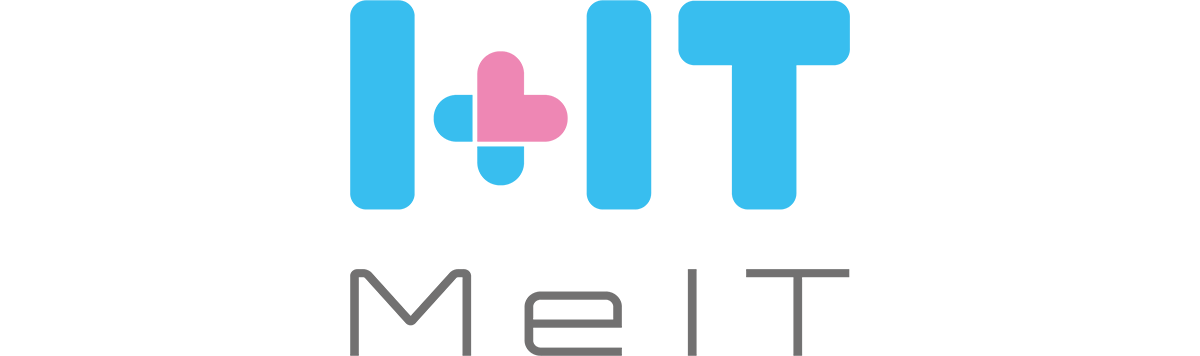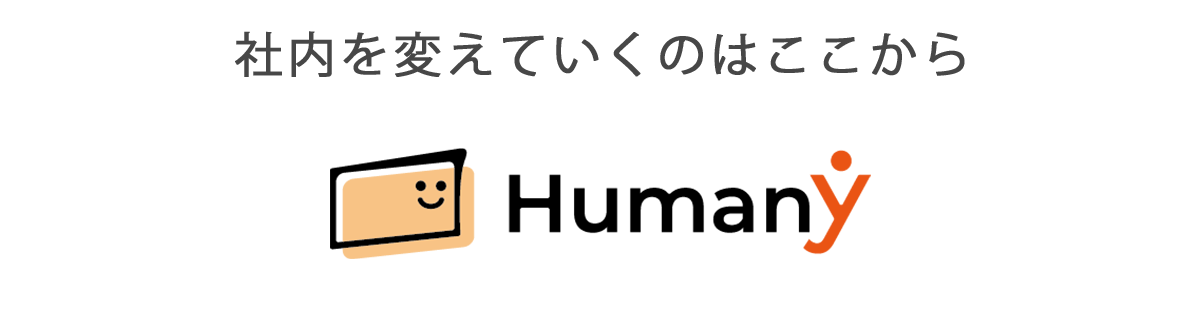今注目を集めているWell-being(ウェルビーイング)とは
更新日:2022/07/05
今注目を集めているWell-being(ウェルビーイング)とは


近今、企業では少子高齢化による労働人口の減少と多様な人材の活用であるダイバーシティが大きな課題となっています。そのため、働き方改革として企業は様々な背景を抱える人材を活用し、多数の仕事を効率よくこなせる体制構築に努めていかなければなりません。従業員のメンタルヘルスを経営課題と捉え、一人ひとりの生産性向上を図り持続可能な社会を目指す「健康経営」という手法を取り入れている企業もあります。しかし、今後ますます加速する労働力不足と人材育成に備えるためには、従業員の幸福を健康、精神だけではなく、労働という社会的な面においても満たすことで企業への満足度や生産性の向上を図る「ウェルビーイング」の考え方が大事になってきます。従業員の離職率を上げないためにも、従業員のメンタルヘルスを管理する立場の方は理解しておくと良いでしょう。ウェルビーイングの概要について解説していきます。
well-being(ウェルビーイング)とは?
「well-being」の言葉の意味は、「幸福」「健康」を指します。そこから、「ウェルビーイング」とは、その本人にとって最善な状態、自己利益にかなうものを実現した状態という意味合いで使われている言葉です。似た言葉では、「QOL(クオリティーオヴライフ)」がありますが、こちらは「人生・生活の価値」を意味します。どちらも「幸福」という意味では同じですが、QOLは「手段」、ウェルビーイングは「目的」として用いられることが多くあるでしょう。
健康の定義
1948年WHO(世界保健機関)憲章の定義によると、「健康とは、病気でないとか、弱っていないということではなく、肉体的にも、精神的にも、そして社会的にも、すべてが満たされた状態にあることをいいます」(日本WHO協会訳)とあります。したがって、ウェルビーイングも同じ定義に基づいて考えられています。
well-being(ウェルビーイング)が注目されている理由
様々な研究調査の結果から、自分の幸福度が高い従業員は創造的であり、高いパフォーマンスを発揮できることが分かっています。ゆえに、高い生産性を実現させることが可能です。そして、その「幸福」には身体の健康のみでなく、やりがい、生きがい、満足できる生活環境など、様々な面からの十分な満足が含まれています。心身ともに健康であることは、持続可能な社会の実現を目指す「健康経営」にも繋がります。メンタルヘルスの問題に取り組まずに放置しておいた場合、生産性が低下するとアメリカ精神医学会は指摘しています。また、雇用の流動化の進んだ現在、従業員の幸福度の低い職場は離職の要因ともなり、従業員の離職率低下を防ぐためにもウェルビーイングの考え方は重要になってくるのです。
少子高齢化による深刻な労働力不足
近年労働力不足が問題になっていますが、今後その問題はますます深刻化していくでしょう。労働力を提供する労働人口は減っていくにもかかわらず、全体的に企業の求人は増えており、アンバランスな状況にあります。また、業務も多岐にわたり従業員一人当たりの業務量も当然多くなります。そのため、人材定着の環境作りには、従来の給与と待遇引き上げだけではなく、ウェルビーイングという考え方が大切になってきます。
一人ひとりの従業員の生産性向上は、どこの企業にとっても重要な課題です。顧客からの要求は厳しく多忙になり、予算は低く、人材の獲得も難しくなっていくとなると、従業員それぞれの処理能力や質を高めていくしかありません。少ない資源で最大限の成果を上げていくしかないのです。かつては従業員の健康管理は「コスト」と認識されていましたが、昨今では従業員の健康管理は投資であり、長期的な企業の維持発展や持続可能な社会の実現を目指す健康経営を重要視する経営方針が強まっています。企業に貢献する生産性の高い人材は大変貴重であり、そうした人材を守っていくためにもウェルビーイングの必要性はますます強くなることでしょう。
ダイバーシティの推進と、コミュニケーションの必要性が高まる
従業員それぞれの背景が違い、考え方が違い、幸福についても違う、けれどもそれぞれの「幸せ」の状態に寄り添っていく必要が今後あります。人種や哲学、宗教、性別、ワークスタイルなどに捉われず、コミュニケーションを円滑にしていくために必要なのがウェルビーイングといえるでしょう。時代の変化が速いなか、従業員が心身ともに健康であることを大切にする企業が増えていることも注目される要因でもあります。
SDGsや働き方改革の推進
2030年までの持続的な開発目標である「SDGs」ですが、17の目標のうち3つ目の目標に「すべての人に健康と福祉を」という項目があり、この目標は企業がウェルビーイングに取り組むべき指針となっています。そして、国をあげて働き方改革が推進されるようになったこともウェルビーイングが企業に注目される理由でもあります。個人個人のワークライフバランスの実現は経営課題の一つとなっており、ウェルビーイングの重要性が増しています。
well-being(ウェルビーイング)のメリット
生産性向上
ウェルビーイングを取り入れるメリットは職場が安心できる環境として機能することです。また、従業員一人ひとりが仕事にやりがいを感じ、意欲的になり、結果的に実務に積極的になります。モチベーションアップが期待でき、従業員のワークエンゲージメント、仕事に対する熱意が高まり、企業全体の生産性の向上が見込めるのです。
離職率低下、優秀な人材確保
多様な働き方、それぞれのワークライフバランスが実現します。職場の雰囲気が良くなることにより、互いに思いやる余裕が生まれるでしょう。人間関係は円滑になり、従業員同士の関係性が良くなれば、会社への帰属意識が高まります。また、多様な人材と協働することでより一層高度な目標の達成が期待できます。その結果、離職率は低下することでしょう。この職場で長く働きたいと思う従業員が在籍していることは「ウェルビーイングに積極的に取り組む企業である」という前向きなイメージを持ってもらえるメリットです。企業のブランド力を向上させ、より一層優秀な人材確保につながるでしょう。社外的なイメージは良くなり、採用活動にも好影響を及ぼし、良い人材が集まりやすくなります。
健康経営推進
「健康経営」とは、経営心理学者であるロバート・H・ローゼン著「The Healthy Company」が始まりとされています。従業員の健康増進を重視し、健康管理を経営的な視点で捉え、戦略的に実践を測ることで、従業員の健康の維持・増進と企業の生産性向上を目指す手法です。近年では、将来的な労働力人口の減少を見越した人的生産性の向上と多様な背景を持つ人材の活用が企業の課題となっており、企業の従業員への健康配慮の必要性が高くなっています。ウェルビーイングを進めることは、先に注目されていた「健康経営」にもつながることでしょう。従業員の活力向上や企業の活性化を促し、結果的に企業へ利益をもたらします。
well-being(ウェルビーイング)達成の5つの要素
アメリカに本社を持つ世論調査企業のギャラップ社が定義するウェルビーイングの5つの指標というものが存在します。ギャラップ社は世界150カ国における調査により、5つの要素を定義しました。
キャリアウェルビーイング(Career Wellbeing)
キャリアの幸福のことですが、生計を立てる仕事だけに限りません。キャリアウェルビーイングは、自分の人生において、奉仕活動や勉強、趣味を意味します。他にも家事や介護、子育てなど一日の大半の時間を費やしているものへの幸福を指します。
ソーシャルウェルビーイング(Social Wellbeing)
ソーシャルウェルビーイングは、人間関係において幸せを感じる関係性をどれだけ作り上げているかを指します。人間関係の幸福ですが、その関係はたくさんの友人関係ではなく、数は少なくとも信頼できる関係であるかです。愛情のある関係性を築けていることを意味します。
フィナンシャルウェルビーイング(Financial Wellbeing)
フィナンシャルウェルビーイングは、経済的な幸せのことです。収入を得る手段があるのか、得られる報酬への満足感はあるのかという、経済面での幸福を指します。安心できる生活のため、資産の管理や運用状態の幸福がきちんと得られているのかも大切です。
フィジカルウェルビーイング(Physical Wellbeing)
フィジカルウェルビーイングは、身体的幸福を表します。心身ともに健康な状態にあり、体のみならず、心も健康であるかが重要となります。ポジティブな感情を持ち、自分のやりたいことやすべきことが、不自由なく活動できる状態であるかを指します。フィジカルウェルビーイングは、企業から受ける影響が大きく、メンタルヘルスの代表例です。
コミュニティウェルビーイング(Community Wellbeing)
コミュニティウェルビーイングは、地域のコミュニティの幸福のことです。仕事やプライベートに限らず、身近な関係性について深く関わり、親密であるかを指します。企業での関係性形成の意味合いもあり、コミュニティでつながっている感覚があるかが大切です。
well-being(ウェルビーイング)はメンタルヘルス対策においても重要
企業において従業員の健康を守っていくことは、SDGsや働き方改革を進める日本でも今後重視していきたい課題です。従業員の仕事への意欲の改善や、働きやすい環境作り、健康経営、福利厚生の充実は、企業の持続可能な発展と生産性向上のためにも必要となっていきます。そして、それを実現するのがウェルビーイングという概念です。メンタルヘルス対策を行う立場である人はウェルビーイングの考え方を取り入れてはいかがでしょうか。