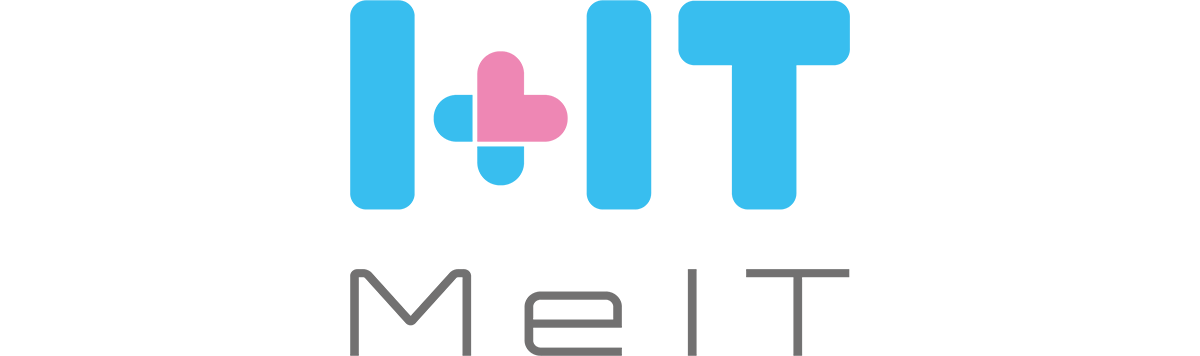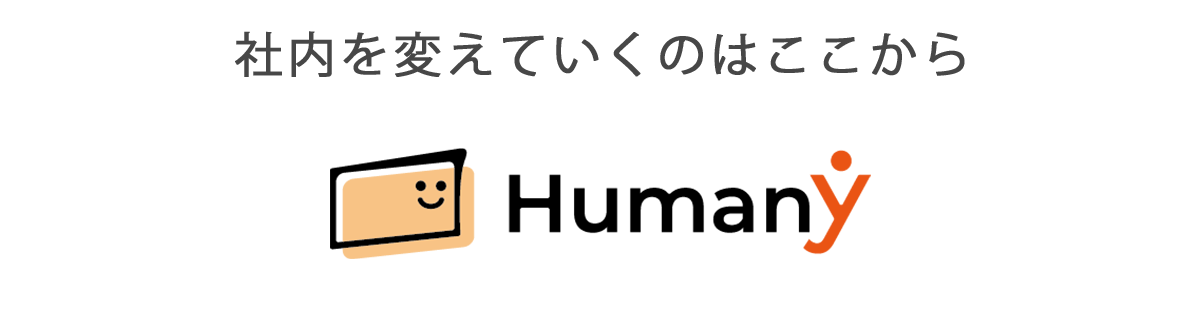【人事担当者必見】メンタルヘルスの一次予防・二次予防・三次予防とは?
更新日:2022/02/04
【人事担当者必見】メンタルヘルスの一次予防・二次予防・三次予防とは?


厚生労働省が発表した「職場におけるメンタルヘルス対策について」によると、強い不安や悩み、ストレスを抱えている労働者の割合は59.5%です(平成28年)。強い不安や悩み、ストレスは、過労死やうつ病などを引き起こす恐れがあるため適切に対処しなければなりません。メンタルヘルス対策として取り組まれているのが、心の健康に関する一次予防、二次予防、三次予防です。具体的に、どのような取り組みを指すのでしょうか。
労働災害防止計画におけるメンタルヘルス対策の位置づけ
厚生労働省では、労働災害を防止するための主要な対策などをまとめた労働災害防止計画を定めています。現在運用されているのは、2018~2022年度までの5カ年を計画期間とする第13次労働災害防止計画です。第13次労働災害防止計画の目標の中には、メンタルヘルスに関するものがあります。具体的には、メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業場の割合を80%以上にする、ストレスチェック結果を活用する事業場の割合を60%以上にするなどが掲げられています。事業場におけるメンタルヘルス対策として挙げられるのが、心の健康に関する一次予防、二次予防、三次予防です。これらを総合的に進めることで、国はメンタルヘル不調に対処しようとしています。
一次予防・二次予防・三次予防とはどのようなものなのでしょうか。
メンタルヘルス対策の一次予防とは
メンタルヘルス対策の一次予防は、メンタルヘルス不調の未然防止を指します。
一次予防は、積極的な健康の保持増進を意味するヘルスプロモーション、仕事による健康障害の防止を意味するヘルスプロテクションを含む取り組みです。
ヘルスプロモーションは、メンタルヘルスについての正しい知識の提供、ストレスに気づく方法、ストレスに対処する方法、良好な人間関係を構築する方法などの研修、事業場内外における相談窓口の整備などの取り組みを指します。ヘルスプロテクションは、労働時間・労務管理・評価制度など、労働者のメンタルヘルスに影響を与える事業場内の要因を見直し、必要に応じて改善する取り組みです。これらを通して、労働者がメンタルヘルスの決定要因に気づき、改善できるようにサポートします。
また、一次予防では、セルフケア・ラインケアが継続的かつ計画的に行われる環境を構築することも欠かせません。ラインケアは、職場のライン上で提供されるケア、つまり管理職が部下のメンタル不調に気づき必要なケアを提供できることを意味します。メンタルヘルス不調は、本人も自覚しないまま悪化することがあります。したがって、ラインケアも重要なメンタルヘルス対策といえます。ラインケアは、管理職に任せておけば機能するわけではありません。有効に機能させるため、管理職を対象とするラインケア研修の導入などが必要です。
一次予防に位置付けられるストレスチェック
一次予防に位置付けられているメンタルヘルス対策のひとつがストレスチェックです。
平成27年に労働安全衛生法の一部を改正する法律が施行されたことで、常時50人以上の労働者を使用する事業場は年1回のストレスチェック実施を義務付けられました。ストレスチェックは、ストレスに関する質問票を用いて労働者のストレス状態を調べる検査です。ストレスチェックにより、メンタルヘルス不調の未然防止を強化できます。未然防止を強化できる理由は、過度なストレスがかかっている労働者の仕事を軽減する、申し出があった労働者に対し医師による面接指導を実施するなどの対策を講じられるからです。また、集団分析を実施することで職場環境の改善も実現できます。なお、ストレスチェックの実施状況などは、労働基準監督署に実施の都度報告しなければなりません。
メンタルヘルス対策の二次予防とは
メンタルヘルス対策の二次予防は、メンタルヘルス不調の早期発見ならびに早期治療を意味します。具体的には、上司や産業保健スタッフなどによる相談対応、定期健康診断による早期発見と適切な対応などが該当します。
また、二次予防でも、一次予防のヘルスプロモーションと同じ取り組みを求められます。
つまり、労働者と管理職へ向けてメンタルヘルスに関する正しい知識の提供、事業所内外における相談窓口の設置などを実施します。同様に、メンタルヘルス不調に気づいた労働者や管理職が適切に対応できるように相談窓口を周知しておくことも欠かせません。相談窓口がわからないと、メンタルヘルス不調に気づいても適切に対応できないからです。事業場に産業保健スタッフが在籍している場合は、産業保健スタッフが最初の相談窓口になるケースが多いでしょう。産業保健スタッフが在籍していない場合は、労働者が気軽に相談できるバックヤード部門などに相談窓口を設置するケースが多いといえます。基本的には、相談を受けた産業保健スタッフなどが医師につなげるなどの対応をすることになります。
二次予防では、セルフケア・ラインケアだけにとどまらず、事業場内産業保健スタッフなどによるケア、事業場外資源によるケアを組み合わせてメンタルヘルスケアに取り組むことが重要です。
メンタルヘルス対策の三次予防とは
メンタルヘルス対策の三次予防は、メンタルヘルス不調で休職している労働者の職場復帰支援ならびにメンタルヘルス不調の再発防止を指します。具体的には、休職している労働者への精神的なフォロー、職場復帰支援プログラムの実施、メンタルヘルス不調で休職している労働者の主治医との連携、管理職に対する職場復帰時における対応研修などが該当します。なお、職場復帰支援についての取り組みは、厚生労働省が発表している「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」を参考にすることができます。
メンタルヘルス不調は再発しやすいトラブルといえます。メンタルヘルス不調が再発すると、離職する労働者が多くなっていきます。三次予防も、一次予防、二次予防と同じく重要なメンタルヘルス対策といえるでしょう。三次予防でも、セルフケア・ラインケア・事業場内産業保健スタッフなどによるケア・事業場外資源によるケアを計画的・統合的に展開して、メンタルヘルス不調で休職している労働者の職場復帰を支援することなどが重要です。
メンタルヘルス対策で働きやすい職場を実現
メンタルヘルス対策は、一次予防・二次予防・三次予防にわかれます。一次予防の役割はメンタルヘルス不調の未然防止、二次予防の役割はメンタルヘルス不調の早期発見ならびに早期治療、三次予防の役割は職場復帰支援ならびにメンタルヘルス不調の再発防止です。これらに取り組むことで働きやすい職場を実現できる可能性が高まります。また、労働生産性も高まると考えられます。メンタルヘルス対策を講じていない事業場は、心の健康に関する一次予防・二次予防・三次予防に取り組みましょう。