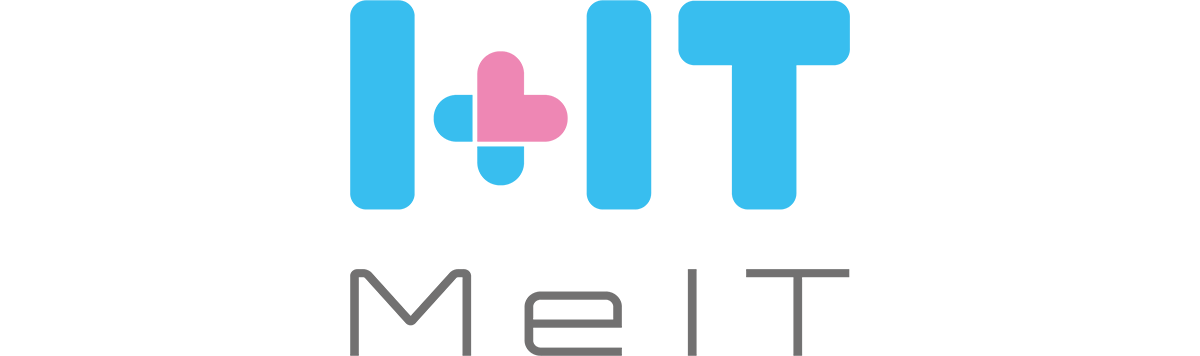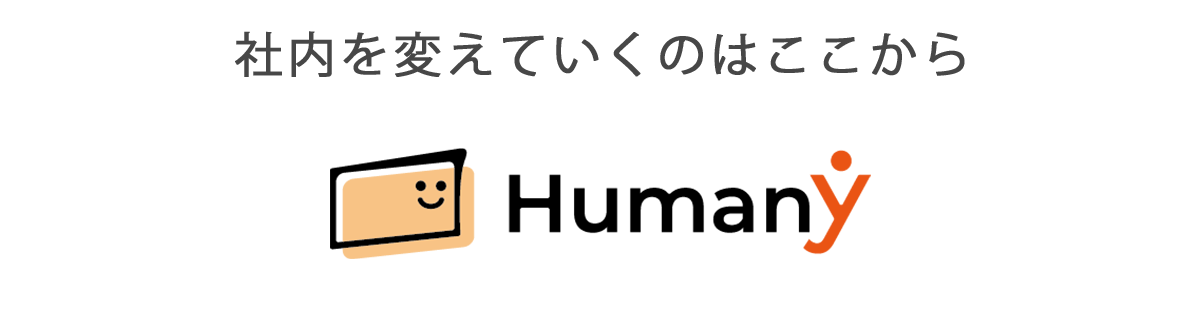ハラスメントとは?意味や種類、法律、対処法まで網羅的に解説
公開日:2021/09/07
更新日:2025/10/03

本記事では「ハラスメント」の意味や種類、関連法規、対処法まで網羅的に解説します。パワハラやセクハラなど職場における代表的なハラスメントを一覧で紹介し、判断基準となる「指導」との境界線も明らかにします。ハラスメント対策を進めるにあたり、基本事項を押さえましょう。
ハラスメントの基本的な定義とは
ハラスメント(Harassment)とは、日本語で「嫌がらせ」や「いじめ」を意味する言葉です。特定の相手に対して、意図的であるか否かにかかわらず、不快感や不利益を与え、その尊厳を傷つけるあらゆる言動を指します。職場や学校、地域社会など、さまざまな人間関係の中で発生しうる社会問題として広く認識されています。
とくに職場におけるハラスメントは、従業員の心身の健康を害し、働く意欲を低下させ、休職や離職につながるだけでなく、企業の生産性低下や社会的信用の失墜にも関わる重要な経営リスクです。そのため、労働施策総合推進法(パワハラ防止法)により職場内ハラスメントの対策義務化が図られるなど、国を挙げた対策が進められています。
判断基準は「相手が不快と感じたか」
ハラスメントが成立するかどうかの最も基本的な判断基準は、行為者の意図ではなく、その言動を受けた相手が「不快と感じたか」「尊厳を傷つけられたと感じたか」という点にあります。
たとえ「激励のつもりだった」「冗談のつもりだった」といった弁明があったとしても、受け手が精神的・身体的な苦痛を感じれば、それはハラスメントに該当する可能性があります。このように、行為者の自覚の有無は問われません。ただし、個人の主観だけでなく、その言動が行われた状況や背景、社会的な常識などを踏まえ、「平均的な労働者の感じ方」を基準に客観的に判断される側面もあります。
「指導」と「ハラスメント」の境界線はどこにある?
職場でとくに問題となりやすいのが、業務上必要な「指導」と「パワーハラスメント(パワハラ)」の境界線です。部下の成長を促すための注意や指導は、企業活動において不可欠ですが、その方法や内容が度を超えるとハラスメントと見なされます。
厚生労働省は、職場におけるパワーハラスメントを「優越的な関係を背景とした言動」「業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの」「労働者の就業環境が害されるもの」という3つの要素をすべて満たすものと定義しています。このうち、「業務上必要かつ相当な範囲を超えているか」が、指導とハラスメントを分ける重要なポイントとなります。具体的な違いは以下のとおりです。
| 観点 | 適正な指導 | ハラスメント(パワハラ) |
|---|---|---|
| 目的 | 業務上の課題改善や、本人の成長を促すこと。 | 相手に精神的・身体的苦痛を与えたり、退職に追い込んだりすること。または、目的が正当でも手段が不適切であること。 |
| 言動 | 客観的な事実に基づき、具体的かつ建設的な表現で伝える。人格や尊厳を傷つけない。 | 人格を否定する暴言、脅迫、他の従業員の前での執拗な叱責、プライベートへの過度な干渉など。 |
| 影響 | 相手の成長やスキルアップにつながり、就業意欲が向上する。 | 相手が萎縮し、心身に不調をきたす。職場全体の雰囲気が悪化し、生産性が低下する。 |
【一覧】職場における代表的なハラスメントの種類
一言でハラスメントといっても、その種類は多岐にわたります。職場においては、パワーハラスメントやセクシュアルハラスメントが広く知られていますが、それ以外にも注意すべきハラスメントは数多く存在します。ここでは、職場における代表的なハラスメントの種類とその内容について解説します。
【関連記事:メンタルヘルス×組織開発で生産性向上!企業の成長を促す最強戦略】
パワーハラスメント(パワハラ)
パワーハラスメント(パワハラ)とは、同じ職場で働く者に対し、職務上の地位や人間関係などの優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて精神的・身体的苦痛を与えること、または職場環境を悪化させる行為を指します。上司から部下への行為が典型的ですが、専門知識の優位性などを背景とした部下から上司への言動や、同僚間のいじめなどもパワハラに該当する場合があります。
6つの類型
厚生労働省は、職場のパワーハラスメントの代表的な言動の類型として、以下の6つを挙げています。これらの行為は、単独だけでなく複数が組み合わさって行われることもあります。
| 類型 | 内容と具体例 |
|---|---|
| 身体的な攻撃 | 殴る、蹴るなどの暴行を加えること。物を投げつける行為も含まれる。 |
| 精神的な攻撃 | 人格を否定するような発言や、他の従業員の前で大声で威圧的に叱責するなど、脅迫や名誉毀損、侮辱にあたる言動を行うこと。 |
| 人間関係からの切り離し | 特定の従業員を意図的に無視したり、別室に隔離したり、仕事を与えずに孤立させること。 |
| 過大な要求 | 業務上明らかに不要なことや、遂行不可能な業務を強制すること。新入社員に必要な研修を行わず、到底対応できないレベルの業務目標を課すことなどが該当する。 |
| 過小な要求 | 本人の能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや、仕事を与えないこと。営業職の社員に草むしりだけをさせる、といった例が挙げられる。 |
| 個の侵害 | プライベートな事柄に過度に立ち入ること。交際相手について執拗に尋ねたり、個人のSNSを監視したりする行為が該当する。 |
部下から上司への「逆パワハラ」にも注意
パワハラは上司から部下へ行われるものというイメージが強いものですが、近年では部下から上司への「逆パワハラ」も問題となっています。部下が集団で上司の指示を無視したり、SNSなどで上司を誹謗中傷したりする行為がこれにあたります。業務経験やITスキルなどの知識の優位性を背景に行われるケースも見られます。
【関連記事:ハラスメント相談窓口の設置・運用ガイド|企業が取るべき対策と注意点】
セクシュアルハラスメント(セクハラ)
セクシュアルハラスメント(セクハラ)とは、相手の意に反する性的な言動により、労働者が不利益を受けたり、就業環境が害されたりすることを指します。労働施策総合推進法や男女雇用機会均等法で事業主の防止措置が義務付けられており、性別に関わらず誰もが被害者・加害者になり得ます。セクハラは、主に「対価型」と「環境型」の2種類に分けられます。
対価型セクハラとは
対価型セクハラは、労働者の意に反する性的な言動に対する反応によって、その労働者が解雇、降格、減給などの不利益を受けることです。職場での地位や権限を利用して、性的な関係を強要し、拒否した相手に不利益な人事評価を行うといったケースが典型例です。
環境型セクハラとは
環境型セクハラは、性的な言動によって職場の環境が不快なものとなり、労働者の能力発揮に重大な悪影響が生じることです。職場にヌードポスターを掲示する、性的な冗談を繰り返す、不必要に身体に触れるといった行為が該当し、従業員の意欲低下や離職の原因にもなります。
カスタマーハラスメント(カスハラ)
カスタマーハラスメント(カスハラ)とは、顧客や取引先などからのクレームのうち、要求の内容や態様が社会通念に照らして著しく不当であり、従業員の就業環境を害する行為を指します。具体的には、従業員に対する暴言、威嚇、土下座の要求、長時間の拘束、SNSでの誹謗中傷などが挙げられます。従業員の心身の健康を守るため、企業として毅然とした対応が求められます。
マタニティハラスメント(マタハラ)
マタニティハラスメント(マタハラ)とは、職場において妊娠・出産、育児休業などの利用を理由として行われる嫌がらせや不利益な取り扱いのことです。「妊娠したなら辞めるべきだ」といった心無い言葉を浴びせたり、妊娠を報告した従業員を意図的に業務から外したりする行為が該当します。男女雇用機会均等法および育児・介護休業法などで禁止されています。
モラルハラスメント(モラハラ)
モラルハラスメント(モラハラ)は、言葉や態度、身振りなどによって、相手の人格や尊厳を傷つける精神的な暴力を指します。パワハラが職務上の優位性を背景にすることが多いのに対し、モラハラは同僚間や部下から上司へなど、あらゆる関係性で起こり得ます。無視や陰口、プライベートへの過剰な干渉など、目に見えにくい形で継続的に行われることが多く、被害者を精神的に追い詰める深刻な問題です。
その他に注意すべきハラスメント
上記以外にも、職場ではさまざまなハラスメントが問題となる可能性があります。以下にその一部を紹介します。
- アルコールハラスメント(アルハラ):飲酒の強要や、飲めない人への配慮を欠く言動など、アルコールに関する嫌がらせ。
- 時短ハラスメント(ジタハラ):具体的な業務改善策を示さずに残業を禁止し、従業員に過度な負担を強いること。
- リモートハラスメント(リモハラ):テレワーク環境下で、オンライン会議の背景や私生活について過度に詮索したり、常時接続を強要したりする行為。
【関連記事:「優秀な人ほど辞めていく」現象をデータで裏付け。離職を防ぐ本当のポイント【調査結果】】
ハラスメントに関する法規制「パワハラ防止法」を解説
ここでは、すべての企業に適用される「パワハラ防止法」について、その概要と企業に課せられる義務、そして法律上のパワハラの定義をくわしく解説します。
パワハラ防止法とは?対象と企業の義務
パワハラ防止法とは、正式名称を「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(労働施策総合推進法)」といい、職場におけるパワーハラスメント対策を事業主に義務付ける法律です。2020年6月1日に大企業を対象に施行され、2022年4月1日からは中小企業を含むすべての企業で義務化されました。
この法律により、事業主はパワハラ防止について以下の措置を講じることが義務付けられています。
| 措置の分類 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 方針の明確化と周知・啓発 |
|
| 相談体制の整備 |
|
| 事後の迅速かつ適切な対応 |
|
| 併せて講ずべき措置 |
|
法律上のパワハラと認定される3つの要件
パワハラ防止法では、職場におけるパワーハラスメントを、以下の3つの要素をすべて満たすものと定義しています。業務上の注意や指導がすべてパワハラに該当するわけではなく、この3つの要件に照らして客観的に判断されます。
- 優越的な関係を背景とした言動
職務上の地位が上位の者による言動が典型的だが、専門知識や経験、人間関係の優位性、集団による行為なども含まれる。部下から上司への言動も該当する場合がある。 - 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
社会通念に照らし、その言動が明らかに業務上必要ない、またはその態様が相当でないものを指す。たとえば、人格を否定するような暴言や、必要以上の長時間にわたる叱責などが該当。 - 労働者の就業環境が害されるもの
その言動により労働者が身体的または精神的に苦痛を与えられ、職場環境が不快なものとなったために能力の発揮に重大な悪影響が生じるなど、その労働者が就業するうえで看過できない程度の支障が生じることを指す。
逆に言えば、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導は、パワーハラスメントには該当しません。
パワハラ防止法に違反した場合の罰則は?
パワハラ防止法には、事業主が防止措置を講じなかった場合に直接科される罰金などの罰則規定はありません。しかし、これは対策を怠って良いという意味ではありません。
ハラスメントの事実を放置したり、対策が不十分であったりする場合、厚生労働大臣が必要と認めれば、事業主に対して助言、指導、または勧告が行われることがあります。そして、その勧告に従わなかった場合には、企業名が公表される可能性があります。
企業名が公表されれば、社会的信用が失墜し、顧客離れや採用活動への悪影響など、事業に深刻なダメージを与える可能性があります。罰則がないからといって軽視せず、法律の趣旨を理解し、実効性のあるハラスメント対策を講じることが企業には求められています。
企業が取り組むべきハラスメント防止対策
企業が具体的に取り組むべき措置について、厚生労働省の指針で大きく3つの柱が示されています。
| 措置の柱 | 主な取り組み内容 |
|---|---|
| 方針の明確化と周知・啓発 | 就業規則への規定、社内広報、研修の実施 |
| 相談体制の整備 | 相談窓口の設置、プライバシー保護、不利益な取り扱いの禁止 |
| 事後の迅速かつ適切な対応 | 事実関係の調査、被害者・加害者への措置、再発防止策 |
以下では、これらの措置について具体的に解説します。
ハラスメントに関する方針の明確化と周知・啓発
まず企業は、職場におけるハラスメントは一切許さないという断固たる方針を明確に示し、それを全従業員に周知・啓発する必要があります。具体的には、就業規則や服務規律にハラスメントの内容、禁止事項、そしてハラスメントを行った者に対する懲戒処分の方針を明記します。これにより、何がハラスメントにあたるのか、そしてそれが処分の対象となることを全社的なルールとして確立します。
さらに、その方針を社内報やポスター、イントラネットなどを通じて継続的に発信し、従業員の意識を高めることが重要です。定期的な研修の実施も欠かせません。管理職向けには部下の言動をマネジメントする視点を、一般従業員向けにはハラスメントの基礎知識や相談窓口の利用方法などを伝え、組織全体のハラスメントに対するリテラシーを向上させます。
相談体制の整備とプライバシーの保護
ハラスメントが発生してしまった場合に、被害者が安心して相談できる体制を整えることも企業の重要な義務です。相談窓口をあらかじめ設置し、すべての従業員にその存在を周知しなければなりません。
相談窓口は、人事部門だけでなく、信頼できる外部の専門家へ委託することも有効です。また、対面だけでなく電話やメールなど、複数の相談方法を用意することで、従業員が利用しやすい環境を整えることが求められます。相談担当者には、内容を傾聴し、中立的な立場で対応するスキルが必要です。
最も重要なのは、相談者や事実確認に協力した人のプライバシーを厳守すること、そして相談したことを理由に解雇や降格などの不利益な取り扱いをしないことです。これらの点は法律でも固く禁じられており、企業は保護措置を講じていることを明確に従業員へ伝える必要があります。
【関連記事:【中小企業向け/専門家監修】離職を防ぐ従業員相談窓口の構築と運用ポイント】
事後の迅速かつ適切な対応と再発防止策
実際にハラスメントの相談が寄せられた場合、企業は迅速かつ適切に対応する義務を負います。まずは中立的な立場で、相談者と行為者の双方から事実関係を正確に確認します。必要に応じて、第三者からもヒアリングを行い、客観的な証拠を集めます。
事実関係が確認できた後は、被害者の状況や意向を尊重し、配置転換や行為者からの隔離といった適切な配慮措置を講じます。一方、加害者に対しては、就業規則に基づいて厳正に処分します。処分が軽すぎれば再発のおそれがあり、重すぎれば不当処分として訴えられるリスクもあるため、事案に応じた慎重な判断が求められます。
対応が完了した後も、同様の事案が二度と起こらないよう、再発防止策を講じることが不可欠です。プライバシーに配慮した形での事案の社内共有や、研修内容の見直し、定期的なアンケート調査による実態把握などが有効な手段となります。
従業員が加害者にならないために気をつけるべきこと
ハラスメント防止は、企業のしくみづくりだけでなく、従業員一人ひとりの意識も重要です。職場では、従業員が加害者にならないために、以下の点を啓発していく必要があります。
- 正しい知識を持つ:どのような言動がハラスメントに該当するのかを正しく理解する。
- 価値観の多様性を認める:自分にとっては「当たり前」でも、相手にとっては不快かもしれないという想像力を持つ。
- アンコンシャス・バイアス(無意識の偏見)に気づく:「男だから」「女だから」「若手だから」といった無意識の思い込みが、不用意な発言につながることを自覚する。
- コミュニケーションを見直す:業務上の指導であっても、人格を否定するような言葉遣いや、大勢の前での叱責は避ける。
従業員一人ひとりがお互いを尊重し、良好なコミュニケーションを心がけることが、ハラスメントのない健全な職場環境の基盤となります。
働きやすい職場づくりはハラスメントに関する理解促進から
本記事では、ハラスメントの定義から、パワハラやセクハラといった代表的な種類、パワハラ防止法などの法規制、そして企業が講じるべき対策まで網羅的に解説しました。ハラスメントの判断基準は、相手が不快と感じたかどうかが重要です。
企業には防止措置が法律で義務付けられており、働く一人ひとりが正しい知識を持つことが、加害者にも被害者にもならないための第一歩となります。誰もが尊重される職場環境を目指しましょう。