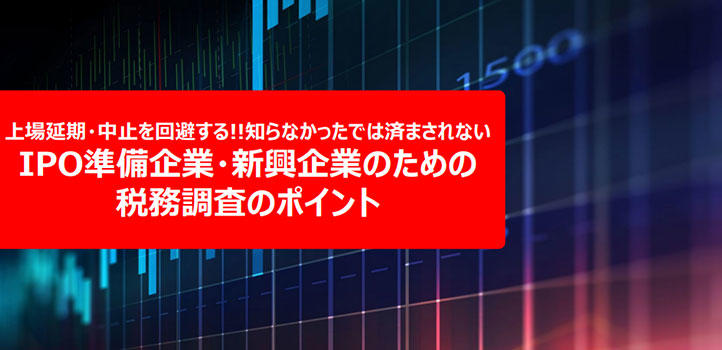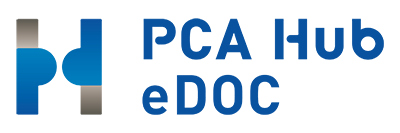電子帳簿保存法改正で、税務調査に与える“本当の”影響とは?
更新日:2022/01/21
電子帳簿保存法改正で、税務調査に与える“本当の”影響とは?


改正電子帳簿保存法、異例の急遽2年猶予へ
2年猶予となる「やむを得ない事情」とは?
報道ベースでは、「2年猶予が当然」という論調ですが、実はこの2年猶予は、無条件に認められる訳ではなく、「やむを得ない事情」がある場合に認められ(条件①)、かつ、「将来の税務調査で電子データの出力書面提出の求めに応じる」(条件②)ことが条件とされています。
この2年猶予の詳細は、実は2021年の【年末に】国税庁から発表されています。数日後に延期措置が始まるギリギリのタイミングで、詳細が発表されてるということも異例ですが、その内容もまた異例なものになっています。
すなわち、通常は法令において「やむを得ない事情」が用いられる場合、「自己の責めに帰すことができない事情」を意味し、自己に起因する状況は認められない等の一定のハードルが設けられています。
これに対し、今回の2年間の猶予の条件①の「やむを得ない事情」とは、「保存要件に従って電子取引データの保存を行うための準備を整えることが困難であること」をいうとされています。
国税庁・電子帳簿保存法取扱通達抜粋
7-10 宥恕措置における「やむを得ない事情」の意義
7-10 (中略)
「やむを得ない事情」とは、電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存に係るシステム等や社内でのワークフローの整備未済等、保存要件に従って電磁的記録の保存を行うための準備を整えることが困難であることをいう。
これは、通常、この法令用語上、同一の用語(例:やむを得ない事情)に関しては、同一の意味を持たせる(例:自己の責めに帰すことができない事情)べきところ、今回の改正ではその原則を歪めて、かなり広く認められているという点は特筆すべき点です。
ここに、国税庁が当初振り上げた拳を、どのように降ろそうか(撤回しようか)と苦慮した様子が垣間見えます。
電子取引の範囲と、保存方法は、どうなっているのか?
電子取引の範囲とは?
電子取引の範囲には、以下が列挙されています。
国税庁・電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】問4抜粋
(1)電子メールにより請求書や領収書等のデータ(PDFファイル等)を受領
(2)インターネットのホームページからダウンロードした請求書や領収書等のデータ(PDFファイル等)又はホームページ上に表示される請求書や領収書等のスクリーンショットを利用
(3)電子請求書や電子領収書の授受に係るクラウドサービスを利用
(4)クレジットカードの利用明細データ、交通系ICカードによる支払データ、スマートフォンアプリによる決済データ等を活用したクラウドサービスを利用
(5)特定の取引に係るEDIシステムを利用
(6)ペーパーレス化されたFAX機能を持つ複合機を利用
(7)請求書や領収書等のデータをDVD等の記録媒体を介して受領
これらに含まれる取引情報を一定の要件に従って保存しないといけない訳ですが、取引情報の定義がかなり広く、「取引に関して受領し、又は交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項」とされています。
また、原則として、経理部を含む、全ての部署(例:販売、購買、在庫契約、債権管理、債務管理、経費精算を行う部署)の取引情報が対象となります。
このため、実務上は非常に煩雑になることが予想されます。
この点、特に実務上、悩ましいのは、従業員の立替経費精算に関する電子取引データ保存と考えられます。
従業員が旅費交通費等の立替経費を支払った際の領収書データをPCやスマホに保存しておく処理も認められます。
しかしながら結局、会社が当該データを従業員から受け取り、7年(最長10年)保存することになります。
ここは、いかに効率的に会社でデータを受取り、保存しておく仕組みを作れるかがポイントになると思います。
電子取引データ保存方法
電子取引に該当する取引を行った場合、その保存方法には、ただ電子取引データを保存すればよい訳ではなく、一定の要件(真実性、可視性等)に従う必要があります。
要件のうち重要なものとして、①真実性(電子取引データが改ざんできないことを証明できるようにしておく)と、②可視性(電子取引データを検索可能な状態にしておく)があります。
さらに可視性の要件の詳細として、ⅰ)取引先・日付・金額での検索、ⅱ)日付・金額での範囲指定検索、ⅲ)2以上の任意の記録項目での組合せ検索、という3種類の検索が行えるようにしないといけないという要件があります。
ただし、上記ⅱ)とⅲ)の検索機能については、税務調査時に調査官から電子取引データのダウンロードの求めに応じることを条件に緩和(免除)されています。
2024年以降の税務調査に与える影響はどうなるのか
ダウンロードの求めという新論点
前述のとおり、電子取引データ保存の可視性要件には、3つの検索条件があり、そのうち2つ(ⅱ)範囲指定検索とⅲ)組合せ検索)は、税務調査で調査官からのダウンロードの求めに応じることにより、緩和されています(ⅱとⅲの検索は不要となる)。
この緩和措置は一見望ましいように見えますが、実は税務調査では不利になる要素になります。なぜならば、場合によっては調査官にPCの中も見られてしまうからです。
ダウンロードされても、隅から隅まで見られても何も痛いところがないという会社はごく僅かですから、その影響は大きいものになると考えられます。
青色申告取消しの可能性は?!
2021年7月頃、改正電帳法に係る国税庁Q&Aで青色申告取消の可能性に言及されました。
この反響は大きく、その後2021年11月頃、国税庁は騒動の火消しのため、「電子取引データが保存されていなかったからといって、直ちに青色申告承認の取り消しが行われるということはない」旨の追加Q&Aを発表することになりました。
この点、国税庁の事務運営指針(法人の青色申告の承認の取消しについて)も改正されており、電子取引データ保存の要件に従っていない場合、「今後の改善可能性等を総合勘案の上、真に青色申告書を提出するにふさわしいと認められるかどうかを検討する」とされ、調査時点と今後の改善可能性等を総合勘案することとされています。
以上の状況を鑑みると、この猶予期間の2年間と、その後の本格適用後も、多少の電子保存の不備によって、調査官から実際に青色申告承認の取消しが主張され、実際に取消しに至るということは考えにくいのではないかと推測します。
青色申告取消よりも恐ろしい、質問検査権の実質的な拡張
前述のとおり、実際に青色申告承認の取り消しに至るというのはレアケースですが、本当に厄介なのは、取消しに至らないまでも、2年間の猶予期間が明けた後、改正電帳法下の税務調査で、電子取引の保存に不備があった場合、青色申告承認の取消しをチラつかされ、すなわち、税務調査の交渉材料として使われ、否認項目の交渉が会社に不利になるというケースです。
この類のある種のバーター取引というべき交渉※は、実は税務調査の現場で頻繁に行われており、改正電子帳簿保存法に限らず、税務調査にあたって、自社において保存要件を満たさない等の法令に従っていないような状況・弱みを握られないようにしておくことが肝要です。
※非常にバリエーションがあり、また、改正電帳法の話から離れてしますので、ここでは詳細は割愛いたします。
まとめ|御社が取るべき対策とは?
今回の電帳法改正は、電子取引の範囲が広いため、また、一定の保存要件も定められているために、非常に煩雑な対応が強いられることになります。
この制度が実務上どの程度定着していくか、今後さらなる緩和措置があり得るのか、本格適用後どのような実務運用(例:保存の不備について、税務調査でどの程度問題視されるのか)がなされるのか等、未知数な事も多いです。
それ以上に、税務調査において、調査官のダウンロードの求めに応じなければならない会社(可視性の検索要件を全て充足できない会社)が多く出てくることにより、質問検査権が実質的に強化・拡張されたといえます。
さらに、電子取引データ保存の範囲が広く、煩雑であることに起因して、電子保存の不備が生じた場合に、税務調査で交渉材料に使われる点も否定できません。
このため、会社側にとっては、非常に厄介な問題を内包する改正となっています。
対策せずにやり過ごせればいいのですが、今回、2年間の猶予(準備)期間が与えられた以上、2024年1月からは、税務調査で電子取引データの保存状況が見られることになるでしょうから、この後、施行されるインボイス制度対応と合わせ、できる限り、会社経理として予算を確保した上で、システム導入・対策を講じていく必要があります。
筆者も、今後の実務運用・執行状況を踏まえた、より詳細な・最新情報を発信してまいりますので、セミナー等の情報発信に是非ご注目・ご参加いただければ幸いです。
元国税調査官・公認会計士。
国税調査官として税務調査等に従事。財務省本省勤務を経て、在職中公認会計士試験合格。
その後、Big4監査法人とBig4税理士法人にて10年以上、上場企業等に対して、会計監査と税務申告アドバイス経験を有する。国税局・中央省庁・Big4勤務経験を持つ、日本で唯一の元国税調査官・公認会計士。
元国税調査官・公認会計士の矢敷 和貴氏の無料メールマガジン登録はこちら。
https://17auto.biz/tax-cpa/registp/entryform3.htm