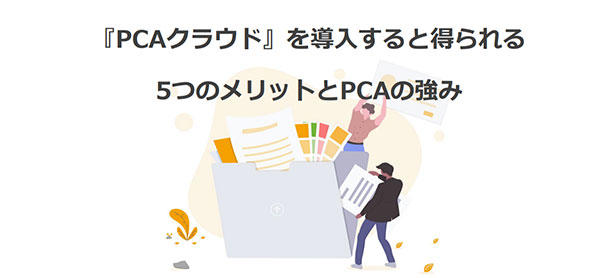会計ソフトをクラウド化するメリットについて
更新日:2020/01/24
会計ソフトをクラウド化するメリットについて


クラウド、クラウド会計とは!?
クラウド(Cloud)とは、「クラウドコンピューティング」を略した呼び方です。Wikipediaによると「インターネットなどのコンピュータネットワークを経由して、コンピュータ資源をサービスの形で提供する利用形態である」とされています(ⅰ)。
由来は諸説ありますが、インターネットを雲の絵で表現されることからその呼び名がついたとされています。クラウド会計とはPCなどのコンピュータにソフトウェアをインストールするのではなく、インターネットにあるサーバーにアクセスします。PCにクラウド用プログラムをインストールして利用する会計サービスや、ブラウザ上で利用する会計サービスをいいます。
東京商工会議所中小企業委員会が2017年に行った「中小企業の経営課題に関するアンケート」の調査結果によると、勤怠管理、給与管理システムと一括りにされているものの、ITを活用していると回答した企業のうち65.4%がクラウド会計をはじめとするこれらのシステムを利用していると回答しており、ITを今後活用するつもりであると回答した企業のうち48.8%がこれらのシステムの導入を検討しております(ⅱ)。さらに政府が発表している未来投資戦略2017において、2022年6月までにクラウドサービス等を活用してバックオフィス業務(財務・会計領域等)を効率化する中小企業等の割合を現状の4倍程度とし、4割程度を目指すとしていることから、今後もクラウド会計の利用者数は増加すると見込まれます(ⅲ)。
クラウド会計のメリットとデメリット
クラウド会計ではインターネットにアクセスをして入力などを行うため、PCのローカル にデータを置いておく必要はありません。そのため経理担当者が顧問税理士に会計のレビューを依頼する際には、オンプレミス型ではバックアップデータを作成し、メールに添付するなどでデータの共有をする必要がありましたが、クラウド型では顧問税理士はインターネットにアクセスすることでデータを閲覧できるため、その手間を省くことができます。一方で、運営会社がアップデートやメンテナンスをしている時間帯には利用ができないことがあるため、その時間帯を把握しておくことが必要となります。さらに複数のデバイスからアクセスできるというのも大きなメリットです。これにより入力者とチェック者が同時にアクセスすることや複数人で入力作業を行うことができます。
リアルタイムのデータの共有ができるという点も特徴です。経営者も現時点の進捗状況を大まかな売上高や利益の状況を把握することができ、会計事務所の担当者も入力状況の進捗状況を確認することができるためです。
一見すると非常にメリットが多いクラウド会計ですが、デメリットも存在します。
クラウド会計はアプリケーションソフトとして提供されている場合が多く、オンプレミス型と比べて自社仕様にカスタマイズするという点では苦手としている傾向があります。既に部門別や業種別など管理会計の要請から基幹系システムと会計ソフトをデータ統合させている大企業の場合には不向きであるといわれております。オンプレミス型会計ソフトは自社で購入しているため、原則として無形固定資産として貸借対照表に計上され、減価償却を通じて費用化されていきますが、クラウド会計は自社で所有はしないため利用料の支払といったように会計においても違った取扱いがされます。
クラウド会計のみの特徴ではありませんが、クラウド会計はインターネットを基盤とするため、ネットバンキングやクレジットカードとの連携は親和性が高く、取引明細の自動取得機能が優れています。クラウド会計ソフトが持つ自動学習機能は摘要によって自動で科目を判別することができ、入力時間の削減につながります。また、給与ソフト、販売、仕入管理ソフトとの連携が優れている点も大きな特徴になります(ⅳ)。
向き不向きあり!?クラウド会計!
クラウド会計は一般的に中小企業、小規模な企業や個人事業者向けといわれておりますが、ここではもう少しその意味を掘り下げて、具体的にどのような企業がクラウド会計に向いているのかを確認したいと思います。
(1) 取引数が比較的少ない企業向け
インターネットを通じて会計ソフトに接続されるため、取引量が多くデータが多い企業については動作の面で時間を要する可能性があるためです。
(2) インターネットを通じたサービスを利用している企業向け
先述したとおり取引明細の自動取得機能が大きな魅力でありますが、それらを利用していない企業にとっては享受できるメリットは半減すると思われます。また、紙媒体での請求書、納品書などの書類のやり取りが多い企業、現金商売や手形での取引が多い企業にとっても変更するメリットはあまり大きくないと思われます。
(3) 個人事業者
クラウド会計は前述した自動取得機能などがあるため労力を軽減できるとともに、簿記の知識がオンプレミス型の会計ソフトと比べて少なくても対応がしやすい仕様となっているためです。
クラウドの流れに乗る前に、自社にとって必要な機能を整理しましょう!
クラウド会計がクローズアップされることが増えてまいりましたが、こちらの記事をご覧いただいた方ならお分かりのとおり、クラウド会計を導入するメリットがある企業とメリットが少ない企業とが存在します。クラウド=効率化という流れに身を任せるのではなく、自社にとって必要な会計は何かをまずは検討する必要があります。また、クラウド会計の進歩も目覚ましいため、現在はオンプレミス型の方が向いている企業も定期的に再検討することが望ましいと思われます。今回のこの記事が少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。
<参考サイト>
(ⅰ)「クラウドコンピューティング」『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』.
2020年1月4日 (土) 14:42 UTC URL:https://ja.wikipedia.org/クラウドコンピューティング
(ⅱ)“中小企業の経営課題に関するアンケート 調査結果” .東京商工会議所.
https://www.tokyo-cci.or.jp/file.jsp?id=117373 (参照:2020-01-17)
(ⅲ)“未来投資戦略2017 -Society 5.0 の実現に向けた改革-” .首相官邸.
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/miraitoshikaigi/dai10/siryou3-2.pdf(参照:2020-01-17)
(ⅳ)“クラウド会計の副次的効果” .中小企業庁.
https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/H30/h30/html/b2_4_3_2.html(参照:2020-01-17)

2011年9月から大手資格専門学校にて税理士講座の専任講師(所得税法担当)を務め2015年8月末をもって退社。2015年9月に辻・本郷税理士法人に入社。
2018年10月より川口東事務所の所長を務める。
税理士試験合格(簿記論、財務諸表論、所得税法、法人税法、消費税法)。
URL:NEXTA(https://nexta-pro.com/)
URL:https://www.ht-tax.or.jp/