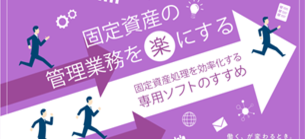減価償却資産の耐用年数はどのように決まる?
更新日:2020/12/22
減価償却資産の耐用年数はどのように決まる?


減価償却とは、資産価値の減少に合わせて費用を各会計期間に割り振っていく会計手続きのことを指します。減価償却を行っていく資産は、パソコンや車など企業の活動に欠かせないものが多く、会社の会計処理を行っていく以上避けては通れない処理になります。
その処理に欠かせない要素として耐用年数がありますが、この耐用年数が適正に設定されていないと、固定資産を使用できなくなった時点で償却不足が生じ、十分な買い替え資金が留保できていないというケースもでてきます。
この記事では、減価償却資産の耐用年数はどのように決まるのか、また、その実務上のポイントはどこなのかを詳しく解説していきます。
固定資産の減価償却とは?
会社の決算を行うためには、会計処理を正しく理解しておくことが必要です。
会計処理にはさまざまなルールがあり、なかには資金の増減と損益が一致しない形で処理するケースもあります。そういった処理を行うものの1つが減価償却です。減価償却とは、資産価値の減少に合わせて費用を各会計期間に割り振っていく会計手続きのことをいいます。減価償却を行う必要がある資産は、土地など一定の勘定科目を除く有形固定資産や無形資産などが対象です。これらの資産は、取得後すぐに会社内で消費されるのではなく、複数の会計期間にわたって使用されることを前提として取得されます。
すぐに消費されるものを取得した場合は、固定資産として計上するのではなく、取得した会計期間における費用として処理しても問題ありません。たとえば、事務用品や消耗品などはおおむね一年以内に使い切ってしまい、金額も少額です。こういったものを取得したときは、資産計上せずにそのまま適切な費用勘定を使って処理することになります。しかし、複数の会計期間にわたって使用される資産については、建物や機械装置などの固定資産勘定で処理して資産計上を行うことが必要なのです。資産計上された資産は、使用されて時が経過することによって取得時の資産価値が減少していきます。この資産価値の減少分を、資産の使用可能期間に割り振って費用化していくのです。減価償却とは、資産の価値を使用可能期間に対応させて処理する会計処理だと理解しておけばよいでしょう。
減価償却計算によって各会計期間に割り振られた費用の勘定科目名は、減価償却費です。減価償却によって使用可能期間に費用を分割して処理することによって、適切に収益と費用を対応させることができるようになります。
減価償却における耐用年数とは?
減価償却の処理を行うにあたって欠かせない要素の1つは、耐用年数です。
減価償却は、取得した資産を複数の会計期間に分割して費用化する処理であるため、何年間にわたって分割処理を行うかによって各会計年度の費用が変動することになります。より適切に収益と費用を対応させるためには、減価償却処理の対象となる固定資産を使用している期間に合わせて減価償却計算を行うことが合理的です。この資産の使用可能期間のことを、耐用年数といいます。資産が使用に耐える年数という意味です。
土地など使用しても資産価値が減少しないものを除けば、固定資産を取得したあと事業のために使用していくとその資産は古くなり、やがて使えなくなります。その資産を各会計年度に適切に割り振るためには、使えなくなるまでの期間を減価償却計算を行う初年度から把握しておくことが必要です。しかし、実際の使用可能年数は、使い終わってみなければわからないでしょう。それでも、どの程度の期間使用可能なのかについては、資産の種類ごとに標準的な期間を決めておくことは可能です。減価償却は、資産を取得した年度から計算を行う必要があります。この段階では、実際の資産寿命は不明であるため、資産の種類ごとに事前に決めた予想使用可能年数を耐用年数として減価償却計算を行うことになります。
会計上は、会社ごとに使用実態に合わせて耐用年数を事前に決め、それに従って減価償却を行えばよいことになっています。しかし、税法上は資産の種類ごとに国税局が定めている資産分類と耐用年数を使用することが必要です。恣意的に耐用年数を設定することによって不公平な課税が生じないようにするために、税法上の耐用年数の定めがあることは認識しておきましょう。
耐用年数を決めるポイント
減価償却資産は、多種多様です。それぞれ使用可能年数も異なるでしょう。そのため、耐用年数を一律で決めてしまうことは適正な期間費用配分などの観点から問題があります。また、取得年度以降の減価償却費は支出を伴わない費用であり、キャッシュアウトを伴わずに利益を下げることになるため、利益額と比較して、会社内に資金を留保できるという点がメリットです。減価償却を行うことによって、固定資産を買い替えるための原資を蓄えることにもつながります。
ただし、耐用年数が適切でなければ、固定資産を使用できなくなった時点では償却不足が生じ、十分な買い替え資金が留保できていないというケースもあるでしょう。そういったことが生じないためにも、耐用年数はできるだけ実態にあったものにすることが重要です。
しかし、数多くの資産の使用実態を踏まえて個々に耐用年数を決定していくことは実務上かなりの困難を伴います。そのため、政令で定められている「法定耐用年数表」を利用して決めるのが一般的です。法定耐用年数表で資産の種類ごとの耐用年数を確認して、耐用年数を決めていけばよいでしょう。
減価償却処理を行う場合における実務上のポイント
減価償却処理の実務を行う場合における主なポイントは、3つあります。
取得固定資産が中古である場合の耐用年数の決め方
まず1つ目は、取得した固定資産が中古である場合の耐用年数の決め方です。
中古の固定資産の耐用年数は、新品の固定資産とは異なります。その中古品の残りの使用可能年数が判断できる場合はその年数を耐用年数として減価償却すればよいですが、実際には残りの使用可能年数を見積もることは困難なケースが多いです。そういった場合は、簡便法で耐用年数を算出することが認められています。簡便法の計算式は、法定耐用年数全期間がすでに経過している資産は法定耐用年数の20%、一部が経過している資産は「(法定耐用年数-経過年数)+経過年数×20%」です。
取得して減価償却を行っている資産を、修繕した場合の処理
2つ目のポイントは、取得して減価償却を行っている資産を修繕した場合の処理です。
修繕は、資本的支出とそれ以外の2つに大別されます。資本的支出とは、資産価値が高まったり耐用年数が延びたりする修繕のことです。資本的支出を行った場合は、取得価額にその支出額を加算して減価償却していく必要があります。資本的支出に該当しないケースは、修繕費として費用処理を行います。
減価償却資産が耐用年数まで使用できない場合の処理
3つ目は、減価償却資産が耐用年数まで使用できない場合の処理です。
耐用年数表に記載されている耐用年数は、各資産が使用された場合に妥当とされる一般的な使用可能期間になっています。しかし、実際の使用状況が異なり法定耐用年数よりも短い期間で使い終わってしまう可能性もあるでしょう。そういった場合は、耐用年数の短縮承認申請を税務署に提出することで、税法上の耐用年数を短縮できる可能性があります。
まとめ
固定資産の耐用年数を決めていく上では、政令で定められている「法定耐用年数表」を利用して決めるのが一般的ですが、実務上それに当てはまらないケースのポイントを解説しました。
会社の決算を行うには会計処理を正しく行うことは重要なので、減価償却における耐用年数の決め方を間違いの内容に対応していきましょう。