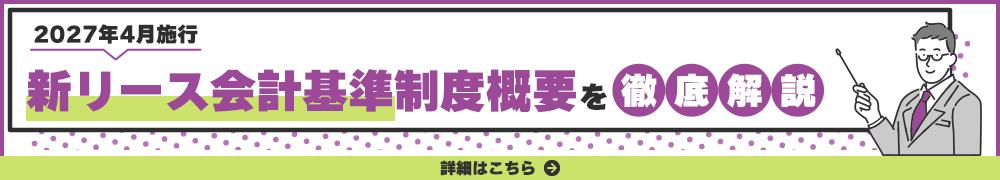新リース会計基準とは?企業が今押さえておくべき変更点と実務対応
更新日:2025/07/22

企業のリース契約に大きな影響を及ぼす「新リース会計基準」が2027年4月以降、強制適用されます。新基準では原則すべてのリースを資産・負債として計上する必要が生じるため、財務諸表の見え方や経営指標への変化が予想されます。
そして経理担当者や財務責任者にとっては、資産・負債の計上方法や会計処理の見直しが求められる重要な改正です。
本記事では新リース会計基準の概要や変更点、実務への影響、そして導入に向けて準備すべきポイントをわかりやすく解説します。
そもそもリース会計基準とは?
リース取引とは企業が設備や機器などを借りて一定期間使用し、対価を支払う契約を指します。この際、会計上の取り扱いには明確なルールが必要です。
その理由は、リースは「借りているだけ」に見えても、実質的には購入と同等の経済的効果をもつ場合があるためです。
リースには2種類がある
リースには、「所有権が移転するかどうか」という観点で大きく分けて2つのタイプがあります。
現行の日本基準では、リースは以下の2種類に分類されます。
①ファイナンス・リース取引
リース期間終了後に所有権が移転する、もしくは実質的に購入とみなされる契約。リース資産とリース負債として貸借対照表に計上されます。
②オペレーティング・リース取引
所有権の移転がなく、資産の経済的価値も利用期間中に企業へ移らないと判断される契約。支払額を単純な費用として処理します。
借りるだけでなく最終的に所有権が移る「ファイナンス・リース取引」は、資産の取得とみなされ、会計上も資産計上が必要となります。
一方、所有権が移らず単に使用権を得るだけの「オペレーティング・リース取引」では、一定の条件下では費用処理のみで済むケースもあります。
リースの分類は財務諸表の見え方にも関係あり
先述のリースの分類は、企業の財務諸表における「見え方」に大きく影響を与えます。
たとえば同じ額を支払っている場合でも、ファイナンス・リースなら「資産・負債」が膨らみ、オペレーティング・リースなら「費用」だけが増えるという違いがあります。
こうした背景から、リース会計の目的は単に形式的な分類ではなく、資産・負債を適切に表示し、リースの経済的実態を正確に財務諸表に反映させることにあります。
今回の新リース会計基準では、この点をより厳密に評価し、すべてのリース取引を網羅的に把握する仕組みに変わろうとしています。
新リース会計基準への改正の背景
今回の新リース会計基準は、国際会計基準(IFRS16)との整合性を図るために導入されました。
これによりグローバルに展開する企業でも、国内外で一貫性のある財務報告が可能になります。
またこれまでの制度では、オペレーティング・リース取引が貸借対照表に載らないため、実質的には資産や負債を抱えていても、それが財務諸表に表れないケースが多く見られました。
こうした“オフバランス”の状態は、財務状況を過小に見せるリスクがあり、場合によっては「粉飾的」ともとられかねません。
新基準ではこの問題を是正し、投資家や金融機関に対する財務の透明性を高め、企業間の比較可能性も確保する狙いがあります。リースという契約の経済実態を正しく反映させることが、今回の改正の最大の目的といえるでしょう。
新リース会計基準の内容
新リース会計基準では、原則としてすべてのリース取引を資産・負債として「オンバランス計上」とすることが求められます。
すべてのリース契約をオンバランス計上へ
オンバランス計上とは、企業の貸借対照表(バランスシート)に取引に関する資産や負債を明示的に記載することを意味します。つまり「リース契約であっても借金して資産を買ったのと同じように、財務諸表に反映させる必要がある」という意味です。
【現行のリース会計基準】
・ファイナンス・リース取引
……リース資産・リース負債として計上
・オペレーティング・リース取引
……費用として計上、資産計上は不要(オフバランス)
【新リース会計基準】
借手はリース契約に基づき、使用権資産とそれに対応するリース負債を貸借対照表に計上します。
具体的には
・契約期間中に使用する資産の価値(使用権資産)
・支払うべきリース料の現在価値(リース負債)
上記を見積もり、リース期間・割引率・支払総額などをもとに評価。
※費用計上していた「オペレーティング・リース」も減価償却費と支払利息が計上されます。
国際基準であるIFRSを適用していた企業ではすでに新リース会計基準が適用されており、オペレーティング・リース取引とファイナンス・リース取引の区別が廃止されています。
しかし今後は、日本の基準においてもオンバランスでの計上にするとの方針が示されています。
【日本の新基準方針】
| 借手の費用配分 | 現行ルールとIFRS16との整合性を確保 |
| 代替取扱いや経過措置 | 国際的な整合性を保ちつつ、実務上の負担に配慮して代替的な取扱いや一定の猶予措置を設ける方向で検討が進められている |
| 会計処理の一致 | 借手とリース会社(貸手)で処理の食い違いが起きないよう、現在の会計基準に対して改正 |
新リース会計基準の簡便措置と財務報告における表示と開示
1年以内の短期リースや、取得価格が明らかに少額なリースについては、従来通り費用処理できる「簡便措置」が認められています(例:日常的に使用されるOA機器など)。
また、財務諸表における財務報告については、「使用権資産」「リース負債」「利息費用」の3つの開示、および借手・貸手の注記が必要になります。
【財務諸表への記載が必要な項目一覧】
| 開示が必要になる項目 |
|
| 借手の注記 |
|
| 貸手の注記 |
|
新リース会計基準の適用時期はいつから?
新リース会計基準は、2027年4月1日以後開始する事業年度から強制適用とされています。ただし、それ以前の早期適用も可能です。
同基準は2023年5月に企業会計基準委員会(ASBJ)より公表され、2024年9月の企業会計基準委員会で承認されました。
今後、上場企業を中心に、順次導入に向けた準備が進められると見込まれています。
新リース会計基準の対象企業
上場企業や大企業は対象に
原則として金融商品取引法が適用される上場企業、およびそれらの子会社・関連会社が適用対象となります。
また、会計監査を設置している企業とその子会社も対象となるため、会社法で会計監査人の設置が義務付けられている大会社(大企業)も新リース会計基準の適用対象となります。
【新リース会計基準の適用対象】
- 上場企業
- 上場企業の子会社や関連会社
- 大会社(資本金5億円以上、または負債200億円以上の企業)
中小企業以下の適用は任意
一方で中小企業については、新リース会計基準の適用は任意となります。
中小企業には従来の「中小企業の会計に関する基本要領」や「中小企業の会計に関する指針」の適用が継続されるため、従来の会計処理でも問題ありません。
また、公益法人・医療法人・社会福祉法人などの非営利法人についても、今後の取り扱い方針が注目されています。現時点では対象範囲の明確な線引きが検討中の段階です。
(参考:公益法人会計基準の検討経過(令和6年度会計研究会)|PDF)
新リース会計基準のポイントや現行基準との変更点

新リース会計基準の最大の変更点は、従来「オフバランス」で処理されていた一部のリースも「オンバランス」計上の対象となる点です。
これにより、企業の財務諸表における見え方や主要な経営指標が変わる可能性があります。
| 比較項目 | 現行基準 | 新基準(2027年4月以降) |
|---|---|---|
| リースの分類 | ファイナンス・オペレーティングのいずれかに区分 | 区分なし(原則オンバランス) |
| 会計処理 | 一部は費用計上のみ | 使用権資産・リース負債を計上 |
| 財務諸表への影響 | 負債圧縮・利益率が高く見える可能性 | 資産・負債が増加、ROA等に影響 |
| 対象 | 一定条件を満たす長期リースのみ | 原則全リース(例外あり) |
リースの定義と識別方法
新リース会計基準では、リースの定義がより明確かつ実態に即したものに変更されました。
具体的には「原資産を使用する権利を、一定期間にわたり対価と交換に移転する契約」がリースとされます。
さらに、「契約にリースが含まれるかどうか」は、以下の3つの要件を満たすかで判断されます。
- 特定の資産であるかどうか
- 使用から得られる経済的利益の大部分を受け取る権利があるか
- その資産の使用方法を指図できるか
これらの条件をすべて満たす場合、契約書に「リース」と明記されていなくても、リースとみなされます。
そのためこれまでリースと認識されていなかったレンタル契約や不動産賃貸契約も、新基準ではリースとして処理が必要になる可能性があるのです。
それに従い経理担当者は、契約の再確認と分類の見直しが求められます。
貸借対照表・損益計算書の見え方が変わる
リース契約を資産・負債として計上することにより、企業のバランスシートはより実態に即した形に近づくといえます。従来は表面上の借入が少なく見えていた企業でも、リース債務を含めた実質的な財務状況が明確になります。
損益計算書では、リース料の支払いを一括で計上していた従来の方法から、利息費用と減価償却費に分けて段階的に計上する形となり、期間損益の構造にも変化が生じます。
特に導入初期は費用の前倒し計上(フロントローディング)となりやすく、利益の変動が大きくなる点にも注意が必要です。
経営指標(ROA・EBITDA)への影響
オンバランス処理により「リース資産」や「リース負債」が貸借対照表に計上されるため、総資産が増加します。この結果、総資産利益率(ROA)は一時的に低下することが想定されます。
一方、損益計算書上では、リース料の全額を販管費として処理していた従来の方式から、減価償却費+利息費用への振替が行われます。
これによりEBITDA(利払前・税引前・償却前利益)は増加する傾向にあり、投資家からの企業評価が変わる可能性があります。
具体的な会計処理方法と経理業務への影響
これまでオペレーティング・リースとして費用処理(損益計算書のみ)されていた契約も、今後はすべてのリース契約を原則「オンバランス」で処理(貸借対照表に計上)する必要があります。
その際には以下のように処理を行います。
- 「使用権資産(資産)」と「リース負債(負債)」を計上
- 費用の形も、賃借料から「減価償却費+支払利息」へ変更
新リース会計基準での会計処理の流れ
新リース会計基準における会計処理の流れは以下のとおりです。
【会計処理の流れ】
1. リース契約の締結・取得
↓
2. 契約内容の確認
└─ リース期間・支払条件・対象資産の分類など
↓
3. 割引率の決定
└─ インクリメンタル借入利率 or 契約上の利率
↓
4. 初期認識
└─ 「使用権資産」と「リース負債」を貸借対照表に計上
↓
5. 毎期の処理(定期処理)
├─ リース負債の利息費用を計上(利息法)
└─ 使用権資産の減価償却を実施(定額法など)
↓
6. 会計システムや台帳への反映
└─ 固定資産台帳・仕訳処理・開示書類と連携
↓
7. 既存契約の棚卸・再評価
└─ 移行時は旧契約も含めオンバランス対象の精査が必要
新リース会計基準における仕訳例
1.初期認識時の仕訳(リース開始日)
| 借方 | 貸方 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| 使用権資産 | 1,000,000円 | リース負債 | 1,000,000円 | リース期間中の支払総額の現在価値で認識 |
- 使用権資産:リース物件を使用する「権利」を資産として計上。
- リース負債:将来支払うべきリース料の現在価値。
2.毎期処理の仕訳(例:月次)
(1) 減価償却費の計上(定額法の場合)
| 借方 | 貸方 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 83,333円 | 使用権資産減価償却累計額 | 83,333円 | 1,000,000円 ÷ 12か月(1年契約の場合) |
(2) 利息費用と元本返済の計上(利息法)
| 借方 | 貸方 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| 支払利息 | 5,000円 | リース負債 | 5,000円 | 利息法に基づく利息費用の認識 |
| リース負債 | 95,000円 | 現金預金 | 100,000円 | 月額支払い:元本返済+利息 |
リース負債の利息計算は「利息法」で行うため、支払総額を均等に按分するのではなく、残高に応じて利息部分が変動します。
また先述のとおり、短期リース・少額リース(例:12か月未満、PC1台等)についてはオンバランス処理の対象外とすることも可能です(簡便法の選択)。
注意点
新リース会計基準の導入により、経理部門ではすべてのリース契約を把握し、オンバランス処理の対象かを判断する必要があります。
使用権資産とリース負債の金額は、契約期間や割引率などをもとに算定し、利息法に基づいた処理が求められることも知っておきましょう。
また短期・少額リースには例外処理もありますが、要件の確認が重要です。加えて減価償却や利息計算に対応した会計システムの導入・整備も不可欠となります。
開示項目が増えるため、注記情報の準備も早めに進めましょう。
新リース会計基準に対応するために準備すること
新リース会計基準の導入に向けては、企業として複数の準備項目に対応しておく必要があります。以下では、実務上特に重要なステップを整理してご紹介します。
【新リース会計基準への対応準備】
- 現行のリース契約の洗い出し
- リース契約書の確認・再分類
- 割引率やリース期間の見積もりルール策定
- 会計システム・管理台帳の見直し
- 社内マニュアル・運用フローの整備
- 社内外(税理士・監査法人など)との連携
1.現行のリース契約をすべて洗い出す
まず行うべきは、自社が現在締結しているすべてのリース契約の洗い出しです。
リース資産の種類や契約期間、支払条件などを一覧化して把握しておくことで、移行後の処理がスムーズになります。
2.契約内容の確認と再分類
洗い出した契約の内容をもとに、新基準に照らしてリースの分類を見直す必要があります。
短期リースや少額リースに該当するものは例外扱いが可能なため、事前の見極めが重要です。
3.割引率やリース期間の見積もりルールの策定
使用権資産やリース負債の計上にあたっては、将来キャッシュフローの見積もりが必要になります。
割引率の設定やリース期間の見積もり方針を明確にし、社内で統一しておくことが求められます。
4.会計システムや台帳の見直し
新基準への対応には、使用権資産やリース負債の処理に対応した会計システムの整備が欠かせません。
固定資産台帳やリース管理台帳との連携も含め、業務フロー全体を見直す必要があります。
5.社内マニュアルと運用フローの整備
新しい処理基準に沿った社内マニュアルの更新や、経理・財務部門の運用フローを整えることも重要です。
担当者ごとに判断がぶれないよう、具体的な処理ルールを文書化しておくと安心です。
6.税理士や監査法人などとの連携
税務・会計上の判断や開示・監査への対応を円滑に行うには、外部専門家との連携も欠かせません。
早い段階から情報共有を進め、リスクを回避できる体制を整えておきましょう。
注意点:対応の遅れはトラブルの原因に
対応が後手に回ると、決算処理や財務諸表の開示、監査対応の場面でトラブルが生じる可能性があります。特に仕訳処理や台帳管理の見直しには時間を要するため、早めに準備を始めることが肝心です。
まとめ
新リース会計基準では、原則すべてのリース契約を「オンバランス」で処理し、資産・負債として計上することが求められます。これにより、従来オフバランス処理されていた契約も財務諸表に反映され、企業の経営状況がより明瞭になります。
2027年4月1日以降開始の事業年度からは強制適用となるため、今のうちから既存契約の棚卸や会計システムの整備など、計画的な準備を進めておくことが重要です。
また、本改正は経理部門だけで完結する話ではなく、資金調達や投資判断にも影響を及ぼすため、経営層や関係部門と連携しながら全社的な対応が求められます。
早期の対応によって混乱を最小限に抑え、スムーズな移行を実現しましょう。