2024年10月に予定されている郵便料金の値上げを解説!企業における請求書などの郵送コストを抑える方法も紹介
更新日:2024/09/20


証憑類の電子化が進む一方で、請求書等の書類送付時には郵送を利用している企業も依然として多く見られます。
そんな中、2023年12月に総務省では「早ければ2024年の秋に、定形郵便物をはじめとする郵便物の料金を値上げする」という省令案が公表され、大きなニュースとなりました。その後、6月に日本郵便は10月1日に郵便料金の値上げを総務省に届け出ました。
郵便料金の値上げは消費税増税時を除いておよそ30年ぶりとなりますが、「どのような影響があるのか」「どんな対策が必要なのか」と懸念されている企業様も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、2024年10月実施となる「郵便料金の値上げ」についてわかりやすく解説します。具体的にどれくらい料金が上がるのかといったことや郵便料金改定の背景・理由、企業ができる対策についてもご紹介していますので、ぜひご参考になさってください。
予定されている料金改定の内容
郵便料金の改定内容は以下のとおりです。
- 郵便料金について、2024年(令和6年)10月から以下の値上げが実施される。
【具体的な変更点】
| 第一種定形郵便物 | 25gまで | 84円→110円 |
|---|---|---|
| 50gまで | 94円→110円 | |
| 第二種郵便物(はがき) | 63円→85円 | |
| 50g以下の定形外郵便物(規格内) | 120円→140円 | |
| レターパックライト | 370円→430円 | |
| レターパックプラス | 520円→600円 | |
| スマートレター | 180円→210円 | |
| 速達 | 250gまで | 260円→300円 |
| 250g~1kgまで | 350円→400円 | |
| 1kg超え | 600円→690円 | |
| 第三種、第四種郵便物、書留等 | 据え置き | |
参照元:郵便料金の改定および新料額の普通切手の発行などについて|日本郵便
このうち特に注目されているのが、第一種定形郵便物(以下、定形郵便物)の料金値上げです。
25g以下の定形郵便物といわれると分かりにくいですが「A4用紙4~5枚程度を入れた封書」をイメージしていただくと分かりやすいでしょう。企業においては請求書や納品書などの送付の際に、かなりの頻度で用いられるサイズ・重量の郵便物です。
この25g以下の定形郵便物については、「郵便法の施行規則で定める上限を超えて設定してはならない」というルールがあります。また上限額については、軽量の信書(一般的なサイズ・重量の封書)の重要性や国民の負担能力、物価などを考慮して決定しなくてはならないという決まりもあります。
このような規定をベースとし、最小限の値上げ幅でかつ利用者がわかりやすい料金とするため、総務省令(郵便法施行規則)での上限額が84円から110円へと改定されました。
また郵便料金の値上げについては、経営状況に応じて短期間に再度見直しを行うことも念頭に置いたものであるとされています。
郵便値上げの背景と理由
総務省の資料では、郵便料金値上げの背景が以下のように説明されています。
- デジタル化の加速によって今後も郵便物数の減少が見込まれる
- 営業費用の削減に取り組んできたが、令和4年度には民営化以来初の営業損益▲211億円の赤字に陥った
- 賃金引き上げの実施、燃料費等の高騰を適切に委託料等に転嫁することが社会的な要請となっている
- 人件費、集配運送委託費が営業費用全体の約3/4を占めており、営業費用の大幅な減少は見込まれない
- 郵便事業の安定的な提供を継続するために見直しを行う
参照元:郵便法施行規則の一部を改正する省令案及び民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則の一部を改正する省令案 (P10~P28)|総務省
郵便料金の値上げはこれまでにも行われてきましたが、いずれも消費税引き上げに伴うものでした。
しかし今回の値上げについては、収益源となる郵便物の数の減少に伴い郵送料金による収益も減っていることに加え、郵便事業にかかるコストの増大が大きな要因となっています。
このように今回の値上げはこれからも安定的なサービスを継続して提供するための値上げであり、「郵便に関する料金は、郵便事業の能率的な経営の下における適正な原価を償い、かつ、適正な利潤を含むものでなければならない(郵便法第3条)」という法令のもとで料金が決められています。
企業におけるコストへの影響は?
郵便料金の値上げにおける一般家庭の家計消費支出への影響はごくわずか(年間約1,100円)です。
しかし企業においては、封書をはじめとする郵便物を大量に発送するケースも多く、郵便料金の値上げによってコストが増大するおそれがあります。
仮に月100通の封書(25グラム以下の定形郵便物)を送付していたと仮定すると、改正前は8,400円(84円×100通)で済みますが、改正後は11,000円(110円×100通)。その差はひと月あたり2,600円となります。
これが1,000通になればひと月あたり26,000円、年間では312,000円もの差額が生じることになります。
また、企業規模が大きくなるとひと月に数千~10,000通以上の郵送を行う場合も珍しくありません。
郵便物の数が多くなるほどコスト面での影響は大きくなり、収益にも影響を及ぼす可能性が高いでしょう。
【郵便料金の値上げによる郵送費用の変化】
| 封書の郵送数 (ひと月あたり) |
郵便料金 | ひと月あたりの差額 | 年間あたりの差額 | |
|---|---|---|---|---|
| 改正前 | 改正後 | |||
| 100通 | 8,400円 | 11,000円 | 2,600円 | +31,200円 |
| 500通 | 42,000円 | 55,000円 | 13,000円 | +156,000円 |
| 1,000通 | 84,000円 | 110,000円 | 26,000円 | +312,000円 |
| 5,000通 | 420,000円 | 550,000円 | 130,000円 | +1,560,000円 |
| 10,000通 | 840,000円 | 1,100,000円 | 260,000円 | +3,120,000円 |
郵送コストを抑える方法
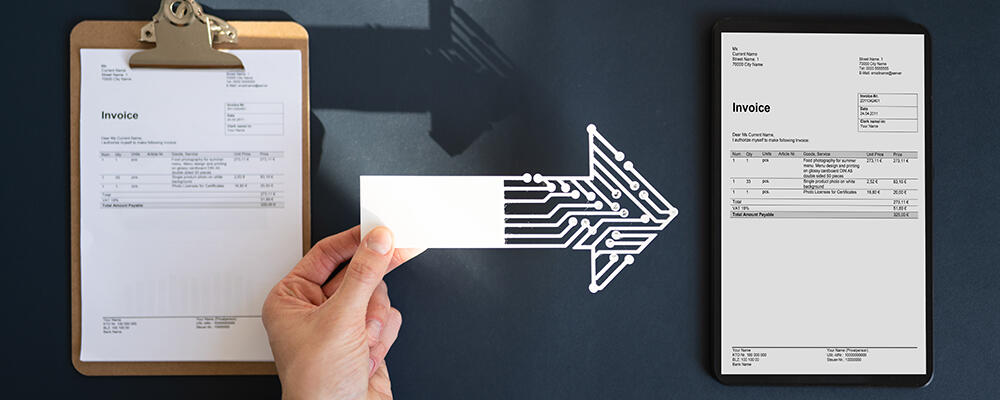
ご紹介してきたように、郵便料金は2024年10月に値上げが実施されます。企業として、今後の郵送コストの増加を防ぎ、収益への影響を最小限に抑えるには、「これまで郵送していた請求書、納品書等の証憑類を電子発行すること」が重要です。
【郵送コストを抑えるための対策】
- PDF等で発行しメール送信する
- 請求書発行サービスの活用
上記の方法で書類発行の電子化を行うことで、郵便料金だけではなく郵送作業にかかるコストと手間(印刷や押印、封入、切手貼り、およびそれらにかかる人件費)を削減できます。
PDF等で発行しメール送信する
郵送コストを抑える方法のひとつに、請求書や納品書等をPDFデータで発行する方法があります。
こちらはExcelなどを用いて作成した電子データを、メールに添付し先方へ送信する方法となります。
これまでメールでやりとりをしていた相手ならば事前準備が不要であり、ツールやサービス等の利用コストがかからないことが利点です。
一方で、発行にやや手間がかかること、誤作成・誤送信などの人為的なミスが生じやすいこと、セキュリティ面・電子帳簿保存法への対応(運用ルールの制定等)などの課題もあることを把握しておかねばなりません。
請求書発行サービスの活用
これまで紙の請求書を送付していた場合、新たに請求書発行サービスを活用する方法もおすすめです。
請求書発行サービスとは、専用のツールを用いて請求書を電子発行するサービスを指します。請求書や納品書といった証憑の作成・発行はもちろん、サービスによっては販売管理や仕入・在庫管理に便利な機能を備えたものもあり、近年では多くの企業が利用しています。
インボイス制度の施行や電子帳簿保存法の改定以降は、それぞれに対応している請求書発行サービスも増えており、法令を遵守しながら効率的に請求書等の発行が行える点が魅力です。
請求書発行サービスを使うことのメリットとデメリット
請求書を紙で発行していた企業が請求書発行サービスを使い始めると、郵送コストの削減が実現します。またそれだけではなく、作業の効率化、顧客(取引先)へ素早く請求書を発行できるなどのメリットも得られるでしょう。ただし、請求書発行サービスを利用する際にはデメリットもありますので、それぞれを比較したうえで導入を検討してみましょう。
請求書発行サービスを利用するメリット
請求書発行サービスを利用するメリットには以下の4点が挙げられます。
- 郵送に関する印刷・封入・発送などの手間や郵送費などのさまざまなコストを削減できる
- 請求書発行のタイムラグを短縮できる
- 基幹システム、業務用ツールと連携してさらなる業務効率化が期待できる
- バックオフィス部署がリモートワークに対応できるようになる
先にご紹介したとおり、請求書発行システムを用いて請求書等を発行・送付すると、これまで必要だった郵送コストと作業の手間を大きく削減できます。
加えて請求書を発行したあと、即時送信ができる点も大きなメリットでしょう。
電子取引を行っている企業に請求書を発行する場合、紙の請求書を送付すると到着までに2~4日かかるだけでなく、先方は電帳法のルールに則ってスキャナ保存等が必要になります。一方はじめから電子データで送付した場合は、即時送信ができるうえ書類スキャンの手間も省けるのです。
一見すると些細なことに思えますが、“細かな手間を減らす心遣い”があるのとないのとでは先方の作業効率にも大きな違いが表れます。先方が保存しやすい形で請求書を発行・送付できれば、結果的に取引先・顧客の満足度アップにもつながるでしょう。
そのほか、請求書発行サービスの中にはクラウドを通じて基幹システムや会計システム等の社内ツールと連携できるものも多く見られます。こうしたサービスを利用すればバックオフィス業務がスムーズに遂行できるだけでなく、会社以外の場所でも作業が可能です。
郵送コストを抑えたい企業はもちろん、DXを推進しながらバックオフィス業務のリモートワーク化を視野に入れている企業は、請求書発行サービスの活用をおすすめします。
請求書発行サービスを利用するデメリット
請求書発行サービスを利用する場合、サービスの利用料金が発生する点に注意が必要です。
サービスの利用料金は提供会社や利用形態(クラウド型かオンプレミス型か)などによっても異なりますし、初期費用がかかる場合もあります。月に送付する請求書等の書類が数十通程度ならば、メール送付のほうがコストを抑えられる可能性もあるでしょう。
ただ、請求書発行サービスを利用した場合、請求書の発行から管理、連携等がスムーズになることは事実です。セキュリティ面やヒューマンエラーの予防の観点からも大きなメリットがあるうえ、クラウド型であればリモート作業も実現します。
トータルでメリット・デメリットを比較したうえで導入するかどうかを検討されるとよいでしょう。
請求書発行サービスを利用して郵便料金の値上げ対策をしよう!
本記事では、2024年10月に予定されている郵便料金値上げについてお伝えしてまいりました。
企業にとって請求書や納品書等の証憑のやりとりは欠かせないものであり、郵送料金はそのような業務に必須のコストとなっています。電子データでのやりとりが普及してきた現在でも、取引先によっては紙の請求書等を送付されている企業もいまだ少なくないでしょう。
しかし今後郵便料金が約3割値上げになれば、企業の経費増加、および利益の減少を招く可能性があります。従来から封書の送付が多い企業様であればなおのことです。
封筒代や印刷代等を含め郵送コストを抑えたい企業様は、郵便料金の値上げへの対策として、請求書配信サービスの活用をご検討されてみてはいかがでしょうか。
『PCA Hub 取引明細』は請求書の発行数がそれほど多くない企業でもコストメリットが出ます。請求書配信サービスを選定の際はぜひ 検討ください。
【郵便料金の値上げ後の郵送費用と『PCA Hub 取引明細』の利用料金 (税込)】
| 封書の郵送数 (ひと月あたり) |
改正後 | PCA Hub 取引明細ひと月あたりの利用料金 | ひと月あたりの差額 | 年間あたりの差額 |
|---|---|---|---|---|
| 50通 | 5,500円 | 4,950円 | 550円 | +6,600円 |
| 100通 | 11,000円 | 8,800円 | 2,200円 | +26,400 円 |
| 500通 | 55,000円 | 38,500円 | 16,500円 | +198,000円 |
| 1,000通 | 110,000円 | 66,000円 | 44,000円 | +528,000円 |





