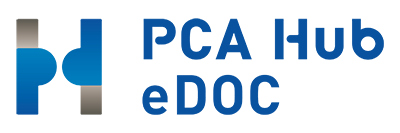経費精算に領収書は必要? ない場合や保管方法について解説!
更新日:2023/09/22
経費精算に領収書は必要? ない場合や保管方法について解説!


経費精算に欠かせない「領収書」。従業員が領収書を紛失してしまったり、発行されなかったりする場合の対応に悩んだことはないでしょうか? また、紙発行から電子データ発行への過渡期である今、領収書の保管方法や要件などの整理・把握ができていない企業も多いようです。
領収書に関し、イレギュラーが発生したときの対応や保管方法を把握しておけば、スムーズな対応が可能となります。
ここでは経費精算に使用する領収書に対し、領収書として扱うために必要な項目、保管方法、紛失時の対応、発行されない場合の対応などをご紹介します。さらに紙・電子・スキャナ保存のそれぞれのケース別に、領収書の保管ルールを解説します。
経費精算に必要! 領収書の役割とは?
そもそも領収書とは、経費精算において「代金の支払いがあったこと」を客観的事実として証明する公的書類です。売り手と買い手の間で領収書を発行・受領することで、以下の二項を証明できます。
- 商品やサービスに代金を支払った(買い手)
- 商品やサービスの対価として代金を受け取った(売り手)
領収書を発行・受領する目的は、主に以下の3つです。
- 代金の過払い、二重請求を防ぐ
- 従業員の内部不正を防ぐ
- 税務申告の際の証憑書類にする
商品やサービスの収受においては、金銭のやりとりが発生します。しかし何の証明書もなく金銭のやりとりを行った場合、払った・払っていないという行き違いが生じる可能性があります。
この行き違いにより過払いが生じたり、二重請求をしてしまったりといったトラブルにつながるおそれがあるのです。領収書を発行・受領していれば、「いつ・誰に対し・どんな内容で・いくらの金額で代金の支払いがあったか」を証明することができ、こうしたトラブルも防げます。
また領収書は、従業員の経費精算において「経費の不正利用」防止の観点からも、提出させることが望ましいです。
領収書がないと、「出張の際に電車で行ったのに新幹線代を請求する」「1泊だったのに2泊分の料金を立て替えたとして請求する」というふうに、従業員が水増しして請求し、差額を利益として受け取るなどの不正が行われてしまいます。
こうした経費精算の不正を防止するため、領収書の提出を義務付け、かつ内容をチェックするようにすると良いでしょう。
なお領収書は、収支の正しい申告をするための証憑として、税務申告の際にも重要な役割を果たしています。
経費精算に使う領収書に必要な項目とは?
領収書には「いつ・誰に対し・どんな内容で・いくらの金額で代金の支払いがあったか」を示すため、所定の項目が定められています。反対に言うと、領収書を証憑として使うためには以下の項目が含まれていないといけません。
【領収書に必要な項目】
| ① 題 | 「領収書」の表題。 |
| ②日付 |
代金を支払った年月日。和暦、西暦どちらでも可。 「R5年」「23年」などの略歴は認められないので注意。 |
| ③宛名 |
支払者の氏名または企業名を正式名称で記載。 ※特定の業種では「上様」と省略記載していても可。 (小売業、旅客運送業、旅行関連事業、飲食業、駐車場業) |
| ④但し書き | 商品・サービスの名称や内容。 「飲食代として」など具体的な内容であるか確認が必要。 |
| ⑤金額 |
金額欄においては訂正や数字の追加(0を追加してケタを水増しするなど)ができない表記がされていることで領収書として認められる。 【必須条件】
|
| ⑥収入印紙 |
支払金額が5万円以上の場合は、収入印紙と消印が必要。 ※クレジットカード払いの場合は収入印紙不要。 |
| ⑦発行者 |
領収書発行者の会社名(店舗名)または氏名の記載を確認。 住所、連絡先の記載も要確認。 |
不足している項目があった場合、証憑として認められないので注意しましょう。
領収書を紛失したときの対応方法は?
領収書をもらったものの紛失してしまった場合は、以下の方法で対応可能です。
- 領収書の再発行を依頼する
- 出金伝票に記録する
領収書の再発行を依頼する
一度発行してもらった領収書を紛失してしまった場合は、発行元の企業・店舗に連絡し、再発行を依頼することができます。
ただし、領収書の再発行はあくまでも任意となりますので、必ず再発行してもらえるとは限りません。企業・店舗によっては再発行を行っていない場合もある点に注意しましょう。
出金伝票に記録する
領収書を無くしてしまった場合は、出金伝票に記入することで領収書として経費精算ができる場合もあります。
出金伝票は紙の証票として記入してもよいですし、Excelなどで作成してもかまいません。
・支払先(企業名や店舗名)
・支払い日
・但し書き
・支払い額
金額の記入ルールは領収書の場合と同じです(例:¥5,000- など)。
ただし出金伝票はあくまでも“例外”であり、恒常的に出金伝票で経費処理をするのは好ましくありません。出金伝票を多用していた場合、税務申告において「この費用は本当に発生しているのか?」と経費の不正申告を疑われてしまう可能性があるからです。
なお、消費税の課税事業者が仕入税額控除を適用する場合、出金伝票のみでは不十分で領収書等の保存が必要とされています。特にインボイス制度開始後は、税込み3万円未満の仕入れの場合に帳簿への記載のみで仕入税額控除が認められるという、これまで認められていた特例がなくなります。特例がなくなり3万円未満でも基本的には領収書の受領と保存が必要となりますので注意が必要です。
なお、次のような適格請求書を交付することが難しい取引では、インボイス制度開始後も帳簿のみの保存が認められます。
- 公共交通機関である船舶、バス又は鉄道による旅客の運送
- 出荷者等が卸売市場において行う生鮮食品等の譲渡
- 生産者が農業協同組合、漁業協同組合において行う生鮮食品等の譲渡
- 自動販売機・自動サービス機により行われる課税資産の譲渡等
- 郵便切手を対価とする郵便サービス
基本は領収書での経費処理を行い、出金伝票を使用する場合は適切な扱いを心がけましょう。
領収書はレシートで代用できる?
領収書はレシートでも代用できます。
証憑として経費精算にレシートを使用する場合は、以下の4項目が記載されていることを確認しましょう。
- 発行者(販売者)の名称
- 取引が行われた日付
- 商品やサービスの内容(品物名など)
- 取引金額
領収書が発行されない場合の対応方法は?
ビジネスにおいては「自動販売機で飲み物を買って取引先に渡した」「慶事・弔事でご祝儀や香典を渡した」など、領収書が発行されないお金のやりとりが生じるケースがあります。
また企業によっては「交通費の経費精算については領収書不要」としているケースもあります。領収書が必要な場合でも、「券売機で切符を買ったが領収書をもらい忘れた」というケースも考えられるでしょう。
領収書が発行されない場合や不要な場合については、どのように対応していけばよいでしょうか。
自動販売機での購入での経費精算
自動販売機で飲み物を購入した場合、レシートや領収書などは発行されません。しかしビジネスでは「建設現場の社員に自販機でコーヒーを購入し、差し入れした」といったケースも多いです。
この場合は、以下の方法で記録を残しておくと経費・損金として算入できます。
- 出金伝票を作成、記録する
- Excelに記録しておく
- 企業用の電子マネーで利用履歴を残す
要は、あとから客観的事実として確認できるような形で記録をしておけばよいということです。
「いつ、誰に渡すために購入したか」を併せて記録しておけばより信頼性が増します。
慶事・弔事などの冠婚葬祭費
冠婚葬祭におけるご祝儀や香典などは、出金伝票で処理をします。
加えて、ご祝儀袋のコピーや、招待状や案内状の原本を一緒に保管しておくと信ぴょう性を高められます。
交通費
券売機で切符を購入したときに領収書をもらい忘れた場合は、出金伝票で処理をします。
また社内規定で領収書が不要な場合は、交通費精算書を利用して経費精算を行いましょう。
なお、交通費精算書は以下の項目を含める必要があります。
- 利用した日付
- 訪問先
- 利用交通機関
- 出発した場所
- 到着先
- 片道/往復
- 利用金額
- 申請者名
- 申請日
経費精算に使う領収書の保管方法は?

経費精算に必要な領収書は、法律で保管期間・保管方法が決められています。
保管期間
領収書の保管期間は、法人・個人事業主ともに確定申告の提出期限翌日から7年間と定められています。
また、繰越欠損金控除(次年度以降への赤字の繰越)を受ける場合は10年間の保管が必要です。
紙の領収書の場合
紙の領収書の場合は原本を月ごと・項目ごとなどに分けファイリングしてから保管しましょう。コピーは認められません。
また紙の領収書は、スキャンして電子データにしてから保管することもできます(スキャナ保存については後述)。
電子保存
2022年以降、電子データで受け取った領収書を保管する場合は、プリントアウトせずデータのまま保管することが原則ルールとなっています。
とはいえ、電子帳簿化の過渡期である現在、領収書においても電子データと紙が混在しているケースが多く見られます。そのため2023年12月31日までは猶予期間が設けられており、「電子データの領収書は要件に従って保存」「電子データの領収書を紙に出力して全部紙で保存」のどちらでも認められます。
ただし、2024年以降は相当な理由がない限り、電子データの領収書をプリントアウトして保存することができません。また電子データをそのまま保存する場合、「真実性の確保」と「可視性の確保」それぞれを満たす形で保存する必要があります。
|
真実性の確保 (4つのうちいずれかの要件を満たす形で保管) |
タイムスタンプを付してから、取引情報の授受を行う |
| 取引情報の授受後、速やかにタイムスタンプを付ける(7営業日以内、または最大2カ月以内の業務手続き終了後から7営業日以内)。保存を行う者または監督者に関する情報を確認できるようにしておく | |
| 記録事項の訂正・削除の操作内容が確認できるシステム、または記録事項の訂正・削除ができないシステムを使用し、取引情報の授受・保存を行う | |
| 内容の改ざん防止のための事務処理規程を定めたうえで運用する | |
|
可視性の確保 (3つすべての要件を満たす形で保管) |
電子取引のデータ保存をする場所に、パソコン、プログラム、ディスプレイ、プリンタと、それらの操作マニュアルを明瞭な状態で備え付け、速やかに出力できるようにしておく |
| パソコンなどで使用する処理システムの概要書を備え付ける | |
以下の検索機能が備わっている
|
スキャナ保存
紙の領収書はスキャナで電子データ化したうえでの保存が認められています。
スキャン後は原本となる領収書を破棄してもかまいません。また過去の領収書についても、さかのぼってスキャナ保存することができます。
税法上、領収書は「重要書類」として扱われ、スキャナ保存を始めた日より前に作成・受領した領収書は「過去分重要書類」として扱われます。
過去分重要書類をスキャナ保存するには、あらかじめ税務署に届出書を提出する必要があります。
参照:[手続名]国税関係書類の電磁的記録によるスキャナ保存の適用届出(過去分重要書類)|国税庁
またスキャナ保存をするには、以下の適用条件を満たす必要があります。
スキャナ保存開始日以降の領収書(重要書類)と過去の領収書(過去分重要書類)ではそれぞれ必要な用件が異なるので把握しておきましょう。
【スキャナ保存の適用条件について】
| 要件 | 重要書類 (現年度の領収書) |
過去分重要書類 (過去の領収書) |
|---|---|---|
| 入力期間の制限 | ◯ | - |
| 200dpi以上の解像度での読み取り | ◯ | ◯ |
| 赤・緑・青各256階調でのカラー画像読み取り | ◯ | ◯ |
| タイムスタンプの付与 | ◯ | ◯ |
| 解像度及び階調情報の保存 | ◯ | ◯ |
| 大きさ情報の保存 | △ (受領したA4以下の書類は不要) |
◯ |
| ヴァージョン管理 | ◯ | ◯ |
| 入力者等情報の確認 | ◯ | ◯ |
| 適正事務処理要件 | ◯ | ◯ |
| スキャン文書と帳簿の相互関連性の保持 | ◯ | ◯ |
| 見読可能装置の備付け (14インチ以上のカラーディスプレイなど) |
◯ | ◯ |
| 整然・明瞭出力 | ◯ | ◯ |
| 検索機能の確保 | ◯ | ◯ |
| 電子計算機処理システム開発関連書類等の備付け | ◯ | ◯ |
| 適用届出書の提出 | - | ◯ |
まとめ
経費精算において領収書は「支払いの確実性」を証明するものであり、適切な規則にしたがって使用・保管をする必要があります。
また、領収書の形式について紙・電子発行・スキャンデータが混在している間は、それぞれ決められた要件を満たしたうえでの保管が必要です。
『PCA Hub eDOC』なら電子帳簿保存法の保存要件を満たしたうえで、領収書や請求書の電子データ保管が可能です。さらに『PCA Hub eDOC AI-OCRオプション』をご利用いただくと、AI-OCRを利用して簡単に取引日、取引金額、取引先の記録項目を追加することができます。
これから電子データでの証憑保存へと移行される企業、既存の領収書をスキャナ保存されたい企業は、電子帳簿保存法に対応した『PCA Hub eDOC』のご活用をおすすめします。