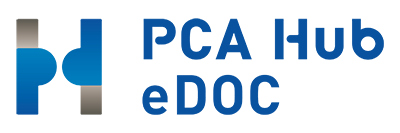紙の領収書や請求書などを電子管理する、文書管理システムとは?
更新日:2022/06/10
紙の領収書や請求書などを電子管理する、文書管理システムとは?


領収書や請求書などを紙ベースで管理する場合、「文書を探すのに時間がかかる」「どこにしまってあるか分かりにくい」という悩みはつきものです。紙で管理するとなると、業務効率の低下や機会損失が起こりやすいだけではなく、重要文書の紛失・持ち出しによる情報漏洩リスクも高くなります。
こうしたリスクを回避するには、「文書管理システムの導入」が解決策となるでしょう。
本記事では、文書を紙からデジタル管理へとシフトする際に便利な「文書管理システム」について、機能やメリット、選び方のポイントをご紹介します。合わせて知っておきたい「e-文書法」「電子帳簿保存法」、スキャナ保存をするための要件についても解説しますので、ぜひご覧ください。
文書管理システムとは?
文書管理システムとは、電子データ文書の保管や保存が簡単にできるツールです。
文書管理システムには以下のような機能が備わっています。
文書管理システムの代表的な機能
- 検索機能
- ドキュメントファイルの管理・共有
- 会計ソフト等との連携機能
- アクセス制限やファイルの暗号化、アクセスログの記録などのセキュリティ機能
- 重要なデータのバックアップ先としての利用
- 電子帳簿保存法への利用(請求書や領収書等の電子取引データ保存、スキャナ保存)
- ファイルのバージョン管理機能
- ファイルの保管期限や更新日の管理機能
文書管理システムの中でも特筆すべき機能は「ファイルの検索機能」です。
電子データ化したファイルには検索しやすいキーワードを付けることもでき、紙に比べてデータを探しやすいのが大きな特徴です。
またネットワークを通じて文書ファイルの共有が可能となるため、組織全体で帳票・資料といった文書管理や、情報共有などがしやすくなるのも文書管理システムの利点です。電子データならではの利点を活かせるため、バックオフィスはもちろんのこと、組織全体の業務効率化も実現できるでしょう。
文書管理システム導入のメリット
文書の電子管理化がスタンダードになりつつある今、文書管理システムを導入する企業が急増しています。
その背景には「バックオフィス業務をはじめとする文書のやり取りの効率化」という目的や、「テレワークの実現」といった目的があると考えられます。
さまざまな目的を達成するツールとして役立つ文書管理システムには、具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか。
①文書の検索・管理がしやすくなる
請求書や領収書などの文書を紙で管理すると、どうしても探す手間がかかります。
文書管理システムでは電子データでの管理となり、検索が容易になります。欲しいデータを見つけやすく、効率的に管理できるようになれば、業務効率化が実現できるでしょう。
②バージョン管理がしやすく、古い文書を使ってしまうミスを防げる
文書管理システムのバージョン管理機能を使えば、最新の文書データが探しやすくなります。これにより、「間違って古い文書や資料を使ってしまった」などのミスの予防につながるでしょう。
③データの共有・連携がしやすくなる
文書管理システムでは、どこからでもデータの管理・共有ができる点が魅力です。同じ部署・会社だけではなく、取引先等へのデータ共有もしやすくなるでしょう。出社せずとも文書ファイルの閲覧・検索・共有ができるため、テレワーク化を進めるうえでも効果的な対策といえるでしょう。
④閲覧制限がしやすく、セキュリティ対策にも効果的
文書管理システムには閲覧可能権限の設定ができたり、二段階認証が利用できたりする製品も存在します。
また「暗号化ファイル」でのやりとりができる文書管理システムなら、通信途中で外部からファイルを盗み見されたり、攻撃されたりするリスクも減るでしょう。
アクセスログ設定をしておけば、万が一情報漏洩があったときにも不審なアクセスを特定しやすくなります。
⑤ペーパーレス化による時間・経済的コストの削減
「紙」という形式で保管するには、物理的な保管場所だけでなく出力にかかるコピー用紙、印刷トナーなどのコストもかかります。つまり目的の文書を探すのに時間がかかりやすく、人件費のムダが生じやすい状態です。
文書管理システムで文書を電子データ化すれば、物理スペースがいらず、文書もすぐに検索が可能です。時間や手間を節約できるうえ、紙やトナー、人件費といった経済的コストも抑えられます。
文書管理システムの選び方
文書管理システム導入を検討する際は、以下の点をチェックしたうえで最適なものを選びましょう。
①インターフェースの操作性
直感的操作ができるか、誰でも使いやすいか
②使用ブラウザの互換性
複数ブラウザに対応可能か
③ストレージ容量
扱うファイルの数や種類に十分対応できる容量があるか
④セキュリティ対策
アクセス管理機能、二段階認証などの安全を考慮した機能があるか
⑤他ソフトとの連携機能
会計、人事管理等のバックオフィス系ソフトとの連携機能はあるか
⑥共有機能の使い勝手
共有機能が使いやすいか(ダウンロード用URLで共有できるシステムなど)
⑦マルチデバイス対応の有無
タブレットやスマートフォン等からでもアクセス可能か
⑧電子帳簿保存法に対応しているか
電子帳簿保存法対応に必要な機能(タイムスタンプ機能や訂正削除後に記録が残るシステム、または訂正削除ができないシステムなど)を搭載しているか
文書管理システムにはさまざまな製品があり、それぞれ独自の機能・特色を持ったものがリリースされています。
文書管理システムを選ぶ際には上記の条件を満たしたもので、かつ自社の目的に応じた製品を選びましょう。
文書管理システムに関連する「e-文書法」「電子帳簿保存法」とは
紙の請求書や領収書を、文書管理システムで電子保存する際には「e-文書法」及び「電子帳簿保存法」について把握しておく必要があります。
e-文書法(電子文書法)とは
2005年に施行されたe-文書法は、正式には「電子文書法」といいます。
これまでは紙での保存が義務付けられていた特定の文書について、電子ファイルとしての保存が認められる法律です。
電子帳簿保存法とは
e-文書法ができる以前の1998年には、「電子帳簿保存法」が施行されました。こちらも文書等を電子保存するための法律ですが、以後は改正を繰り返し、2022年には文書の電子保存がしやすいルールへと変更されています。
企業においては商法・税法で保管義務を求められる文書や請求書、領収書、帳簿などが同法の対象となります。
知っておきたい「e-文書法」「電子帳簿保存法」の違い
- e-文書法(電子文書法)
-
管轄する省庁 法律の内容・対象となる文書 電子化にあたって必要な要件 ・内閣府
・法務省
・財務省
・文部科学省
・厚生労働省
・経済産業省
・国土交通省 など
約250の法律で定められた「幅広い文書の電子化」を認める法律
・財務、税金関係書類 (会計帳簿、請求書、領収書など)
・会社に関連する書類 (定款、株主総会などの議事録)
・その他決算書類など・見読性(可視性)
必要なときにすぐ表示や出力ができるか、データが明瞭に視認できる解像度・諧調か・完全性
内容の改ざんや消去、毀損が生じないような措置が取られているか・機密性
許可された人物以外の不正アクセスができないよう管理されているか・検索性
必要なときにすぐ検索できるよう保管されているか - 電子帳簿保存法
-
管轄する省庁 法律の内容・対象となる文書 電子化にあたって必要な要件 ・財務省
・国税庁
PC等で作成した電子データやスキャナ保存したデータを保存できる法律
スキャナ保存可能な範囲は、いわゆる「証憑類(取引関係書類)」が対象
・契約書
・領収書
・請求書(支払通知書)
・納品書
・契約の申込書 など
及び上記書類の写し(控え)※仕訳帳、総勘定元帳などの「帳簿」、棚卸業や貸借対照表、損益計算書などの「計算、整理、決算関係書類」
→スキャナ保存が認められていない。初めから電子データでの作成・保存が必要・真実性
訂正や追加、削除の履歴が確認できるか。タイムスタンプまたは訂正削除の記録が残るシステムでの保存ができるか・可視性(見読性)
必要なときにすぐ表示や出力ができるか、データが明瞭に視認できる解像度・諧調か
e-文書法で電子化が認められた書類(仕訳帳や総勘定元帳、貸借対照表、損益計算書など)の中には、電子帳簿保存法で「スキャナ保存ができない」とされているものも含まれています。
これらに留意したうえで電子データ化、および文書管理システムでの管理・共有を行いましょう。
文書管理システムにおいて紙の文書保存に必要な要件
紙の文書を文書管理システムで保管するには、「スキャナ保存」で電子データ化する必要があります。
スキャナ保存をするために必要な準備の流れは、次のとおりです。
- 文書管理システムの準備
- 事務処理規定の作成
- 複合機、スキャナ等のスキャン機器の手配
- 14インチ以上のディスプレイ準備
- 連動させたいツールの確認
以前は複合機などのスキャナ付き機器を利用する必要がありましたが、法改正によりデジタルカメラ、スマートフォンでの撮影も認められるようになりました。
文書をスキャナ保存するには、「真実性」「可視性」を確保したうえで電子データ化する必要があります。
【スキャナ保存の要件】
<真実性の確保>
(1)200dpi以上のハンドスキャナ・複合機での読み取り(スマホ、デジカメ利用時は解像度388万画素以上のスペックで撮影)
(2)資金や物の流れに直結、連動する書類(重要書類)は、「カラー画像での読み取り」及び「2ヶ月+7営業日以内の読み取り・保存」を行う必要がある
(3)タイムスタンプの付与、または訂正削除の記録が残るシステムを利用して保存する
(4)A4サイズ以上の文書スキャン時は大きさ情報の保存が必要(A4以下の場合は不要)
(5)バージョン管理の実施
<可視性の確保>
(6)帳簿との相互関連性の保持
(7)見読可能装置の導入(14インチ以上のディスプレイなど)
(8)整然・明瞭出力
(8)システム開発の関係書類の備え付け(導入したシステムのマニュアル、概要書、仕様書など)
(9)検索機能の確保
文書管理システムを導入し、紙の文書をスキャナ保存する際は、以上を把握したうえで実施しましょう。
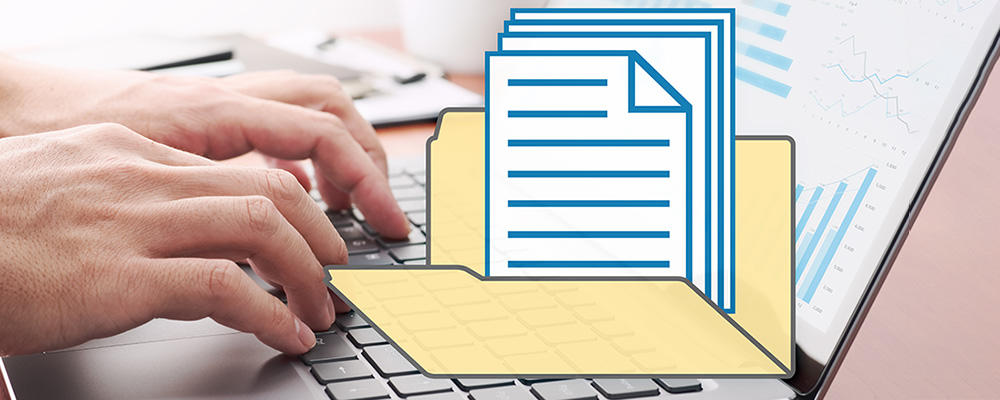
まとめ
文書管理システムを導入する際は、メリットについて理解するとともに、自社の目的を明確にしておくことが大切です。たとえば「文書管理だけではなく、バックオフィス系ソフトとの連携がしたい」という場合は、現在利用しているバックオフィスツールとの連携ができるかを確認したうえで文書管理システムを選定する必要があります。
文書管理システムを導入すると、「文書検索がしやすい」「データ共有・管理がしやすい」などの多数のメリットが得られます。紙での文書管理でお悩みの企業や、業務効率の向上を目指したい企業は、文書管理ソフトの導入を検討してみてはいかがでしょうか。