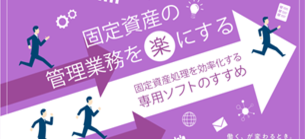減価償却のポイントしっかり押さえよう
更新日:2020/03/03
減価償却のポイントしっかり押さえよう


事業の会計処理に携わる上で、「減価償却」に関する知識や実務を理解しておくことは必須と言っても過言ではありません。
事業拡大のために設備投資をする場合や、効果的な節税方法を検討する場合などでも、減価償却を正しく理解している前提で進めることになります。
扱う機会が多いにもかかわらず、その処理ルールが煩雑で計上を間違ってしまうことも多い減価償却について、その方法・押さえておくべきポイントをこの記事で解説していきます。
減価償却とは
減価償却とは、長期間に亘って使用していく設備・建物・自動車などの固定資産がその時間の経過につれて価値が減っていくのに合わせて、その価値の減った分を費用として、分割して計上していく会計処理の方法です。
高額な固定資産を取得した場合、一般的に資産が生み出すことになる売上・収益は、複数年度に渡って見込めます。
資産を取得したタイミングでその全額を経費として計上してしまうと、その年の収益と費用が不釣り合いなものになってしまいます。
事業運営においては、「費用収益対応の原則」という考え方が好ましいとされるため、耐用年数に応じて経費を分割して計上していくことになります。
減価償却の計算方法
具体的な減価償却の計算手順を確認していきましょう。
・取得価額を確認する
対象となる資産の取得価額が10万円以上の場合は減価償却をします。
10万円未満であれば、取得した年で全額経費計上することになります。
・法定耐用年数を調べる
対象の資産をどのくらいの期間に渡って使用するか、という耐用年数が法によって定められています。
その資産の種類によって法定耐用年数は詳細に区分されており、その年数は実際に使用した年数と一致するわけではない点に注意が必要です。
・2つの償却方法から1つを選択する
減価償却には「定額法」と「定率法」の2つの方法があり、どちらの方法にするか選択します。
対象の資産毎にどちらの方法を選択したかは、所轄する税務署に届け出る必要があります。
・定額法を選択する場合
毎年、一定額を減価償却費として計上する方法が定額法です。
例えば、耐用年数5年の固定資産を100万円で購入した際は、100万円を10年で均等に分割して計上するので、10万円ずつ毎年償却していくことになります。
・定率法を選択する場合
毎年、一定割合を減価償却費として計上する方法が定率法です。
例えば、上記と同様の耐用年数5年の固定資産を100万円で購入して定率法で償却する場合は、「償却率」「保証率」「償却保証額」を確認します。
例えば
・償却率が0.20
・保証率が0.06552
・償却保証額が100万円×0.06552=65,520円
であれば
1年目:1,000,000円×0.200=200,000円
2年目:(1,000,000円-200,000円)×0.200=160,000円
3年目:(800,000円-160,000円)×0.200=128,000円 …
という形で毎年償却していき、償却保証額まで達するとそこからは定額法で算出し、最終的には残存簿価が1円になる形で償却し終えます。
この1円は備忘価額と呼ばれるもので、減価償却したことを忘れないようにするための設定数値となります。
定額法と定率法のどちらを選択するべきか
償却方法は、定額法と定率法のどちらを選択するのがよいのでしょうか。
結論から言えば、どちらがいいということはありません。
ケースによって使い分けるのが好ましいといえます。
特に、「初期に大きく減価償却費を計上したいかどうか」が大きく分かれるポイントになるでしょう。
定率法であれば、初期が一番大きく経費計上されて徐々に計上額が減っていくので、
・近々で売上が伸びる見込みがある
・初期に節税効果を高めたい
などの状況であれば定率法がよいでしょう。
経営状況見込みに変動を組み込まないのであれば、定額法を選択するのがいいでしょう。
計算や管理が容易ではない
計算手順やポイントがわかっていても、正確に計算して計上していくのは容易ではありません。
税務調査時に訂正が入って税金の追徴に繋がるケースもありますので、そうならないためにも固定資産管理システムなどのソフトを利用して管理するのも1つの方法です。
適用する期間のポイント
減価償却適用の開始時期は「資産を取得した日」と思われていることがありますが、実際はその資産の使用を開始した時期「事業の用に供した日」からの適用となります。
設備や備品などで取得してすぐに使用を開始する場合であれば、取得と同時に償却開始で間違いありません。
しかし、使用するまでに準備や工事などの作業が必要な特殊な設備・機械類など、実際に使用し始めるまでに期間を要するものの場合は、使用し始めた時点での償却開始ということになります。
実際にどの時点からの償却が適正なのかが客観的にわかりにくい場合もあり、税務調査時に適正でないと判断されることもあります。
資産取得の前に、減価償却に関して税理士に相談するとよいでしょう。
中古資産を取得した場合
新品の資産を取得する場合に限らず、中古の資産を取得することもあります。
この場合、法定耐用年数を過ぎた資産であれば、法定耐用年数の20%で計算します。
法定耐用年数をまだ過ぎていない資産であれば、法定耐用年数から経過年数を引いて、経過年数の20%を足した年数で計算します。
償却期間を早めるには
1年で大きく経費を計上できると利益が減るので、その年の節税効果は大きくなります。
そのために、償却期間を短くするという方法があります。
少額減価償却
青色申告を行っていて、従業員数が1,000人以下の「個人事業主」または「資本金が1億円以下の法人」であれば、少額減価償却を適用することができます。
取得価額が30万円未満の減価償却資産であれば、一度に減価償却費として費用計上できるという制度です。
一括減価償却
20万円未満の減価償却資産であれば、資産の種類や法定耐用年数を問わず、3年で減価償却する一括減価償却を選択することができます。
少額減価償却のような条件を必要としないので、使い勝手のよい方法といえるでしょう。
資産別に押さえておくポイント
ここまで償却資産の全般的な考え方について確認してきましたが、対象となる資産別のポイントについても見てみましょう。
無形固定資産の場合
設備や備品などの有形固定資産の場合と違って、目に見えない無形固定資産もあります。
「使用可能期間が1年以上」「取得価額が10万円以上」の条件を満たしている場合、減価償却で経費処理することになります。
無形固定資産として、特に扱う機会が多いのがソフトウェアです。
ソフトウェアの減価償却には主に2つの方法があります。
・自社で利用する場合
「将来の収益を獲得する」「費用を削減する」のどちらかに当てはまる場合に、無形固定資産として計上され、その法定耐用年数は5年と見なされます。
・販売する場合
販売を目的として製造されている場合、そのマスターの製作費が無形固定資産として計上され、その法定耐用年数は3年と見なされます。
減価償却しないもの
高額で取得したものでも減価償却の対象とならないものがあります。
時間の経過とともにその価値が減少しないものであり、以下がその例です。
- 土地
- 借地権
- 骨董品
- 書画
- 電話加入権
- 有価証券
これらは売却されたり、手放したりすることがない限りそのまま資産として計上されることになります。
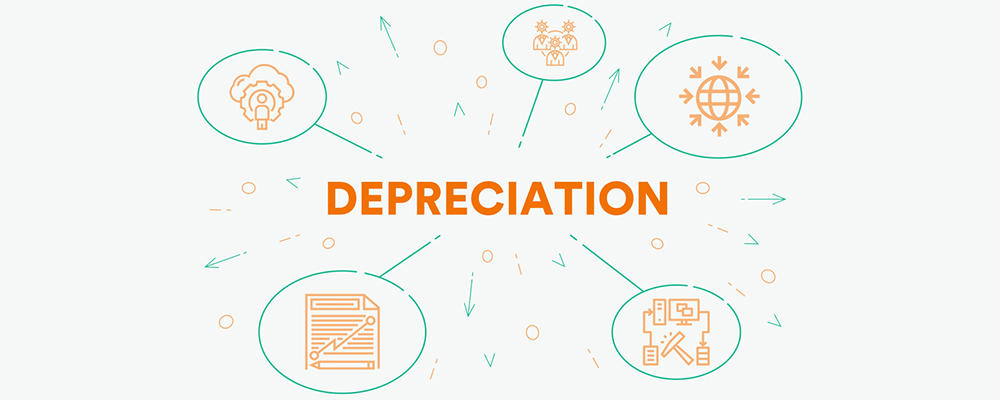
まとめ
減価償却はその適用ルールや計算方法が煩雑で、税務調査の際によく指摘を受けるポイントです。
対象となる資産の耐用年数や償却率に間違いはないか、いつからの適用かを認識できているか、などのチェックポイントをクリアにし、適正な収支の把握・効果的な節税など健全な経営状況に繋げていきましょう。