過失でも問題に!粉飾決算とは何か把握しておこう
更新日:2020/01/28
過失でも問題に!粉飾決算とは何か把握しておこう
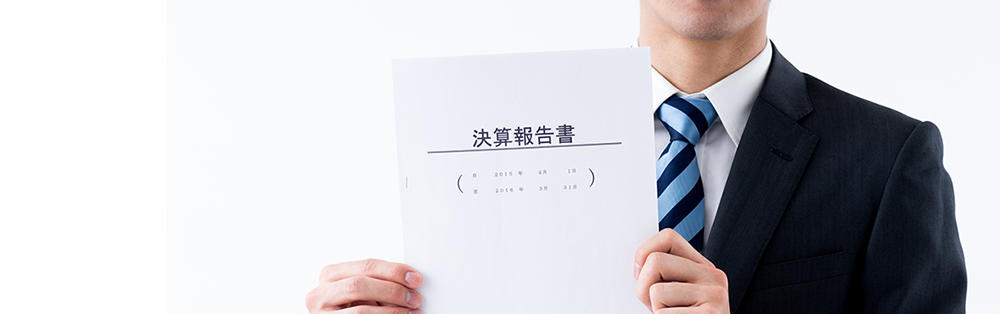
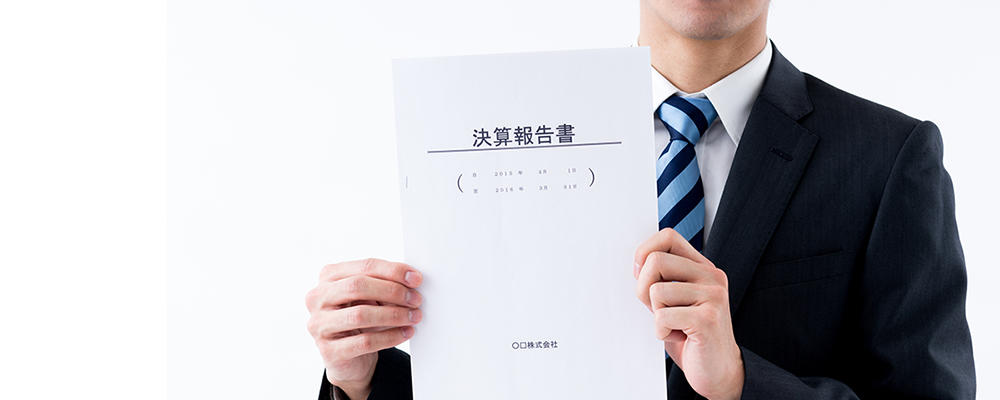
さまざまなメディアで「企業が粉飾決算を起こした」というニュースが流れることがあります。ニュースになる粉飾決算は大企業が多いため、中には「粉飾決算はニュースで大々的に取り上げられるような大企業だから起こるもの」と、勘違いしている方もいらっしゃるかもしれません。
しかしどんな企業にも粉飾決算と同じような状況に陥る可能性があり、たとえ過失でも問題になる恐れがあります。気づかないうちに粉飾決算になってしまわないよう、粉飾決算についての理解を深めておく必要があります。
今回は粉飾決算とは何か、そして起こさないためのポイントなどをわかりやすく解説していきます。
粉飾決算とは
粉飾決算とは「表面だけ取り繕って、自社にとってよくないことを隠した決算」を指します。
粉飾決算は
- 黒字に見せかけて、上場維持を図る
- 経営状態が良好と見せかけて、銀行から多額の融資を受ける
- 株主から責任追及を受けるのを免れる
などの目的で行われます。
粉飾決算は、嘘の決算情報を提示して外部のステークホルダー(企業が経営する上での利害関係者。株主や経営者、従業員にとどまらず、顧客・取引先・金融機関・競合企業・地域社会・行政機関等が含まれます。)などをだまします。これは、企業としての信用を著しく低下させるだけでなく、決算情報が正しく自社の経営状況を現せなくなるため、より経営を悪化させる要因にもなります。
粉飾決算の手口事例
粉飾決算には、次のような手口が見受けられます。
- 架空取引による売上の過大計上
- 利益の水増し
- 経費などの計上タイミング操作
架空取引による売上の過大計上
企業にとって、各期にどれくらい売上を創出できたかは重要な指標になります。そこで売上を過大計上し、実際より多くの売上が上がっているように見せかけるケースがあります。
たとえば取引先A社、B社から売上が計上されたとします。
- A社・・・75万円
- B社・・・125万円
しかし費用が300万発生してしまい、このままでは差し引き100万円の赤字になる状態とします。
この状態では赤字のため、経営を立て直す外部融資を受けにくくなるため、
- ・C社・・・150万円
と、実際には取引がない会社から売上が計上されたと架空の情報を作り出し、決算情報に加えます。その結果、差し引き50万円の黒字になるため外部融資を受けやすくなります。
利益の水増し
利益の水増しも、架空取引による売上の過大計上と同様粉飾決算の代表的な手口です。売上を不当な方法で増やしたり、原価を操作して減少させたりすることで利益が増えたように見せかけます。
たとえば在庫を1個当たり単価900円で1,000個仕入れて、今期中に1個あたり単価1,000円で販売し900個が売れたとします。残りの在庫は100個となり、売上は1,000円×900個=90万円となります。
営業利益は
- 売上‐売上原価(諸経費も加わるが、わかりやすくするために今回は除外)
で計算でき、売上原価は900円×900個=81万円となります。
ですから今回の営業利益は、
- 90万円‐81万円=9万円となります。
ここに架空の在庫100個を追加して、在庫を100個から200個に変更します。
すると営業利益は
- 90万円‐(900円×800個)=18万円
となり、営業利益が増えます。
在庫は資産扱いとなるため、売上原価には実際に捌いた在庫の分しか計上しません。在庫を増やして捌いた在庫の分を減らすと売上原価も下がるので、売上をそのままにしておけば利益が増えたように見せかけられます。
経費などの計上タイミング操作
経費などの計上タイミング操作も、粉飾決算でよく使われる手法です。具体的には今期計上すべき経費を来期に繰り延べて、利益を水増しします。
たとえば今期中に、在庫を合計100万円で仕入れたとします。それを来期に繰り延べれば100万円分の経費が浮き、利益が大幅に向上したように見えます。
今回紹介した手口以外にもあえて赤字に見せかけることで課税逃れを行う「逆粉飾」など、さまざまな粉飾決算手口が存在します。会計は項目が多く複雑なので、こういった不正がはびこりやすいのが現状です。
過失でも粉飾決算に近い状況が発生してしまうことがある
上記のように粉飾決算は意図的に行われるものですが、場合によっては作業ミスなどにより粉飾決算と同じ状況に陥ってしまうこともあります。
たとえば新人の経理担当が自社の経費計上タイミングを知らず、現金主義でまだ支払いが発生していない経費を来期に計上します。しかし実際には取引主義で経費を計上する必要がある場合、本来は今期に計上しないといけない経費を来期に計上してしまったことになります。
また、桁数間違いや桁数が少ないなどの単純な入力・記載のミスでも、意図せず架空在庫や架空取引を発生させてしまう可能性もあります。
このような会計上のミスは誰にでも起こり得ますが、知らなかったでは済まされません。
粉飾決算ではないにしろ、決算内容が明らかに間違っている場合は「不適切会計」とみなされます。過去に大企業などが不適切会計を行い、ステークホルダーと大きな対立になったり一般の方から非難を受けたりと大きな問題になりました。
過失で行ったか意図的に行ったかの違いはありますが、決算が間違っているという点では不適切会計も粉飾決算も同じです。企業としては粉飾決算を行わないのはもちろんのこと、不適切会計が発生してしまわないように適切な会計を行う必要があります。
間違った決算を起こさないためのポイント
ここからは、間違った決算を起こさないためのポイントをご紹介していきます。
- ダブルチェックなどでミスを防ぐ
- 会計士・税理士に相談する
- クラウド会計ソフトを利用する
ダブルチェックなどでミスを防ぐ
基本的なところですが、人為的なミスを減らすにはダブルチェックなどを行う方法が考えられます。
会計業務に慣れているベテランでも、ヒューマンエラーを起こして間違った情報を記載することもあります。「人間はミスを犯すもの」という認識を忘れずに、ダブルチェックなど基本的なミスを防ぐ取り組みを欠かさないだけで、不適切会計が起きてしまう可能性を減らせます。
会計士・税理士に相談する
自社だけで細かい会計業務を行うのは難しい面もあり、正しい会計知識が必要になります。そのため、会計士・税理士にいつでも相談できる体制を整えておけば、安心して会計業務を行えます。
会計士・税理士は決算情報など、さまざまな会計に関する書類をチェックして間違いを指摘してくれます。特に「自社は正しいと思っていたが、計上の仕方が間違っていた」などの思い込みによるミスなどを防げるという点で有益です。
会社の規模が大きくなってきて、会計処理が大変になりつつあるという場合は会計士・税理士に相談できる体制を作っておいてください。
クラウド会計ソフトを利用する
転記のミスを防ぐためには、会計ソフトの導入がおすすめです。
会計ソフトの自動入力・自動仕訳などの各機能で、ミスのない効率的な会計処理を実現できます。

まとめ
今回は粉飾決算とは何か、そして粉飾決算を始めとした不適切な会計を起こさないためのポイントなどを解説しました。
粉飾決算を行うと社会的な信頼を失うので、絶対に行ってはいけません。また、たとえ過失であっても、不適切会計を行ってしまうと責任追及を受けてしまい信頼を失ってしまいますので注意しましょう。





