今さら聞けない旬ワード「STEAM教育」
更新日:2025/09/04
新聞やニュース、ウェブサイトなどで当たり前のように使われているけれど、じつは正確な意味を知らない言葉。そんな「旬ワード」をご紹介するコラムです。今回は政府も力を入れている次世代の学びである「STEAM教育」について解説します。
問い・勉強を楽しくする方法を考えなさい
ヒント・1たす1は必ずしも2にはなりません
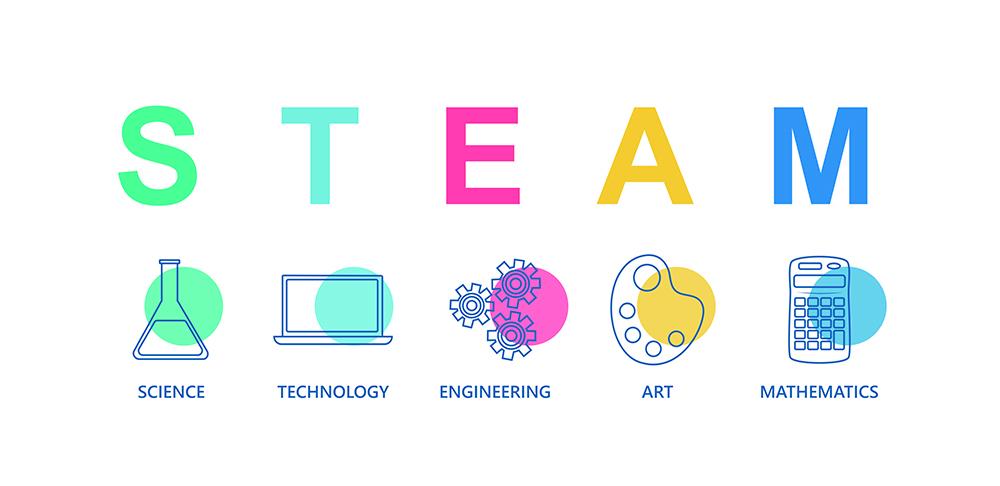
理系科目に教養を統合した総合的な次世代教育のありかた
近代日本の成長を支えてきた原動力が、科学技術であることは間違いありません。ものづくりの長い歴史を持ち、それを支えるさまざまな分野の技術開発や研究が盛んに行われて、今日を築きました。その礎となっているのは科学(Science)、技術(Technology)、工学(Engineering)、数学(Mathematics)のSTEM教育でした。理系科目と呼ばれるそれらの学習に、日本では昔から力を入れており、統一問題での学力テストでは、各学年ともに世界と比べてもトップレベルにあります。
一方、2000年代のアメリカでは、未来の競争力低下への懸念やITなどの高等技術を用いる職種の人材不足などから、STEM教育の強化が叫ばれるようになりました。そして2006年にブッシュ政権下で「STEM教育強化 10の指針」が出された後、2011年にはオバマ大統領が一般教書演説でSTEM教育を最優先課題とし、2013年にはそれを国家戦略と位置付けたのです。
対して日本では伝統的なSTEM分野の実力は高いものの、アメリカのITプラットフォームに代表されるような、イノベーションを起こすクリエイティブ力の不足が近年とくに言われるようになりました。1998年に策定された新しい学習指導要領で、複数の教科を組み合わせたり、自発的に課題を解決するプロセスを重視したりする「総合的な学習」の時間が設けられるなど、教科の枠にとらわれない、横断的、総合的な学習を目指す動きが続いてきたのもそのためです。
その延長として2019年に中央教育審議会に諮問された「新しい時代の初等中等教育の在り方について」の中で、文系・理系にかかわらずさまざまな科目を学ぶこととともにSTEAM教育の推進が取り上げられました。
従来のSTEM教育に加えられた“A”はアートですが、必ずしも芸術ではありません。アメリカでも2007年ごろからすでに提唱されていたもので、人文学、芸術、自然科学、社会科学などを幅広く学ぶ、リベラル・アーツに近い概念です。日本では、広義の“教養”という表現がわかりやすいかもしれません。
理系と文系の学問を統合した実社会の課題解決を目指す学び
2021年の中央教育審議会の答申によれば、STEAM教育とは「各教科での学習を実社会での問題発見・解決にいかしていくための教科横断的な教育」といいます。それを通して「文系・理系といった枠にとらわれず、各教科等の学びを基盤としつつ、さまざまな情報を活用しながらそれを統合し、課題の発見・解決や社会的な価値の創造に結びつけていく資質・能力の育成」が求められているというのです。
社会課題解決というフレーズは最近の企業活動でも定番ですが、そのためにはたんに優れた技術があればいいわけではなく、まずそこにある課題を課題と気づく感性や、なぜだろうという疑問を持つ好奇心が必要です。
じつはそれを涵養する教育は、日本でも昔からありました。多くの学校で課されていた夏休みの自由研究は、まさにそれだと思いませんか?
地元の博物館で地域の歴史を調べたり、お年寄りの話を聞いて戦争の恐ろしさを学んだり。鉄道好きの子がお目当ての車両の乗りつぶしの旅に出るのも、乗り物好きがエンジンの構造やハイブリッド車の仕組みを調べるのも、れっきとしたSTEAMの“A”のアクションなのです。
食材の産地や料理法、おいしさの秘密などを調べて料理を作るのも、ミニ四駆をチューニングして最速のマシンを作るために、最適なギヤ比や軽量化に知恵を絞るのもSTEAM。ハイキングに釣りにキャンプまで、どんなアクティビティだって自由研究=STEAM教育の素材になるはずです。
勉強は義務的にやらされているうちは苦行ですが、好奇心のスイッチが入ると、てきめんわくわくする冒険やチャレンジになります。そのスイッチを入れることがSTEAM教育のポイント。となれば、その役割を担うのは、必ずしも学校の先生ではありません。STEAMのAは、子供が目を輝かせる瞬間を誰よりも喜べる親である、“あなた”かもしれません。
ライター
アニメーション雑誌を皮切りに、自動車雑誌や男性誌の編集者として多くの新雑誌やヒット企画の立ち上げに参画。94 年に独立後も、芸能インタビューから政治経済まで、幅広いジャンルの企画・制作・執筆に携わる。




