今さら聞けない旬ワード「X Y Z α世代」
更新日:2024/12/13
新聞やニュース、ウェブサイトなどで当たり前のように使われているけれど、じつは正確な意味を知らない言葉。そんな「旬ワード」をご紹介するコラムです。今回は主にマーケティングの世界で世界的に使われている、ターゲットとする客層を分類した「X、Y、Z、α」と呼ばれる世代の分け方とそれぞれの特徴について解説します。
【問い】先輩や後輩とスムーズにコミュニケーションする方法を考えなさい
【ヒント】どんな大人にも、夢中で遊んだ幼少期がありました
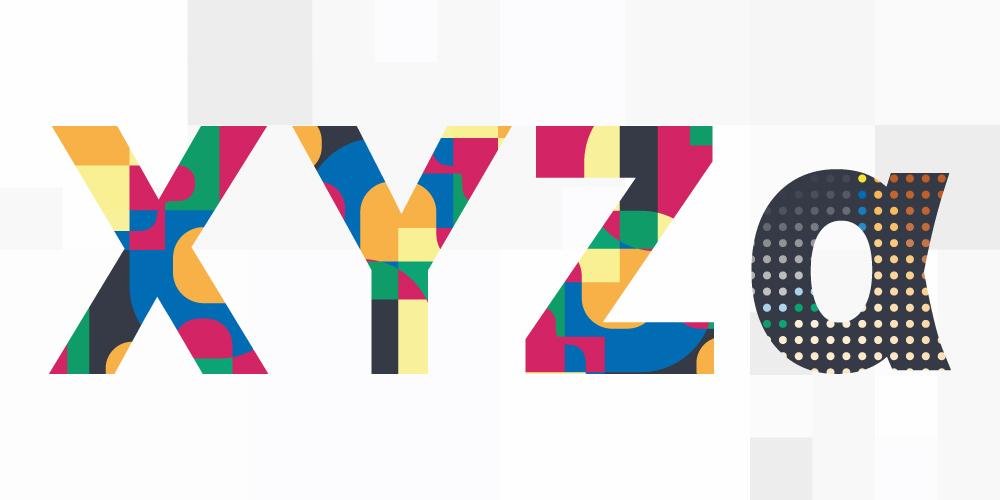
育った時代背景が違えば意識も行動様式も変わる
最近テレビでは、世代間のギャップを話題にしたクイズ番組が人気です。昔の駅のホームでサラリーマンたちが喫煙している様子に若者が驚いたり、子供の遊びがままごとやゴム飛びからカードゲームやボードゲーム、さらにテレビゲームやスマホゲームへと変化する様子を振り返るなど、育った時代によって異なる風俗や意識のズレが面白さになっているようです。
人々を世代ごとに分類して特徴づけることは、学術分野でも、報道やマーケティングの分野でも、つねに行われてきました。
日本でも昭和ひとけた世代あたりから、団塊世代、シラケ世代、新人類世代、バブル世代、氷河期世代、ゆとり世代などが知られています。それぞれの世代は生まれ育った環境や時代背景によって意識や行動様式が異なり、それが政治や経済などの社会的な動きにどのような影響を及ぼすかが、学者やメディアなどによって折々に分析・研究されてきたのです。
市場が求める商品をジャストなタイミングで投入することを求められるマーケティングの世界でも、世代ごとの特徴や傾向を正確に知ることは、大切な仕事です。
X、Y、Z、αという世代の分類も、主に欧米でマーケティング用語として生まれて、近年は日本でも使われるようになりました。その特徴は、生まれ育った時代のデジタル環境から消費行動の違いにアプローチしていることです。
未知なる世代=Xから始まった欧米での分類
欧米、中でもマーケティング大国のアメリカで世代という概念が言われるようになったのは、第二次大戦後の1950~60年代前半に生まれたベビーブーマーあたりからでした。日本では団塊世代に近いこの世代は、少年時代からテレビというマスメディアに接し、ブラウン管を通して新しい商品や流行を知りましたが、まだ戦前からの伝統的な価値観も色濃く受け継いでいました。
その次の1960~70年代に生まれたのが、X世代=ジェネレーションXという世代です。
ちなみに「Generation X」という言葉は、写真家のロバート・キャパが1950年代にアメリカの若者たちを被写体として発表した写真集のタイトルが初出とされています。戦後の平和な世の中で自由にふるまう、その後の日本でも石原裕次郎が演じて「太陽族」などと呼ばれたような型破りな若者たちを、「未知なる世代」としてXと称したもの。それを後のマーケティング業界が援用し、新世代の消費者の代名詞としてX世代としたわけです。
この世代の大きな特徴は、働き盛りの20~30代のころにデジタル革命を迎えたこと。1995年のウィンドウズ95の登場で、職場に急速にPCが普及し、それまでは専門職に任せておけばよかった公式文書や企画書の作成、会計ソフトを使った経理などの業務を、誰もが自分のデスクトップでするようになったのです。
それ以前の団塊世代では、当時企業への導入が進んでいたFAXが使いこなせず、間違った相手に送ってしまったり、同じ文書を何回も送りつけたりといった失敗が笑い話になっていましたが、X世代ではそうした機器は扱えるのが当たり前になったのです。携帯電話もウィンドウズの後を追うように普及が進んでいますが、端末はまだガラケーで、情報機器というよりあくまでも持ち歩ける電話でした。
X世代はまだ新聞や雑誌などの活字メディアやテレビなどのマスメディアへの信頼感が厚い一方、デジタルツールへのリテラシーには濃淡があるため、コンピュータウイルスへの感染やネット通販トラブルなどにも巻き込まれがち。本人も必ずしもデジタルを全面的に信じてはいません。
子供時代にどんなガジェットが存在したかが消費行動を左右する
ところが、1980年代から90年代半ば生まれのY世代(2000年代に大人になったことから、ミレニアム世代とも呼ばれます)や、90年代後半から2010年代初頭に生まれたZ世代となると、物心ついたときにはPCや携帯電話、スマートフォンなどに触れていた、いわゆる「デジタルネイティブ」です。
情報収集の手段は、主にSNS。マスメディアのようにあらかじめフィルタリングされた情報を受け身で待つのではなく、自分が求める情報を取りに行く一方、デジタルメディアの特性として、本人が好む情報がカスタマイズされて届くようになるため、世界観はより狭く、深くなっていきます。
しかも、接する情報の出所はワールドワイドなインターネット。おかげでY世代以降は国ごとの伝統的な行動様式のバラツキが減り、世界共通の消費者像として認識されるようになりました。
一般的にY世代はワークライフバランスを重視し、それ以前の世代と比べてモノへの執着が少なく、さらにモノよりコト、すなわち体験価値を求めるなどと言われています。
Z世代はさらにデジタルとの親和性が高く、新聞などの活字を読まないどころか、テレビすらあまり見ません。日本では生まれた時から不景気で、コロナ禍などの不確実性の高い時代を生きているためか、将来展望がY世代より悲観的で、貯蓄や投資への関心が高いとも言われます。
消費動向ではY世代のコト消費からさらに進み、エモ消費、すなわち心が満たされるエモーショナルな体験を好むとも。デジタル全盛の時代に、あえてフィルムカメラで撮った写真の思わぬ発色や仕上がりを楽しんだり、昭和の匂いのするクラシックな喫茶店巡りをするといった具合です。
それでいて、タイパ(タイムパフォーマンス)を重視して、動画サイトで映画を倍速で見たり、イントロを飛ばして音楽を聴いたりもするのです。
デジタルツールを完璧に使いこなすことで可能になったそうした特性は、今、最も新しい世代分類であるα世代(アルファベットをZまで使い切ったので、ギリシャ文字を当てた)でも、より先鋭化すると予想されています。
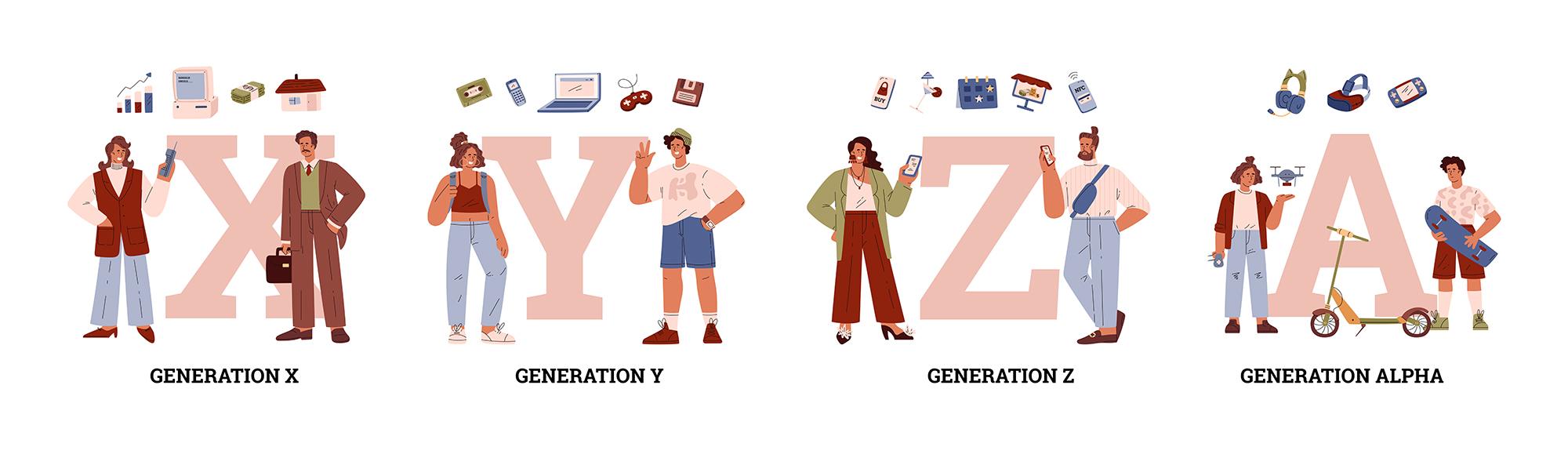
おおむね2010年代序盤以降の生まれとされるα世代が消費者の中心となるのはまだ先のことですが、物心がついた時にはスマートフォンをいじっていたZ世代と、スマートウォッチなどのウェアラブルデバイスの武装も加わるα世代は、20年後には世界の中では大きな人口比率を占めると予想されています。そうなると、マーケティングの手法もがらりと変わる可能性があるのです。
ウィンドウズPCとインターネットが世界と仕事を変え、スマートフォンは暮らしを変えました。これからも多くのデジタルガジェットが生まれ、人々を、そして子供たちの意識や行動をも変えていくことでしょう。
願わくは私たちは、デジタルに支配されるのではなく、賢く使いこなす人であり続けたいものです。
ライター
アニメーション雑誌を皮切りに、自動車雑誌や男性誌の編集者として多くの新雑誌やヒット企画の立ち上げに参画。94 年に独立後も、芸能インタビューから政治経済まで、幅広いジャンルの企画・制作・執筆に携わる。




