確定申告に使う所得控除の種類をわかりやすく解説
公開日:2023/01/25
更新日:2025/07/18
確定申告に使う所得控除の種類をわかりやすく解説


確定申告をする際には、条件を満たした場合に「所得控除」を受けられます。所得控除を受けると課税対象となる所得額が減り、節税につながります。ただし、所得控除を受けるには所定の条件を満たさなくてはなりません。
ここでは確定申告に使う所得控除の仕組みや種類、適用される条件を解説します。
所得控除の仕組み
そもそも「所得控除」とは、所得の合計額からさらにお金を差し引くことを指します。
納税者が支払う「所得税」「住民税」は、働いたり何らかの方法で得たりした「所得額」をもとに計算し、納付額が決まる仕組みです。
この所得額から、個人の事情に応じた金額を「控除」することで、適切な税額を決定できるようになります。
所得税や住民税の金額は「課税所得」の額で変わる
税金の計算に使う所得は「課税所得」ともよばれ、
「収入-経費(※)-所得控除=課税所得」
という計算式で算出できます。
所得税の場合、課税所得の額に応じた「所得税率」(以下表参照)を掛けると、税額が算出できます。
※経費を差し引けるのは、事業所得や雑所得など、限られた所得のみです。給与所得からは経費を差し引くことはできません。
所得税の速算表
| 課税される所得金額 | 所得別の税率 | 控除額 |
| 1,000円~1,949,000円 | 5% | なし |
|---|---|---|
| 1,950,000円~3,299,000円 | 10% | 97,500円 |
| 3,300,000円~6,949,000円 | 20% | 427,500円 |
| 6,950,000円~8,999,000円 | 23% | 636,000円 |
| 9,000,000円~17,999,000円 | 33% | 1,536,000円 |
| 18,000,000円~39,999,000円 | 40% | 2,796,000円 |
| 40,000,000円~ | 45% | 4,796,000円 |
所得税は「累進課税」であり、課税所得の額が大きくなるほど税率も高くなります。
また課税所得の額は、翌年度に支払う「住民税」の算定額にも大きな影響を及ぼします。
住民税は「所得割(10%)+均等割(数千円)」で算出されますが、このうちの所得割については「課税所得×10%」となるのです。当然ながら、課税所得が多いほど翌年の住民税は高くなるでしょう。
所得から所得控除を差し引き、課税所得が少なくなれば、算定される所得税・住民税が低くなります。
個人の事情に応じて税の負担を軽減できるのが「所得控除」
同じ年収400万円でも「独り身の場合」と「家族を養っている場合」とでは、実質的な収入が大きく変わります。
同じ税率・税額でも後者のほうが支出も多くなりますし、一人世帯に比べると税の負担が大きく感じるはずです。
こうした「個人それぞれの事情」を反映しつつ、税負担の不公平感を軽減するものが「所得控除」というわけです。所得控除額が増えるほど税の負担は少なくなり、実質的に手元に残るお金は多くなります。
確定申告で使う15種類の所得控除について解説

前項では、所得控除を受けることで、最終的な税金額が低くなることをお伝えしました。
所得控除には大きく分けて「人的控除」「物的控除」の2つがあり、それぞれを細分化すると合計15種類があります。
その中には、すべての人が対象になる所得控除もあれば、特定の条件を満たした人のみ適用される所得控除もあるのです。
【人的控除:納税者の家族構成、個人的事情などで適用される控除】
- 基礎控除
- 扶養控除
- 配偶者控除
- 配偶者特別控除
- ひとり親控除
- 寡婦控除
- 勤労学生控除
- 障害者控除
【物的控除:社会・政策的な配慮により受けられる控除】
- 社会保険料控除
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
- 小規模企業共済等掛金控除
- 医療費控除
- 雑損控除
- 寄付金控除
ここでは、それぞれどのような所得控除なのかを解説します。
①基礎控除
基礎控除は、合計所得金額が2,500万円以下の人すべてに適用される所得控除です。
合計所得金額が2,400万円以下の人は48万円が、2,400~2,500万円までの人は金額に応じて16~32万円の基礎控除が受けられる仕組みです。
ただし、2,500万円以上の納税者は、基礎控除がありませんので注意しましょう。
令和6年分 基礎控除の額
| 納税者の合計所得金額 | 基礎控除額 |
|---|---|
| 2,400万円以下 | 480,000円 |
| 2,400万円超2,450万円以下 | 320,000円 |
| 2,450万円超2,500万円以下 | 160,000円 |
| 2,500万円超 | 0円 |
②扶養控除
扶養家族がいる場合に適用される所得控除が「扶養控除」です。
扶養控除の金額は、家族の年齢や同居の有無によって異なります。
令和6年分 扶養控除の額※1
| 控除の種類 | 控除額 | |
|---|---|---|
| 一般の控除対象扶養親族 | 380,000円 | |
| 特定扶養親族※2 | 630,000円 | |
| 老人扶養親族※3 | 同居老親等以外の者 | 480,000円 |
| 同居老親等 | 580,000円 | |
※1 扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の方
※2 控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の方
※3 控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の方
③配偶者控除
配偶者控除は、次の条件に当てはまる配偶者を持つ人に適用されます。
- 民法上の「配偶者」であること(内縁の妻、夫は対象外)
- 納税者自身と生計を一にしている
- 配偶者の合計所得金額が48万円以下(給与収入のみの場合は103万円以下)である
- 青色申告者の事業専従者、または白色申告者の事業専従者ではない
なお、納税者自身が合計所得金額1,000万円以上の場合は、配偶者控除の対象外となります。
④配偶者特別控除
配偶者特別控除は、配偶者の合計所得金額が48万円以上、133万円以下の場合に受けられる所得控除です。
こちらも「配偶者控除」と同様に、納税者の合計所得金額が1,000万円以下である必要があります。
所定の条件をクリアする必要がある点にも注意しましょう。
控除額は納税者、配偶者の合計所得金額に応じて1~38万円の間で変化します。
「配偶者控除」に比べると控除額は少なくなるものの、配偶者控除が受けられなかった人にとってはありがたい所得控除制度といえます。
⑤ひとり親控除
納税者がひとり親である場合は、ひとり親控除として一律35万円の所得控除が受けられます。
その年の12月31日時点で、次の3条件に該当していると適用されます。
- 生計を一にする子どもがいる
- 法律上の婚姻関係、または同様の事情にあると認められる人がいない
- その年の合計所得金額が500万円以下である
⑥寡婦控除
夫と離別・死別した人に対し適用されるのが「寡婦控除」です。
寡婦控除が適用されると、一律27万円の所得控除が受けられます。
ひとり親控除の適用外であっても、以下のいずれかに当てはまれば適用されます。
- 夫と離婚したあと婚姻しておらず、かつ扶養親族がいて、合計所得金額が500万円以下である
- 夫と死別後、婚姻をしていない。または夫の生死が不明であり、合計所得金額が500万円以下である
2番目の条件については、子の有無は問われません。
よって子どもがいないご家庭や、子どもが独立し生計を一にしていないご家庭も対象になる可能性がある、ということになります。
なお寡婦控除もひとり親控除と同じく、「事実上の婚姻関係にあると認められる人(内縁の夫など)」がいると対象外になります。
⑦勤労学生控除
その年の12月31日時点で一定水準以下の給与所得がある学生は、「勤労学生控除」という一律27万円の所得控除が適用されます。
- 給与所得など、勤労による所得を得ている学生
- 合計所得金額が75万円以下、勤労以外の所得が10万円以下
- 特定の学校(※)の学生や生徒であること
※「特定の学校」については国税庁の公式ホームページで細かく要件が定義されています。
⑧障害者控除
納税者や生計を一にする配偶者、扶養家族が障害者である場合、「障害者控除」が適用されます。
障害者控除は年齢にかかわらず適用されるため、扶養親族が16歳未満であっても対象となるのが特徴です。
障害者控除の適用後は、最大75万円の所得控除が受けられます。
⑨社会保険料控除
国民健康保険や国民年金、国民年金基金の掛け金などの社会保険料を支払った場合、「社会保険料控除」が適用されます。
納税者自身が支払った社会保険料だけではなく、以下のようなケースも控除対象となります。
- 同一生計配偶者の社会保険料
- 20歳以上の子どもの年金を親が支払っている場合
社会保険料控除では「実際に支払った金額」、または「給与・公的年金等から天引きされた社会保険料の全額」が控除額となります。
⑩生命保険料控除
生命保険料控除は、以下の3つの支払額に応じて適用される所得控除です。
- 生命保険料
- 介護医療保険料
- 個人年金保険料
生命保険料控除は、保険契約を締結した時期によって控除額が異なります。
平成24年1月1日以降……新契約(最大12万円まで)
平成23年12月31日以前……旧契約(最大10万円まで)
控除額は年間の保険料支払い額、および新契約・旧契約のどちらかによっても異なります。
⑪地震保険料控除
地震保険料を支払った場合には、地震保険料控除が適用されます。
控除額は最大5万円で、支払った保険料の金額によって決定されます。
⑫小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済等掛金控除とは「小規模企業共済」や「個人型年金(iDeCo)」などへ掛金を支払った人が受けられる所得控除です。
以下に該当する人は、その年に支払った掛金の全額を所得控除として申告できます。
- 小規模企業共済法の規定により、「独立行政法人中小企業基盤整備機構」と結んだ共済契約の掛金
- 確定拠出年金法に規定する「企業型年金加入者」の掛金や、「個人型年金(iDeCo)」の掛金を支払った場合
- 地方自治体実施の「心身障害者扶養共済制度」の掛金を支払った場合
⑬医療費控除
その年の1月1日~12月31までに支払った医療費が一定額を超えた場合、「医療費控除」の適用を受けられます。
控除額は、「実際に支払った医療費の合計額-補てんされる保険金-10万円」で算出できます。
「医療費」には納税者自身だけでなく、以下の医療費も合算可能です。
- 同居している家族(妻や子、親)の医療費
- 仕送りをしている別居の両親の医療費
医療費には交通費や薬局で購入した薬代なども含められます。
⑭雑損控除
盗難や災害、横領などの“突発的な事象”で損害を受けた場合、雑損控除が受けられます。
雑損控除の金額は、
①(差し引き損失額-総所得金額等)×10%
または
②(差し引き損失額のうち、災害関連支出の金額)-5万円
のどちらか多い方の金額が控除されます。
⑮寄附金控除
寄附金控除は、以下の団体へ一定の寄付をすると受けられる所得控除です。
- 地方公共団体
- 公益社団法人
- 公益財団法人
人気の「ふるさと納税」もこの寄附金控除の対象となります。
控除額は、次の2つのどちらか低い金額から、2,000円を差し引いた金額です。
- 1年間(1月1日~12月31日)に支出した特定寄附金の合計額
- 1年間(1月1日~12月31日)の総所得金額の40%相当
※ふるさと納税には「ワンストップ特例制度」があり、利用した場合は確定申告が不要です。
ただし、個人事業主やフリーランスはワンストップ特例制度を利用できないため、確定申告が必須です。
また、6カ所以上にふるさと納税をした場合も確定申告が必要になります。
確定申告で所得控除を受けるには? 証明書が必要な所得控除
個人事業主やフリーランスが所得控除を受けるには、確定申告で控除額を申告しなくてはなりません。
確定申告書の中に所得控除額を記載する欄がありますので、記入したうえで提出しましょう。
また、所得控除の中には証明書が必要になるものもあります。
【証明書が不要な所得控除】
- 基礎控除
- 扶養控除
- 配偶者控除
- ひとり親控除
- 寡婦控除
- 障害者控除
【証明書が必要な所得控除】
以下の所得控除については、所定の証明書が必要です。
-
配偶者特別控除(配偶者が非居住者の場合、親族関係や送金関係を示す書類)
-
社会保険料控除(社会保険料控除証明書など)
-
生命保険料控除(生命保険料控除証明書など)
-
地震保険料控除(支払金額や控除を受けられることを証明する書類)
-
勤労学生控除(在学先の長が交付した証明書など)
-
小規模企業共済等掛金控除(支払った掛金の証明書など)
-
医療費控除(医療費や通院交通費の領収書など)
-
雑損控除(やむを得ない支出にかかった領収書)
- 寄附金控除(寄付金の受領証など)
必要書類、証明書は所得控除によって異なりますので、あらかじめ確認しておきましょう。
なお会社員の場合は、年末調整で「医療費控除」「雑損控除」「寄附金控除」以外の所得控除が受けられます。
ただし3つの所得控除については確定申告が必要ですので、気をつけましょう。
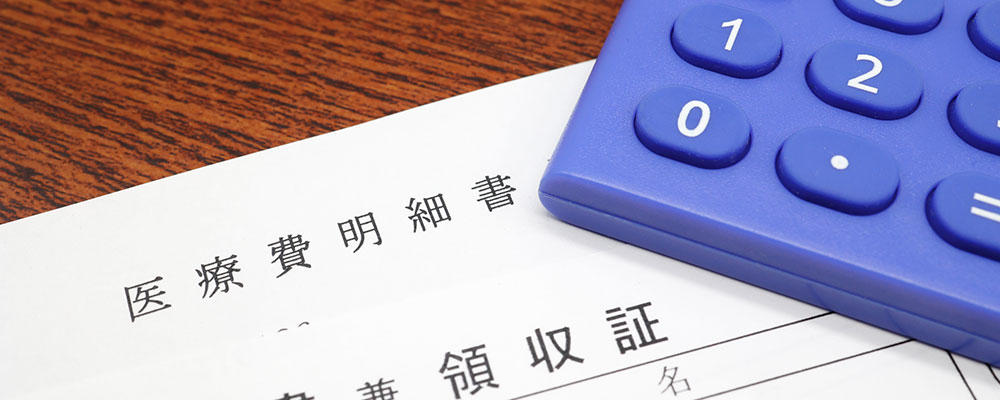
まとめ
本記事では確定申告で申告できる15種類の所得控除についてご紹介しました。
所得控除の中には、確定申告で自動的に差し引かれるものと、自身で申告しないと差し引かれないものがあります。また申告に証明書が必要になるものもあるので、必ず確認しておきましょう。




