稟議書とは? 通りやすい稟議書の書き方を解説
更新日:2021/02/02
稟議書とは? 通りやすい稟議書の書き方を解説


会社組織に属すると、稟議書を作成することがあります。いったい稟議書とはどのようなものなのでしょうか。
稟議書とは自分の権限だけでは決定できない件について説明する文書が稟議となり、この稟議を会社の上層部に回覧し承認を得る文書となります。稟議書は申請すれば必ず承認されるものではなく、差戻しや棄却といって承認が得られずに戻されることもあります。
この記事では稟議書がどのようなものか、その概要や、通りやすい稟議書の書き方などを詳しく解説します。
稟議書とは
稟議書(りんぎしょ)は会社組織で物事を始めたり、導入したり、物品を購入するときに承認を得るために作成する書類です。実務では稟議書で決済を得て、初めて物事が進められます。
具体的に稟議書を作成すべき案件か否かは会社ごとに定められています。通常は規定のなかに「権限規程」として規程化されていたり、決済権限一覧表などが会社ごとに定められていたりします。
その定めにより、稟議が必要な内容であれば稟議書を作成して承認権限者に回付して承認を得るシステムです。
すでに、社内でワークフローシステムを導入している場合は、稟議書を作成すると自動で承認権限者のもとにデータがとびますので、承認権限を意識することは少ないかもしれません。
稟議書は「起案された内容について決済権限をもつ権限者に承認を得るための文書である」と認識しておきましょう。
稟議書の必要性
では、なぜ稟議書が必要なのでしょうか。
会社組織は承認権限が明確に定められています。承認権限のないことを勝手に進めることはできません。勝手に進めると、内容によっては懲戒にあたることもあります。
例えば、営業マンが上席者に承認を得ることなく1億の新規取引をしたとしましょう。売上が1億でも利益はマイナス1千万かもしれません。1億の受注やマイナス1千万の利益の取引が、上司の知らないうちに進められていたら大問題です。
物品を購入する場合も、会社にとっての必要性や価格が適正であるかなどを検討します。一定の金額以上であれば担当者の判断だけでは進まないものです。100万までは係長の承認、300万までは課長の承認、300万を超えたら部長の承認が必要などと決済権限に沿って進めることになります。
権限規程では細かな項目と決済権限をもつ金額が定められていますので、稟議書は担当者→係長→課長→部長となるように順番に捺印して回付していきます。最終決裁権限者にいくまえに合議部として関係部署の意見が記載されて、部長が承認します。
このように一定のルールを定めて組織を運営していくために稟議書は必要なのです。
稟議書を回付すれば上長に説明して回る手間がはぶけます。一般的に上長は忙しいので時間をとってもらうのも大変です。説明する時間がなく稟議事項が進まないということもあります。そういった意味で稟議書を作成するメリットは大きいのではないでしょうか。
稟議書の書き方
稟議書の基本様式は会社ごとに定められており、諸届用紙やワークフローシステムの中に掲げられていることが多いです。
稟議書は起案番号を振って管理し、最終承認者が承認すれば決済となり決済番号を振ります。
稟議書は承認を得るためのものです。口頭で説明しなくても内容が伝わり、上司が判断をくだせるものでなければなりません。内容別に最低限記入すべきことを確認しましょう。
稟議書に添付すべき資料の例とあわせて参考にしてください。
●物品購入の稟議書に書くべきこと
- 件名
- 購入する物品の品名や型番、仕様などの情報
- 物品の用途
- 購入金額
- 購入先
- 購入する部署(固定資産にあたる場合は償却年数なども記載)
- 購入する理由
- 購入時期
※資料として製品カタログと購入金額の根拠となる見積書を添付します
●受注の稟議書に書くべきこと
- 件名
- 受注先
- 提出予定の見積額
- 予想利益
- 受注経緯
- 与信情報
- 予定納期(工期)
- 受注についての特記事項
※資料として提出予定の見積書と信用調査の結果を添付します
●採用の稟議書に書くべきこと
- 件名
- 採用する人の氏名
- 年齢や所持している資格などの個人情報
- 社員身分
- 給与
- 配属先
- 採用する理由
- 入社時期
- 試用期間の有無や試用期間中の給与など
※資料として履歴書を添付します
通りやすい稟議書のポイント
ここまで、稟議書に書くべきことをご説明しましたが、通りやすい稟議書とはどのようなものなのでしょうか。
稟議書には決済・条件付き決済・差戻し・棄却があり起案すれば必ず通るものではありません。差戻しや棄却となると稟議内容を検討して対応しなければならず、業務が滞ってしまいます。
それでは、通りやすい稟議書のポイントを説明していきます。
(1) 理由を明確にする
稟議の決裁者は稟議を起こした経緯を知りません。必要性や選定した理由を詳細に説明しましょう。
例えば、採用であればなぜその人なのか。必要としている公的資格を所持しているとか、過去に同じ仕事の経験があるとか、同業他社からの転職で業界の新卒採用の状況に詳しいなどが理由となります。
(2) 費用を明確にする
会社組織では期首に当期の予算が定められています。なかには、予算に組み込まれていれば稟議を要しないとする会社もあると思います。
稟議を申請して通す案件は予定外の支出のため、金額によっては会社の資金繰りに影響します。そのため、価格表や見積書を添付して決裁者に費用を示しましょう。
(3) 時期
稟議書には時期も記入しましょう。
費用面の調整も必要なため、稟議を決裁した場合に費用がいつ頃支出するかを示します。
物品の購入であれば購入予定日を記載します。金額の根拠となる見積書にも見積有効期間が記載されているのが一般的です。仕入先の見積書提出から1年後に購入するのであれば再度見積書をとることになります。
時期は、採用であれば入社予定日を、退職であれば退職予定日を記載します。物品の購入や受注など決済後の動き次第という場合は「決済後速やかに」や「決済後遅滞なく」などと記載します。
稟議書は決裁する承認権限者や合議部をいかに説得できるかがカギです。必要最低限の記載事項が羅列してあるだけでは不十分です。エビデンスを示して、言葉で説明する以上に細かな内容を記載して作成しましょう。
稟議書決済後の取り消しや内容変更はどうする?
稟議書は上長に直接説明する手間をはぶける反面、稟議内容に変更が生じた場合は、再稟議や内容修正の稟議を起こさなければなりません。
例えば採用の稟議で決済を得ていても、稟議の入社日予定日が変更になれば「入社日変更」の稟議書を作成しなければならないのです。
物品購入でも100万円で決済を得ていたものを120万円でしか購入できないとなれば、購入金額変更の稟議書を作成します。条件付き稟議で初めから120万以下の金額であれば「可」となっていれば稟議の必要はありません。
一度決済された稟議は訂正印で訂正するように簡単には内容変更できませんので、作成するときに注意して、できる限り具体的に内容を詰めておくとよいでしょう。
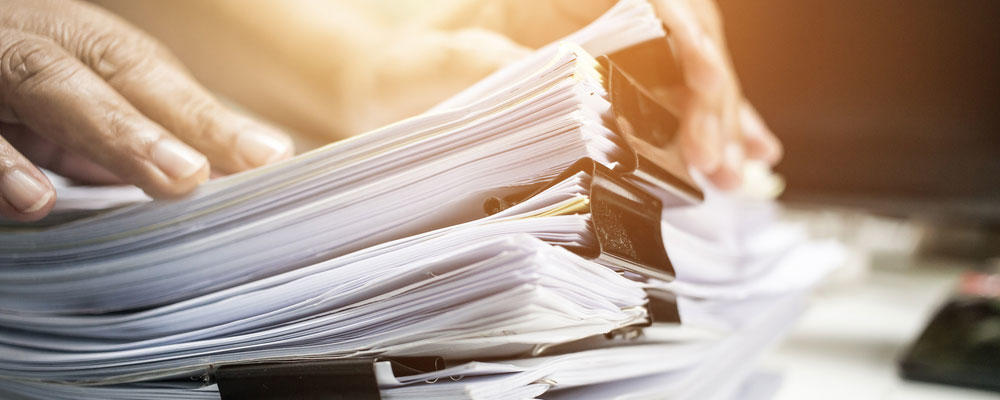
まとめ
会社組織で稟議書はかかせないものです。
入社して日の浅い新入社員が作成することは多くありませんが、ある程度のポジションになると稟議書を作成するようになります。営業や人事関係の業務では日常的に稟議を切っているのではないでしょうか。
稟議がスムーズに通るか否かは仕事のスピードに影響しますので、差戻しや棄却のないようにポイントを押さえて作成するように心がけましょう。





