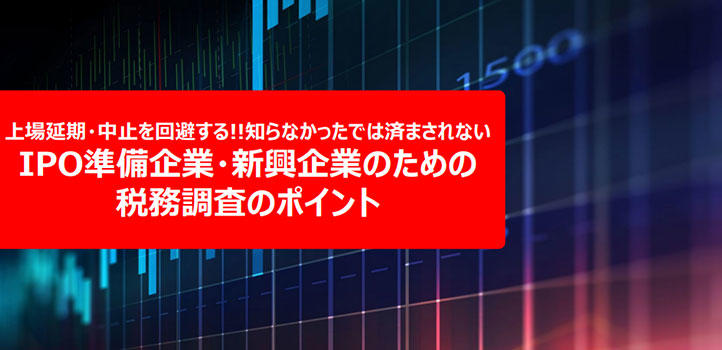税務調査を受ける際の流れやポイントを解説
公開日:2019/12/10
更新日:2025/04/14
税務調査を受ける際の流れやポイントを解説


企業活動を行う上で、納税は当然の義務です。そして税金に関するすべてを統括・管理する国税庁や税務署では、正しく納税が行われるよう各種対策を行っています。
代表的なものの一つが税務調査です。健全な納税をしていても急な税務調査が行われる可能性もあるので、企業としては調査が行われる際の心構えや準備ができていると安心して対応ができます。
令和5年度に実施された税務調査の件数は5.9万件、実地調査以外の簡易な接触件数は7.0万件とのことです。
令和5年度の法人税の申告件数は318万件ですので、申告法人の約4.1%は税務署から何かしらの調査を受けている計算となり、決して多くはないですが、勤務している会社に調査が入ることは十分にありえます。
今回は税務調査とはそもそも何か、そして調査の流れや、気をつけておきたいポイントについても解説していきます。「税務調査とは何か知りたい」「税務調査にもし入られたらどう対応すればよいのか知りたい」という方はぜひご覧ください。
税務調査とは
税務調査とは、国税庁や税務署が納税者の申告内容を確認し、誤りがある場合に是正などを行うことを指します。
税務調査には、
- 任意調査・・・通常の税務調査
- 強制調査・・・意図的な脱税の疑いなどがある際に行われる調査
の2種類があります。
強制調査が入るケースはごくまれで、よほどの問題がない限りは任意調査が行われます。任意調査は企業によって実施されるスパンが異なり、税申告に関して不審な部分が多い企業ほど受ける可能性が高くなります。ただし赤字企業にも税務調査が入る場合もあるので、幅広い企業税務調査を受ける可能性はあります。 任意調査が行われる場合は対象企業や対象者に事前に連絡がありますが、現金決済で取引を行っている場合などはありのままの経営状態を把握するため、連絡なしで税務調査が入るケースもあります。
税務調査の流れ
ここからは、実際の税務調査の流れをわかりやすく解説していきます。
- 税務署や国税庁から連絡が入るので、調査の日時等を調整
- 来訪した調査員の聴き取りに回答
- 詳細な現状確認の実施
- 調査結果の連絡を元に対応
1.税務署や国税庁から連絡が入るので、調査の日時を調整
最初に税務署や国税庁から、調査予定日の前に電話が入ります。その際、
- 調査日時
- 調査場所
- 調査目的
- 調査の対象期間
- 税務調査官の氏名
などが伝えられます。
調査日時については、調査時間を長く確保できる日時を設定しましょう。ただし余りにも先の日時を指定すると、不要な疑いの余地を生む場合がありますので優先的な日程調整をするのが好ましいです。
また状況によっては抜き打ちでの税務調査が入る可能性もあります。その場合も慌てず調査理由などを確認し、落ち着いて調査に対応できるようにしておきましょう。
2.来社した調査員の聴き取りに回答
日時が決まれば当日税務調査官が来訪するので聴き取りに回答します。一般的に来訪時間は、午前10時になることが多いようです。
はじめは何気ない雑談から始まることが多いそうですが、この時の雑談でも税務調査官の聴き取りたい内容が混ざっている場合もあります。不必要な内容を話してしまうことで本来調査する箇所でない余計な調査項目が増える可能性もあり、調査期間が長引く原因にもなるので気をつけましょう。
3.細かい現状確認の実施
雑談が終わった後は、細かい現状確認が行われることになります。
- 取引における業務工程や管理体制
- 伝票や帳簿の作成者や保管者など
- 期末棚卸資産計上の項目
といった内容を調べられますので、いつでも調査してもらえるように各種書類の準備をしておきましょう。
また調査開始2日目では帳簿について細かく調べられます。対面での税務調査は、2日目の帳簿調査が終わった時点で終了するパターンが多いです。ただし2日目でも調査が終わらない場合は、3日目以降に持ち越されます。
4. 調査結果の連絡を元に対応
調査が終了した後、税務調査官は管轄署に戻り、集めたデータを元に税に関する不正がないか再びチェックを行います。
何も問題がない場合はその旨の連絡が届きます。しかし問題がある場合は指摘事項に関する連絡が行われ、修正を求められます。問題部分を修正して再申告を行い、不足分の税金を納付すれば税務調査は終了となります。 場合によっては指摘事項に不服があり、税金納付をよしとしない場合もあるかもしれません。その場合は再調査の請求などを行って、納得のいく結果を得る方法もあります。ただしほとんどの場合は追加調査を受けてさらに調査項目が増えることを避け、そのまま修正申告に応じる企業が多くなっています。
税務調査を受ける際に押さえておきたいポイント
税務調査を受ける際は、次のポイントを押さえておきましょう。
- 日ごろから税務調査対策を行っておく
- 取引のある税理士がいる場合は、相談をする
- 正直に回答を行い、真摯に対応する
日ごろから税務調査対策を行っておく
健全な運営を行ない、今まで調査された経験がなくてもある日突然税務調査が入る可能性もあります。万が一に備えて日ごろから税務調査に関する対策を取っておくことが重要です。
例えば、売上は必ず税務調査の際に確認されます。売上はきちんと計算・管理を行っていると思っていても、入金ずれにより計上漏れが起こるなどミスが起こりやすい項目です。また経費に関しても、固定資産を減価償却費にすることが漏れてしまい、経費を購入年に過剰に計上してしまったりと間違いが起こりやすくなっています。
そのため売上や経費の計上方法の見直しを行ない、入金・出金タイミングのずれがないか、計算方法を間違えず適切なタイミングで計上ができているかなどを確認する必要があります。領収書に関してはどんな小さなものでも保管し、調査が入った際に証拠として提出できるようにしておくと安心です。
また、ずさんな収益管理が発覚した場合は重い罰を受ける可能性もあります。
例えば、利益が小さい場合に収益として計上せず、そのまま従業員の飲食などに売上を使っていたケースなどが考えられます。こういったケースがないように従業員との関係も密にしておきましょう。 また見直しに関して自社で申告ミスを発見した場合は、税務調査が入る前に修正申告を行うとペナルティが軽減されます。自社で自己申告を行っておけば、後日税務調査が入った際も短時間で調査を終わらせることができるでしょう。
取引のある税理士がいる場合は、相談をする
もし税務調査が入った場合は、必ず取引のある税理士にも相談しましょう。
税に関するプロである税理士に相談できるとわかっていれば、税務調査を受けても気持ちを自然と落ち着かせられ、指摘に対して不満な点があった場合も税理士からアドバイスを受け、適切な方法で対応できるようになります。
正直に回答を行い、真摯に対応する
当然のことですが、税務調査官の質問に関しては包み隠さず回答しましょう。
税務調査官は「質問検査権」を持っており、質問検査権を持っている税務調査官に対して虚偽の証言などを行うと、罰則を受けなければなりません。また質問に関して回答しない行為黙秘権の行使が認められていません。 また任意調査は任意とされてはいますが実質拒否権利はありません。
「任意だから受けなくてもよい」と思わずに連絡が来たら必ず真摯な対応をしましょう。

【流れやポイントを解説】税務調査を受ける際の心構えのまとめ
今回は税務調査とは何か、そして実際の調査の流れや受ける際のポイントなどを解説しました。
税務調査は税申告に関して疑わしい企業が受ける可能性が高くなりますが、健全な運営をしている企業でも調査連絡が来ることもあるので油断はできません。万が一に備えて、日ごろから細かい内容に関してもずれや漏れなどがないよう経理を行い、指摘される部分をなくすことが重要です。
税務調査対策をしっかり行い、調査を受けられるようにしておきましょう。